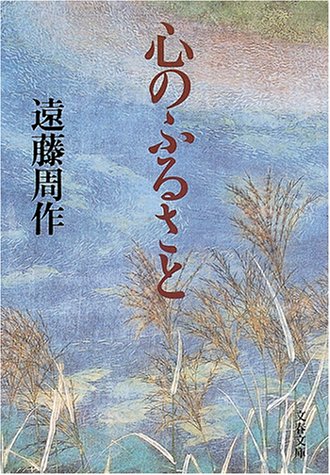10/21に各地の会場及びオンラインで開かれた、SORACOM UG Explorer 2023にLT登壇しました。
公式サイト
この日は、実は全国規模のイベントが目白押しでした。
弊社ブログにも書いた通り、CLS高知が行われ、SORACOM UG Explorer 2023が行われ、さらに地域クラウド交流会全国グランプリが釧路で行われていました。
上のブログにも書いた通り、私はオーガナイザーとしての妻の応援と、弊社がちいクラ山梨を開催する準備も踏まえて釧路を選びました。
ただ、SORACOM UG Explorer 2023はオンライン会場もあるということで、藤田さん(なっちゃん)にはLTで登壇する旨をお伝えしていました。
上のブログにも書いた通り、朝の時点で釧路市観光国際交流センターのどこでつなげば、音声や画像共に問題なく接続できるかは確認し、昼前の接続テストにもきちんと参加して、SORACOM UG運営の皆さんへの心配は解消しておきました。
その後は、ちいクラ全国大会の終了時刻(16:30)から20分後(16:53)の登壇というタイムスケジュールに間に合うかどうかが問題でした。
ところが、ちいクラ全国大会の終了時刻が少し伸びてしまい、集合写真の撮影が始まったのが終了予定時刻でした。
ちいクラ全国大会の集合写真には必ず入りたかったので、私は皆さんと一緒にポーズを決めていましたが、にこやかに写真向きの笑顔をキメる私の内面はかなり焦っていました。
無事に写真撮影が終わったのが40分。そこから私の時間までは10分強。
前もって決めていた場所に走り、パソコンを設置し、接続音響マイクカメラもセットしました。
間に合った!
私が接続したちょうどその時、SORACOMのMaxによるSORACOM MVCの発表が行われていました。
私が入った時は、ちょうど大口さんが選ばれていました。SORACOM UG Explorer 2023も少しスケジュールが押していたとか。Maxの熱意がスケジュールをいつものように動かしてくれたようです。ありがたい。フォローに感謝です。
大口さんは、私が主催したkintone Café 神奈川とSORACOM UGのコラボイベントでも登壇してくださいました。
さらに、その前に選ばれた木村さんも、先日の六本木でのしらす2万匹のイベントで初めてお会いすることができました。
そして続いての片岡幸人さん。
先日までkintoneエバンジェリストとしてもご活躍いただいていた幸人さんには、高知、神奈川の両コラボイベントだけでなく、小田原で開催したkintone Café 神奈川でも多大なる貢献をしてもらいました。
今、私がいる釧路でもCLS道東でお会いするなど、全国をまたにかけた行動力は素晴らしい。
高知、神奈川の両イベントではSORACOMとkintoneの接続ハンズオンをオンラインとリアルで同時にやり遂げると言う偉業を成し遂げました。MVCに選ばれたのも納得ですね。
六月のkintone Café 高知の際に幸人さんから託されたkintoneエバンジェリストタグは、今回も釧路に持ってきています。
私が接続してすぐ見られたのが、kintone Caféにゆかりのある皆さんのMVCに選出された姿だったのは本当にすばらしいと思いました。また、私の登壇への弾みにもなりました。
MVC発表のスライド
続いては、SORACOM UGとコラボする各コミュニティーの紹介の第二部です。
私は、スケジュール上のご配慮で、トリを務めさせていただきました。
私の前に話された、
Nerves JPさん
公式サイト
Tech-onさん
公式サイト
の両コミュニティも、kintoneやkintone Café界隈とあまり接点がないだけに、かえって興味深かったです。
Tech-onをお話しいただいた須田さんとも、先日の六本木でのしらす二万匹でお会いできたので、また何か一緒にやれればと思います。
さて、私の出番です。
私の登壇資料は、結構ぎりぎりになって完成しました。
というのも、まずはkintone Café 事務局に登壇の連絡とお伺いを立てる必要があったからです。
SORACOM UGからの登壇のご要望があったからとはいえ、kintone Caféを盛り上げているのは私だけではありません。全国にいらっしゃるkintoneプレーヤーの皆さんの力によってkintone Caféは成り立っています。
私がお伺いを立てたのは、私が主催するkintone Café 神奈川や主催するイベントだけではなく、全体のkintone Caféについて私が紹介してよいか、ということです。
私がkintone CaféとSORACOM UGの三つのコラボイベントに関わったのは事実とは言え、私がkintone Caféを代表して登壇するにあたっての確認がしたかったのです。
事務局からのご回答をまって以下のスライドを作成しました。
スライド
私がスライドを作成したのは、釧路に来る前に一泊していた十勝の大樹町です。登壇まで猶予がなかったとはいえ、私の中に焦りはありませんでした。
というのも私が書く内容は明確だったからです。kintone CaféとSORACOM UGの間には間違いなく親和性があります。
kintoneのサービスを紹介し、kintone Caféのコミュニティを紹介し、さらにお互いのコラボ実績を書くだけで、SORACOM UG Explorer 2023に参加された皆さんにはその意図が伝わる。
そう思っていました。
もちろん、私もまだkintoneとSORACOMのコラボの可能性は探っているところです。
とくにSORACOM Lagoonとkintoneの使い分けについてはもう少し研究したいと思っています。
また、弊社のkintoneビジネスの中でどうすればSORACOMのIoTを活かせるのか。
それについては、昨年度のSORACOM MVCに選ばれたSEEDPLUSの前嶋さんと模索しています。Cybozu Daysにも出展のご協力をいただきましたし、その取り組みはもちろん案件にもつながっています。
SEEDPLUSさんの記事
まずは私もSORACOMのサービスを理解し、よりよい提案につなげられるようにすべきでしょう。
まずは今回、ほとんど参加できなかったSORACOM UG Explorer 2023の内容をおさらいするところから始めたいと思いました。
SORACOM UGおよびSOARCOM社の皆さん、参加者の皆さん、ありがとうございました!