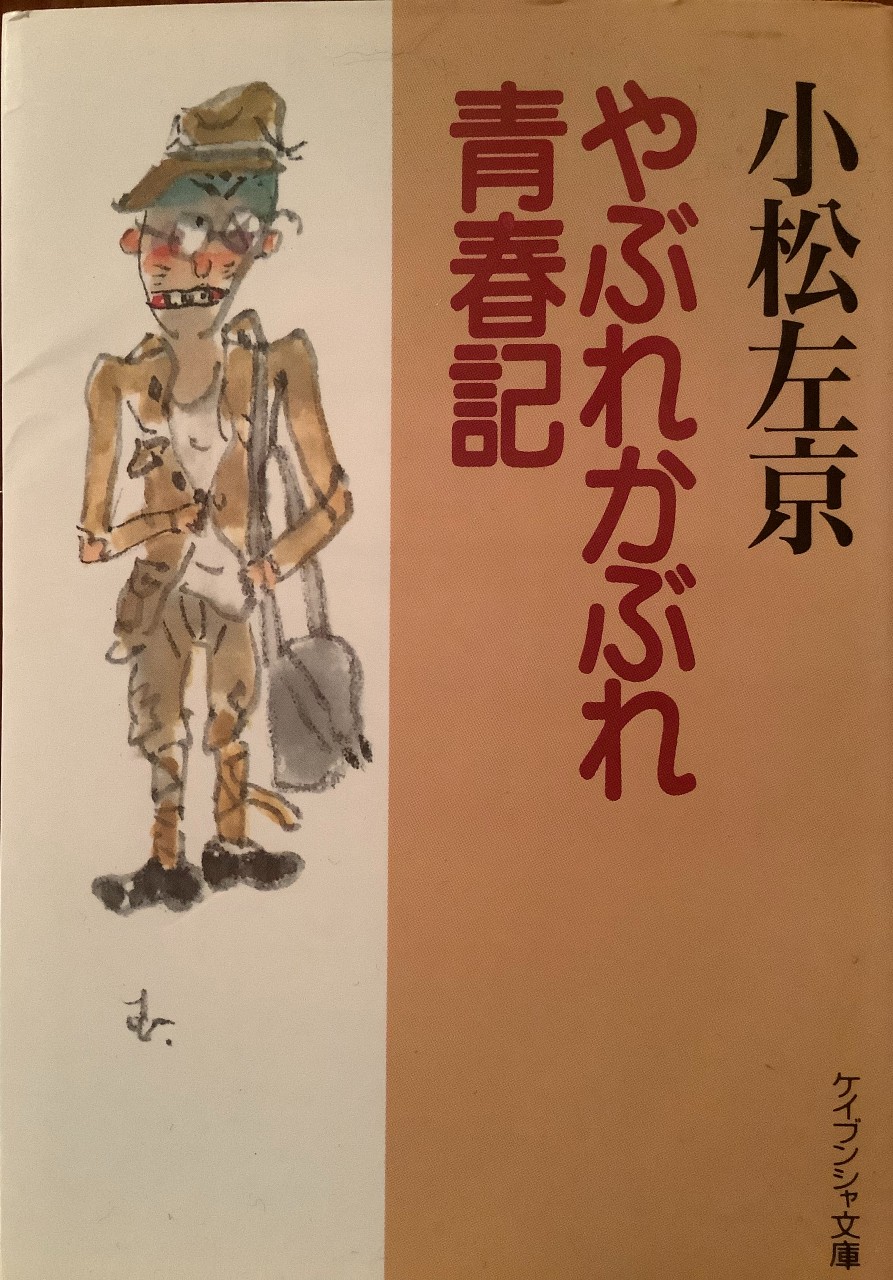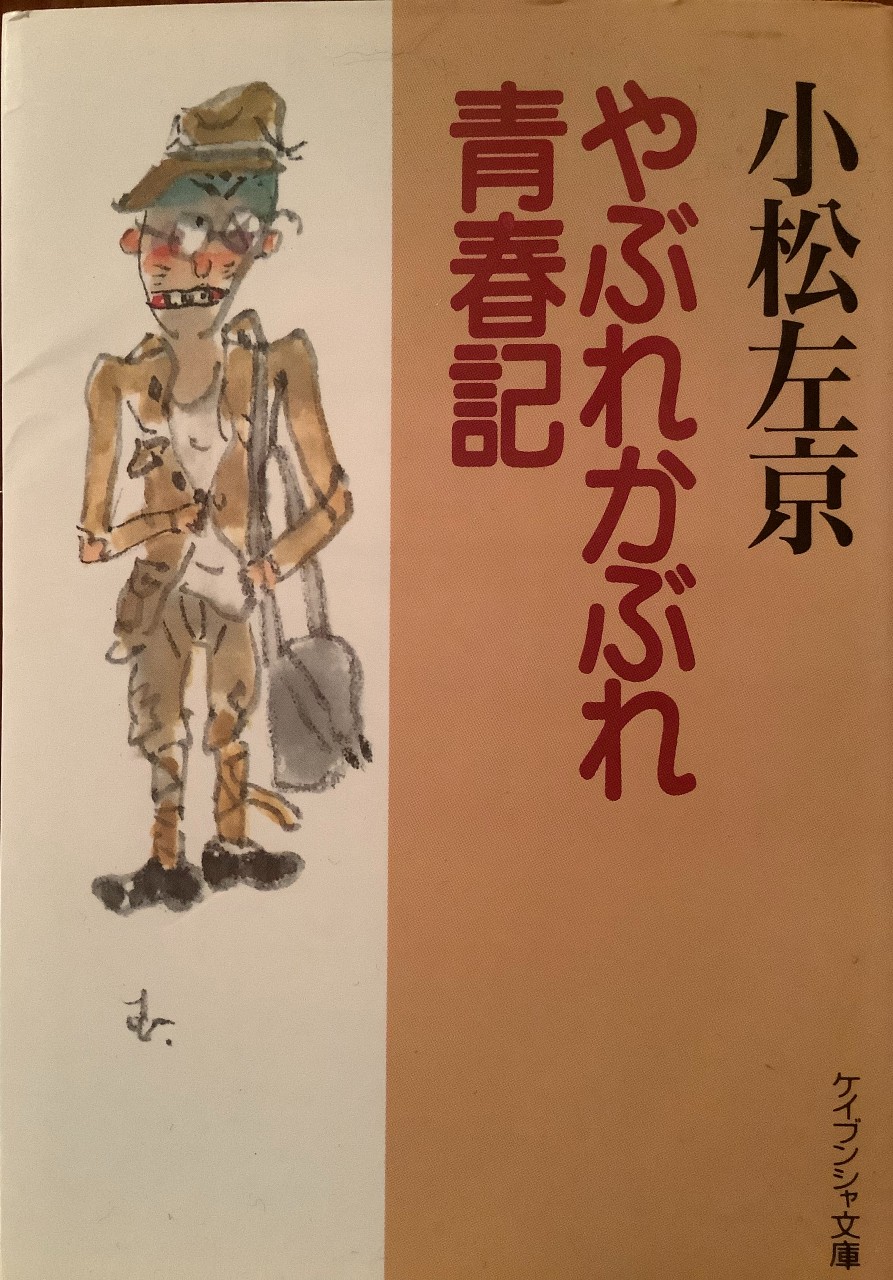小松左京展を見に行ってから、著者に興味を持った私。集中して著者の作品を読んだ。本書はその最後の一冊だ。
本書はショート・ショート傑作選と銘打たれている。
ショート・ショートといえば、第一人者として知られるのが星新一氏。星新一氏といえば、著者や筒井康隆氏と並び称されるSFの三巨頭の一人として著名だ。
三巨頭といってもそれぞれに得意分野がある。
著者の場合、あまりショート・ショートは発表していない印象がある。私は今まで著者のショート・ショートを読んだことがなかった。
本書は著者が1960年代から70年代中期にわたっていろいろな雑誌に発表したショート・ショートが収められている。
いろいろな、といっても本書に収められているのは雑多なショート・ショートではない。構成として五部のカテゴリーに分けられている。
例えば第一部「向かい同士」に収められた八編。それらは、「団地ジャーナル」が初出展だそうだ。
雑誌名から想像できる通り、八編は全て団地をテーマにしたショート・ショートだ。団地という濃縮された人間関係の中で起こり得る出来事をタネにアイデアを膨らませたこれら。ショート・ショートとしても傑作に仕上がりだと思う。
団地から想像されるのは、サラリーマンと核家族の集まり。そして、そうした世帯に付き物の小市民そのものの出来事。
著者はそれらから話を膨らませ、簡潔でしかもオチのあるショート・ショートにまとめている。
団地の上も下も筒井という名字の家族が住んでいたり、ゴールデンウィークと仕事人間を風刺したり、不倫に忙しい二組の夫婦を描いたり、団地への憧れを逆手にとったり、酔った亭主が最上階の家へと昇ったり、訪問販売員への風刺をしてみたり。
第二部「歌う空間」の四編は「新刊ニュース」が初出展のようだ。四編のどれもがSFの彩りを備えた作品だ。
宗教を風刺してみせたかと思えば、コミュニケーションの脆弱な本質を暴いてみせ、コンピューターに依存する人類の未来を予言したかと思えば、意識と肉体の実存について鋭くついてみせる。
ここで取り上げられた四編のどれもがショート・ショートというには長い気がする。原稿用紙に換算して二枚近くに及ぶような。
また、内容も、現代から見るといささか発想に古さを感じる。だが、これらのショート・ショートが発表されたのが、EXPO’70が開催された頃だと考えれば、どれもが未来への深い洞察を感じさせる。
第三部「一生に一度の月」は、毎日新聞で発表された一編だ。アポロ13号の月面着陸に湧く世間をよそに、一番盛り上がるはずのSF作家の生態を描いていて面白い。月面着陸を中継するテレビ番組をしり目に、マージャンに興じるSF作家というのがたまらない。まさに逆説そのものだ。
その時の感慨を表すのにふさわしく、著者はマージャンパイを月に向けて投げ、これが現代だと喝破する。なんとも本質をついているようで面白い。
テレビ中継で月の様子が見られる。そのイベントは当時よりもさらに技術が発達し、ネット社会になった今、考えてもすごいことではないだろうか。
ましてや当時の技術力ではとてつもない出来事で、一生に一度の月だったはず。
SF作家の矜持として、その様子をテレビにかじりつくことをよしとせず、あえてマージャンに身をやつし、無視して見せることで逆に技術の到達を体験した。その逆説的な態度がとても印象に残った。
第四部「廃虚の星にて」に収められた十三編は、朝日新聞が初出展とある。全てが環境問題に着想の源をもとめたブラックな内容になっている。
これらもまた、環境問題がしきりに起こっていた当時の世相を表している。ましてや当時はオイル・ショックによって高度経済成長が止まる前に書かれた話。だからどの編も明るそうに見える前半とそれが環境問題としてはね返ってくる後半の対比になっており、SF作家が鳴らす未来への警鐘としてもてはやされたのだろうなと思わせる。
それと同時に、不思議なことにこれらのショート・ショートが現代でも通じるのではないかという相反する思いすら感じた。
つまり、高度経済成長やバブル景気の破綻を経験した今の日本と、当時、未来を予見していた著者の立場が同じだったのではないか、ということだ。それが著者の尋常ではない学識を表していたとも言える。すでにある程度の経済レベルや技術力や文明の高みを達成したという意味で、著者と今の私たちはそう変わらないと思う。
第五部「人生旅行エージェント」に収められた十一編は、媒体もまちまちだ。雑誌名からはそれが何をテーマとしたものか判然としない。例えば原子力についての雑誌であれば、それに沿ったテーマのショート・ショートなので納得できるが、何を表しているのか定かではない出展もとも記されている。
それぞれのショート・ショートが指折りの内容なのはもちろんだ。それにも増して感心させられるのは、その雑誌に合わせてテーマをかき分ける著者の筆力だ。
もちろん著者の博学の広さと深さゆえであるのは今ら言うまでもない。
『日本沈没』のような一つのテーマに知識量を詰め込めるタイプの小説とは違い、ショート・ショートはテーマに沿った気の利いたオチがもとめられる。
だからかえって書くのは難しいように思う。
それをさまざまな媒体に描き分けた著者の筆力とアイデアに感服する。
本書のあちこちには、著者が人間を根本的な部分で信頼しておらず、むしろ愛すべき愚かな存在として慈しむ様子が感じられる。一方で自然や科学が必ずしも人間にとって有益ではないという哲学も見られる。
だからこそ、著者はSFをテーマに作品を書き続けたのだろう。
著者のSF史における立ち位置や、ショート・ショートの歴史などについては、本書の解説で最相葉月氏が触れている。『星新一』という評伝を発表した氏。著者についても評伝を手掛けてほしいものだ。
‘2020/01/04-2020/01/05