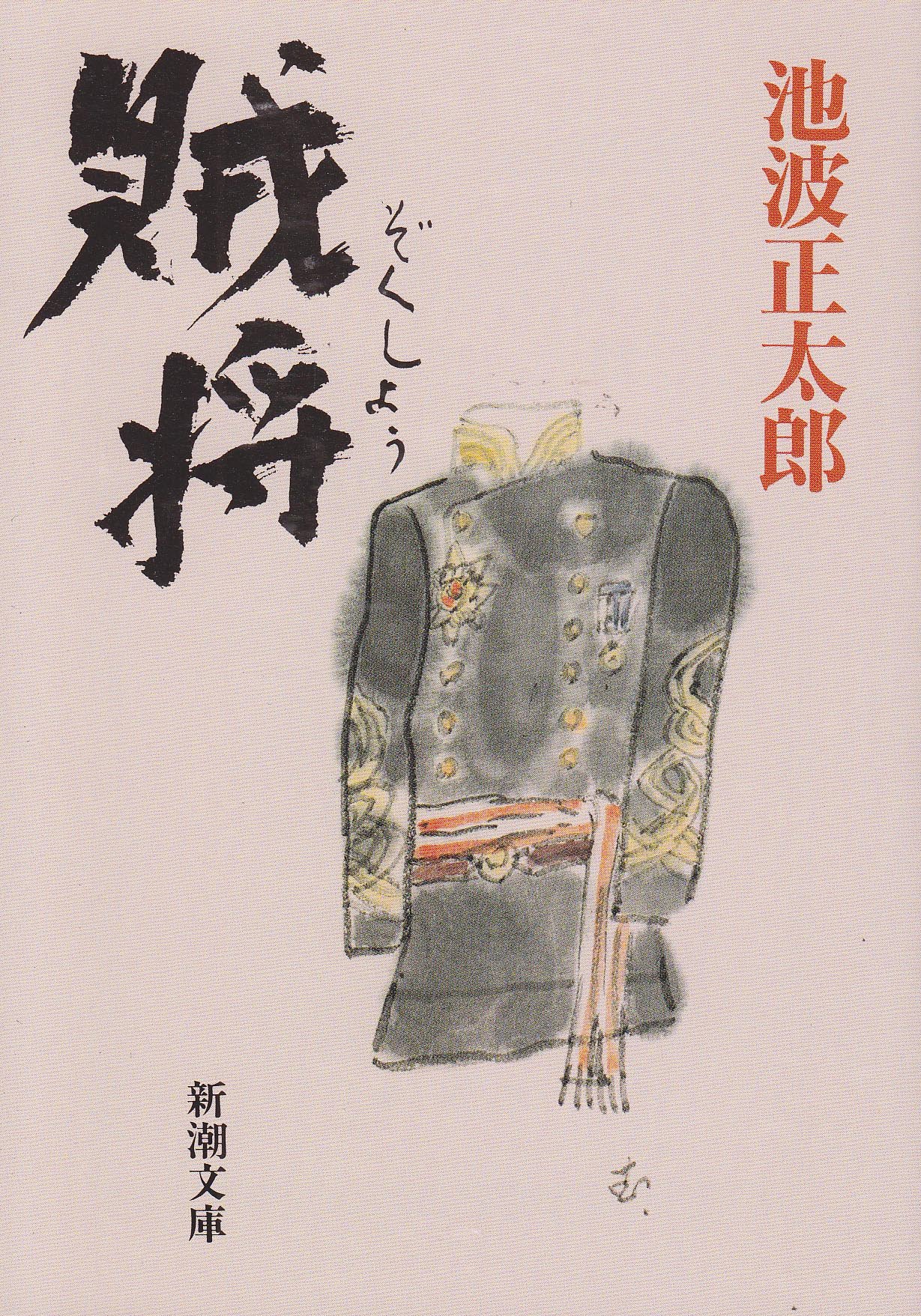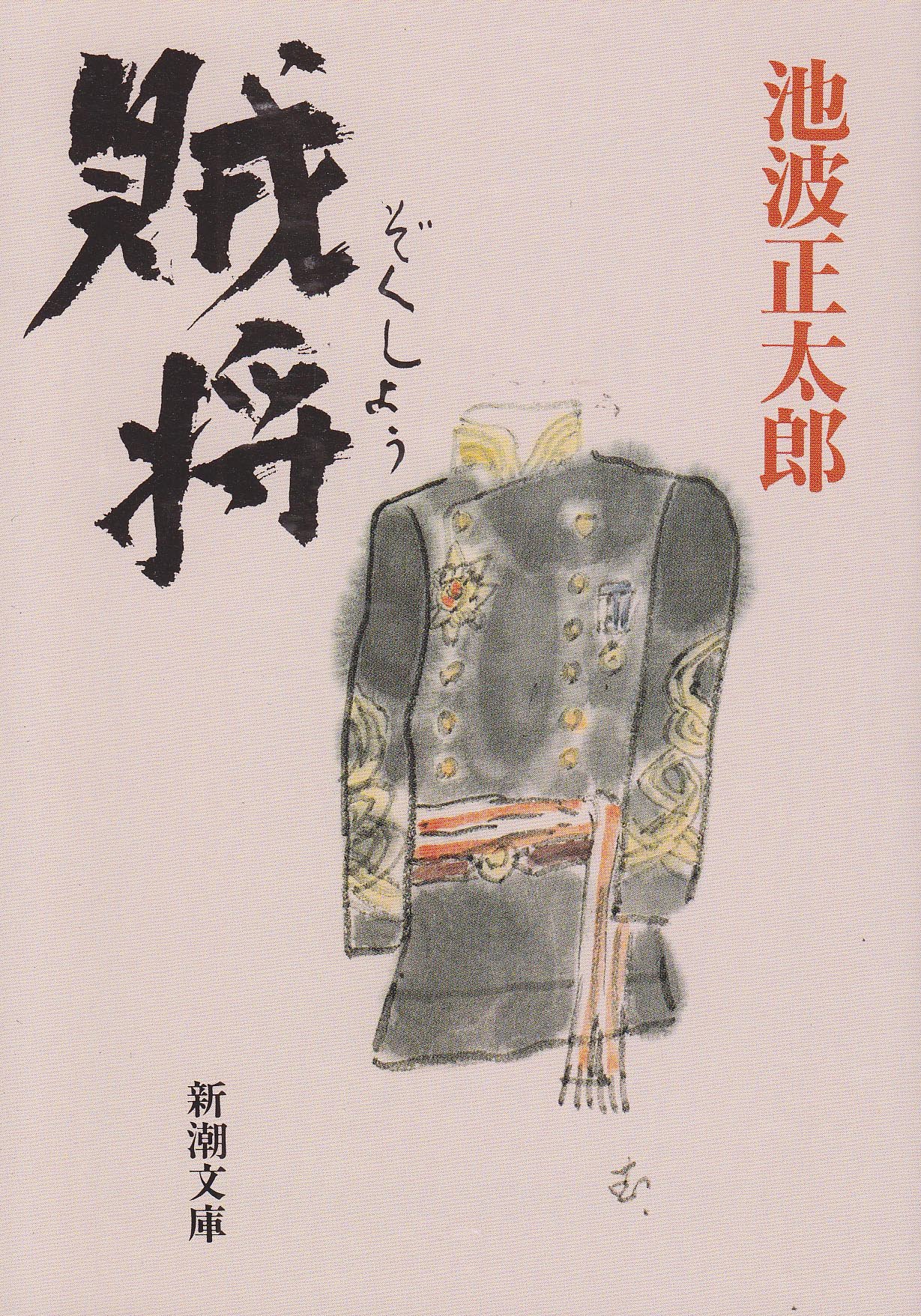先日に読んだ『立花三将伝』はとても面白かった。本書はそれに続いて読んだ一冊だ。
『立花三将伝』は、立花家の滅びを描いていた。作中の中でも史実でも、立花家は一度終わった。そして、新たな立花家の当主に就いたのが、戸次道雪とその養子である立花宗茂だ。
立花宗茂といえば関ヶ原の戦いで西軍に属し、一度は領地を没収された。その境遇から旧領に復帰した唯一の大名としてよく知られている。
その起伏に満ちた生涯を描いていているのが本書だ。
著者はさまざまな歴史上の人物を取り上げ、それを小説仕立てにする技術に長けている。
立花宗茂の生涯を小説にし、概観するには適任の方だ。
本書は、関ヶ原の敗戦後から始まる。肥後の加藤家の下で食客として過ごす中、京に出て浪人となる道を選ぶ。殿についていきたいと願う多数の家臣から一九名をくじで選び、故郷を出た一行。京では日々の糧を得るため、虚無僧に身をやつしたり、人足に出かけたりする家臣たち。皆、殿のために役に立てることに喜びを感じ、進んで労役に就く。
その時期の立花宗茂を表すとしてよく取り上げられるのが、以下の挿話だ。
家臣が干飯を作ろうと干していた飯を、雨が降り出して台無しになりつつある中、何もしなかった立花宗茂。
小事にこだわらず、大事にまい進する。将たるものはこうでなければ。小事にこだわらない立花宗茂の姿勢を示し、将の心構えを端的に表す挿話としても分かりやすい。
この挿話は浪人時代、十九人の家臣と京にいた時のものだ。何百、何千、何万の家臣を従えているならまだしも、十九人ならば私の手の届く人数だ。
少ない人数であれば、それぞれがそれぞれのことに手一杯。さらに十九人がそれぞれすべての事を差配しなければならない。だが、そのような中にあって、立花宗茂は小事にこだわらない。
将が悠揚とした姿勢を貫く事は容易ではない。ここで卑屈になってはならない。家臣たちの心を案じて同じ視点を持ち、同じように振る舞ったらそれはもう殿ではない。家臣からの信を失ってしまう。
家臣たちもそんな殿だからこそ仕えがいがあると信じてついて行く。
もちろん立花宗茂は暗愚な武将ではない。干飯が十九人の糧であることも何となく察している。その上でその様な些事にあえて手を付けないことも自分の役割だと分かっている。そして彼は自分を「作為的な道化者」として演じる道を選ぶ。
著者は、このときの立花宗茂の心中をこのように書いている。あえて家臣たちが自分に信じてついてきてくれている。そうである以上、家臣が付いて来てもらえるのにふさわしい将たる姿勢を演じよう、と。それが家臣の安心につながるのであれば良いではないか。将とは、人の上に立つものとは、案外そういうものかもしれない。同じ船に乗っていても友達のようになってはダメなのだ。
私も勤め人から独立し、経営者になってきた。そして今は人を雇用するようになった。その中で、人の上に立つ者としてのあり方は何かを考えてきた。細かいことは気にせず、器を大きく保ち続けなければ、と。
だが、実際のところはまだ私がコーディングをすることが多い。商談も私が表に出る事がほとんどだ。そうした時、小事にこだわらねば事態は進まない。
小事にかかずらう度、私は自分の未熟さを痛感する。まだまだだと。もっと大局から見るようにしなければ、と。
本書は、冒頭の挿話を描いた後、立花宗茂の幼少から語り直していく。大友家中の二大大将として知られる高橋紹運と戸次道雪。高橋家に生まれた宗茂は、やがて戸次道雪の娘誾千代と夫婦になり、戸次家の養子になる。この二大将の下、人としての生き方や筋の通し方を学んでいく。島津家の侵攻に抗して豊臣軍について戦う日々。実父は、岩屋城の戦いとして知られる激烈な戦闘の末に命を落とし、いくさ人としての死にざまを人々に刻み付けた。
やがて、時代は豊臣家から徳川の世に移る。そして関ケ原の戦い前夜へ。その時、立花宗茂は、豊臣家の恩顧を忘れぬため、あえて西軍についた。
そこから京、そして江戸での浪人生活を経て、二代将軍秀忠の御相伴衆として呼ばれる。そこで秀忠の信任を得、陸奥棚倉一万石で大名に復帰する。さらに家康が亡くなってしばらくの後、旧領の柳川への復帰を果たす。
立花宗茂は筋を通したことによって道を開いてきた。それに尽きる。
棚倉をかりそめの地とは考えず、徳川家の恩を返すために必死に励んだ。そのため、骨を埋める覚悟を家臣たちや領民に示し、必死になって内政に取り組んだ。
本書にも書かれている通り、棚倉の地形を故郷の立花山城に似ているとして鼓舞するシーンもそう。私も棚倉には訪れたが、三つのこぶの山を探したものだ。
筋を通すことも私の課題だ。私は同じことをすることが嫌いだ。昨日と今日が違わず、同じであると苦痛を感じる。
私が大名であれば、次々と領地を変えてほしいと願うかもしれない。これではいけない。ついてくる人には筋道を示してやらないと。それも太く伸びる一本の筋を。
もちろん、私も弊社の中でも筋を示そうとはしている。クラウドを担いでシステムを提供する業務を社業に据えると。そのクラウドとはkintoneだ。弊社の業務を情報処理とし、それを一本の太い道として伸ばし、その道にはkintoneと書かれている。
だが、私は決してkintoneだけに限ろうとしない。IoTやメタバースにも手を出す。他のPaaS/SaaSにも関わってゆくし、kintone Caféやワーケーションのイベントにも頻繁に参加する。
もし一本の筋だけを進むことが真理なら、さしずめ私は節操がない代表なのだろう。
本書を読み、そうした経営者としての姿勢についてあらためて考えさせられた。
おそらく私の性分は、同じことを繰り返すことを今後とも嫌い続けるだろう。昨日と同じ明日を断じて避ける事だろう。
だが、それにメンバーを振り回さぬよう、自戒しなければ。
本書は将たるものの示すあり方を私に教えてくれた。
2020/10/29-2020/10/30