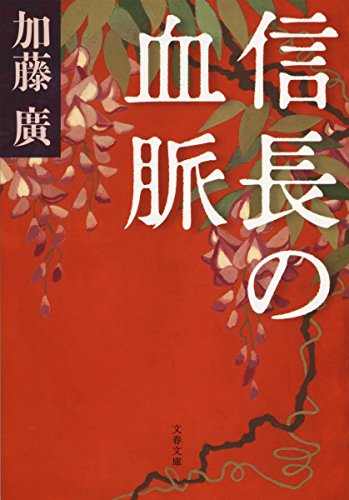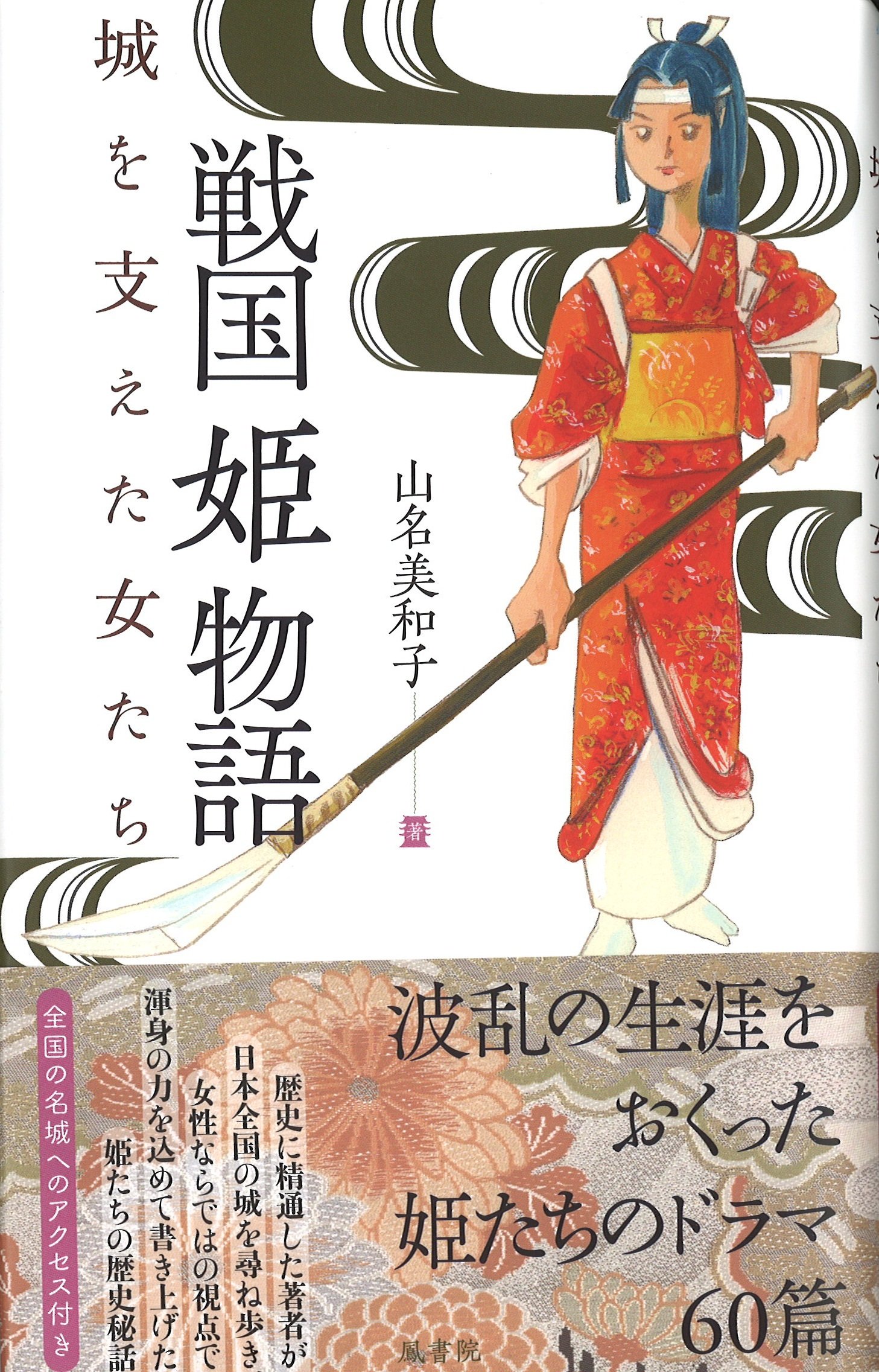
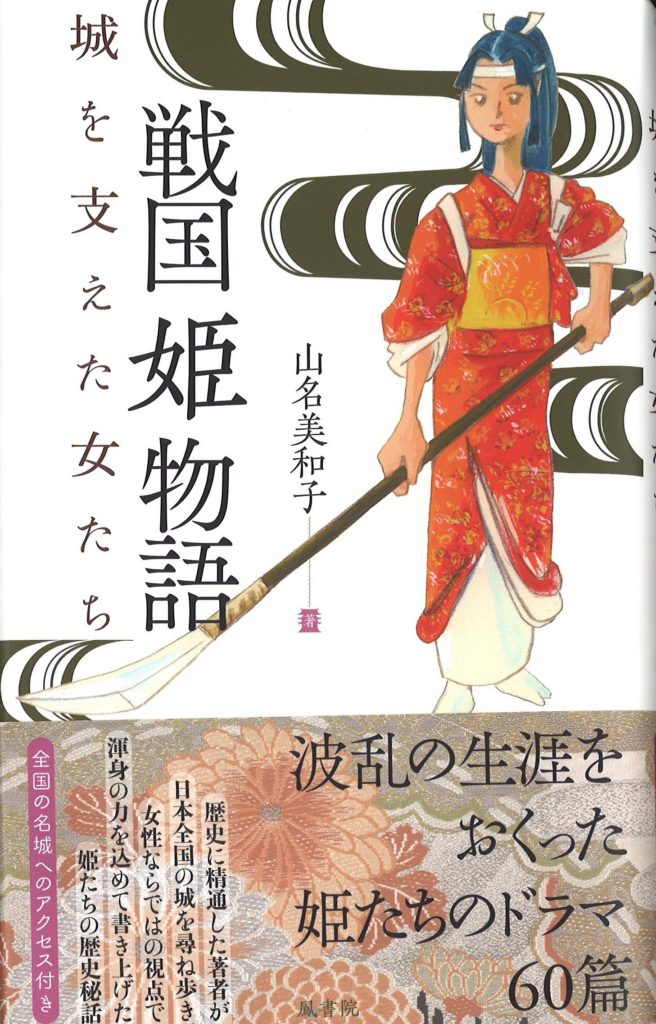
ここ数年、城を攻める趣味が復活している。若い頃はよく各地の城を訪れていた私。だが、上京してからは家庭や仕事のことで手一杯。城巡りを含め、個人的な趣味に使う時間はとれなかった。ここにきて、そうした趣味が復活しつつある。それも誘ってくれた友人たちのおかげだ。
20代の前半に城を訪れていた頃は、有名な城や古戦場を訪れることが多かった。だが、最近は比較的マイナーな城を訪れている。なぜかといえば、名城の多くは明治に取り壊され、江戸時代の姿をとどめていないことが多いからだ。そうした城の多くは復元されたもので、残念ながらどこかに人工的な印象を受ける。私は今、そうした再建された広壮な城よりも、当時の姿を朽ちるがままに見せてくれる城に惹かれている。中でも山城は、山登りを好むようになった最近の私にとって、城と山の両方をいっぺんに達成できる魅力がある。
城を訪れる時、ただ城を眺めるだけではもったいない。城の歴史や、城を舞台に生きた人々の営みを知るとさらに楽しみは増す。特に人々が残した挿話は、人が活動した場所である以上、何かが残されている。もちろん、今に伝わる挿話の多くは有名な城にまつわるものだ。有名な城は規模も大きく、大勢の人が生活の場としていた。そこにはそれぞれの人生や葛藤が数知れずあるはず。だが、挿話が多いため、一つ一つに集中しにくい。印象も残りにくい。だが、埋もれつつある古城や、こぢんまりとした古城には人もあまりいなかったため、そうした地に残された挿話には濃密な情念が宿っているように思えるのだ。
その事を感じたのは、諏訪にある上原城を訪れた時のことだ。先に挙げた友人たちと訪れたこの城は、諏訪氏と武田氏の戦いにおいて重要な役割を担った。また、ここは諏訪御料人にゆかりのある城だ。諏訪御料人は、滅ぼされた諏訪氏の出で、一族の仇敵であるはずの武田信玄の側室となり、のちに武田家を継ぐ勝頼を生んだ女性だ。自らの父を破った信玄に身を任せたその心境はいかばかりか。戦国の世の定めとして、悲憐の運命をたどった諏訪御料人の運命に思いをはせながら、諏訪盆地を見下ろす。そんな感慨にふけられるのも、古城を訪れた者の特権だ。
戦国時代とは武士たちの駆け抜けた時代であり、主役の多くは男だ。だが、女性たちも男たちに劣らず重要な役割を担っている。諏訪御料人のような薄幸の運命を歩んだ女性もいれば、強く人生を全うした女性もいる。本書はそうした女性たちと彼女たちにゆかりの強い60の城を取り上げている。
本書は全七章からなっている。それぞれにテーマを分けているため、読者にとっては読みやすいはずだ。
第一章 信玄と姫
躑躅ヶ崎館と大井婦人 / 小田原城と黄梅院 / 高遠城と松姫 / 伏見城と菊姫 / 上原城と諏訪御料人 / 新府城と勝頼夫人
第二章 信長と姫
稲葉山城【岐阜城】と濃姫 / 小牧山城と生駒吉乃 / 近江山上城とお鍋の方 / 安土城と徳姫 / 金沢城と永姫 / 北庄城とお市の方 / 大坂城と淀殿 / 大津城とお初 / 江戸城とお江 / 岩村城とおつやの方 / 坂本城と熙子
第三章 秀吉と姫
長浜城とおね / 山形城と駒姫 / 小谷城と京極龍子 / 美作勝山城とおふくの方 / 忍城と甲斐姫
第四章 家康と姫
勝浦城とお万の方 / 岡崎城と築山殿 / 浜松城と阿茶局 / 鳥取城と督姫 / 松本城と松姫 / 姫路城と千姫 / 京都御所と東福門院和子 / 宇土城とおたあジュリア / 江戸城紅葉山御殿と春日局 / 徳島城と氏姫
第五章 九州の姫
首里城・勝連城と百十踏揚 / 鹿児島城と常盤 / 平戸城と松東院メンシア / 佐賀城と慶誾尼 / 熊本城と伊都 / 鶴崎城と吉岡妙林尼 / 岡城と虎姫 / 柳川城と立花誾千代
第六章 西日本の姫
松江城と大方殿 / 吉田郡山城と杉の大方 / 三島城と鶴姫 / 岡山城と豪姫 / 常山城と鶴姫 / 三木城と別所長治夫人照子 / 勝龍寺城と細川ガラシャ / 大垣城とおあむ / 彦根城と井伊直虎 / 津城と藤堂高虎夫人久芳院 / 掛川城と千代 / 駿府城【今川館】と寿桂尼
第七章 東日本の姫
上田城と小松殿 / 越前府中城とまつ / 金山城と由良輝子【妙印尼】 / 黒川城【会津若松城】と愛姫 / 仙台城と義姫 / 米沢城と仙洞院 / 浦城と花御前 / 弘前城と阿保良・辰子・満天姫
これらの組み合わせの中で私が知らなかった城や女性はいくつかある。なにしろ、本書に登場する人物は多い。城主となった女性もいれば、合戦に参じて敵に大打撃を与えた女性もいる。戦国の世を生きるため、夫を支えた女性もいれば、長年にわたり国の柱であり続けた女性もいる。本書を読むと、戦国とは決して男だけの時代ではなかったことがわかる。女性もまた、戦国の世に生まれた運命を懸命に生きたはずだ。ただ、文献や石碑、物語として伝えられなかっただけで。全国をまんべんなく紹介された城と女性の物語からは、歴史の本流だけを追うことが戦国時代ではないとの著者の訴えが聞こえてくる。
おそらく全国に残る城が、単なる戦の拠点だけの存在であれば、人々はこうも城に惹かれなかったのではと思う。城には戦の場としてだけの役目以外にも、日々の暮らしを支える場としての役割があった。日々の暮らしには起伏のある情念や思いが繰り返されたことだろう。そして、女性の残した悲しみや幸せもあったはずだ。そうした日々の暮らしを含め、触れれば切れるような緊張感のある日々が、城を舞台に幾重にも重なっているに違いない。だからこそ、人々は戦国時代にロマンや物語を見いだすのだろう。
むしろ、本書から読み取れることは、戦国時代の女性とは、男性よりもはるかにまちまちで多様な生き方をしていたのではないか、ということだ。男が戦や政治や学問や農商業のどれかに従事していた以上に、女はそれらに加えて育児や夫の手助けや世継ぎの教育も担っていた。結局のところ、いつの世も女性が強いということか。
私が個人的に訪れたことのある城は、この中で25城しかない。だが、最近訪れ、しかも強い印象を受けた城が本書には取り上げられている。例えば勝連城や忍城など。まだ訪れていない城も、本書から受けた印象以上に、感銘をうけることだろう。本書をきっかけに、さらに城巡りに拍車がかかればよいと思っている。まだまだ訪れるべき世界の城は多いのだから。
‘2018/09/25-2018/09/25