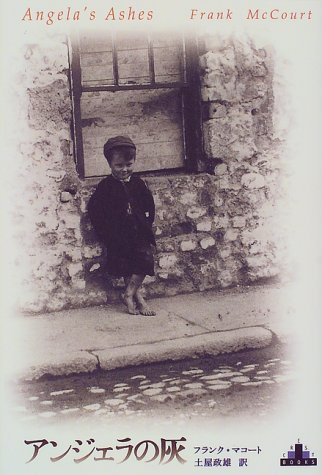
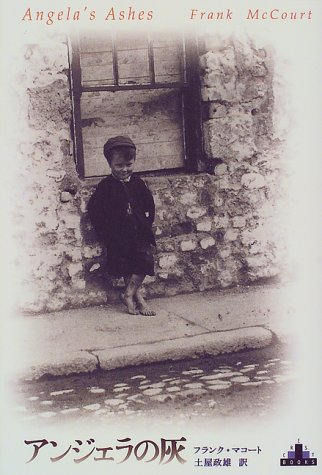
文書はピューリッツァー賞受賞作だそうだ。
伝記部門で受賞した。
1930年に生まれた著者が68歳の時に発表した自伝だそうだ。
著者は長い間教師を勤めた方で、物語を書くのは初めてだそうだ。だが、教師人生の中で英文の授業を担当してきた。あらゆる国から来た生徒たちに英語を教える手法の一つに、親の伝記を書いてみる指導を行っていたらしい。
その中で著者も、自分自身の自伝を何回も書いていたそうだ。それが本書の底になっているということを解説で知った。
冒頭にこのような一文がある。
「惨めな子供時代だった。だが、幸せな子供時代なんて語る価値もない。アイルランド人の惨めな子供時代は、普通の人の惨めな子供時代より悪い。アイルランド人カトリック教徒の惨めな子供時代は、それよりももっと悪い。」(7ページ)
アイルランドと言えば19世紀半ばのジャガイモ飢饉による人口減で知られる。人がたくさん亡くなり、アメリカなど諸外国への移民が大量に発生したためでもある。
本書のマコート一家も一度はニューヨークへ移住する。だが、すぐにアイルランドに戻ってきてしまう。
なぜか。父のマラキが無類の酒飲みだったから。
飲んだくれの父親に振り回される家族の悲劇。昔からのよくある悲劇の一形態だ。本書は父の酒飲みの悪癖が、主人公や主人公の母アンジェラを苦しめる。その悲惨な毎日の中でどのように子供たちはたくましく生き延びようとするのか。
給与を必ず持って帰ると言いながらもらったその場ですぐに飲み代に使ってしまうだらしない父。それでいて、避妊など知らないので次々と母の体内に子供を増やしていく。主人公のフランク、弟のマラキ、双子のマイクルとアルフォンサス。さらにマーガレットと名付けられた妹やオリバー、ユージーンという弟もいたが、三人は幼い頃になくなってしまう。もちろん、劣悪な環境のためだ。
幼い子供たちを育てながら、三人の子供を亡くしながら、頼りにならない夫をあてにせず生き抜こうとする母。
およそ自覚が欠けており、夫として親として頼りがいのない父。でも、子供たちにとっては父は最大の遊び相手。遊んでほしいと父を求める姿がとてもいじらしい。
子供たちも母を助けるために、クリスマスの日に金を稼ぐ。石炭が運搬される道に沿ってこぼれた石炭を拾い集める仕事。真っ黒になってびしょ濡れになって帰ってくる。息子たちが金を稼いできても、父は動かない。たとえお金がなくなっても恵みを受けるような仕事はプライドが許さないからだ。
プライドが高く、それでいて生活力がない。まさに絵に描いたようなダメ親父だ。
本書は、カトリックの文化の中で育つ主人公の物語だ。そのため、カトリックの文化に則った出来事が多く描かれる。例えば初聖体受領、さらに信心会への出席。堅信礼。
ところが、カトリック文化は酒を許容する。まるで人を救ってくれるのは神だけでは足りないとでも言うように。酒も必要だと言うように。
父はそうした背景に甘え、赤ん坊ができても気にせずに酒に溺れて帰ってくる。
主人公が10歳を過ぎる頃にはもう父は、尊敬すべき対象ではなくなっている。
私も酒が好きだ。そのため、本書の描写はとても身につまされた。
アイルランドは、今でもアイルランド・ウイスキーの産地として知られる。もちろんギネス・ビールの産地としても。
酒は百薬の長と言うが、退廃を呼び覚ます悪い水でもある。
酒の悪い側面を本書で見せられると、暗澹とした気分になる。
私は幸いにして酒にそこまで溺れずに済んだ。
本書は、酒文化の悪い面を示すには格好の教材なのかもしれない。
ちょうど本書の描かれている時代は、アメリカの禁酒法の時代だ。なぜ禁酒法が生まれたのかを知るためには、悲惨な目にあうマコート一家の様子を見れば良い。
もちろんその原因の大部分は父の意思の弱さがあるのだろう。だが、そもそも酒があるからいけないのだ、とする考えが禁酒法の根底にはある。
その一方で主人公は徐々に成長する。チフスによる入院も乗り越え、角膜炎による失明の危機を乗り越え。性に対して興味を持ち、徐々に母のために家計を手伝うようになる。
電報配達の仕事を通じ、自分の家以外のさまざまな家庭の内実を知る。そこで童貞を捨て、別の仕事(借金の督促状の執筆)を受ける。主人公にはすでにアメリカに渡る明確な目標があるので、それに向け、何で身を立てていくのかが見えてくる。それは文章を作成する能力だ。
本書は相当に分厚い本だ。だが、読み始めるとあっという間に読み終えてしまう。まさにそれこそが、主人公が培った文章作成能力の結果だろう。
絶望の中でも仕事は与えられるし、そこからチャンスは転がっている。本書は、主人公がアメリカに向かうところで終わる。
19歳の主人公が酒に興味を持つ兆しはない。おそらく父を反面教師としているからだろう。
本書には続編があるらしいが、そうではアメリカで主人公が経験したさまざまな苦難が描かれると言う。また読んでみたいと思う。
‘2020/03/01-2020/03/05


