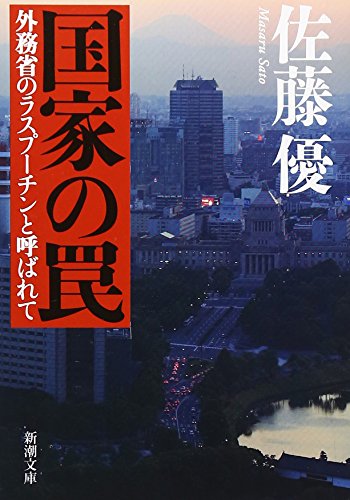
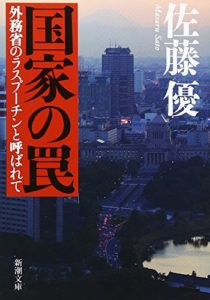
「広島 昭和二十年」のレビューで、淡路島の学園祭のバザーでたくさんの本を入手したことは書いた。本書もそのうちの一冊だ。そして本来なら、私に読まれるまで本書は積ん読状態になっていたはずだ。ところが、本書が読まれる日は案外早く訪れた。
そのきっかけはプーチンロシア大統領の来日である。来日したプーチン大統領は、安倍首相との首脳会談に臨んだ。当然、首脳会談で焦点となるのは北方領土問題だ。プーチン大統領は、日露間に領土問題は存在しないと豪語する。だが、われわれから見ると領土問題が横たわっていることは明白で、プーチン大統領の一流の駆け引きがそう言わせていることも承知している。そして、その駆け引きを読み解けるわが国の第一人者が著者であることは今さら言うまでもない。私は少し前に入手した本書を手に取った。
プーチン大統領が駆け引きを駆使するように、日本政府も本音と建前を使い分ける。あくまで北方領土は日本のものであると主張しつつ、ロシアによる統治が敷かれている現実も直視しなければならない。ただ、北方領土におけるロシアの主権を認めては全てが水の泡になってしまう。だから慎重にことを進めるのだ。国際法の観点で、外交の観点で、条約の観点で。ロシアによる実質の統治を認識しつつ、その正統性は承認しないよう腐心しつつ。だからビザなし交流といった裏技があるわけだ。ビザの手続きを認めると北方領土がロシアの統治下にあると認めたことになるため。
その日本政府による苦心はムネオハウスにも現れている。ムネオハウスとは、元島民が国後島を訪問した時のための現ロシア住民との友好施設だ。ムネオハウスは、実質的なロシアの領土となっている北方領土に援助する物証とならぬよう、また、ロシアの建築法に抵触して余計な政治的問題を招かぬよう、あえて簡素に作られているという。
こういった配慮や施策はすべて鈴木宗男議員の手によるものだ。外務省に隠然たる力を及ぼしていた鈴木議員は、外務省への影響力を持ちすぎたがゆえに排除される。その排除の過程で最初に血祭りに挙げられたのが著者だ。本書は著者が被った逮捕の一部始終が収められている。
当時の報道を思い返すと、あれは一体なんだったのか、と思える騒動だった。あれから十年以上が過ぎたが、鈴木氏は新党大地を立ち上げた。党を立ち上げる前後にはテレビのバラエティー番組でも露出を増やした。タレントとしても人気を得た。著者はすっかり論客として地位を得ている。結果として、検察による逮捕は彼らの議員生命や外交官生命を断った。だが、社会的地位は奪ってはいない。それもそのはずで、逮捕自体が国策によるもの。言い換えると鈴木氏が持っていた外務省への影響力排除のための逮捕だったからだ。
著者は本書で国策捜査の本質を詳しく書く。
と著者の取り調べを担当した西村検事とのやり取りは、とてもスリリング。国策捜査であることを早々に明かした西村検事と著者の駆け引きが赤裸々に描かれている。とても面白いのだ、これが。
例えていうなら完全に舞台を自分のコントロールにおきたい演出家と、急きょ裏方から役者に引っ張り出されたにわか役者の対決。双方とも自らの解釈こそがこの舞台に相応しいと舞台上で争うような。舞台上とは取調室を指し、演出家は西村検事を指す。そして舞台に引っ張り出されたにわか役者とは著者を指す。演出家とにわか役者はけんかしているのだけれども、ともに協力して舞台を作り上げることには一致している。当然、普通の刑事事件の取調べだとこうはいかない。容疑者と刑事の利害が一致していないからだ。本書で描かれるのはそんな不思議な関係だ。
それにしても著者の記憶力は大したものだ。逮捕に至るまでの行動や、取調室での取調の内容、法廷での駆け引きの一部始終など、良く覚えていられると思うくらい再現している。著者は記憶のコツも本書で開かしている。イメージ連想による手法らしいが圧巻だ。
もうひとつ見習うべきは、著者がご自身を徹底的に客観的に見つめていることだ。自分の好悪の感情、官僚としての組織内のバランス、分析官としての職能、個人的な目標、カウンターパートである検察官への配慮。それら全てを著者は客観視し、冷静に見据えて筆を進める。
著者の強靭な記憶力と、文筆で生きたいとの思い。それが著者を駆り立て、本書を産んだのだろう。それに著者の日本国への思いと、鈴木氏への思い。これも忘れてはならない。
結果として本書は、あらゆる意味で優れた一冊となった。多分、ロシアとの北方領土問題は今後も長く尾をひくことだろう。そしてその度に本書が引用されるに違いない。そして私も交渉ごとのたびに、本書を思い返すようにしたいと思う。
‘2016/12/17-2016/12/22


