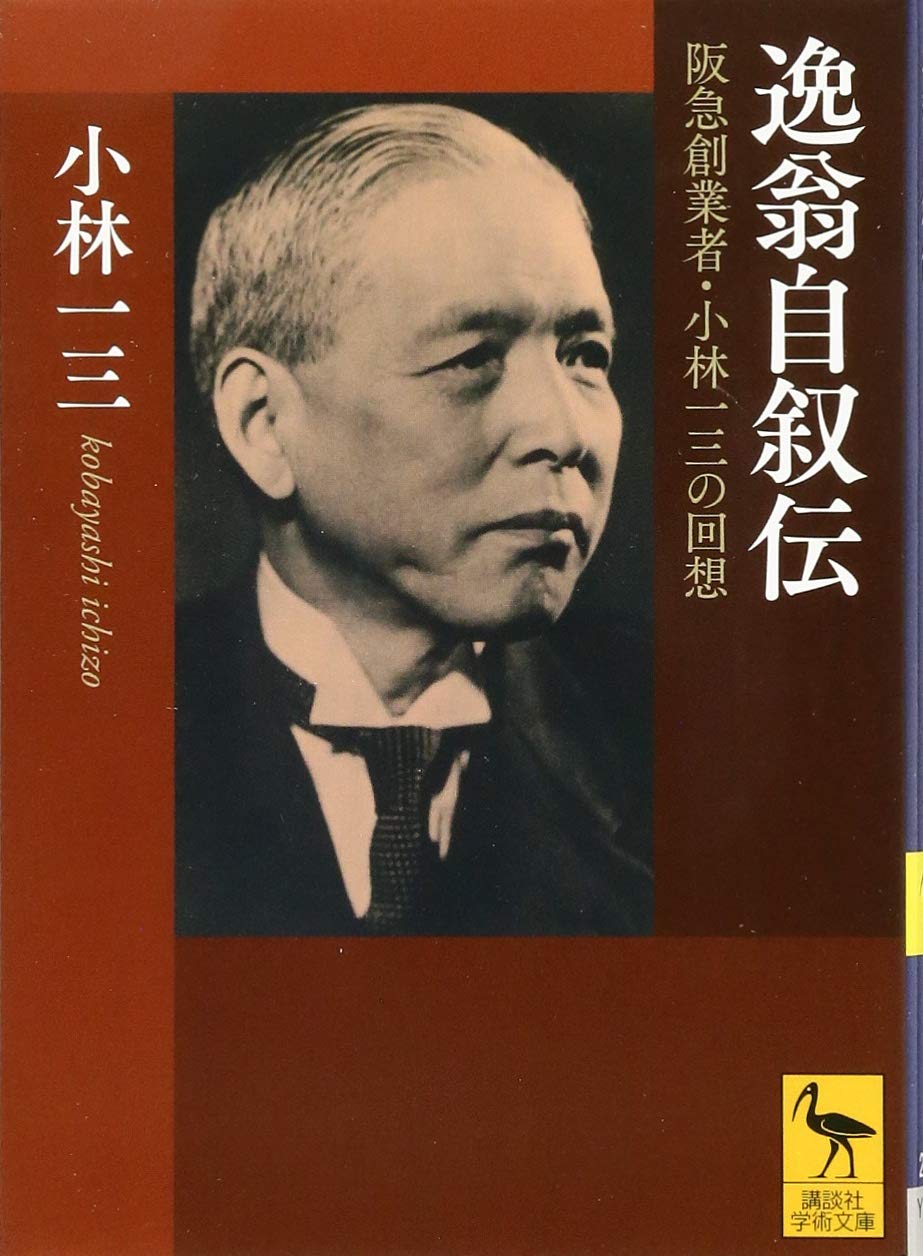
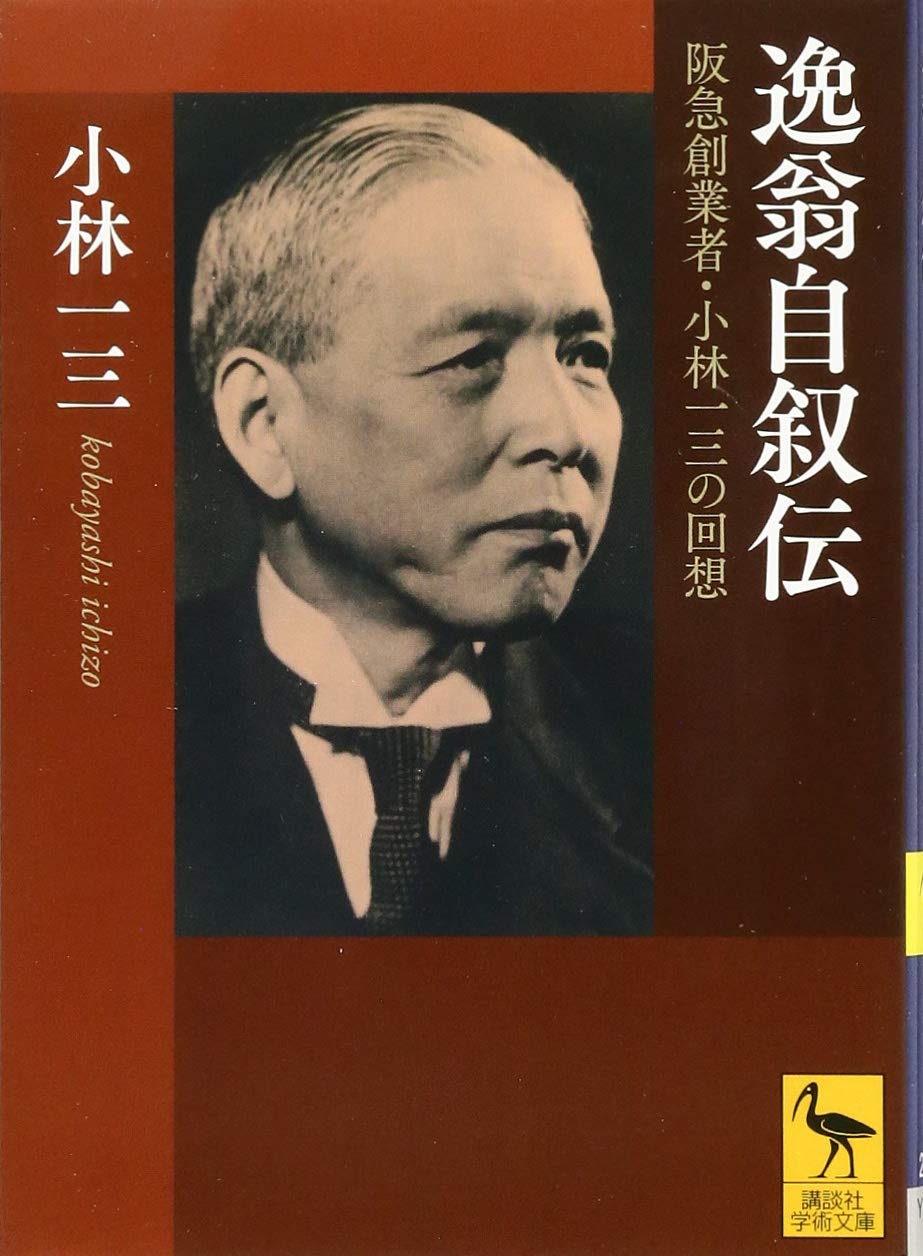
本書こそまさに自伝と呼ぶべき一冊。本当の自伝を読みたいと願う読書人に薦められる一冊であると思う。
阪急電鉄を大手私鉄の雄に育て上げただけではなく、宝塚歌劇団や東宝グルーブ、阪急ブレーブスの創設など興業の世界でも日本で有数の企業を育て上げた立志伝中の人。
線と点からなる鉄道を面の事業として発展させ、鉄道を軸にした都市開発や地域開発に先鞭をつけたアイデアマン。
独創的な着眼点でわが国の近代企業史に燦然と輝く経済人。
小林一三。ロマンチストであり続けながら経営の世界でも実績と伝説を残した希有の人物である。
明治以降、わが国の財界は多くの人物を輩出してきた。それら錚々たる人物列伝の筆頭に挙げられる人物こそ、小林一三ではあるまいか。
本書はその小林一三が自らしたためた自伝だ。しかも財界人が自らを思い返したただの随想ではない。かつて作家を目指し、新聞に連載小説を受け持っていた人物が書く自伝である。それが本書を興味深い一冊にしている。
小林一三が残した遺産の多くは、幼い頃の私にとっておなじみのものだった。阪急電車。西宮スタジアム。西宮球技場。宝塚ファミリーランド。宝塚大温泉。
私の人間形成において、おそらく小林一三が残した影響はいまだに残っているに違いない。
だが、このブログでも何度も書いたとおり、私は今の宝塚歌劇団の経営姿勢に良い印象を持っていない。
その一方で、小林一三が宝塚少女歌劇団を創設したときの純粋な志まで否定するつもりはない。少女歌劇を立ち上げるにあたっての試行錯誤は、小林一三が作家として挫折した思いを考えると尊い。
不評で廃業したプールの上に蓋をした「ドンブラコ」から始まったタカラヅカは、いくつもの試練を乗り越え、100年続く劇団に育った。その功績は小林一三のものだ。
自ら戯曲を書き、作詞まで手がけた異彩の人を抜きにしてタカラヅカは語れない。
小林一三は「私が死んでもタカラヅカとブレーブスは売るな」と言い残したと伝えられている。が、今の阪急グループを見て小林一三は何を思うだろうか。ロマンチストのアイデアがふんだんに盛り込まれたはずの事業は、企業を存続させるための論理の前にはかなくついえた。しかも阪急自身の手によって。
阪急ブレーブスはとうの昔に身売りされた。タカラヅカも少しずつ公演の重心を有楽町に移しつつある。宝塚ファミリーランドはなくなり、跡地にはどこにでもある商業施設がのさばっている。
本稿をアップする三週間ほど前、宝塚ファミリーランド跡地の横を車で走り抜けた。が、何の感興も湧かなかった。無惨と言うしかない。
今の阪急グループは大企業となった。つまり、株主や投資家の期待に応え、従業員を養わねばならない。それはわかる。だが、今の阪急グループにワクワクする感じを期待する事は出来ない。
経営が現実の中に縛られてしまっているのだ。経営が現実の中に逃げ込むほど、ロマンチストの思いを経営に色濃く反映させた小林一三の凄さは際立つ。
私は小林一三には尊敬の念しかない。
文学で身を立てようとして挫折し、実業界で才能を発揮した転身の妙。それも私には強烈な魅力として映る。
同じ経営者として、小林一三のユニークな経歴から学ぶべきことは多い。憧れと言ってもよい。
その型破りな発想の秘訣はなんだろうか。その発想の源泉はどこにあるのか。
その答えは、著者が自分を語る本書に載っているはずだ。小林一三が若き日の無軌道な振る舞いの中に。
著者は自分の幼いころからの日々を振り返り、その中で犯した過ちも包み隠さず書いている。
大学を十二月に卒業し、三井銀行に就職が決まった後も、入社式や卒業式もほったらかしで熱海に逗留しつづけ、そこで知り合った女性のことが忘れられず、ズルズルと出社を延ばして、結局三カ月も出社しなかったという。今の世では絶対に許されない行いだろう。
考えてみればのどかな時代ではある。現代の方が物質的にも技術的にもきらびやかで洗練されている。技術も進歩し生活も豊かである。が、実は日本人の精神力は半比例するように硬く貧しくなり、衰えているのではなかろうか。小林一三の破天荒な青年時代はそんなことさえ思わせる。
本書で語られる前半生の著者を見ていると、自分の核がない代わりに、降ってくる話を拒まない。自らの天分と天職に巡り合うまで、自らの境遇を定めずにいる。まず飛び込んでから身の振り方を考えている。
その姿勢こそが著者の大器を晩成させたのだろう。
その姿勢は、上にも書いた通り、本気で作家を目指していた著者の資質から導かれたものだろう。
慶応大に在学中の著者が山梨日日新聞に連載していた小説「練絲痕」も本書には収められている。
いくら当時の文壇が発展途上だからといって、新聞に連載を持ったことは大したことだ。著者は半ば職業作家だった。そして、そのような経歴の持ち主で、かつ著者ほどの実績を打ち立てた経営者を私は知らない。
著者の前半生は、謹厳な経営者とは真逆だ。無頼派と呼ぶにふさわしい乱脈なその姿は、作家が文士と呼ばれた頃のそれを思わせる。
著書がすごいのは、そこから生まれ変わったかのように経営に目覚めたこと。そして、経営にしっかりと若き日の自由な発想を活かしたことにある。
それでいながら、鉄道の開通にあたって資金繰りの厳しい時に見せた辛抱強さなど、それまでの著者とは打って変わった人間性を見せた事も著者の人生を決定づけたはずだ。
こうした著者の動きを念頭におき、仮に著者が同じ人格を持っていたとしよう。ここでもし著者が世間に合わせて勤め人であろうとし、冒険を控えていたらどうだっただろう。あくまでも仮定でしかないが、阪急で成し遂げたような多角化の発想は生まれなかったのではないだろうか。
自由な発想の持ち主が心の赴くまま、自由な振る舞いにおぼれ、存分に自らの心魂を理解したからこそ、経営者になった著者の脳内には発想の豊かな泉が涸れずに残ったのではないかと思う。
今のわが国の停滞が叫ばれて久しい。
その理由を画一的な学校教育に求める人も多い。
だが、同じくらい企業文化の中にも画一化の罠が潜んでいるように思う。
本書を読み、経営者としての目標の一つに著者を設定した。
2020/11/7-2020/11/10



