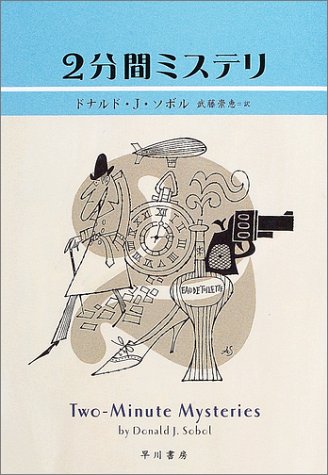
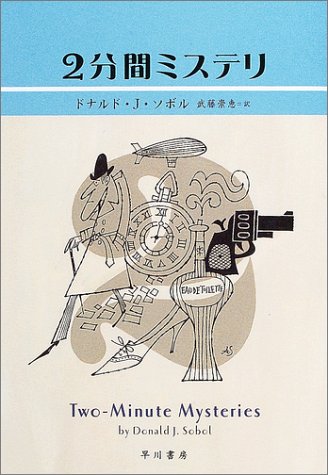
私は子供の頃から、ミステリーを読んでいる。
小学生の頃は、少年探偵団モノや、ルパンシリーズ、ホームズシリーズなどの他にも名作とされた世界の推理小説を読んだ。
中学生になってからは赤川次郎氏の一連の作品や、西村京太郎氏の著作にもかなりお世話になった。
子どもの頃の私は、それらの鉄板のシリーズの他にもさまざまな本に食指を延ばしていたように思う。私が覚えているのはマガーク少年探偵団などだ。
だが、当時もよく知られていたという「少年たんていブラウン」のシリーズについては読んだ記憶がない。そもそも当時はシリーズ自体を知らなかったように思う。
「少年たんていブラウン」のシリーズを知ったのは、本書のレビューを書くにあたり、著者のことを調べてからだ。著者は「少年たんていブラウン」の生みの親として知られていたようだ。
私は「少年たんていブラウン」は読まぬまま、大人になってしまった。
だが、前述のマガーク少年探偵団や、コロタン文庫シリーズなどの子供向けに書かれた推理関連の本をさまざまに読んだことは覚えている。
そうした本の中には、もっぱら、推理クイズを収めていたものがあった。
なぞなぞよりは一段高尚な雰囲気。子供の頃はそうした本も随分と楽しんだ覚えがある。
本書を読み、そうした子どもの頃の読書の思い出が蘇った。
本書に収められている2分間ミステリの数は七十一編にもなる。
その一編ごとに、ほぼ見開き二ページにわたって状況が描かれ、謎が読者に提示される。
その謎はもちろん明かされるが、ご丁寧なことに答えはすぐには分からないように工夫されている。
次の編の末尾に上下が逆さまに印字されていれば、うっかり答えを知ってしまうこともない、という配慮だ。
冒頭に「読者の皆さんへ
クイズの答えは、うっかり目に入ってしまわぬよう、
万全を期して天地逆に刷ってあります(印刷ミスで
はありませんので念のため)。
と言う注意書きがあるのが良い。
各編の内容は、二ページのほとんどで事件が描かれる。そして状況をみてとったハレジアン博士が、最後に放つセリフで、裏の秘密を見抜いていることを示す。
その直後になぜ博士がそう思ったのか、という問いが読者に対して提示される。
七十一編のほぼ全てがそのように構成されている。
だが、それだけだと単調になってしまう。
そこで著者は、二ページの短い中で単調にならぬよう、筋立てと人物と事件と謎を作り込む。
その職人芸のような技が本書の読みどころだ。
著者の技の一つは、登場人物を多様にする工夫を凝らしていることだ。
もちろん、どの編にもハレジアン博士が登場し、博学を示し、読者よりも先に謎を解く構成には変わりない。
それにも関わらず、事件が起きるタイミングや時期、場所、ハレジアン博士の関わり方に工夫を凝らすことで、各編に変化を生じさせている。
登場人物は複数回登場する人物は以下の通りだ。ウィンターズ警視や資産家のシドニー夫人、ハレジアン博士のデートのお相手であるオクタヴィア、儲け話に騙されやすいバーティ・ティルフォード、たれ込み屋ニック。
そうした人物が登場する筋書きは、よくある殺人事件の展開も多い。一方でそれ以外の趣向を凝らした話も多く収められている。
おそらく『名探偵コナン』も『金田一探偵の事件簿』も、本書で示された単調にならないための工夫の影響は大きく受けているはずだ。
本書にはイラストがない。すべて文字だけだ。
つまり、読者がやれることとは、文字に記された地の文とセリフから矛盾を見つけることだけなのだ。
これが案外と難しい。解けるようで、まんまと著者の仕込んだ謎を見落としていることがある。私も半分以上は答えを頼ってしまった。
それはすなわち、読解能力の問題だ。
読解能力とは、単に文の意味を理解するだけではない。そこに書かれた事物の背後に横たわる関係にまで想像力を膨らませる必要がある。論理的な思考力が求められる。
それは当たり前のことだが、探偵や刑事には必須の能力だ。
だが、探偵や刑事だけではない。論理的な思考とは、普通の仕事にも必要な能力ではないだろうか。
文章に記された各単語の背景に隠された関係を結びつけ、その関係の整合性を判断する。矛盾があれば、状況とセリフのどこかに間違いかウソがある。
実は私たちは、ビジネス文章を読む際、そうした作業を無意識の内に行っている。そうみるべきだ。
ビジネス文書にかぎらず、日常生活で目にする景色のすべてからそうした論理を無意識に理解し、日常生活に役立てているのが私たちだ。
いわゆるロジカル・シンキングとも言われるこの能力は、日本ではそれほど要求されない。が、仕事の中ではとても重要な要素であることは間違いない。
そしてわが国において、論理的な思考を訓練する機会が義務教育の間に与えられることはほぼない。
そのことは、以前から識者によって唱えられている通りだ。
上にも挙げた通り、子供向けには本書やその類書のような推理クイズが出されている。今もたくさんのジュニア向けの推理ものが出版されている。
それなのに、もっともそうした能力が求められる大人向けには、本書のような書物があまりない。
本書は大人になった読者にとっても論理的な思考、つまりロジカル・シンキングを養える良い本だと思う。
むしろ、惰性で文章を読む癖がついてしまっている大人こそに本書を薦めたい。
‘2019/01/30-2019/01/31




