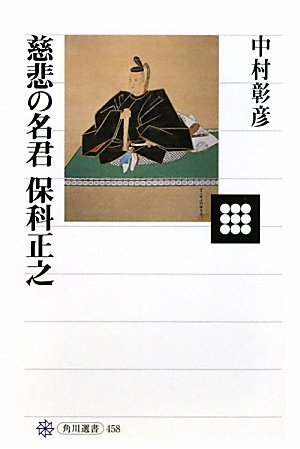
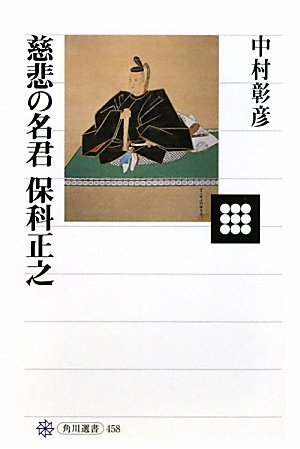
上杉鷹山、細井平州、二宮尊徳、徳川光圀。
2016年の私が本を読み、レビューを書いてその事績に触れた人物だ。共通するのは皆、江戸時代に学問や藩経営で名を成した方だ。
だが、彼らよりさらにさかのぼる時代に彼らに劣らぬほどの実績をあげた人物がいる。その人物こそ保科正之だ。だが、保科正之の事績についてはあまり現代に伝わっていない。保科正之とはいったい何を成した人物なのだろうか。それを紹介するのが本書だ。本書によると、保科正之とは徳川幕府の草創期に事実上の副将軍として幕政を切り回した人物だ。そして会津藩の実質の藩祖として腕を振るった人物でもある。今の史家からは江戸初期を代表する名君としての評価が定まっている。
ではなぜ、それほどまでに優れた人物である保科正之の業績があまり知られていないのだろうか。
その原因は戊辰戦争にあると著者は説く。
2013年の大河ドラマ「八重の桜」は幕末の会津藩が舞台となった。幕末の会津藩といえば白虎隊の悲劇がよく知られている。なぜ会津藩はあれほど愚直なまでに幕府に殉じたのか。その疑問を解くには、保科正之が会津藩に遺した遺訓”会津家訓十五箇条”を理解することが欠かせない。”会津家訓十五箇条”の中で、主君に仕えた以上は決して裏切ることなかれという一文がある。その一文が幕末の会津藩の行動を縛ったといえる。以下にその一文を紹介する。
一、大君の儀、一心大切に忠勤に励み、他国の例をもって自ら処るべからず。
若し二心を懐かば、すなわち、我が子孫にあらず 面々決して従うべからず。
明治新政府からすれば、最後まで抵抗した会津藩の背後に保科正之が遺した”会津家訓十五箇条”の影響を感じたのだろう。つまり、保科正之とは明治新政府にとって封建制の旧弊を象徴する人物なのだ。それは会津藩に煮え湯を飲まされた明治新政府の意向として定着し、新政府の顔色をうかがう御用学者によって業績が無視される原因となった。それが保科正之の業績が今に至るまで過小評価されている理由だと思われる。
2016年、本書を読む三カ月前に私は会津の近く、郡山を二度仕事で訪問した。そこで知ったのは、会津が情報技術で先駆的な研究を行っていることだ。私が知る会津藩とは、時代に逆らい忠義に殉じた藩である。そこには忠君の美学もあるが、時代の風向きを読まぬかたくなさも目につく。だが、情報産業で先端をゆく今の会津からは、むしろ時代に先んずる小気味良さすら感じる。今や会津とかたくなさを結びつける私の認識が古いのだ。
私がなぜ会津について相反するイメージを抱くのか。その理由も本書であきらかだ。会津藩の草創期を作ったのが保科正之。公の業績は、それだけにとどまらない。本書の記載によれば保科正之こそ江戸時代を戦国の武断気風から文治の時代へと導いた名君であることがわかる。つまり、保科正之とは徳川260年の世を大平に導いた人物。そして、時代の風を読むに長けた指導者としてとらえ直すべきなのだ。そんな保科正之が基礎を作った会津だからこそ、進取の風土に富む素地が培われているのだろう。
冒頭に挙げた上杉鷹山のように藩籍返上寸前の藩財政を持ち直させた実績。水戸光圀のように後の世の学問に役立つ書を編纂した業績。保科正之にはそういったわかりやすく人々の記録に刻まれる業績が乏しい。ただでさえ記憶に残りにくい保科正之は、明治政府から軽んじられたことで一層実績が見えにくくなった。そう著者は訴える。
さらに、保科正之は徳川四代将軍の補佐役として23年間江戸城に詰めきりだった。その一方で藩政にも江戸から指示を出しながら携わり続けた。幕政と藩政の両方で徳川幕府の確立に身骨を注いだ生涯。また、保科正之が将軍の補佐にあたった時期は、その前の知恵伊豆と呼ばれた松平信綱の治世とその後の水戸黄門こと徳川光圀の治世に挟まれている。その間に活躍した保科正之の業績が過小評価されるのも無理もない。
それゆえに著者は保科正之の再評価が必要だと本書で訴える。そして本書で紹介される保科正之の業績を学べば学ぶほど、保科正之とは語り継がれるべき人物であったことが理解できる。冒頭に挙げた人々に負けぬほどに。
保科正之が幕政に携わったのは、島原の乱が終わってからのことだ。秀忠、家光両将軍による諸家への改易の嵐も一段落した頃だ。戦国時代の武断政治の名残を引きずっていた徳川幕府が文治政治へと方針を変える時期。改易が生んだ大量の浪人は、文治に移りゆく世の中で武士階級が不要になった象徴だ。それは武士階級の不満を集め、由井正雪による慶安事件を産み出す原因となった。そんな社会が変動する時代にあって三代家光は世を去る。そして後を継ぐ家綱はまだ十一歳。補佐役が何よりも求められていた時だ。保科正之の政策に誤りがあれば、江戸幕府は転覆の憂き目を見ていたこともありうる。
また、正之の治世下には明暦の大火が江戸を燃やし尽くした。その際にも、保科正之が示した手腕は目覚ましいものがあったようだ。特に、燃え落ちた江戸城天守閣の処遇について正之が果たした役割は大きい。なぜならば正之の意見が通り、天主はとうとう復元されなかったからだ。今も皇居に残る天守台の遺構。それは、武断政治から文治政治への切り替えを主導した正之の政策の象徴ともいえる。また、玉川上水も正之の治世中に完成している。本書を読んで2か月後、私は羽村からの20キロ弱を玉川上水に沿って歩いた。そのことで、私にとって保科正之はより近い人物となった。
では、幕政に比べて藩政はどうだろう。本書で紹介される藩政をみると、23年も江戸に詰めていたにしては善政を敷いた名君といえるのではないだろうか。高齢者への生涯年金にあたる制度など、時代に先んじた視点を備えていたことに驚く。おそらく正之が副将軍ではなく、上杉鷹山のように窮乏藩を預かっていたとしてもそれなりの名を残したに違いない。
結局、保科正之の偉大さとはなんだろうか。確かに若い将軍を助け、徳川幕府を戦国から次の時代につなげたことは評価できる事績だ。だが、それよりも偉大だったのは時代の潮目を見抜く大局的な視点で政治にあたったことではないか。
本書は、保科正之の生い立ちから書き起こすことで、その大局的な視点がいつ養われたのかについても触れている。保科正之は秀忠が大奥の側室に手をつけ産まれた。そのため秀忠の正室である於江与の方をはばかり、私的には認知、公的には非認知、という複雑な幼年期を過ごす。そして於江与の方から隠されるように武田信玄の娘見性院に養育され、一度は甲斐武田家の再興を託される立場となる。その結果、保科正之は武田家の有力家臣だった保科家を継いだ。正之に思慮深さと洞察力を与えたのも、このような複雑で幼い頃の経験があったからだろう。また、武田家が長篠の戦で新戦術である鉄砲に負け没落したこと。それも大局的な目を養うべきとの保科家の教訓として正之にこんこんと説かれたのだと思う。
それゆえに、正之にしてみれば自分の遺した”会津家訓十五箇条”が子孫から大局的な視点を奪ったことは不本意だったと思う。正之が”会津家訓十五箇条”を残した時期は、まだ戦国時代の残り香が世に漂っており、徳川体制を盤石とすることが優先された。そのため、公の残した”会津家訓十五箇条”は200年後の時代にはそぐわないはずだ。だが、それは遺訓の話。保科正之その人は時代の変化に対応できる人物だったのではないか。だから今、会津が情報化の波に乗っていることを泉下で知り、喜んでいることと願いたい。
保科正之の生涯から私たちが学べること。それは大局的な視点を持つことだ。そして彼の残した遺訓からの教訓とは、文章を残すのなら、時代をこえて普遍的な内容であらねばならないことだ。それは、私も肝に銘じなければならない。あまた書き散らす膨大なツイートやブログやウォールの文章。これらを書くにあたり、今の時代を大局的に眺める努力はしているだろうか。また、書き残した内容が先の時代でも通じるか自信を持っているか。それはとても困難なことだ。だが、保科正之の業績が優れていたのに、会津藩が幕末に苦労したこと。その矛盾は、私に努力の必要を思い知らせる。努力せねば。
‘2017/01/15-2017/01/15


