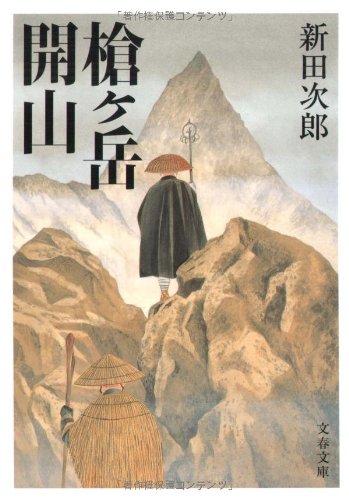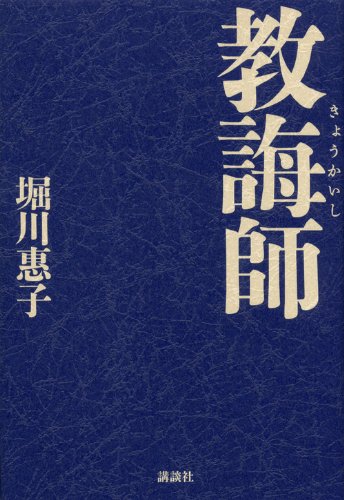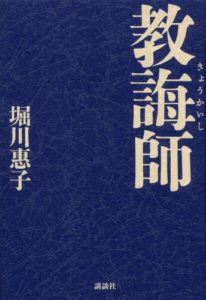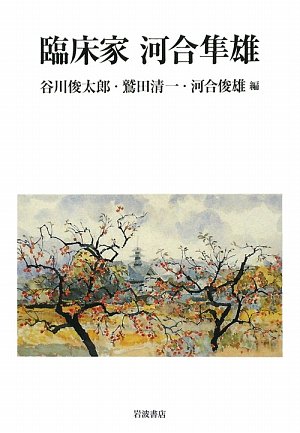
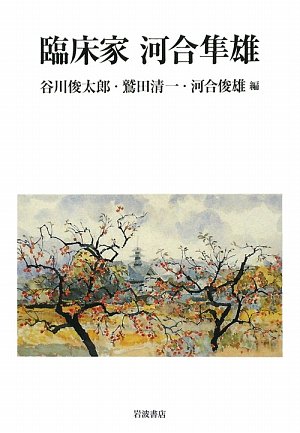
私が河合隼雄氏の著作をあれこれと読んでいたのは20代の前半の頃だ。どうやって生きて行くのか、どうやって身を立てるのかもわからずにいた私の迷走の時期。当時の私はそもそも自分の心さえ持て余していた。他人の心を理解する以前に、自分が何を欲しているのかもわからなかった。それでいて、安易に社会の流れに乗ることをかたくなに拒んでいた。そんな私が社会に入れるわけもない。人生の意味を掴みかねていた私は、完全に宙に浮いていた。いつになれば這い上がれるのか、どこに行けばたどり着けるのか。その答えはどこにもなく、救いのかけらも感じられない毎日。私はそれらの答えを純文学の諸作品や心理学に求めようとした。当時は河合氏の著作に限らず心理学関連の書物を手当たり次第に読んでは、自分の心の動きをつかみ、社会にうごめく人々の心のありようをつかみ、どうすれば社会に出られるのかを模索していた。
そんな手負いの私に、河合氏のスタンスは新鮮に映った。「わかりませんなあ」というセリフ。第一人者でありながら無知を恥じることなくそれを認め、己を低くする。本を何冊も著し、高名であったにもかかわらず、無知に関して潔い。河合氏のその姿勢は、当時の私にとても影響を与えた。今の私は仕事で人に教えたりすることも多い。問われることもある。でも、わからない時はわからない、というようにしている。河合氏のように。まだ「わかりませんなあ」という河合氏の口調は真似できないけれども。
悩みの多かった私は、いつしか上京し、職に就き、家族をもち、家の問題で揉まれ、成長していった。それにつれ、私が河合氏の本だけに限らず、心理学の本を読む機会は減っていった。私が河合氏の亡くなったことを知ったのは、氏が亡くなられて翌々年ぐらいのこと。河合氏の死に気づかないほど、上京して以降の私は、心理学に救いを求めることなく。生きていけるようになっていた。多分、私は誰もが青年期にぶつかるであろう危機をいつのまにか克服できていたのだろう。
今、私は年頃の娘を二人養っている。二人とも難しい時期だ。多分、若い私が感じたような世の中の矛盾や人の関係に悩み、この先も苦しんでいくことだろう。人生の意義が何なのかについての疑問にもぶち当たってゆくに違いない。そこで私がどう助言してやれるのか。そのためには再び河合氏の力が必要だ。家族だけではない。仕事で知り合った方、親交を結んだ方に何ができるのか。単なる技術の継承や、世過ぎ身過ぎのノウハウを伝えるほかに何ができるのか。
ここ一年半ほど、私が参加している地元のランチ会がある。ある時、その中で学校のいじめを語り合う機会があった。私はいじめられた経験を持っている。そして、娘たちや妻にも同様の経験がある。自分の力でその時期を耐え抜き、やり過ごした私や妻や娘たちはいい。だが、やり過ごすすべを知らずに自死を遂げる子どもや若者の存在。辛い気持ちになる。大人ですら、油断していると簡単にいじめの対象に祭り上げられる。そんな人々をどうやれば救えるのか。ランチ会でお話を伺ったカウンセラーの方の言葉はとても参考になった。そして、私に再び心理学への興味を呼び起こしてくれた。本書はそれをきっかけに、私が再び河合隼雄氏に触れようとした一冊だ。
河合隼雄という人物は巨大だ。そして「わかりませんなあ」の言葉が表しているように謙虚な巨人でもある。多分、河合氏は苦労も重ね、その過程では悪態や過ちもつくこともあっただろう。だが、それらを乗り越え河合氏は大きな人となった。「無知の知」を本心から理解し、それを正直に語る。それを実践することが大切であることは、頭では理解できる。だが、行うのは簡単ではない。そうした境地に至った河合氏とはいかなる人物なのか。その全貌に、あらためて関心を持った。
本書はさまざまな角度から見た河合隼雄氏についての本だ。臨床家。ユング派精神分析の資格者。文化庁長官。講演が上手。ゼミの教授。フルート奏者。ダジャレが好き。人間だからマイナスの感情も出すし、温和な表情の裏に冷たい視線を覗かせることもある。本書で河合隼雄氏を語るのは、ユング派の分析者であり、同じ精神医学の徒であり、分析を受ける患者であり、高名な指揮者であったり、共著を出したことのある詩人だ。そうした人々が河合氏をさまざまな視点から語り、人物を造形してゆく。それが本書だ。
私は本書を読むまで知らなかったのだが、息子の河合俊雄氏も精神医学の現場で医師として働いているそうだ。序論は河合俊雄氏が筆をとっている。息子からみた父が描き出す序論は、すでに総論として完成している。実に見事な分析だ。肉親であり、同じ分析家からみた父。だからこそここまで書けるのだろう。息子から描かれた河合隼雄氏は序論の短い中でありながら、人物像を簡潔で的確につかんでいるように見える。さすがというべきか。「個人的には、あれほど勝手に生きて、なおかつあれほど人のために生きた人もないと思っている。その矛盾がまさに両立する生き方であった。」(7P)などは、子が親に対して送りうる要約の見本ではないだろうか。また、こんな一文もある。「河合隼雄にとって死者が生きていたように、われわれにとっても河合隼雄は死者として生きているのではないだろうか。そして臨床家として、われわれに出会ってくれるのではないだろうか。」(8P)
肉親がこのように語ることで、なおさらその人物像が鮮やかに浮かび上がる。
本書の出だしは「家を背負うということー無気力の裏に潜むもの」と題し、心理療法の研修会でクライアントの夢の内容を発表した岩宮恵子氏(島根大学教育学部教授)に対する河合隼雄氏の分析が紹介されている。夢の分析は私もかつて自分の夢に対してよく行っていた。一人のクライアントが来院し、治癒していく経過。その一連の出来事が描かれたこの章はとても面白い。河合氏の解釈もユング派分析家の方法論が感じられ、とても興味深く感じた。シャドウや死、イメージの解釈など、連想とイメージの結びつけを厳密にせず、クライアントに作ってもらった箱庭の解釈も含め、人間の内面を掘り下げていく。そんな一連の手続きこそが、悩める若き私が、自分自身に対してしたかったことだ。
続いては「河合隼雄語録ー事例に寄せて」。これは解題によると、京大の研究室で河合氏が折々に語った語録を筆記しておいたた桑原知子氏が、河合氏が京大の教授職を定年で退職するにあたって編集したものだそうだ。桑原知子氏の言葉によると、本来ならば事例あってのコメントなのだが、プライバシーに配慮した結果、事例は割愛したのだとか。はしがきで河合氏自身がこの語録についてのコメントを残されていて、本書にもその全文が転載されている。それによると、当時のことゆえ、必ずしも正しくはないとか。それを裏付けるかのように、本編にはざっくばらんで肩の力の抜けた河合氏の言葉が並ぶ。まさに生の肉声だ。そして、ここからは著書や対談でみられるソフトな河合氏ではなく、内輪に見せる河合氏の様子が垣間見える。もちろん河合氏の言葉に裏表は感じられず、より専門家向けに語っているだけなのだが。
ついで本書は、さらに河合隼雄氏を掘り下げてゆく。[河合隼雄の分析]として、数人の精神分析の専門家による河合隼雄論が並ぶ。
まずは「臨床家 河合隼雄ー私の受けた分析経験から」。山中康裕氏(京都大学名誉教授)によって書かれている。私も山中氏の名前は存じ上げている。同じ分析家が分析家を分析する。その内容は高度で、そもそも山中氏の見る夢からしてとてもリアルで具体的。夢をきちんと記録した山中氏はさすが分析家だ。自分で夢を記録し、分析ができる山中氏のような方であれば、本来は夢分析を受けなくてもよいような気もする。だが、他の分析家からの視点は必要なのだろう。
続いての「分析体験での箱庭」。川戸圓氏(大阪府立大学人間社会学部教授)が河合隼雄氏に分析を受けた際の箱庭療法の経緯が、箱庭の実際の写真とともに載せられている。ここでは厳しい河合氏が登場する。指導を受ける側からすればそう感じて当たり前だ。だが、このような厳しさがあってこそ、あれだけの業績をあげ、慕う門下生も多数いるのだろう。また、クライアントの精神に引きずられないためには、自己を凛とさせておかねばならないのは素人の私でもわかる。
皆藤章(京都大学大学院教育学研究科教授)氏による「河合隼雄という臨床家」は、皆藤氏が河合氏に師事するまでの専攻分野の揺れ(もともと工学部に入学したそう)が、河合氏との出会いでこの分野に定まるまでのいきさつが書かれている。ここでは教育分析という言葉が出てくる。皆藤氏は30歳の時、最初に教育分析を受けたそうだが、河合氏から30歳という年齢は、教育分析を受けるには若いと言われたそうだ。つまり、教育分析とは、精神的な疾患を自覚していない人でも受けられるのだ。山中氏の書かれた文章もそうだが、精神分析家が、自己の心のありようをさらに深めてみつめるため、別の方から精神分析をうける、というのはありなのだろう。私はそのことに気付かされた。そういえば河合氏がアメリカやスイスで学ぶ際も、先輩の分析家から分析を受けた経験を読んだことがあるが、あらためて合点がいった。
角野善宏(京都大学大学院教育学研究科教授)氏は「スーパーヴィジョンの体験から」で、自らが分析している心理療法について、河合氏から指導を受けたときのことを著している。スーパーヴィジョンとは指導を受けることを意味する。スーパーヴァイザーと同じ語源なのだろう。その中で角野氏は、分析には時間がかかることと、本当に患者が自ら分析の必要がないと思うまで、分析家の主観で終了時期を判断する危険性を述べている。他にもこのような記述もある。
「河合先生がもっとも大切にしたことは、心理療法であった。臨床実践であったのである。これがすべてと言ってもよいほど、重要視していた。もちろん研究も大切にされていたが、研究はあくまで臨床実践があってのことで、基本的に心理療法がすべて中心となっていた。」(148p)
「本当に事例において困ったとき、進退窮まったときに、先生が言われていたことは、「もう最後の最後は、クライエントの治癒力を信じることです」であった。」」(148p)
また、角野氏の文章の中で印象に残る記述があった。それは親鸞が師の法然について語った歎異抄の抜粋だ。「たとい、法然上人にすかされまいらせて、念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからずそうろう」(150p)。これは角野氏が河合氏を師として信ずるに至った文脈で出てきた言葉だ。明恵を取り上げた論考やユング心理学と仏教を取り上げた論考など、河合氏の著作からは僧侶の面影を感じることが多い。角野氏の記述はまさにそれを裏付ける。
伊藤良子(京都大学名誉教授)氏による「河合隼雄の心理療法」は、河合氏の膨大な論考のうち、イニシエーションとコンステレーションについて解説している。それぞれ通過儀礼と布置という言葉が対応する。通過儀礼の重要性についてはいまさら言うまでもない。日本で行われる卒業式や成人式は、すでにセレモニーですらなくなりつつある。今の日本の若者は、壁にぶち当たる経験が与えられにくい。だから、若者が壁にぶちあたる理由も場所もまちまちになっている。私がまさしくそうであった。そのため、自らの社会的な位置も見つけにくくなっている。リアルの友人、ネットの知り合い。さまざまなチャネルで、無数の集まりで、友人や知り合いの組み合わせは無数に作れる。それだけに、世に出てゆく若者は、自らの確かな立ち位置を見いだしにくい。私は自分の経験からもそう思っている。自由があるがゆえに不自由。外に向けて放たれているがゆえに、自分の心に縛られる。若者にとっては切実な問題だと思う。伊藤氏はそこに目をつけ、河合氏の考えを紹介したのだと思う。
ついで登場するのは、心理療法を専門としていない人々からの寄稿だ。
[河合隼雄という体験]
「対談:河合さんというひと」谷川俊太郎×山田馨
河合氏と毎年遊びのイベントで一緒だったというお二人。谷川氏は高名な詩人。山田氏は岩波書店で河合氏を担当していた編集者。そんな三人の間柄は、もともとは仕事での関係から始まったという。それがある時期を境に、仕事を抜きにした関係を構築したのだとか。仕事をきっかけに始まるプライベートな付き合いは、私もいくつか持っている。それはとても大切なことだと思う。そして、そうした関係を作りあげるのが、日本人はとても苦手なことも。ましてや、そうした関係を長年維持することはさらに難しい。それを長年続けた三人に、私は心からのうらやましさを感じる。そして、私ももう少しそうした付き合いを増やしていきたいと思った。人間関係の難しさと喜びを知っている私は、三人のような関係を構築したいと思う。
ここでは山田氏による編集者としての目から見たエピソードも登場する。河合氏の原稿に話し言葉が多く含まれ、それが編集者泣かせであることも印象的だ。また、涙もろく、講演中に号泣する河合氏のことも触れられていた事も心に刻まれる。本書の何人かの執筆者も、河合氏の涙もろさについては触れられておられた。そういえば私は物語や映画には泣かされるが、人との付き合いの中で涙を見せることはそうそうない。殻をかぶっていて、身構えた部分が残っているからだろうか。
「物語を生きる人間と「生と死」」柳田邦男。
有名なノンフィクション作家の柳田氏の著作を私は多分、まとまった書籍として読んだことがない。「死を日常の中から排除してしまった現代のジレンマという問題意識」(211)ページというとおり、柳田氏は河合氏の物語を重視する姿勢を、人の生き方の問題と捉えている。科学の論理に偏りすぎ、物語を忘れてしまった現代。柳田氏は危機管理という観点から、科学の危うさに警鐘を鳴らし続けてきた作家だと思っている。私も技術者の端くれとして、あらためて柳田氏の著作を読まねばと思った。
「河合先生との対話」佐渡裕
佐渡氏は有名な指揮者だ。そしてその立場から芸術を愛する河合氏の思い出を語っている。ページは三ページに満たない。だが、佐渡氏は貴重なエピソードに筆を割いている。舞台に臨む前、河合氏と撮った写真に触れていたという佐渡氏は、きっと河合氏から安心を受け取っていたのだろう。それは間接的に河合氏の器の広大さをしめしているに違いない。そんなことが読み取れる一編だ。
「私の「河合隼雄」」を寄稿した中鉢良治氏はソニーの副会長だ。ソニーは文化支援にも力を入れている。だから、文化庁長官の河合氏とはご縁も深かったことだろう。本編はソニーの社員研修に来た河合氏の講演から中鉢氏が得た気づきを、経営者の視点から取り上げている。それはもちろん、私にとっても有意だ。河合氏といえば無為の思想の提唱者でもある。中鉢氏もそのことを河合氏から教えられたようだ。
「河合さんはリーダーの本質を「積極的無為」であり「全力を挙げて何もしないこと!と喝破されていた」(224ページ)
こうした文章を読むにつけ、私自身がダメダメな経営者である事を思い知らされる。そもそも、自分で手を動かしてコーディングに励んだり、日々、営業に出かけている事自体、無為とは程遠い。私がその境地に至れる日は、果たして訪れるのだろうか。
[インタビュー]
ユング派河合隼雄の源流を遡る J.M.シュピーゲルマン(聞き手:河合俊雄)。
シュピーゲルマン氏は、河合氏が精神分析の世界に入るにあたり、最初に分析を行った方だという。河合氏の2年年上だというから、もうかなりのお年だ。その方が河合氏との出会いを振り返っている。本編を読むと、見知らぬ世界に飛び込み、そこで鍛えられた河合氏のすごさがわかる。
本書を読んであらためて思うのが、河合氏の人間としての幅だ。人に与えられた360度の可能性を限りなく使った人、と言ってもよい。そして、幅を広げながらも、それぞれの分野の可能性を深く追求した人だったのだなあと、自らの至らなさを比べて慨嘆する思いだ。それこそが河合氏の巨人たるゆえんだ。私が河合氏の域まで達するにはあと何万年、時間が必要なのだろうか。人生の短さと、残り少ない私の余生に暗澹とする。
[資料]河合隼雄年譜が巻末に付されているが、私自身の人生と比べてみても、その質の違いは明らかだ。
‘2018/07/26-2018/07/28