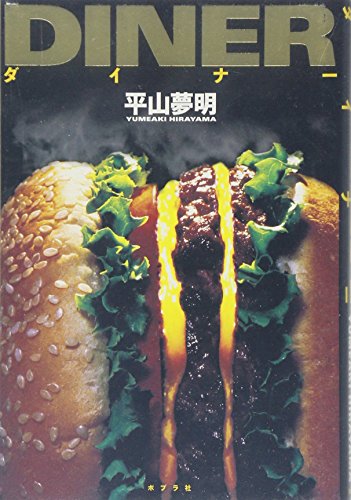
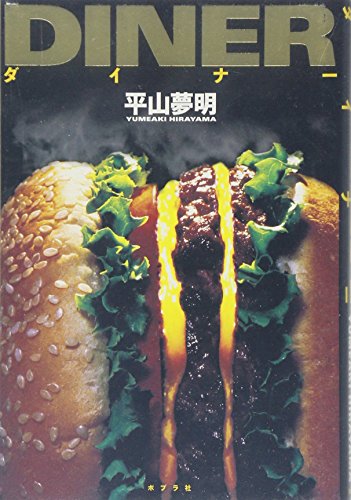
人体。私たちは常に、自らの体がこうあるという身体感覚を持っている。この感覚が狂った場合、私たちが感じるのは気持ち悪さだ。それは自分の体が狂った場合だけではなく、他人の体でも当てはまる。他人の体が人体としてあるべき状態になっていないとき、私たちは本能的に気色悪さを覚える。例えば障害を抱えた方の体を見た時、残念ながら気持ち悪さを感じてしまう事だってある。これは本能の振る舞いとして認めなければならない。
だからホラー映画でハラワタがのたうち、血が飛び散る描写をみると私たちはおののいてしまう。そうした描写が私たちの心の闇をかき乱すからだ。ホラーに限らず、人体がグロテスクに変貌する描写は、ほとんどの人にとって、動揺の対象となる。もちろん、人によって動揺には強い弱いがあるだろう。だが、その動揺が表に出なかったとしても、居心地の悪さを感じることに変わりはない。
著者の名前を一気に有名にした『独白するユニバーサル横メルカトル』は、あらたな人体改造の可能性を描いた奇書である。身体感覚が歪む読後の気持ち悪さ。それは読者に新たな感情をもたらした。本書もまた、著者の身体への独特の感性が自在に表現される。その感性はもはやある種のすごみさえ発している。何しろ本書に登場するほとんどの人物がいびつな人体の持ち主なのだから。
オオバカナコは、人生の敗残者になりかけている三十歳。当座をやり過ごすための金を求め、闇求人サイトで三十万の運び屋の仕事に応募する。だがその仕事はヤバい筋にちょっかいを掛ける仕事。捕まったオオバカナコはその筋の者たちに拷問され、生きながら人が解体されて行くところを見せつけられる。ヤクザ者の手に墜ち、オークションにかけられる。そして誰も買い手が付かなかったため、人の絶えた山奥で生き埋めにされる。穴に埋められ、スコップで土を掛けられるオオバカナコ。彼女は自分の利用価値を認めてもらうため、やけっぱちで「料理ができる!」と絶叫する。その叫びがかろうじて裏社会に張り巡らされた求人条件にマッチし、あるレストランのウェートレスとして送り込まれる。
そこは殺し屋だけが訪れる会員制のレストラン”キャンティーン”。ウェートレスといっても、実態は買われた奴隷そのもの。店を仕切っているボンベロに逆らえばすぐに殺される。カナコの前任も、客の気まぐれで肉片に変えられた。カナコは欠員の出たウェートレスに送り込まれたのだ。もちろん使い捨て。
全てが不条理な状況。その中に放り込まれたカナコはしぶとくボンベロの弱みを握り、生き延びようとする。全てが悪夢のような冗談に満ちた不条理な店。しかし殺し屋たちやボンベロにとっては当たり前の日々。彼らはそこでしか居場所を見いだせないのだから。身体中に縫い目が走り、破れっぱなしの頬から口の中が見えるスキン。見た目はこどもなのにそれは全身整形の結果。中身は非情な殺し屋キッド。異常に甘いものしか食わない大男のジェロ。超絶美女なのに凄腕の毒を盛り、相手をほふる炎眉。妊婦の振りをして膨れた腹に解毒薬を隠す毒婦のミコト。そんな奇天烈な客しか来ない”キャンティーン”は、客も店主もぶっ飛んでいる。そして、ボンベロが振る舞う料理もまた神業に近い。居心地の良さと料理の質が高いため、客足が途切れないのだ。
そんな”キャンティーン”は組同士の抗争の場にもなるし、いさかいの場にもなる。ボンベロ自身、かつて凄腕の殺し屋として名をはせ、その筋に属する人々だけが来るだけに、なおさら血なまぐさい場となる。
カナコもいろいろな修羅場をくぐらされる。だが、しぶとく食らいつくカナコにボンベロの見方も少しずつ変化する。ボンベロとカナコの間の関係性が少しずつ変わって行く描写が読みどころだ。そして客とボンベロ、カナコとボンベロの間柄が、ボンベロの出す料理で表現されており、そこがまた絶妙だ。
全てが常軌を逸した店の中でカナコはどう生き延びていくのか。そのサバイバルだけでも読者にとって読み応えがある。異常で常識が通じない本書は、すこぶる上質のエンターテインメントに仕上がっている。人体改造や拷問の知識が惜しげもなく披露され、グロテスクで闇にまみれた感覚が刺激される。それを意識しながら、読者はページを読む手がとめられないはず。
人体。それはタブー。だが、それを超えた人間は強靭だ。戦争経験者が一目置かれるように。ダメ女として登場したカナコが心の強さを発揮していく本書は、著者の思いがにじみ出ている。それは、日常が心を強く持たなくても生きていけること、そして、修羅場こそが人を鍛えるということだ。つまり、本書は極上のハードボイルド小説なのだ。日本冒険小説協会大賞や大藪春彦賞を受賞したこともうなずける。面白い。
‘2017/07/26-2017/07/27


