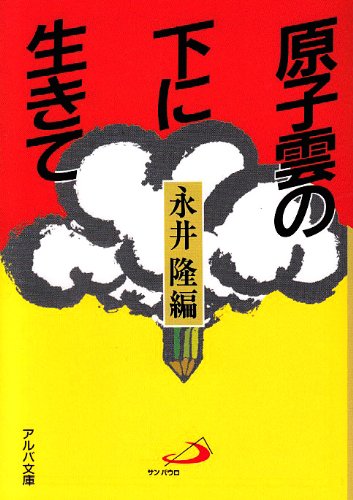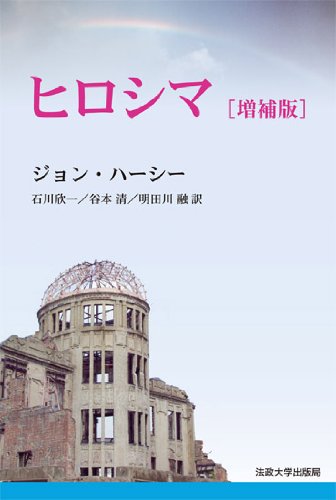
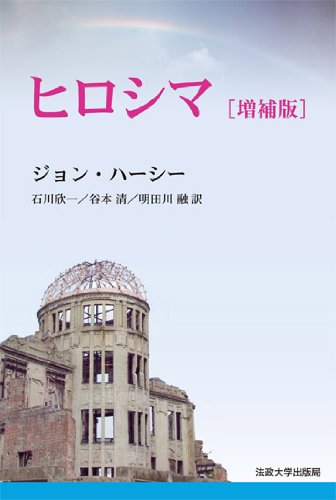
著者の作品は読んだことがないが、第二次大戦の戦場で数々のノンフィクションをものにした方だそうだ。
また、イタリア戦線にも従軍し、その内容を『アダノの鐘』に著し、ピューリッツァー賞の小説部門を受賞したそうだ。それらはウィキペディアに載っている。
ウィキペディアには本書も載っている。その内容によれば、本書は学校の社会科の副読本になり、20世紀アメリカジャーナリズムのTOP 100の第1位に選出されたそうだ。
実際、本書の内容は、原爆を投下した側の国の人が書いたと考えるとかなり詳しい。しかも、まだ被爆の記憶が鮮やかな時期に書かれたことが、本書に資料としての価値を与えている。
本書についてはウィキペディアの英語版でかなり詳しく取り上げられている。ウィキペディアの記述も充実しているが、本書の末尾に付された二編の解説もまた素晴らしい。
一つは、本書を和訳した三人の一人でもあり、本書に取り上げられた六人の被爆者の一人でもある谷本清氏が1948年9月に著した長文の解説。もう一つは、訳者である明田川融氏が2003年6月に著した解説。この二つの解説が本書の内容と価値を十分に説明してくれている。
解説の中では、被爆地である広島で本書がどのように受け止められたかにも触れている。広島でも好意的に受け取れられたそうだが、それだけで本書の価値は明らかだ。
原爆がヒロシマに落とされてから75年の年月がたった。
その間にはいろいろな出来事が起こり、歴史が動いた。そして、記録文学や映画や絵画が数え切れないほど書かれてきたし描かれてきたし撮られてきた。
そうした数多くの作品の中でも、投下から一年以内にアメリカ人によって取材された本書は際立っている。
なにしろ、1946年の8月にニューヨーカー誌面で発表されたというのだから、本書の取材内容の新鮮さは、永久に色あせないだろう。
本書は、六人の被爆者の被爆から数日の日々を取材している。丹念に行動を聞き取り、そこで目撃した投下直後の悲惨な街の状況が克明に描写されている。私たちは、当時のアメリカ進駐軍が被爆地に対して報道管制を敷き、日本人の国民感情を刺激せぬように配慮した事実を知っている。
だから、本書を読み始めたとき、本書にはそこまで大したことが書かれていないのでは、と考えていた。
だが、本書には私が思っていた以上に、原爆の悲惨さと非人道的な側面が記されている。もちろん、本書が発表された当初はさまざまな配慮がなされたことだろう。たとえば、本書が日本ではなくアメリカでのみ発表されたことなど。
そうした配慮によって、日本人の国民感情を刺激せず、同時にアメリカ人に対して自国が行った行いを知らしめる意図を満たしたはずだ。
著者は告発というより、ジャーナリズムの観点から事実を報道することに徹したようだ。だが、恐るべき原爆の被害は、事実の報道だけでもその非日常的さと非道さが浮き彫りになる。
著者は、被爆者が語った内容をそのままに、添削も斟酌もなしに書いているが、それがかえって本書に不朽の価値を与えているのだろう。
当然のことながら、本書に取り上げられた六名の方の体験だけが原爆の被害の全てではない。二十万人以上の人々が被爆したわけだから、悲惨さは二十万通りあって当然だ。
本書に登場する方々は、いずれも爆心地から1キロメートル以上離れた場所で投下の瞬間を迎えた。しかもたまたま建物の影にいたため、熱線の被害にあわなかった方々だ。
言うまでもなく、本書に取り上げられている六名の方の悲劇を他の被爆者の悲劇と比べるのはナンセンスだ。むしろ失礼に当たる。
この六名の方も、無慈悲で無残な広島の光景を十分すぎるほど目に焼き付けたはず。それがどれほど心に深い傷を残したかは、想像するしかない。
本書に描かれた六通りの非道な運命だけで、ほかの数十万の悲劇について、どこまで当時のアメリカの人々に届いたのか。それはわからない。
とはいえ、本書はアメリカ人にとっては報道の役割を十分に果たしたと思われる。自国で生み出された原爆がヒロシマとナガサキの人々の上に筆舌に尽くし難い惨禍をもたらしたこと。多くの人々の人生を永久に変えてしまったこと。この二つを知らしめただけでも。原爆の悲劇が早い時期に報道されたことに本書の意義はある。
本書に登場した六名の被爆者の方々が、西洋文化に理解を持っており、被爆を通してアメリカを恨み続けていないことも、アメリカの方々の心には届いたと思いたい。
夫を南方の戦場で失い、一人で三人の子供を助け、その後の惨状を生き延びた中村初代さん。日赤病院の医師として不眠不休の治療にあたった佐々木輝文博士。同盟国ドイツの人物として、西洋人の目で原爆の惨禍を見たウィルヘルム・クラインゾルゲ神父。事務員で崩れた建物に足を粉砕された佐々木とし子さん、病院の院長であり、崩壊した病院の再建とともに一生を生き抜いた藤井正和博士。かつてアメリカで神学を学んだ牧師として、原爆の被害をアメリカに訴え続けてきた谷本清氏。
六名の方が語る体験が描かれた本書は、後日談も描かれている。
39年後、再び広島を訪れた著者がみた、平和都市として生まれ変わったヒロシマ。その移り変わった世の中を被爆者として懸命に生きた六名の人生。
被爆者としての運命を背負いながら、長い年月を生きた六名の被爆者。ある人は原爆とは直接関係のない理由で亡くなり、ある人はいまだに反核運動に生涯をささげ、ある人は神の僕としてそれなりの地位についている。
上にも書いた通り、もともと六名の方が西洋文化に素養があったからこそ、著者のインタビューを受ける気になったのかもしれない。そうした六人だったからこそ、その後の人生も懸命に生きたことだろう。
六名の方が、被爆直後の恨みを傍にいったんおき、苦しい体験をあの時期に、それも原爆を落とした相手の国のジャーナリストに語る。
その決断が、民間レベルでの日米間の交流にどれほど貢献したかははかりしれない。
そして、その決断にどれほどの葛藤があったことだろう。敬意を表したい。
‘2019/9/6-2019/9/7