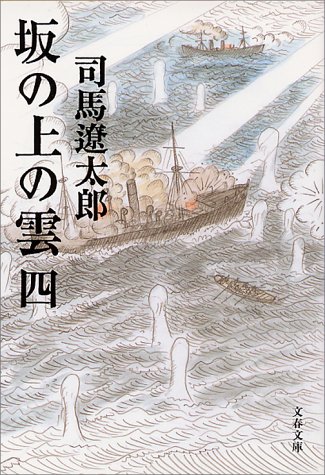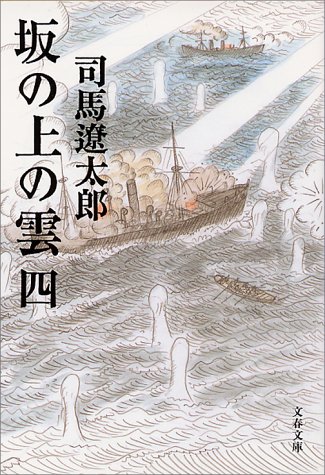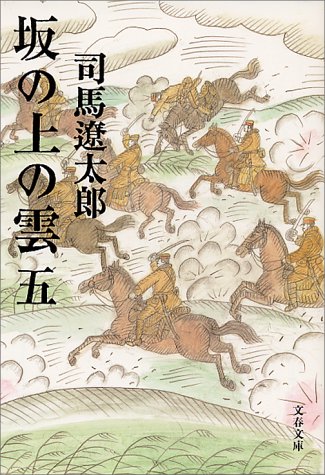
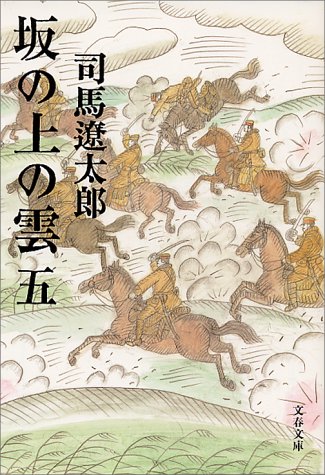
前巻から続く旅順攻略の大苦戦。朝日を拝んでまで人を超えた力を望んだ児玉源太郎の苦悩は晴れない。
悩んだ挙げ句に、児玉源太郎はついに大山元帥に申し出る。第三軍の指揮権を児玉参謀に委任する一筆をもらうことを。そして委任状を懐に忍ばせ、旅順へと向かう。
旅順を攻める第三軍の責任者は乃木大将。ところがこのままの戦況が続けば、日本にとっては国の存続に関わる問題になる。乃木大将と伊知地参謀に任せておいては日本はロシアに負け、そして滅ぶ。
追い詰められた思いを抱き、児玉源太郎は乃木大将に指揮権の一時預かりを申し出る。幸いにも両者の思惑と相手を思いやる思いが通じ、乃木将軍の面目は保たれたまま、児玉源太郎は一時的に第三軍の作戦をひきうけることで落ち着く。
実権を握った児玉源太郎がさっそく取りかかったのが、28サンチ榴弾砲の移設や二〇三高地を重点的に攻める戦略だ。また軍紀を一新するため、戦線を見ずに後方で図面だけで作戦を立てる参謀たちを叱責し、参謀が自ら最前線を視察させるよう指導する。迅速に立て直しを図った児玉策が的中し、第三軍は極めて短時間で二〇三高地を落とすことに成功する。乃木将軍と伊知地参謀の面目は対外的には保たれた。だが、内心はいかばかりだったか。
ところが、この二〇三高地を巡る下りは、今に至るまで賛否両論なのだという。
本書では、著者は伊地知参謀をこれでもかとこき下ろす。一方で乃木大将のことは人格者として、全軍を統括する大将であり、実際の作戦の立案には関わっていないとして否定しない。だが、著者が振るう伊地知参謀への批判の刃は、間違いなく乃木将軍をずたずたにしている。
その事を許せないと思う人がいるのか、著者と全く違う見解を持つ人もいる。
その説によれば、実は伊地知参謀の立てた策は戦場の現実を考えると真っ当で、著者の批判こそが戦場を見ずに書いた空想だという。
その説は詳しくはWikipediaに書かれている。が、私にはどちらの説が正しいのかわからない。
本書の記述が誤っているのか、それとも史実は全く違うのか。別の説によると、児玉源太郎が旅順で計画を立て直したことすら事実ではないという。もしそれが正しければ、本書の記述は根底から覆ってしまうのだが。
二〇三高地の陥落によって、高地から旅順港の旅順艦隊にやすやすと砲弾を降らせることが可能になった。そして旅順要塞そのものの攻撃も容易になった。ここに戦局は一つの転換を迎える。
印象的なのは、旅順が落ちた後、児玉源太郎が乃木大将に詩会をしようと声をかけるシーンだ。ここで著者は、児玉の漢詩と乃木大将の詩を比べる。そして、詩才においては乃木のそれが児玉を遥かに凌駕していたことを指摘して乃木の株を上げる。その時に乃木が吟じたのが爾霊山の詩だ。
爾霊山嶮豈難攀
男子功名期克艱
鉄血覆山山形改
万人斉仰爾霊山
爾霊山という言葉は二〇三高地にかけた乃木大将の造語であり、「この言葉を選び出した乃木の詩才はもはや神韻を帯びているといってもよかった」(148P)と著者は最大の賛辞を寄せている。
著者がここで言いたいのは、人の才とは適所を得てこそ、という事に尽きる。
乃木大将の才能は戦にはない。けれども、人格や詩才にこそ、将軍の才として後世に伝えられるべきだといいたいかのようだ。
著者は旅順戦については第三軍をこっぴどく非難している。だが、それは直ちに乃木大将の人格を否定するものではない、という事を強調したかったのだろう。
旅順艦隊はほぼ撃滅され、残討処理は第三軍に任された。そして、連合艦隊も旅順艦隊の監視をせずに良くなり、佐世保で修理に入る。
旅順要塞は、旅順艦隊が掃討された後も激烈な抵抗を繰り返す。だが、ついにステッセル将軍の戦意は萎え、日本に降伏を申し出る。
二〇三高地は落ちても、それがすぐ旅順戦の終結にならなかったことは覚えておきたい。
一方、バルチック艦隊はバルト海を出航した。だが、その航海は前代未聞の長大なものであり、苦難に満ちていた。
北海では日本の艦船と勘違いしてイギリス漁船を砲撃し、英露間に戦争を起こす寸前の事態を招いている。
つまり、航海のはじめからバルチック艦隊の士気は低く、あまり意気揚々とした航海ではなかった。司令長官のロジェストウェンスキーは水兵や将官に厳しくあたり、人を容易に信じない人物として描かれる。
四巻から描かれた航海の描写ではアフリカ沿岸を南下し、マダガスカルに行くところまでが描かれる。
本書では、日本と同盟を結ぶイギリスの妨害が日本に有利に働く。露仏同盟を結んでいるはずのフランスも、イギリスからの圧力でバルチック艦隊に港を提供することを渋る。
折しも、極東でロシアが敗北を繰り返す報が入り、バルチック艦隊の前途を危うくする。
そんな中で航海を続けたことの方が大変なこと。むしろ今では、バルチック艦隊は日本海海戦で全滅したことを嘲られるより、無事に航海を成し遂げた偉業が讃えられているぐらいだ。
ステッセル将軍は降伏時の会見で乃木将軍の態度に感銘を受ける。
そうした場での所作の一つ一つが絵になり、また感銘を与える。それが乃木将軍の良い点だ。
乃木将軍に限らず、本書に主に登場する人物の多くは、戊辰戦争の時代を知る人々だ。
乃木、大山、山本、東郷、小村。
本書の主人公は秋山兄弟と正岡子規であるが、彼らではなく、維新の風を知る人物が脇を固めることで、本書で描かれる明治の様相は層が厚く、説得力も増す。
一方のロシアは、相変わらず官僚的な発想が幅を利かせ、軍に弊害をもたらす。
クロパトキンとグリッペンベルクの争いもその一つだ。
日本は秋山騎兵団が背後を撹乱し、戦線を維持している。が、ロシアの全軍が乱れず総力をあげられれば突破されてしまう薄さしかない。ところがロシアの軍を率いる二人の意見が衝突し、さらに官僚の保身が邪魔して、意思の統一が図れない。この点も日本にとっての僥倖だった。
‘2018/12/14-2018/12/17