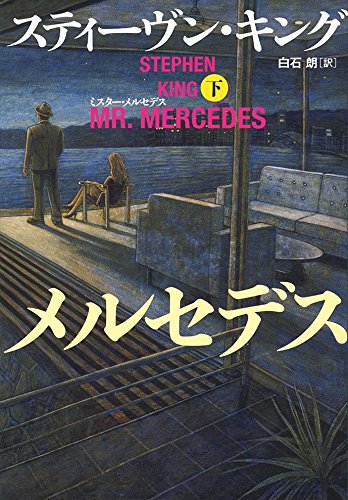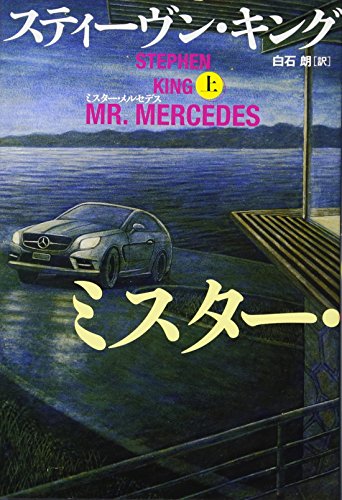読読と名付けたこのブログをはじめてからというもの、真の意味で本を読むようになったと自負している。もちろん、今までもたくさんの本を自分なりに楽しみ、夢中になって読んできた。だが、今から思うと、本から得られたはずのものはもっと多かったのではないかと思っている。
本は読んだ後の振り返りが重要なのだ。それを著者の「1Q84」の三冊を読み、レビューを書くことで痛感した。著者の小説は言い方は悪いが読み流す事ができる。それは著者の文体が読みやすいからだ。読みやすく、すらすらと筋を追えてしまう。なので、読み終えた後に消化する作業がなければ内容を忘れてしまう。
著者の作品を例にあげると、「ノルウェーの森」と「ダンス・ダンス・ダンス」はあら筋すら覚えていない。今から28、9年前、中学生の時分に友人に借りて読んだのだが、そのことしか記憶にない。「羊を巡る冒険」や「ハードボイルドワンダーランド」も高校の頃に読んだ記憶はあるが、ほとんど記憶にない。ようやく「海辺のカフカ」あたりから筋を覚えている程度だ。上記にあげる各作品は、何を得られたかを問われると覚束ない。
「1Q84」を読んだとき、すでに読読ブログを始めていたので、自分の中でレビューとして文章に起こすことで反芻できた。その結果、共同体なるものの連帯感とはそもそも幻想でしかなく、生命同士の結び付きこそが共同体に他ならないとの知見を得た。つまり、規則や規約といった約束事のあいまいさだ。
こういった知見は本を読んだ後自分で意識しないと忘れてしまう。それでは本を読んだことにならない。本を読んだとは、読み返したあとに感想を文としてまとめて初めて言えるのかもしれない。そう言い切ってよいと思う。
多分、本書もレビューに落とさぬままだと、現実の忙しさに忘れてしまいかねない。だが、本作は読みやすい文体の隙間に人生への識見が織り込まれている。そこをレビューとしてまとめておきたいと思う。本書もまた、著者の傑作の一つだと思えるから。
本書の題名は長い。長いがその分だけ情報が豊富に含まれている。その中でも「色」「つくる」「巡礼」の三つは重要なキーワードではないか。以下、それによってレビューを進めようと思う。
その前に、本書のあらすじを一文で表してみる。個性を持たないことで共同体を放逐されたことに傷付いた人はいかに己を再生すべきか。という感じだろうか。
ここでいう個性とは、すなわち「色」だ。主人公多崎つくるは、自分の個性の欠如に劣等感を抱いている。名古屋で過ごした彼の高校時代。そこで固い絆で結ばれた五人の仲間。つくる以外の四人の名字には色を表す文字が含まれている。黒白青赤。そしてつくるの名には色が含まれていない。
一人だけ東京の大学に入ったつくるはある日、名古屋に帰る。が、彼はいきなり理由も告げられぬまま四人の仲間から遠ざけられた自分に気づく。そして死を思うまでに傷つく。つくるはその理由れを自分に「色」つまり個性がないせいだと思い悩む。おそらくつくるが持つ悩みとは今の若者の多くが抱えている悩みなのだろう。私自身はおなじ悩みを持っていなかったが、個性を持たねば、という自覚はあったように思う。
だが個性とは、身に付けるものでも後からそなわるものでもない。さらにいうと産まれた瞬間にもたらされるのでも、卵子に受精した瞬間に定まるのでもない。そんなものとは無関係に、存在することがすなわち個性ということだ。
よく、人生を勝ち組負け組という。それに対してよく言われるのは、そもそも何億も放たれた精子との争いに勝った時点で勝者なのだという。でも、そんなことを持ち出すまでもない。存在自体がすでに個性なのだ。
なので、個性をうんぬんするのはあまり意味のないことだと思う。多崎つくるは、本書の終盤になり、かつての仲間に逢う。そこで彼は自ら感じていた劣等感が仲間からは違う見方でとらえられていたことに気づく。自分が内側からみた個性と人からみた個性が全く別物であること。彼が学んだのはそれだ。
だが、個性がないと悩んでいる当の本人には、こんな客観的な言葉は響かないのだろう。
では、個性がないことに悩んでいる人は何に救いを求めるのか。それを多崎つくるは「つくる」ことに求める。多崎つくるはどうやって喪失感を克服したか。それは彼が駅をつくるという生きがいを得たからだ。それを人は天職と呼ぶ。
主人公の名前を「つくる」としたのは、著者なりの考えがあったからだろう。個性を持たない主人公が、生きるために「つくる」ことに慰めを求める。それは、人の営みにとって必要な栄養なのだろう。
生をこの世に受けた人は、作ることに生を費やす。自分をつくり、家族をつくり、サービスをつくり、後継者をつくる。そして死んで行く。個性を出そうと躍起になったり、組織で自分を目立たせようと足掻いたり。結局のところそれらは「つくる」ための副産物にすぎない。やりがいだ自分探しだと人は奔走する。でもそれは「つくる」という行いがあってのことなのだ。
五人の仲間の一人にクロがいる。彼女の生き方はそれを実践している。日本から遠く離れた国に住み、家族を暮らし、陶芸をつくる。つくる事に没頭できる日々をとても大切にする彼女の日々は単調だがとても充実している。
その姿は、車のセールスマンとして優秀なアオや、自己啓発セミナーで有数の会社を起こしたアカをかすませる。彼らも確かに組織をつくり、部下を作っている。だが、クロのように後に何も残さない。他人が作った車を売り、人の練り上げたノウハウを提供するだけ。そこには「つくる」喜びが見えない。
しかし、つくるやクロの人生は「つくる」営みだ。「つくる」ことで人生に立ち向かえている。著者が言いたいのは「つくる」ことが人生の意義であり目的であることのようだ。私は、著者の言いたいこととはこれではないかと思う。情報があふれ、得たいものが容易に得られる今、何を人生のよりどころとするか。張り合いも生き甲斐も感じられないまま自殺に走る。そんな若者たちに、著者は「つくる」ことに人生を見出だせないか、と問いかけている。
では、最後の「巡礼」とは何か。それを著者は、救い、と同じ意味で取り扱っていると思う。
個性のなさに悩むことの無意味さ。それに気付き「つくる」ことで人生の目的を見いだす。では次に人は何をたよりに人生にたち向かうのか。それを著者は「巡礼」という言葉で表したのだと思う。
本書で多崎つくるは、かつて自分を死を思うまでに苦しめた過去に向き合おうとする。その過程とは、四人から突然拒絶された理由を探る旅だ。その旅は、つくるにとってかつての自分に向き合うための「巡礼」に他ならない。その旅によってつくるは四人から遠ざけられた理由を知ることになる。そればかりではなく、色を持たない自分自身への劣等感を払拭する。そして「つくる」という行いが、人生に与えるはかり知れぬ重み。つくるは巡礼の旅によって、得難いものを手に入れることになる。
人は存在することで、その時代に応じた個性を身につける。何かをつくることで人生への手応えを手に入れる。だが、そのことにはなかなか気づけないもの。気付くには、切っ掛けが必要なのだ。著者に云わせると、きっかけこそが巡礼の旅なのだろう。
もしかするとその事に気づかぬまま、死を迎える人もいるだろう。本書でいうシロのように。巡礼どころか、何も思い返す間もなくやって来る突然の死。そうかと思えば自らに与えられた生を静かに充実させようとするクロのような人生もある。はたまた、消息も不明のまま物語の途中で退場してしまう灰田のように黒白はっきり付けられない人生もある。
われわれは、どういった人生の幕引きをしたいだろうか。色を持たない多崎つくるのような?それともは白紙のまま突然世を去るシロのような?または人知れず退場する灰田のような曖昧な?または原色のまま現代を生きるアカやアオのような?
人によって価値観はさまざまだろう。だが、色彩を持たない多崎つくるは、巡礼によってそれぞれの人の持つ色合いを感じることができた。それこそが巡礼の持つ意味ではないだろうか。
人は生まれ、老い、死んでゆく。死ぬまでの間に巡礼できる域まで達せられる人はどれぐらいいるのだろう。自分の色を知り、作ることで人生を豊かにし、巡礼で人生の意味を知る。せめて、生きているからには、そこまで達成して死にたいではいではないか。
‘2016/09/11-2016/09/12