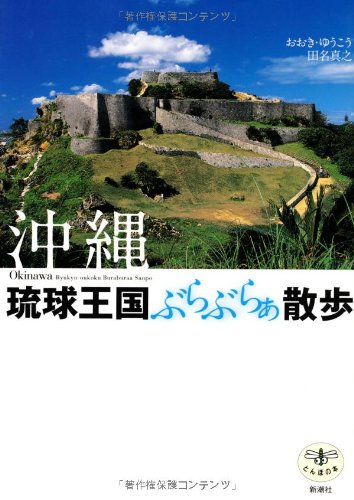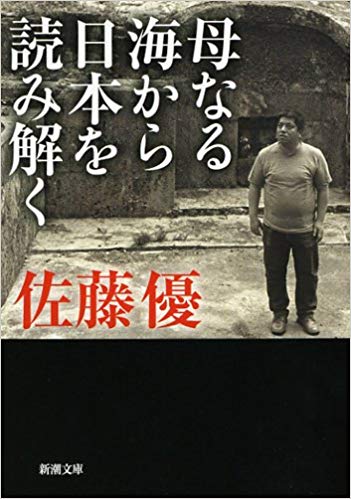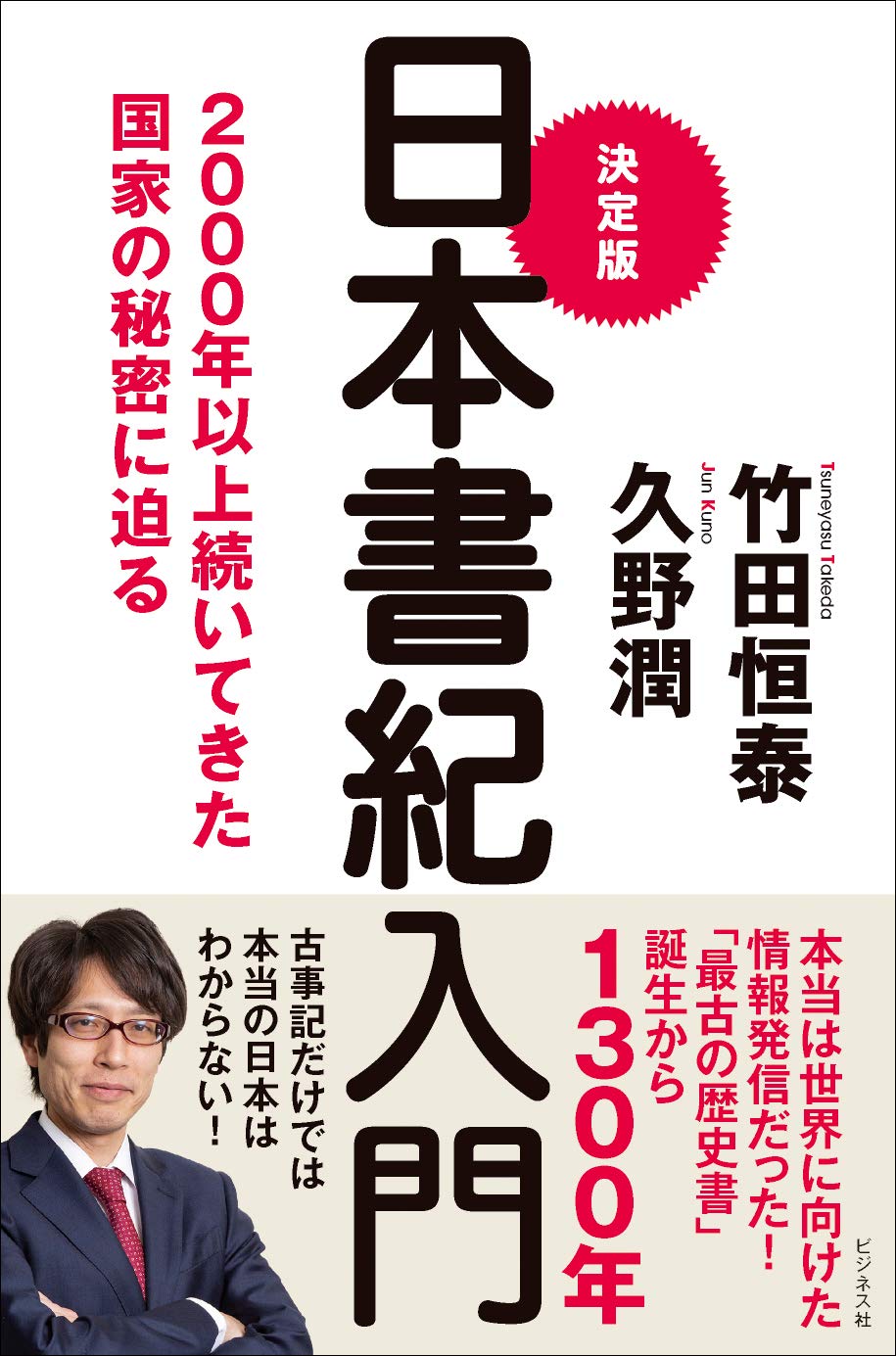
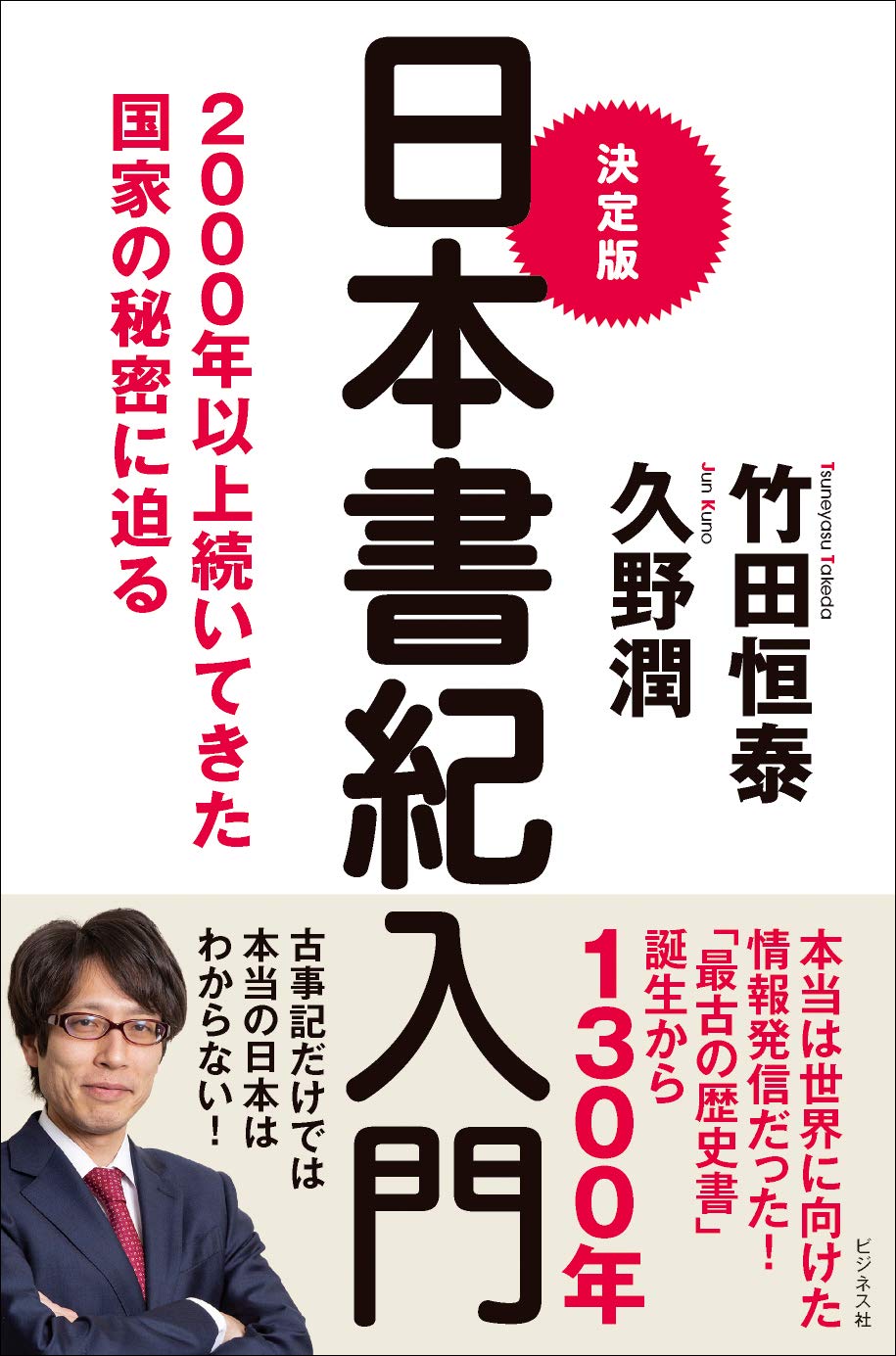
私が持っている蔵書の中で、著者本人から手渡しでいただいた本が何冊かある。
本書はその中の一冊だ。
友人よりお誘いいただき、六本木の某所でセミナーと交流会に参加した。
その時のセミナーで話してくださった講師が著者の久野氏だった。
セミナーの後、本書の販売会が開催された。私もその場で購入した。著者による署名もその場で行っていただいた。恵存から始まり、私の名前や著者名、紀元二六八〇年如月の日付などを表3に達筆の毛筆で。
私は今まで作家のサイン会などに出たことがなく、その場で署名をいただいたのは初めてだった。その意味でも本書は思い出に残る。
著者が語ってくださったセミナーのタイトルは「オリンピックの前にこそ知っておきたい『日本書紀』」。
くしくもこの年は日本書紀が編纂されてから1300年の記念すべき年。その年に東京オリンピックが開催されるのも何かの縁。あらためて日本書紀の素晴らしさを学ぼうというのがその会の趣旨だった。
私はこの年にオリンピックが開かれることも含め、日本書紀について深く学ぶよい機会だと思い参加させていただいた。
私は幾多もの戦乱の炎の中で日本書記が生き残ったことを、わが国のためによかったと考えている。
古事記や風土記とあわせ、日本書記が今に伝えていること。
それは、わが国の歴史の長さだ。
もちろん、どの国も人が住み始めてからの歴史を持っている。だが、そのあり様や出来事が記され、今に残されて初めて文明史となる。文献や史実が伝えられていなければただの生命誌となってしまう。これはとても重要なことだと思う。
そうした出来事の中にわが国の皇室、一つの王朝の歴史が記されていることも日本書紀の一つの特徴だ。日本書記にはその歴史が連綿と記されている。それも日本書記の重要な特徴だ。
たとえその内容が当時の権力者である藤原氏の意向が入っている節があろうとも。そして古代の歴史について編纂者の都合のよいように改ざんされている節があろうとも。
ただ、どのような編集がなされようとも、その時代の何らかの意図が伝えられていることは確かだ。
日本書記については、確かにおかしな点も多いと思う。30代天皇までの在位や崩御の年などは明らかに長すぎる。継体天皇の前の武烈天皇についての描写などは特に、皇室の先祖を描いたとは思えない。
本書では継体天皇についても触れている。武烈天皇から継体天皇の間に王朝の交代があったとする説は本書の中では否定されている。また、継体天皇は武力によって皇統を簒奪したこともないと言及されている。
在位年数が多く計上されていることについても、もともと一年で二つ年を数える方法があったと説明されている。
ただ、前者の武烈天皇に対する描写のあり得ない残酷さは本書の中では触れられていない。これは残念だ。そのかわり、安康天皇が身内に暗殺された事実を記載し、身内に対するみっともない事実を描いているからこそ真実だという。
その通りなのかもしれないが、もしそうであれば武烈天皇に対する記述こそが日本書記でも一番エキセントリックではないだろうか。
素直に解釈すると、武烈天皇と継体天皇の間には何らかの断裂があると考えたくもなる。本書では否定している王朝交代説のような何らかの断裂が。
本書は久野氏と竹田恒泰氏の対談形式だ。お二人は日本書記を日本史上の最重要書物といってもよいほどに持ち上げている。私も日本書記が重要である点には全く賛成だ。
ただ、本書を完全な史書と考えるのは無理があると思う。本書は一種の神話であり、歴史の真実を書いたというよりは、信仰の世界の真実を描いた本ではないだろうか。
ただ、私は信仰の中の本であってもそれは真実だと思う。私はそう捉えている。
書かれていることが確実に起こったかどうかより、ここに書かれた内容を真実として人々が信じ、それに沿って行動をしたこと。それが日本の国の歴史を作り上げてきたはずなのだから。
例えば新約聖書。キリスト教の教義の中でも一番超自然的な出来事が死後の復活であることは言うまでもない。新約聖書にも復活に当たることが書かれている。
だが、ナザレのイエスと呼ばれた人物がいた事は確かだろう。そして、その劇的な死とその後の何かの出来事が復活を思わせ、それが人々の間に熱烈な宗教的な思いをもたらしたことも事実だと思う。要は復活が事実かどうかではなく、当時の人々がそう信じたことが重要なのだと思う。
それと同様に、日本の天皇家の先祖にはこういう人々がおり、神々が人と化して葦原の中つ国を治め始めたことが、信仰の中の事実として伝えられていればそれでよいのだと思う。今から欠史八代の実在を証明することや、神武東征の行程を正確に追うことなど不可能なのだから。
残念ながら、このセミナーの少し後に新型コロナウィルスが世界中で蔓延した。
東京オリンピックは一年延期され、日本書記が完成してから1300年を祝うどころではなくなった。
著者とも何度かメールの交換をさせていただいたが、私自身も仕事が忙しくなってそれきりになっている。
だが、日本書記が今に残っているのは確かだ。キリのよい年であろうとなかろうと、学びたいと思う。本書を読むと1300年前の伝統が確かに今に息づいていることと、その良い点をこれからに生かさねばならないと思う。
‘2020/02/13-2020/02/13