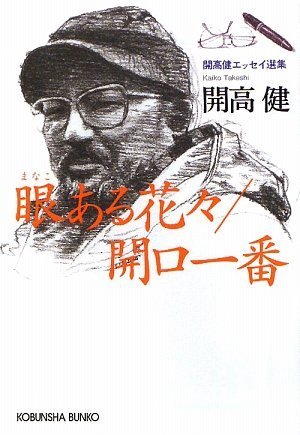

洋酒文化と純文学。私がそれらに興味を持ったのは20代前半の頃だ。酒文化の方が少し早い時期だったと覚えている。今もなお、その二つは私にとって人生を生きる原動力となっている。その二つの文化を代表する作家として、著者の名前を外すわけにはいかない。
その二つの文化を体現していた著者は、当時、苦悩の淵に沈んでいた私に光を照らしてくれた。それ以来、著者のことは常に意識していた。著者は壽屋(現サントリー)の広報部に属し、キャッチコピーやその他の文章で健筆を振るっていたことで知られる 。なので、洋酒文化に興味を持った私は、著者の文章に相当多くの知識を授けられて来た。サントリーの広報誌「洋酒天国」の総集編の書籍は、わざわざ古本屋の通信販売で取り寄せた。
だが、読むべき作家とは知りながら、著者の作品は思うように読めなかった。私が著者の作品を読まなければと思ったのは、ある日茅ケ崎市の開高健資料館の存在を知ってからだ。なぜそのことを知ったのか。そのきっかけは、茅ケ崎でジーンズショップを開くKさんとのご縁だ。何度かKさんのお店に遊びに行くうちに、茅ヶ崎市には開高健資料館がある事を知った。いずれ行こうと思っていたが、それから数年の月日が過ぎてしまった。私がようやく訪れることができたのは、本書を読む少し前のこと。
訪れた記念館で私が受けた開高健の印象。それは行動する作家ということ。ベトナム戦争に従軍し、世界各国の魚を釣らんと訪ね巡る。その行動は、書斎にこもる作家のイメージとは対極にある。そのような著者のライフスタイルは、私の求める理想にかなり近い。それを知り、著者が残した作品を片っ端から読みたいと思った。そのはじめの一冊が本書だ。
本書はかつて刊行された二冊のエッセイ集から成っている。二冊を一冊に編みなおし、文庫化したのが本書だ。わあ最初の「眼ある花々」は旅の作家にふさわしく、世界の旅先で著者の目に焼き付いた花々についてのエッセイを集めている。
メコン川の豊穣な流れと、肥沃な大地にあるベトナム。凄惨で救いのない戦闘がすぐ近くで行われていながら、花の都の呼び名にふさわしく、多種多様な花が売られている街並みに、人の、自然の営みのたくましさを思う。「君よ知るや、南の国」
パリの街角にさりげなく活けられている花の取り澄ました感じを眺め、そこから都市論に話を伸ばしてゆく。芸術家たちが愛した街の都市の景観と、初のオリンピックを前に切りはりの発展を遂げようとする東京を比較する。「一鉢の庭、一滴の血」
鬱に沈んでいた著者がアラスカの大地でサケと出会い、生命の奔放さに活力を取り戻す。釣りやサケの魅力に内容がほぼ費やされるが、最後に、アラスカの国花がワスレナグサであり、その慎ましやかな花が雄大な大地を象徴することに自然のバランスを感じる。「指紋のない国」
ジャスミン茶が茶碗に浮いている様子から、花茶の数々を並べ立て、ウンチクを傾ける著者。やがて著者の初めての海外旅行で味わった中国での思い出話と、その後の文化大革命が著者の想い出を汚したことに感傷を挟む。「茶碗のなかの花」
ついでに著者は北海道に目を向ける。スズラン、そしてハマナス。実は北海道が花にあふれた北の国であることに気づかされる。原生花園。原野。著者の第一の関心事は魚にあるのかもしれないが、花の描写が楽しげで旅情を刺激される。北海道を描いた旅のエッセイとして覚えておきたい。「寒い国の花」
また別の日に著者はカメラマンとバンコクに飛ぶ。美しい海とそこで獲られる貝。そこに著者は花の美しさを重ねる。饒舌な会話がちりばめられる中、著者の観察は目を飽きさせないほど生息する色とりどりの動植物を味わい尽くす。その豊かさこそが人生の味わいとでも言うかのごとく。「南の海の種子」
続いてはギリシャだ。白い家々に多彩な花弁が咲き誇る様は、さぞや見応えがあるだろう。著者はギリシャの豊穣な神話や戦争で明け暮れた歴史にギリシャの雑多さをみる。著者の想像力は、ギリシャに咲き誇る百花斉放の花の一つ一つがギリシャを主張しているかのように表現する。それが。あゝと叫ぶ。「 ああ!・・ 」
著者は続いてソバの花を語る。あの白くて小さいやつだ。ソバの花の可憐でひっそりとしたすがたに著者は価値を見いだす。痩せた大地でも花を咲かし実をならせる生命力に著者の称賛はやまない。そして痩せた大地の恵みに妙味を発見した人類のたくましさを著者は褒めそやす。「ソバの花」
同じ白い花でも、著者が続いて取り上げる塩の花、つまり死海に咲く塩の華は、投げ込んだ枯れ枝に群がった塩が、ひっしとしがみついて花を咲かせる。それは著者に自然の摂理の美しさと人類には決して味わい尽くせない妙味を教えてくれる。「死の海、塩の華」
著者の旅はバリ島へと至る。バリ島といえば人々の集う地。そこで著者の思索は人種の差とは何かにたどり着く。人間、どこに生まれようと営みは一緒。それを思い出させるようなエッセイだ。分析のような論理展開がなく、ダラダラとつながっているだけのような文の行間から、著者の考えを立ち上らせるあたり、見事。「バリ島の夜の花」
かと思えば、著者は越前岬の荒々しい自然にたたずむ旅の宿で、冬の水仙を堪能している。越前岬はかつて福井の母の実家まで自転車で走破した際に通り過ぎたことがある。人のおらぬ地で旅情に浸る。これもまた、著者の流儀だ。本書を読んでいると、つくづく思わせてくれる。旅人が備えるべき観察眼とはかくありたいものだ、と。「寒い国の美少年」
最後を締めてくれるのは、アンコールワットやノイシュヴァンシュタイン城のような城が歴史を超えて咲き誇っている様をバラに見立てた著者の着眼だ。城がその精妙で複雑な造形で数百年後にも残り続けているように、バラもその飽きさせない姿で私たちの目を数千年のちまで楽しませてくれるはず、と。「不思議な花」
花々のイメージを豊かに世の事物とつなげ合わせ、語る手法。それは私にエッセイの妙とその味わい方を教えてくれた。
本書の後半六割は「開口一番」が収められている。「開口一番」はかつて出版されたエッセイ集の再録だ。こちらはテーマを絞っていない。さまざまに話題が展開される。釣り、魚、パイプ、スキー、セキフェなどのゲテモノ料理、銘酒の数々。著者の博学はとどまるところを知らない。
そうかと思えば、三浦朱門氏が唱えた結婚反対論に挑戦し、「早婚絶対幸福論」と題して硬軟を織り交ぜた議論を展開する。 「結婚は人生の墓場である」とのたまう三浦朱門氏の論に対し、慇懃かつズバリとその矛盾をつき、たしなめるのだ。曽野綾子氏を伴侶に持つ三浦朱門氏の言葉は、曽野綾子氏への侮辱ですよ、といわんばかりに。まあ、著者の唱える結婚も、希望も何もないサバサバとしたものだが。
そして著者の筆は美女の定義を求めてさまよう。各国の中でルーマニアが一番美女ぞろいであったという著者の感想を皮切りに、本書は急速に品を落として行く。ルーマニアで翻訳を頼んだ女性に日本語の一、二、三(ひー、ふー、みー)と話すと、その二番目がルーマニア語で女性器を表していたため、彼女を恥じらわせてしまった話。中国語のウォーアイニーも発音によっては我愛泥になってしまう話題とか。
続いて著者が語るのは銀座だ。著者の庭のような場所なので話は尽きない。次から次へと店や名物、名酒が登場し、客の酔態が暴かれる。話題は銀座から麻布や六本木へと移動しつつ、著者のウンチクは都内の繁華街を縦横に取り上げてゆく。その行く先はゲイの発展場。著者の話題に果てはない。
次いではスリだ。東京のスリは世界一の腕前だとか。警視庁の警部に取材した会話を交えつつ、その中で披歴されるスリの手口や生態。それらをつらつらと俎上に乗せ、批評する。読んでいるこちらまでスリの専門知識を蓄えてしまう。著者の語り口にはただ酔わされるばかりだ。
そしてついに著者はわいせつを語り始める。編集者たちを集めてブルーフィルムの鑑賞会を開帳した話。そこであからさまに映し出される性器の形をあれこれ品評する話から、諸外国での大人のオモチャ屋さんやエログロメディアの今を語ってゆく。何でも規制が緩むことは、表現者にとっては必ずしも恵まれてはいない、と釘をさしつつ。
このような話題の乱雑さと広大な論理の展開。これこそ私がそうありたいと望む生き方なのだ。引き出しが多いとはまさにこのこと。著者の生き方に一つの目標を見いだしている私にとって、著者の高みは遥か先にある。
飽きを知らない豊富な話題を語りつつ、その中に人生の叡智を紛れ込ませる技。その技はあとがきで女優・演出家の野崎美子氏が語る通り、作家が一瞬見せたナイフの研がれ様。著者の域に達するにはあとどれぐらい旅をすればよいのだろう。
若きの日に
旅をせずば、
老いての日に
何をか、
語る?
中国の古典が原典というこちら、開高健記念館で購入した絵葉書に書いてある文句だ。老いて語れるような人間になるためにも、まだまだ旅をせねばなるまい。本書は家族で訪れた東京ディズニーシーで読んでいたが、東京にあるジャングルではなく、ジャングルにあるジャングルで読んでこそ旅の感性は養われるのだから。
‘2017/11/17-2017/11/20


