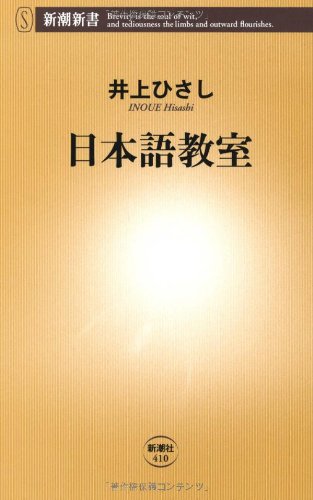

『相手に「伝わる」話し方』()に続いて読んだのが本書。二冊とも表現がテーマだ。私が続けて同じ分野の本を読もうと思ったのは、私の向上心ゆえだ。今後、世の中を渡っていく上で求められるスキルは無数にある。私もその中のいくつかは装備して世渡りの助けとしている。中でも文章を書く能力は、私が独力で、組織の力を借りることなく、世に打って出られる可能性の高いスキルだと思っている。
私が最近予想すること。それは今後、人工知能がいつの間にか、世のあらゆる分野になくてはならない存在になる、ということだ。それは、組織のあり方を劇的に変えてゆくはずだ。世の中の多くの組織は段階を踏んで解体されて行き、今私たちがなじんでいるものとは違う組織になっていることだろう。今までは組織の人員の力で対応しなければ成し遂げられたなかった仕事が、人口知能によって相当の領域で置き換えられていくに違いない。それは、人工知能vs人間といったわかりやすい構図ではなく、いつのまにか人工知能に深く依存し、そこから引き返せなくなる未来として私の脳裏に思い浮かぶ。
ただ、組織の未来を考えるとき、人の組織への帰属心は容易には消えないはずなので、組織は何らかの形で残っていくに違いない、とも思う。一方で組織の中で働く個人に求められるスキルは変わっていくことだろうという予想も湧き出てくる。つまるところ、組織に勤めていようが独立していようが、これからの個人に求められるスキルとは、組織の中で人々を調整する力よりも個人の力ではないかと思うのだ。とくに個人は、実名で何かを発信しなくては、かなり厳しくなるのではないか。
そのための準備として私が鍛えるべきなのは文章力、そして日本語力だ。著者は日本語にこだわる作家としてよく知られている。ちなみに私は著者の小説は読んだことがない。私の親が著者の文庫本を何冊も持っていて、そのタイトルをそらんじられるにもかかわらず。それなのに、著者の名作たちを差し置いて、はじめに読む著者の本が講演集であることの後ろめたさ。さらにいうと私は著者のことを何も知らなかった。そもそも著者が上智大学出身であることすら、本書を読んで初めて知った次第だ。
本書は著者の出身校である上智大学での講演を書籍化したものだ。講演であるため、本書は話し言葉で貫かれている。つまり、すらすらと読める。しかも時々脱線する。そうした酒脱な雰囲気が本書には始終流れており、楽しく読める。
著者の軽妙な姿勢は、日本語に対する考えからも感じ取れる。本書の第一講「日本語はいまどうなっているのか」では、現代の日本語に英語が幅を利かせつつある状況を紹介する。ところが著者はそれをただ憂うのではない。日本語原理主義を振りかざすこともしない。著者は英語が氾濫する今の日本語に警鐘を鳴らしつつ、言葉は変わりゆくものと柔軟な意見も開陳する。正直いって私も今のカタカナ語の氾濫には閉口している。IT業界に属していると、ビジネス用語も含めた外来語の氾濫にさらされる。しかもIBMなどの外資系の文化が横行する現場だとなおさらだ。それゆえ、過度の日英の単語がちゃんぽんされ、飛び交う現状にはこれ以上ついていけない。だから、その融合するスピードをもう少し緩められないか、という著者の意見に与したい。著者は第二講の「日本語はどうつくられたのか」の中でリコンファームやエンドースメント、そしてコレクトコールのような言葉は無理に日本語訳にせず、外来語のままでよい、とも言っている。そのあたりの柔軟さは必要だし、本書はその点で好感が持てる。
昔、漫画『こち亀』の中で外来語を日本語に律義に言い換えるおじさんが登場したことがある。たとえば「ローリングストーンズ」を「転がる石楽団」とかいう感じで。日本語に相当する言葉がないのなら、珍妙な日本語を作ることにこだわらず、外来語は外来語のままで、というのが著者の主張だ。
第二講で著者は、明治期に西周や福沢諭吉といった人々が外来語を苦労して日本の言葉に翻訳した歴史を紹介する。当時は彼らのような碩学が苦労して翻訳の労を取ってくれた。だが、今は当時とは違い、情報の流入量が違いすぎる。どこまでを外来語として取り入れ、どこまでを日本語に翻訳していけば良いか。それは常に文を書く上で意識していくことが求められる。もう一つ、第二講では、著者の政治的な意見も吐露される。どちらかといえば左寄りの発言が知られる著者の想いが。
たとえば、「完璧な国などないわけですね。かならずどこかで間違いを犯します。その間違いを、自分で気が付いて、自分の力で必死で苦しみながら乗り越えていく国民には未来があるけれども、過ちを隠し続ける国民には未来はない。」(118P)との箇所がそうだ。著者も含め、左寄りとされる論客は話が国際関係に及んだとたん、その主張の説得力がなくなってしまう。対象が自分の国だけならそれで良い。けれど、相手の国があると理想主義を貫くのは難しい。
第三講「日本語はどのように話されるのか」で著者が語るのは、日本語の音韻の特徴だ。日本語の母音は”あ”、”い”、”う”、”え”、”お”の五つからなっている。その特徴を説明するため、著者は斎藤茂吉の短歌を取り上げる。
「最上川 逆白波の たつまでに ふぶくゆふべと なりにけるかも」
ここで最初の「もがみがわ」の中の”あ”の母音が三つ含まれるところに、著者は開放的な語感を指摘する。また、”う”が五つも続く「ふぶくゆふべ」の語感からは、「吹雪く夕べ」に耐える様子が表現されている指摘する。語感から日本語を指摘する見識はさすがだ。
この前に読んだ『相手に「伝わる」話し方』でも音読の重要性について学んだばかり。母音の数が少ない日本語は、同音異義語、つまりダジャレの土壌となる。また、言葉が母音で終わる日本語の特徴は、外国人の耳に美しい言葉として聞えるらしい。もう一つ、「茶畑」と「田畑」の読みが「ばたけ」と「はた」というように音が濁る場合とそうでない場合についても解説されている。「田」と「畑」のように並列の場合は濁らず、「茶」の「畑」のように従属関係にある場合は濁る。著者はこういった使い分けが日本語に連綿と語り継がれていることを指摘する。これらはとても興味深い。
もう一つ、興味深かった点は、日本語で一息で発音できる音節が十二という記述だ。十二を六と六に分けるとリズムがでない。なので、五と七に分けた。それはつまり俳句のリズムだ。短歌から連歌に発展したリズムが、俳句とつながってゆく。この部分もとても勉強になる。俳句が世界で一番短い詩と言われる秘密がさらりと示される。
第四講「日本語はどのように表現されるのか」では、著者は文法を取り上げる。日本語の文法の構造は、外来語が入ってきたところでおいそれと崩れないことも指摘する。言われてみれば確かにそうだ。「私は」「旅が」「好きだ」と日本語はSOV(主語+目的語+動詞)の順番に並ぶ。しかし英語は「I」「Like」「Travel」とSVO(主語+動詞+目的語)の順に並ぶ。どれだけ英単語が日本語に入り込もうとも、「私は好きだ旅が」という表現が日本で市民権を得るのは難しいし、もしそうなるとすれば、相当の年月がかかるはずだ。それゆえ著者は文法を整理した学者の努力を認めつつ、「私たちは日本語の文法を勉強する必要はないのです。無意識のうちにいつのまにか文法を身につけていますから」(161P)と結論付けるのだ。結局、無意識に刷り込まれた文法の構造こそ、著者にとって守るべき日本語の芯なのだろう。そして日本文化の芯なのだと思う。
先に書いたとおり、本書には右傾化する日本を揶揄する著者の毒が何カ所かで吐かれる。でも、それはあくまで外交関係や領土の領分の話。そういった観点で日本のナショナリズムを主張するのではなく、著者のように文化の立場から日本のナショナリズムを主張してもよいのではないか。私は本書を読んでそう思った。それをごちゃまぜにするのではなく、文化は文化として守るべき。そう考えると左寄りと見られがちな著者は、立派に愛国心を持った人物だと見直すことができる。イデオロギーでカテゴライズすることの浅はかさすら感じさせるのが本書だ。
本書をきっかけに、著者の著作も読んでみなければ、と思うようになった。そこにはきっと、手本にすべき美しい日本語が描かれているはずだから。
‘2018/01/18-2018/01/19


