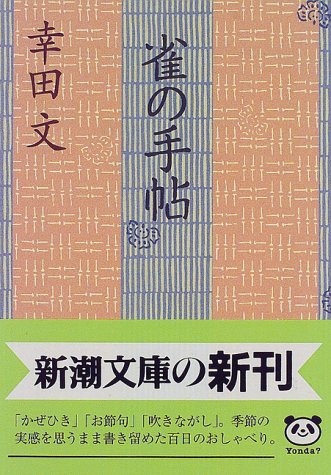これこそ著者の毒がそこいらにまかれたスラップ・スティックの宝の山だ。
著者にかかればタブーなどどこ吹く風。性も英雄も深刻な事件も政治も茶化してしまう著者の悪ノリが盛り込まれている。
「誘拐横丁」
複数のご近所家族が子どもを誘拐しあうぶっ飛んだ内容の短編。
ご近所同士で子を奪い合い、金をよこせとお隣さんの間で金が飛び交う。
そんな狂った関係も本当の殺戮につながらず、最後は乱交パーティーに突入するあたりが、本編のユーモラスな後味につながっている。
そこには著者の根本の人の良さが垣間見える。
「融合家族」
一つの家屋を奪い合った結果、二組の夫婦が標準的な広さの家屋に無理やり同居する話。
片方の家族の居間がもう片方の家族の使う台所で、片方の家族の玄関はもう片方の家族の夜の寝室を使う。しかもお互いを意識しつつ無視しながら。
こんなこんがらがった設定は小説ならでは。本編こそ映像化できない作品といえるのではないか。そして著者のすごさが堪能できる作品だと思う。
ちなみに本編も最後は乱交パーティーに突入する。
「陰悩録」
本書を読む一カ月前に訪れた世田谷文学館の筒井康隆展で、数作品の拡大された生原稿のすべてが壁に掲げられていた。
「関節話法」「バブリング創世紀」と並んで本編も。
ひらがなを主体に記された本編は、ユーモアを失わずにオチで読者を驚かせる。その点からも著者の名作の一つである事は言うまでもない。
おそらくは著者が入浴した際にひらめいたのだろうけど、そこから本編にまで発想をふくらませられたことがすごい。
「奇ツ怪陋劣潜望鏡」
人の心に潜む欲望が妙な幻覚として日常をむしばんでいく様子が描かれている。妙な幻覚とは、抑圧された性への渇望を抱えたまま結婚したあるカップルに起こる。
具体的には潜望鏡の形をとって日常のあらゆる場所に登場する。
今から思うと、よくありがちなネタなのだろう。だが、無意識の現れなど随所に著者の心理学の知識が現れているのが面白い。
もっとも、本編が前提としている性の抑圧は、ネット上でいくらでも性的な発散ができる現代では通用しない気もするが。
「郵性省」
これまた性のエネルギーについて。
オナニーによってテレポーテーションができる能力を身につけた益夫の物語。
男子の、しかも高校生の性のエネルギーはかなり高そう。だから、本編のような突き抜けた物語もあながち夢物語には思えない。
それにしても著者の突き抜け方はさすがと言うしかない。着想からの展開の広がりは、著者の感嘆すべき点だ。
本編はオチも秀逸。
「日本列島七曲り」
表題作。発表された当時、盛んだったハイジャックを風刺している。
こうした深刻な事件も著者の筆にかかれば、スラップ・スティックの格好の題材になる。実際、思想のために飛行機を乗っ取る行いなど、悪い冗談でしかない。9.11でワールドセンタービルに飛行機が突っ込む瞬間を中継で見ていた私は、なおさらそう思う。
本編を不謹慎というのは簡単だが、テロ行為をこうした手法で批評したっていいじゃないかと思う。
「桃太郎輪廻」
桃太郎という誰もが知る童話も著者が翻案すると、悪趣味な内容へと早変わり。
桃太郎だけでなく、グリム童話の名作も取り込んだ内容は、童話のほのぼの感とは無縁。
本能のままに突き進んだ桃太郎一行がやらかす悪事は、童話として中和され薄められた物語の元となった逸話がもっとギラギラとヤバかった事を思わせる。
本編のオチは有名な桃太郎の冒頭シーンにきっちりと輪廻させていて、そうした部分に著者の着想のすばらしさを感じる。
「わが名はイサミ」
メタキャラとして著者が顔を出しまくる本編は、新撰組局長の近藤勇を茶化しまくっている。歴史上の英雄だろうが知ったことか、とばかりに。
勝沼の戦いに赴くまでに甲陽鎮撫隊が連日宴会を繰り返しながら進軍し、新政府軍に先に甲府城を押さえられた失態は史実に残されている。その史実をモチーフに、近藤勇の人物を徹底してけなしている。
まったく、著者にはタブーなどないのか、と思いたくなる。
「公害浦島覗機関」
本編は著者の作品の中でも上位に挙げられるべき作品ではないかと思う。
ホテルの中にある謎の空間の存在に気づいた主人公。
空間からは二つの部屋がのぞける。部屋の様子から、どうも空間の中は周囲に比べて時間の進みが遅くなるらしい。
客室の一つでは首都から人を追い出すため公害を促進しようと画策する政治家が指示を出している。その政策が功を奏し、人が住めないレベルにまで大気汚染が進む。ところが人は首都圏にしがみつき続けそして。
作品のオチが見事。
「ふたりの秘書」
二人の女性の秘書に二股をかける社長のドタバタ。
著者にはフェミニストを敵に回す作品がいくつかあるが、本編もその一つ。
見えと虚栄と相手との比較に余念がない女性の一面を、二人の秘書を描くことで表現している。
ロボット秘書もチラッと登場させることで、人間の人間臭さを揶揄しつつ、人間のおかしみを出すあたり、著者の人の良さがわずかに見える気がする。
「テレビ譫妄症」
テレビ評論家が大量のテレビを見ているうちに、現実との境目が曖昧になっていく様が描かれている。
これはありがちな設定かもしれない。だが、数日間ぶっ通しでオンラインゲームをして死ぬ若者が報道される今、違う意味で現実味を持って迫ってくる。
VRやARなどが私たちの暮らしに身近になってきた最近では。
‘2018/11/08-2018/11/09