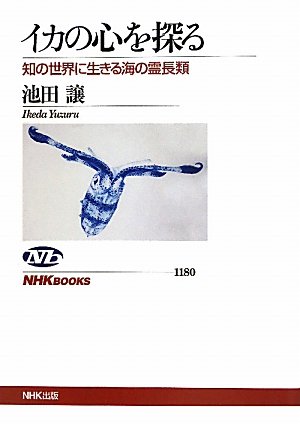著者の名前は最近よく目にする。
おそらく今、乗りに乗っている作家の一人だからだろう。
私は著者の作品を今まで読んだことがなく、知識がなかったので図書館で並ぶ著者の作品の中からタイトルだけで本書を手に取った。
本書の内容は地方創生ものだ。
都会で生活を見失った若者が田舎で生きがいを見いだす。内容は一言で書くとそうなる。
2017年に読んだ「地方創生株式会社」「続地方創生株式会社」とテーマはかぶっている。
だが、上に挙げた二冊と本書の間には、違いがある。
それは上に挙げた二冊が具体的な地方創生の施策にまで踏み込んでかかれていたが、本書にはそれがないことだ。
本書はマクロの地方創生ではなく、より地に足のついた農作業そのものに焦点をあてている。だから本書には都会と田舎を対比する切り口は登場しない。そして、田舎が蘇るため実効性のある処方も書いていない。そもそも、本書はそうした視点には立っていない。
本書は、田舎で置き去りにされる年配者の現実と、その介護の現実を描いている。そこには生きることの実感が溢れている。
生きる実感。本書の主人公である麻生人生の日常からは、それが全く失われてしまっている。
小学生の時に父が出て行ってしまい、母子家庭に。その頃からひどいいじめにさらされ、ついには不登校になってしまう。高校を中退し、働き始めても人との距離感をうまくつかめずに苦しむ日々。そしてついには引きこもってしまう。
生計を維持するため、夜も昼も働く母とは生活リズムも違う。だから顔を合わせることもない。母が買いだめたカップラーメンやおにぎりを食べ、スマホに没頭する。そんな「人生」の毎日。
だがある日、全てを投げ出した母は、置き手紙を残して失踪してしまう。
一人で放りだされた「人生」。
「人生」は、母の置き手紙に書かれていたわずかな年賀状の束から、蓼科に住む失踪した父の母、つまり真麻おばあちゃんから届いた達筆で書かれた年賀状を見つける。
マーサおばあちゃんからの年賀状には「人生」のことを案じる文章とともに、自らの余命のことが書かれていた。
蓼科で過ごした少年の頃の楽しかった思い出。それを思い出した「人生」は、なけなしの金を持って蓼科へと向かう。
蓼科で「人生」はさまざまな人に出会う。例えばつぼみ。
マーサおばあちゃんの孫だと名乗るつぼみは、「人生」よりも少し年下に見える。それなのにつぼみは、「人生」に敵意を持って接してくる。
つぼみもまた社会で生きるのに疲れた少女だ。しかもつぼみは、立て続けに両親を亡くしている。
「人生」の父が家を出て行った後、再婚した相手の実子だったつぼみは、「人生」の父が亡くなり、それに動転した母が事故で死んだことで、身寄りを失って蓼科にやってきたという。
「人生」とつぼみが蓼科で過ごす時間。それはマーサおばあちゃんの田んぼで米作りに励みながら、人々と交流する日々でもある。
その日々は、人として自立できている感触と、生きることの実感を与えてくれる。そうした毎日の中で人生の意味を掴み取ってゆく「人生」とつぼみ。
本書にはスマホが重要な小道具として登場する。
先に本書は田舎と都会を比べていない、と書いた。確かに本書に都会は描かれないが、著者がスマホに投影するのは都会の貧しさだ。
生活の実感を軸にして、蓼科の豊かな生活とスマホに象徴される都会の貧しさが比較されている。
都会が悪いのではない。スマホに没頭しさえすれば、毎日が過ごせてしまう状況こそが悪い。
一見すると人間関係の煩わしさから自由になったと錯覚できるスマホ。ところがそれこそが若者の閉塞感を加速させている事を著者はほのめかしている。
「人生」がかつて手放せなかったスマホ。それは、毎日の畑仕事の中で次第に使われなくなってゆく。
そしてある日、おばあちゃんが誤ってスマホを池に水没させてしまう。当初、「人生」は自らの生きるよすがであるスマホが失われたことに激しいショックを受ける。
だが、それをきっかけに「人生」はスマホと決別する。そして、「人生」は自らの人生と初めて向き合う。
田舎とは人が生きる意味を生の感覚で感じられる場所だ。
本書に登場する蓼科の人々はとにかく人が良い。
ただし、田舎の人はすべて好人物として登場することが多い。実際は、それほど単純ではない。実際、田舎の閉鎖性が都会からやってきた若者を拒絶する事例も耳にする。すべての田舎が本書に描かれたような温かみに満ちた場所とは考えない方がよい。
本書で描かれる例はあくまで小説としての一例でしかない。そう受け取った方がよいだろう。
結局、都会にも良い人と悪い人がいるように、田舎にだって良い人や悪い人はいるのだから。
そして、都会で疲れた若者も同じく十把一絡げで扱うべきではない。田舎に合う人、合わない人は人によってそれぞれであり、田舎に住んでいる人もそれぞれ。
「人生」とつぼみはマーサおばあちゃんという共通の係累がいた事で、受け入れられた。彼らのおかれた条件は、ある意味で恵まれており、それが全ての若者に当てはまるわけではない。その事を忘れてはならない。
そうした条件を無視していきなり田舎に向かい、そこで受け入れられようとする甘い考えは慎んだ方がよいし、受け入れられないからと言って諦めたり、不満をSNSで発信するような軽挙は戒めた方が良いだろう。
私は旅が大好きだ。
だが私は、今のところ田舎に引っ越す予定はない。
なぜなら生来の不器用さが妨げとなり、私が農業で食っていく事は難しいからだ。多分、本書で描かれたようなケースは私には当てはまらないだろう。
一方で、今の技術の進化はリモートワークやテレワークを可能にしており、田舎に住みながら都会の仕事をこなす事が可能になりつつある。私でも田舎で暮らせる状況が整っているのだ。
そうした状況を踏まえた上で、田舎であろうと都会であろうと無関係に老いて呆けた時、都会に比べて田舎は不便である事も想定しておくべきだ。
本書で描かれる田舎が理想的であればあるほど、私はそのような感想を持った。
間違いなく、これからも都会は若者を魅了し続けることだろう。そして傷ついた若者を消耗させてゆくだろう。
そんな都会で傷ついた「人生」やつぼみのような若者を受け入れ、癒やしてくれる場所でありうるのが田舎だ。
田舎の全てが楽園ではない。だが、都会にない良さがある事もまた確か。
私はそうした魅力にとらわれて田舎を旅している。おそらくこれからも旅することだろう。
都会が適正な人口密度に落ち着く日はまだ遠い先だろう。
しばらくは田舎が都会に住む人々にとって、癒やしの場所であり続けるだろう。だが、私は少しずつでもよいから都市から田舎への移動を促していきたいと思う。
そうした事を踏まえて本書は都会に疲れた人にこそお勧めしたい。
‘2019/01/20-2019/01/20