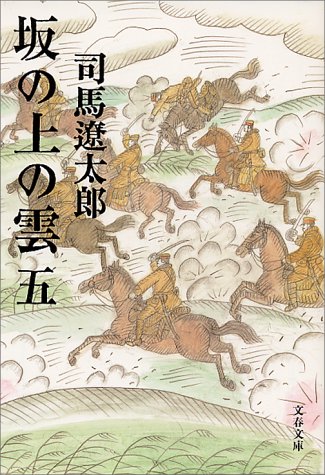ここ数作のミッション:インポッシブルは、次女と映画館へいって鑑賞することが恒例になっている。
今回も同じ。私と次女の予定を合わせる必要があったので、私たちが劇場に行ったのは公開されてからほぼ1ヵ月後。劇場は閑散としていて、私たち2人を含めても10人ぐらいしか劇場にはいなかったように思う。
さすがのトム・クルーズの話題作であっても、1ヵ月もたつとこれほどまでに人が減ってしまうのかと思った。
減った理由として一瞬脳裏をよぎったのは、主演のトム・クルーズの加齢だ。
本作は、前作の『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』よりもトム・クルーズが容貌がさらに老けたような気がした。そう感じたのは私だけだろうか。
先日公開された『トップガン:マーヴェリック』も次女と劇場でみたが、トム・クルーズが演ずるマーヴェリックは自らの加齢を前提にしていた。そして、並み居るパイロットたちを導く立場で出演していた。
ところが本作のトム・クルーズは第一線に立って体を張っている。スパイとして走り、飛び、闘う。現役のアクションスパイである。
私は『トップガン:マーヴェリック』のレビューの中でこのように書いた。
「本作のマーヴェリックの姿にうそっぽさがないとすれば、トム・クルーズの演技に年齢の壁を越え、さらなる高みへと努力する姿が感じられるからだろう。」
まさに本作もそう。加齢によってトム・クルーズの口の脇に刻まれたほうれい線が特に目についた。
もっとも、ほうれい線など、今の技術であれば簡単に消せるはずだ。だが、トム・クルーズはそれをよしとしない。
人は加齢する。これは当たり前のことだ。
その当たり前をごまかそうとしない潔さ。それでいて60歳を超えたとはとても信じられないアクションをスタントマンに頼らずに自らでこなす。
この真っ当さがいいのだ。この正直なところに私たちは惹かれるのだ。
本作もパンフレットが買えなかったので、どのシーンがスタントマンを使わずにトム・クルーズがこなしたのか、私はあまり知らない。
ただし、メイキング映像がYouTube(https://youtu.be/SE-SNu1l6k0)で上がっている。その動画を紹介する記事だけは事前に読んだ。
それによると、500回のスカイダイブ、そして1万3000回ものモトクロスジャンプの練習をこなしたらしい。その練習の成果があのシーンに現れているそうだ。
まさに、努力の塊である。
一万時間の法則という理論がある。人が何かの分野で一流になるためには、一万時間を費やしている、というものだ。
この法則はマルコム・グラッドウェルというジャーナリストが発表した本の中に書かれているらしい。
もしそれがまことなら、トム・クルーズは本作の一シーンだけのために一万三千時間以上を練習に費やし、一流になっているはず。それも一生ではなく、一本の映画を作るたびに何かで一流になっている。
その姿勢は素晴らしいというしかない。
本作には、かつて登場した人物も登場する。30年の、というセリフ幾たびか出てくる。若きイーサン・ハントこと、トム・クルーズのかつての写真も登場する。
あえて、今のトム・クルーズと対比させるように、過去の自らを登場させる。そうすることで、加齢した自らを受け入れ、加齢した自らを顕示し、退路を断った上で走り回る。アクションする。闘う。スタントを自らが行う。
その姿勢こそが最近の『ミッション:インポッシブル』シリーズに新たに備わった魅力ではないかと思う。
技術には頼らない。その上で痛々しさは見せない。やり切る。
世界的に寿命が延び、高齢者の割合が増加する今。本作は60歳などまだまだ若造じゃわい、という風潮を象徴する一本になると思われる。
さて、風潮という意味では、本作の中でAIの脅威が大きく取り上げられていることも見逃せない。
暴走するAIの脅威と、それをコントロールした国家こそが次世代の世界の覇者となる。そんな構図だ。
果たして、そのような未来は到来するのだろうか。
かつてアメリカのハンチントン教授が唱えた、国際関係のあり方が西洋東洋や南北対立軸から、各地の文明の衝突に変わったという論がある。
本作にはそうした構図を奉じるCIA長官や諜報部員が執拗にイーサン・ハントを追う場面が描かれる。AIを利用して次世代の国際社会の覇権を握ろうとする立場だ。だが、その立ち位置はどちらかというとイーサン・ハントの宿敵というよりは、コミカルかつ茶化された扱いに甘んじている。トリックスターのような扱いといえばよいだろうか。
かつてのスパイものの定番だった東西の対立軸。そんなものはとうに古び、茶化される存在になってしまった。
上に書いたようなAIをコントロールした国家こそが次世代の世界の覇者となる構図を奉じて走り回る。そんなCIAの立場はもはやない。
となると、本作において、AIはどういう立ち位置になるのだろうか。
暴走するAIとそれに対するイーサン・ハントという対立軸は、それはそれで手垢のついた構図のように思える。
その一方で、もはや人は争う対象ではない。それどころか、ありとあらゆる思惑が入り乱れ、単純な二極対立が成り立たない時代になっている。
スパイ映画を作る立場としては、題材を選ぶのがとても難しい時代になったのではないか。
だが、AIとイーサン・ハントを対立軸に据えると、敵、つまりAIに観客が一切共感できないとのリスクが生じる。
いわゆる、それまでのスパイ映画の悪役は人間の思考論理の延長にある悪の正義にのっとって行動しており、まだ観客には悪役を理解できる余地があった。
ところが、AIを悪役に仕立ててしまうと、そのよって立つ論理が観客に伝わらない。共感も理解もされない。
それは作品としての奥行きを著しく狭めてしまうはずだ。
本作は二部制になっている。
次の作品は本作の続きとなり、来年夏ごろの公開らしい。
本作に登場したAIが次作ではどのよう立ち位置で描かれるのか。どのようなシナリオになるのか、今から楽しみでならない。
‘2023/8/16 109シネマズ ムービル