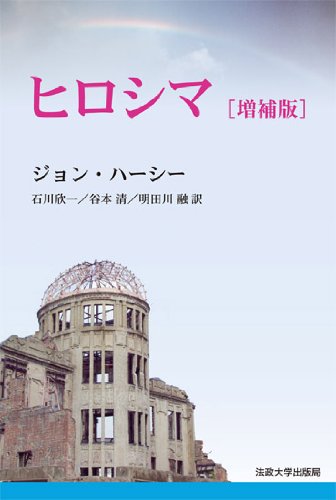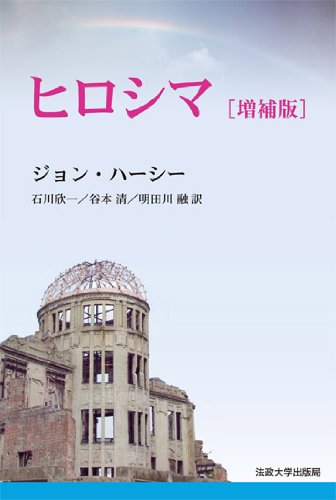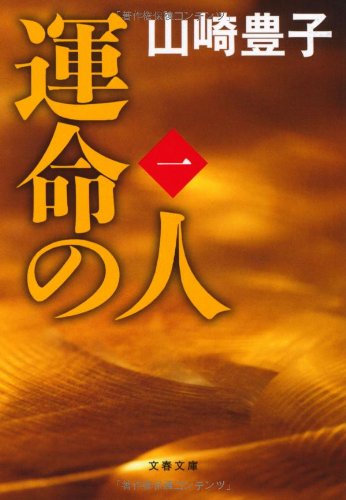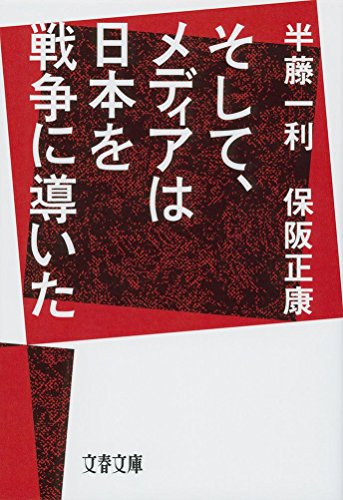空港。私たち一般人が利用できる施設のうち、おそらくは最も高いセキュリティが敷かれている場所だろう。
それはハイジャックのリスクがあるからだ。
国際空港の場合は、出国と入国審査が必須なので、より高いセキュリティが求められる。怪しい人物を自由に出入国させないための措置だ。
それゆえ、一度出国審査を終えて空港内に入ると、その間の身分は不定となる。ひとたびゲートを過ぎてしまうと、その瞬間だけはどの国の人でもなくなってしまう。トム・ハンクス主演の『ターミナル』のような事態を思い起こさせる。
もちろん、そうした事態を防ぐために、空港のセキュリティや身分チェックは厳重になっている。
本書のタイトルである神隠しとは、まさにそのゲートで消えてしまった子供の状態のことだ。本書はある家族の前で行方が分からなくなった子供の行方を追うミステリだ。
本書の面白さの一因は、舞台がアメリカに設定されていることだ。上に書いた空港とはロサンゼルス国際空港である。
アメリカが舞台なので、本書の登場人物のほとんどはアメリカ人である。
日本人が書いた日本語の小説でありながら、アメリカ人の会話や行動の描写が大部分を占めている。
もちろん、登場人物の中には日本人もいる。だが、本書に登場する日本人はほんのわずかだ。主人公のグレッグの妻の郁恵と日本の寺の住職ぐらいだろうか。あとはほぼアメリカ人。
日本人がそのような小説を書くのは大変だろう。
だが、著者のプロフィールを読むとその心配は無用だ。著者はアメリカに渡米後、起業を果たし、今もアメリカに住んでいるそうだ。
つまり、アメリカの暮らしやビジネスや事物が具体的に描写できる。
特に、空港の人が行きかう様子の描写はテンポがよい。おそらく著者は普段から空港を利用し慣れているのだろう。そして、それを文章に落とし込むための観察術にも長けているのだろう。
ロサンゼルス国際空港とは、多様な人種が集う場所である。もちろん、日本人がいることに違和感は覚えない。また、そこで最も多くを占めるのがアメリカンなのはいうまでもない。他にもヨーロッパの各国やアフリカにルーツを持つ人々が混在している。
多くの人種がひしめくことで起こること。それは人種問題だ。むしろ、人種問題とは無縁ではいられない。
そして、アメリカは多民族国家だ。
特にアメリカの場合、ほんの数十年前まではアフリカン・アメリカンの人々への差別感情が色濃く残っていた。だからこそ、人種問題には敏感であるべきだ。
在米日本人も太平洋戦争中は収容所に入れられた苦難の歴史を持っている。
だからこそ、人種問題について社会的な仕組みも整っているだろうし、人々の間に人種間の軋轢に対処するための知恵が蓄積されている。
著者の問題意識は日常からそうした問題に常に向いていて、本書はまさにそうした問題意識から描かれたと言っても良いだろう。
本書のテーマは空港のセキュリティだけではない。グレッグが勤めるジャーナリズムの現場は、インターネットに押されて終焉を迎えつつある。さらには警察司法行政改革も取り上げられている。
しかし、それらのテーマを超えて、本書で最も強調されているのは親子の愛情や絆だ。それは人種や文化を超えて同じであり、尊い。
尊いだけではなく、人はそれを守るために思いもよらない力を発揮する。
アメリカでは銃撃事件が絶えない。生命の安全が常に脅かされている。その一方で、家族や肉親を守ろうとする人々の思いは強い。
言うまでもなく、その感情は同じ人間である以上は持っていて当たり前だ。日本人であろうとアメリカ人であろうと変わりないはず。
ただ、それは頭では理解していても、実感と心から理解しているかというとためらいがある。同じ人間であり、同じ感情を共有できるはずであることは分かっていても、アメリカに住んだことのない私のような読者にとっては、実際に感情で理解しているかどうかは心もとない。
そうした微妙な文化や感情の揺れを描いていることが本書の価値なのだと思う。それを描くのが日本人の感性を持ち、アメリカの生活事情に精通した著者であることも。
もちろん、アメリカにも優れた小説家は無数にいる。日本語に翻訳されたアメリカの小説はいくらでも読むことができる。
だが、翻訳されたアメリカの小説と日本人の小説家が書いたアメリカの暮らしは、何かが違う。
本書からは翻訳小説を読んでいるような印象は受けなかった。それはおそらく、本書に登場するアメリカ人の言動が日本人と同じとの印象をうけるからではないだろうか。
なぜだろう。
それは、日本人である著者が小説を書くにあたって無意識に脚色していることもあると思う。本書はアメリカで出版されるのではなく、日本人向けに描かれている。そのため、著者はアメリカが舞台である特色は活かしつつも、家族や肉親の絆をテーマとする際に日本人の感性でアメリカ人を描いたと思われる。
家族や肉親の絆をテーマとするため、日本人の読者に向けたアメリカ人になってしまったというべきだろうか。
ただ、この私の感想は、私がアメリカ人と親しくなったことがないための誤解かもしれない。
私が正しいかどうかはどうでもよい。むしろ本書は、私に自分の認識のあやふやさを教えてくれたことに意味があると思っている。
私もなるべく日本人の殻に閉じこもらないようにしようと考えている。ただ、私の日常で付き合いがあるのは公も私もほぼ日本人だけだ。
私の年齢が上がっていくにつれ、さらに海外の人との付き合いがうまくできなくなっていくことだろう。脳が柔軟性を失っていき、慣れ親しんだ日本人との日常に埋没してしまうだろう。
本書は、私に異文化に触れていない気づきを与えてくれた。
2020/12/11-2020/12/12