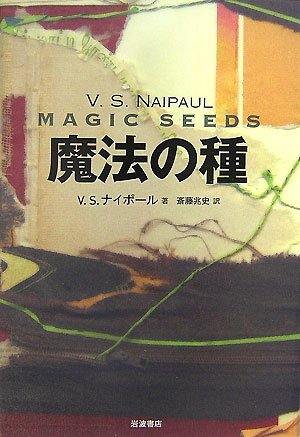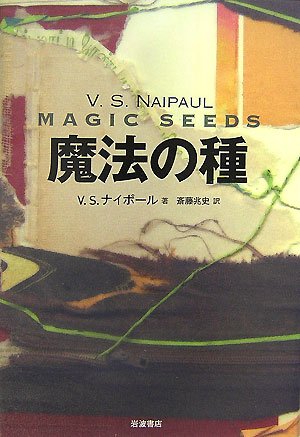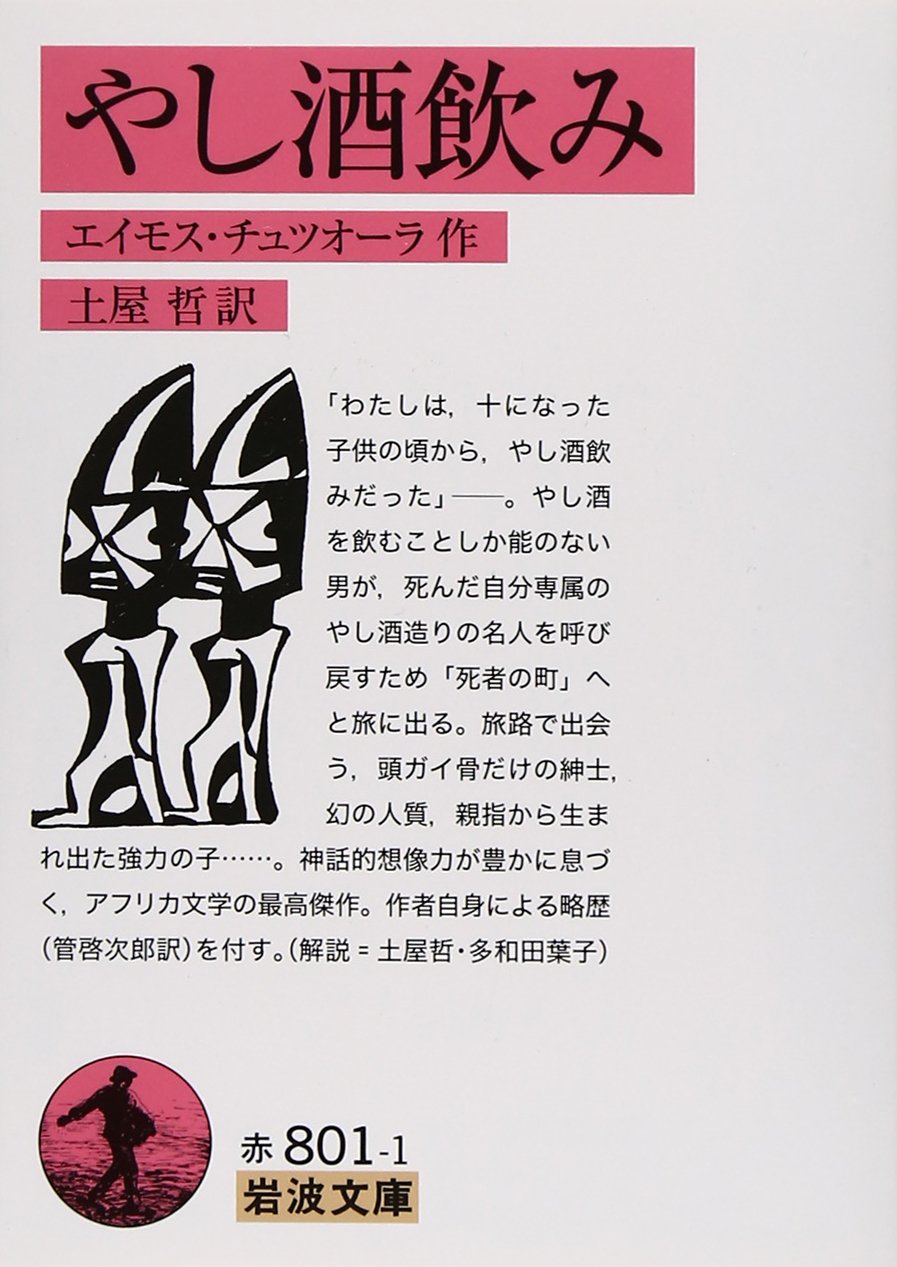
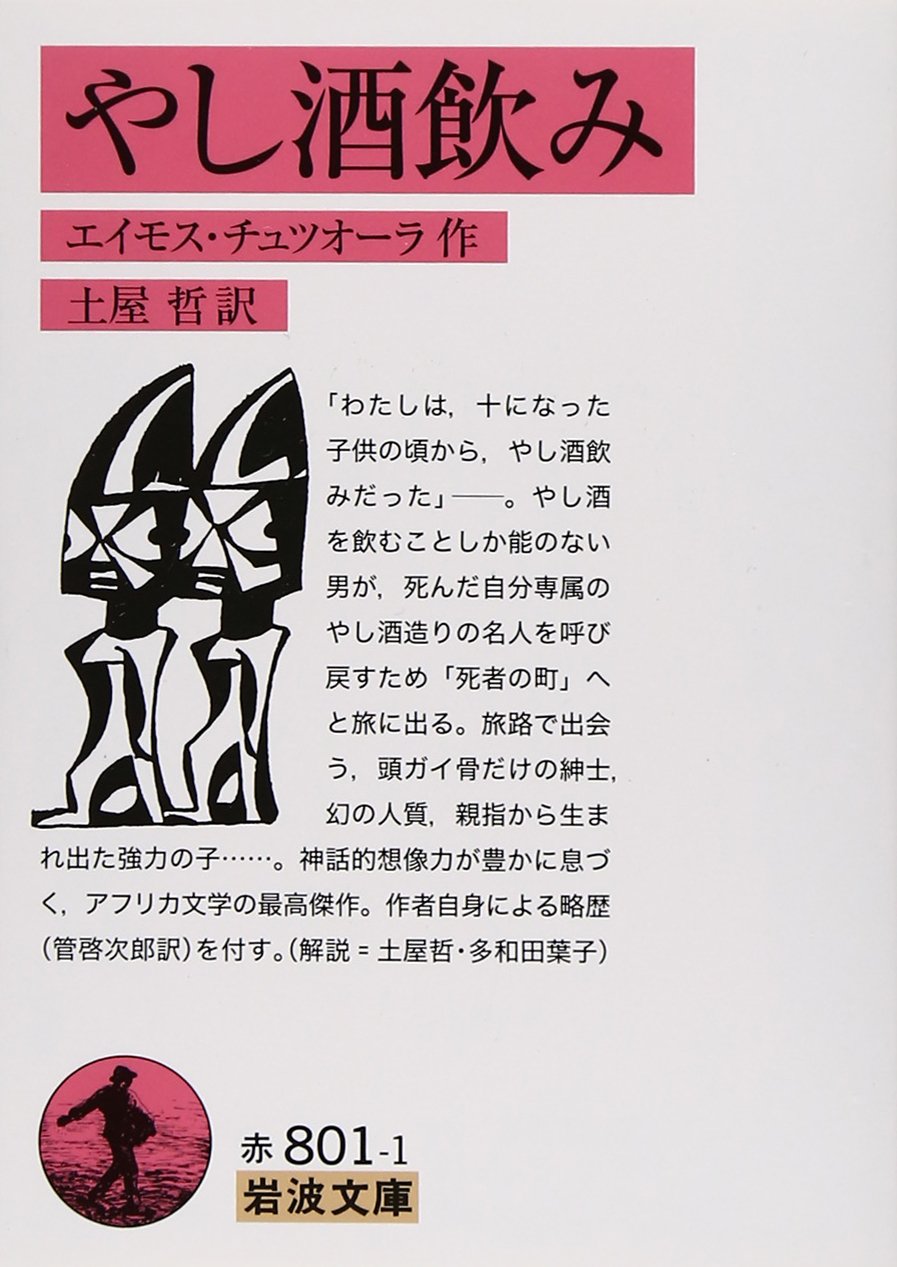
本書はアフリカ文学の最高峰としての評価を得ているようだ。
私も本書の独特の世界に惹かれた。
アフリカと聞くと、私たちは子供の頃に刷り込まれたイメージに縛られてしまう。
未開の地。広大なサハラ砂漠を擁する北部。またはサバンナのそこら中に野生動物が闊歩している大陸。
旱魃や腹を肥大させた子供の写真が脳裏に刻まれている。ルワンダのフツ族とツチ族の凄惨な内戦がニュースを彩った日からさほどたっていない。
民族同士で無益な抗争に明け暮れる一方で、極度の飢えに苦しんでいる。そんな印象が強い。
いわゆる発展途上国だらけの大陸。
そんな印象が今や一新されていることは、ネットで少し検索してみればすぐ分かる。
大都会には高いビルも並んでいる。インフラが整う前に世界の情報技術の恩恵を受けたため、モバイルを使ったマイクロ・エコノミーが他国より発達している。
むしろ、文明に疲れ始めた西洋文明の諸国よりもアフリカにこそ今後の発展が約束されている。そんな話もよく耳にする。
とはいえ、アフリカは遠い。私たちにとってネットで知る実情のアフリカは、幼い頃に聞いたターザンがジャングルで動物と語らうアフリカに及んでいない。それが正直な印象だ。
その印象に縛られた視点から見た時、本書が描くアフリカは私たちの幼い頃の印象を上書きしてくれる。
呪術が有効で、不可思議な出来事が頻繁に起こる地。
主人公はやし酒造りの名人を求め、あちこちを旅して回る。
この構成は、私たちがよく知る日本神話の世界に近い。
日本神話の中では、イザナギが黄泉の国に行った妻を追い、山彦は兄たちに言いつけられて旅をする。そしてスサノオは、さまざまな地をさまよう。
旅は神話にとって、欠かせない要素だ。ギルガメシュも旅をしていたし、モーゼと彼に従う人々もエジプトから約束の地を目指した。
本書は、まさに神話の世界を現代の物語として著している。
もっとも、アフリカにも人々が語り継いできた物語があるはずだ。著者がそれらを思い起こしながら本書を著したことは間違いない。
しかも本書で主人公たちはJUJUというものに願いをかけ、その力で困難を乗り越えていく。
JUJUとは、依り代のようなものに違いない。それは私たちも神話の世界でお馴染みのものだ。
例えばスサノオは八岐大蛇を退治する前、生贄にされそうになっていたクシナダヒメを櫛に変えて八岐大蛇と対決する。
そもそも、国産み神話からして、イザナギとイザナミがかき混ぜた矛から滴り落ちた雫から国が産まれる。スサノオもイザナギの鼻から産まれたとされている。(左の眼から天照大神、右の眼から月読命)。神自体をものから産まれたものとみなすのが日本神話だ。
今でも山そのものを御神体とみなして祈る風習は私たちの中に普通に息づいている。他にも呪いの藁人形の習俗もある。
本書で主人公がJUJUに願いをかけ、願いを託す行動は、実は日本人にとっては特に珍しくないことが分かる。
また、本書に登場する出来事は乱雑で雑多に思えるかもしれない。だが、それらは日本であってもお馴染みの概念だ。
例えば王様やそこで働く人々の間にある労働のあり方。さらには、生産と消費のつながり。また感情と制度の反目も描かれている。芸術と仕事の対立も。
もちろん本書が最も念入りに描いているのは生と死の表裏一体の関係だ。結局、先に挙げた概念も生と死を取り巻く出来事に過ぎない。
私たちは何のために生き、死ねばどうなるのか。それは日本だろうがアフリカだろうが全く関係なく、どこでも共通の関心事である。
本書をそのように読めば、この混沌とした物語の筋が通り始めてくる。
本書はやし酒をモチーフにしている。物心がついた後、飲むことしか能のない主人公がやし酒造りの名人を求めてさまよう話だ。だが、単なる酔っ払いの話ではない。
もちろん、人は酔うとあれこれおかしな妄想を頭に湧かせる。
一方で、普段の生活ではそのような妄想は理性の名の下に押さえ込み、人前ではおくびにも出さない。
その裏側では押さえ込まれた想像力がスキを見つけて表に出ようとたくらんでいる。
酒を飲めば理性のブロックが外れ、あらゆるものが混じり合った想像力の出番だ。人の内面には得体のしれない想像力が渦巻いている。
だからこそさまざまなものが入り混じった、本書のような取り留めもない神話の世界は私たちをどこか懐かしい思いにさせる。
理性にブロックされた整然とした世界でなく、ありったけの想像力を駆使した奇想天外な世界。
本書は、そのような多彩な物語を展開するからこそ、西洋文明の人々に支持されたのだろう。
本書の巻末で訳者の土屋哲氏が、実は本書はアフリカでは評判が高くなく、西洋諸国でとても高評価を得ていると紹介している。
それは西洋が理性の名のもとに押さえつけた、整然としない内面を本書が存分に開放しているからだろう。
冒頭に記した通り、幼い頃に植え付けられたアフリカに対するイメージはぬぐいがたい。だが、そのイメージのまま、豊かな想像力を押さえ込むのが正しいと思い込まされていないだろうか。むしろそのような原始的な力こそが、人間を人間として強くするように思う。
これから情報技術はより進化し、私たち人間の外で圧倒的な力を発揮していくに違いない。その時、私たちはもう一度自らの人間的な能力に目を向けるはずだ。この豊潤の想像力をどのように操るか。本書はそれをまさに体現した一冊だと思う。
‘2020/05/26-2020/05/29