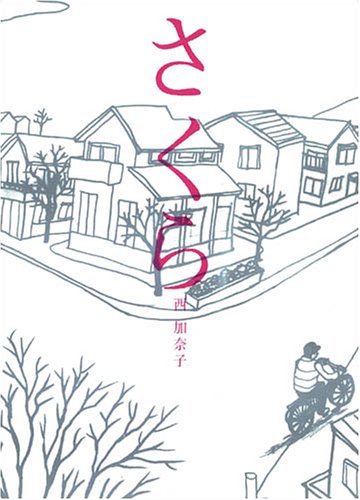
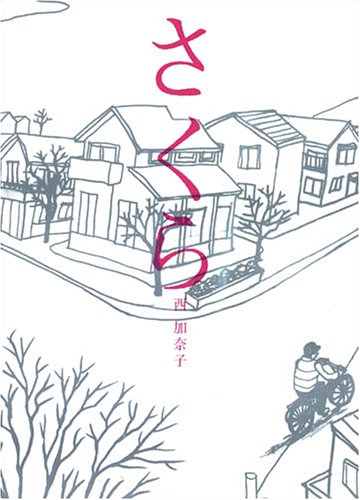
最近の私が注目している作家の一人が著者だ。
著者の「サラバ!」を読み、その内容に心を動かされてから、他の作品も読みたくて仕方がない。
著者の作品は全てを読むつもりでいるが、本書でようやく三冊を読んだにすぎない。
本書は著者が上梓した二冊目の作品らしい。
本書を読んでみて思ったのが、二冊目にして、すでに後年の「サラバ!」を思わせる構成が出来上がりつつあることだ。
基本的な構成は、ある奇矯な家族の歴史を描きながら、人生の浮き沈みと喜怒哀楽を描くことにある。
個性的な家族のそれぞれが人生を奔放に歩む。そして、それぞれの個人をつなぐ唯一の糸こそが家族であり、共同体の最小単位として家族を配している。
「サラバ!」も家族が絆として描かれていた。本書もまた、家族に同じ意味合いを持たせている。
本書でいう家族とは長谷川家のことだ。
主人公の薫が久しぶりに帰京する場面。本書はそこから始まる。
薫が帰ってきた理由は、広告の裏に書かれた父からの手紙がきっかけだった。
薫が帰った実家に待っていたのは、太った母親と年老いた犬さくらの気だるいお迎えだ。その傍らで妹のミキが相変わらずお洒落に気を使っている。
なにやらいわくがありそうな長谷川家。
著者は長谷川家の今までのいきさつを語ってゆく。
美男と美女だった父と母。二人が出会い、結婚して最初に生まれたのが薫の兄、一だ。
さらに薫が生まれ、しばらくしてミキが生まれる。美しく貴いと書いてミキ。
その名前は、はじめての女の子の誕生に感動した父が、こんなに美しく貴い瞬間をいつまでもとどめておきたいと付けた。
この時、長谷川家は幸せだった。幸せを家族のだれもが疑うことがなかった。
誰にでもモテて人気者の兄。それなりに要領よく、目立たぬようにそつなくこなす薫。そして誰の目をも惹く美貌を持ちながら、癇の虫の強いミキ。三人が三様の個性を持ちながら、幸せな父と母のもと、長谷川家の将来は晴れわたっているはずだった。
そんな家族のもとにやってきたのが、雑種の大型犬であるさくら。
その時期、両親は広い庭のついた家を買い、さくらはその庭を駆け回る。
何もかもが満たされ、一点の曇りもない日々。
なんの屈託もない三人兄妹と両親にはユニークな知り合いが集まってくる。
父の昔からの友人はオカマであり、ミニには同性愛の傾向がある。兄の一の彼女は美貌をもちながら家庭に問題を持つ矢嶋さん。
長谷川家をめぐる人々に共通するのは、マイノリティという属性だ。
同性愛もそうだし、性同一性障害も。
周りがマイノリティであり、そのマイノリティの境遇は長谷川家にも影響を及ぼす。それは本書の展開に大きく関わるため、これ以上は書かない。
とにかくいえるのは、本書がマイノリティを始めとしたタブーに果敢に挑んだ作品ということだ。
尾籠な話と敬遠されがちなうんこやおしっこに関する話題、子作りのセックスに関する話題、そしてマイノリティに関する話題。
どれもこれも書くことに若干のためらいを覚えるテーマだ。ところが著者はそのタブーをやすやすと突破する。さり気なく取り上げるのではなく、正面切って描いているため、読む人によっては抵抗感もあることだろう。
だが、ここまでタブーを堂々と取り上げていると、逆に読者としても向かい合わずにはいられなくなる。本書の突き抜けた書き方は、タブーをタブーとして蓋をする風潮に間違いなく一石を投じてくれた。
何よりもわが国の場合、文学の伝統が長く続いている割には、そうしたタブーが文学の中から注意深く取り除かれている。もちろんそれは文学の責任ではない。
今までの日本文学もその時代の日本の世相の中では冒険してきたはずだと思う。
だが、その時代ごとの日本社会にはびこるタブーが強すぎた。そのため、今から考えるとさほど刺激が強くないように思えても、当時の世論からはタブーを取り扱ったことで糾弾されてきた。
そして、今までに文学で取り上げられてきたタブーの中でも、障害者の問題や性的マイノリティの問題はまだまだ正面から描いた作品は少ないように思える。
そんなマイノリティを描いた本書であるが、マイノリティであるからこそ、それをつなぐ絆が求められる。
それこそが家族だ。本書では、マイノリティをつなぐ紐帯として家族の存在を中心に置いている。
あまりにも残酷な運命の神は、長谷川家をバラバラにしようと向かい風をひっきりなしに吹き付けてくる。
本書の表現でいうと、「ああ神様はまた、僕らに悪送球をしかけてきた。」という感じで。
そうした逆境の中、薫と父の帰還を機に家族が一つになる。
そして、一つになろうとする家族にとって欠かせないのがさくらの存在だ。
さくらは言葉がしゃべれない。それゆえに、自己主張が少ない。だからこそ奇天烈な家族の中でさくらは全員をつなぐ要であり得た。
著者はさくらの心の声を描くことで、さくらにも人格を与えてる。むろんその声は作中の人物には聞えない。だが、さくらの心の声をさりげなく混ぜることで、さくらこそが家族をつなぎとめる存在であると伝えているのだろう。
実は人間社会にとって、ペットも立派なマイノリティだ。
そして、ペットとはマイノリティでありながら、要の存在にもなりうる。そのようなペットの役割を雄弁に語っているのが本書だ。
実際、著者はあとがきにもそのことを書いている。そのあとがきによると著者の飼っていたサニーという雑種がさくらのモデルらしい。著者はいかなる時も尻尾を振って意志を表わすサニーにどれだけ慰められたかを語る。その経験がさくらとなって本書に結実したのだと思う。
私もペットを二匹飼っている。彼女たちには仕事の邪魔もされることが多いが、慰安となってくれる時もある。
ワンちゃんを飼うとその存在を重荷に感じることがある。だが、本書を読んでペットもマイノリティであることを感じ、もう少し大切にしないとな、と思った。
また、私の中に確実にあるはずのマイノリティへの無意識のタブー視も、本書は意識させてくれた。勇気をもってタブーに目を向けていかないと。そして克服していかないと。
そもそも誰しもマイノリティだ。
自我は突き詰めると世界から閉ざされている。その限りにおいて、人は本質では確実に孤独で少数派の存在なのだ。
だからこそ、最小の信頼しあえるコミュニティ、家族の重要さが際立つ。
そして、人生にはマイノリティにもマジョリティにも等しく、山や谷が待ち構えている。
そうした試練に出会う時、本心から心を許せる家族を持っていると強い。
本質的にマイノリティな人間であるからだ。
マイノリティが自らの核を家族に預けられた時、マイノリティではなくなる。たとえ社会の中ではマイノリティであっても、孤独からは離れられるのだ。
その確信をくれたのが本書だ。
‘2019/3/24-2019/3/28


