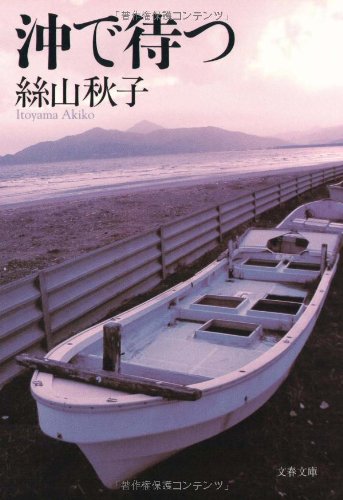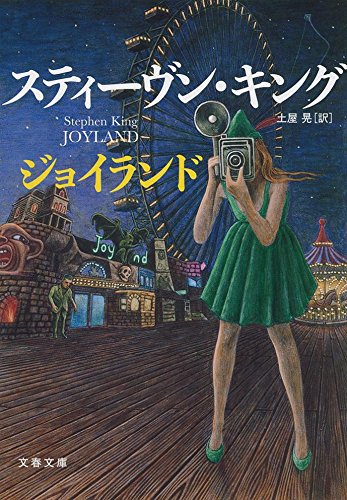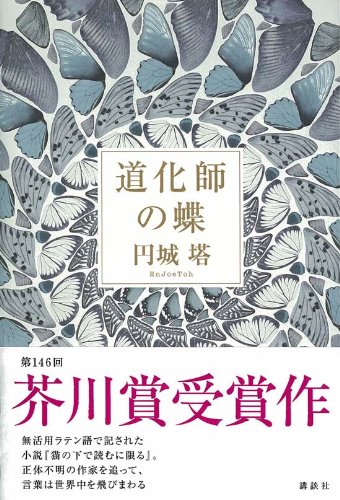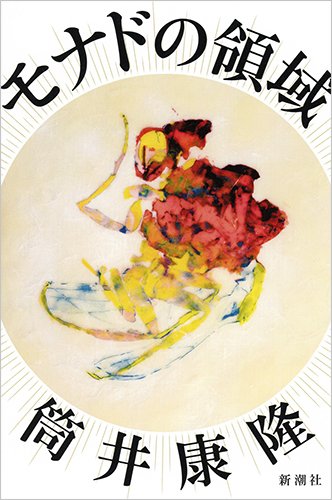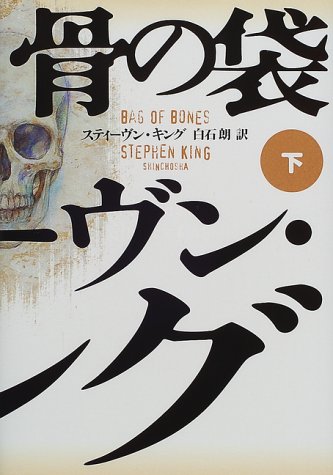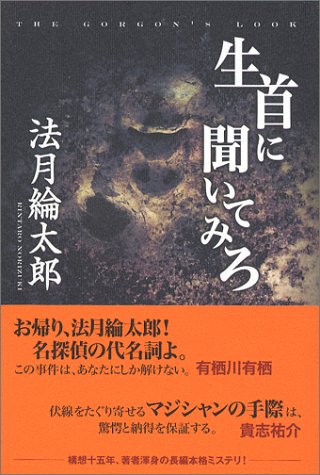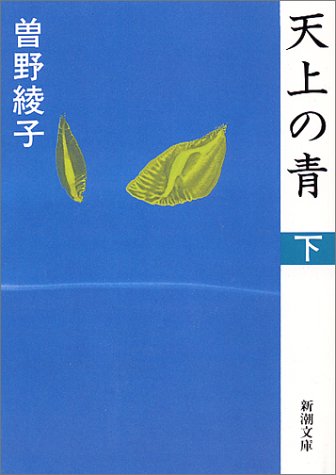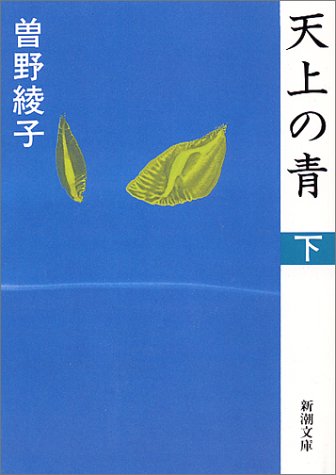
上巻を通して宇野富士男の性格は充分すぎるほど読者に披露された。一見すると穏やかそうに見えて話も達者。だが、一度、自分に都合の悪いことが起こると気の短さが爆発し、見境のない行動に走る。そういう性格の持ち主は、権威にも激しい敵意を示す傾向にあると思う。
富士男の悪い面は、偶然の出会いで車に乗せた少年に対して顕著に現れる。11歳のひどく大人びた、生意気な口調で話す少年。気圧された富士男は不機嫌が募ってゆく。少年は父が検事であることを誇示し、悪いヤツは罰せられるべきだと持論を振るう。少年との会話は富士男の衝動に火をつける。そして、「僕を殺したりすると、国家的損失だよ」の言葉に富士男の理性は吹き飛ぶ。自分よりもかなり年下の少年との会話にむきになり、自制のできない富士男の幼さが出てしまう瞬間だ。少年の死と家への帰りに引き起こした交通事故が富士男の命取りとなる。
逮捕と勾留。富士男を取り調べるのは、財部警部補と檜垣巡査部長のコンビだ。取調室で取り調べと韜晦のせめぎ合いが始まる。富士男がのらりくらりと尋問をかわしても警察の組織力が次々と矛盾を暴いてゆく。富士男視点で尋問は進むので、いわゆる犯人からの視点で物語が進む倒叙型のミステリーとでもいおうか。読者は富士男がいかにして尋問を切り抜けるのか、または、彼の狡知を警察がいかに破ってゆくかに興味を惹かれるはずだ。会話の巧みさを自負していた富士男をあざ笑うかのように、証拠が次々と富士男を打ちのめしにかかる。富士男と警察の駆け引きがとてもスリリングでリアルだ。私は著者の作品をあまり読んでいないが、推理小説作家としては認知されていないように思う。だが、取り調べのシーンは間違いなくミステリを読んでいるようだった。著者の作家としての筆力を見せられたように思う。
でも、いくら著者が達者に尋問経過を書き込もうと、本書は事件の意外な真相を描くのではなく、罪と罰、そして救いを描く小説だ。そのため、土壇場で予期せぬ事実が判明することはないし、富士男の替わりに真犯人が現れることもなく、まだ見ぬ共犯者が現れることもない。著者は富士男の罪の意外な事実を暴くよりも、波多雪子の無垢な視点で富士男の罪を考えさせる。それによって読者は波多雪子に興味の視点を注ぐのだ。波多雪子の心がどのように揺れ動き、富士男の罪とどう折り合いをつけてゆくのか。
波多雪子は獄中の富士男に向って手紙を書く。手紙の中で波多雪子が書いた一文にこのようなくだりがある。「お互いに小細工はよしましょう。生きることは小細工では追いつかない、骨太なシナリオを持っているように私は思うのです」。さらに、富士男がレイプした女性の家族がたまたま波多雪子の知り合いだったことから、一つの家族が富士男の行いによって崩壊しつつあることを非難し突き放す。一方で、富士男がたまたま車に乗せ、殺さずに会話を交わして送り出した女性は富士男との会話によって自殺を思いとどまる。その女性も波多雪子の知り合いだった。波多雪子は、富士男が一人の少年や家族を壊しただけでなく、一人の女性を救ったことも思い返す。波多雪子は、投函せずに手元に置いておくつもりだった手紙にお礼と続きを加え、手伝えることがあれば手伝うと申し出る。
取調室で自分だけが被害者だと世をひがんで見せる富士男。そんな富士男に、檜垣巡査部長が自分は捨て子だと明かし、富士男の甘ったれた根性にぐさりと切り込む。檜垣巡査部長は、取り調べに当たった刑事の中でも富士男の心情を見抜き、富士男の心を融かす波長をもつ人物だ。ちょうど大久保清にとっての落合刑事のように。そんな檜垣巡査部長は、富士男の人物を理解するための糸口を求めて波多雪子のもとを訪ねる。そこで波多雪子が語る「どなたにせよ、この世で私のことを思い出して訪ねて来てくださる方がいらっしゃるなんて、私、光栄だと思っていますから」という言葉は檜垣巡査部長を圧倒する。檜垣巡査部長は、この言葉だけで富士男と波多雪子の関係にただれた部分がなかったことを確信させたことだろう。そして檜垣巡査部長は、富士男が弁護士を紹介してくれるよう頼んでいることを波多雪子に伝える。富士男は、義兄の三郎がよこした国選弁護士の話を蹴ったのだ。波多雪子の紹介してくれた弁護士なら、という富士男。それを聞いた波多雪子は、自分こそが富士男にとって唯一残された蜘蛛の糸であることを自覚する。蜘蛛の糸とは、仏が地獄に垂らした一本の糸をさしているのだろう。罪人たちが我先にと糸にとりついたために、切れてしまった仏教説話は有名だ。波多雪子は富士男のこころを罪からすくい上げられるのだろうか。
知り合いに弁護士のいない波多雪子は、偶然、風見渚という弁護士と知り合う。宇野富士男の弁護を引き受けられないか、とおずおずと切り出す波多雪子に、風見渚はこう答える。「私、結婚するとき、主人に言われたんです。弁護士をやるなら、一生、道楽でやれ、って。最低食うだけは僕が引き受けてやる。だからお金になるかならないか、ということじゃなくて、この事件の弁護に自分が関わることが、自分にも相手にも意味がある、と思うものだけやれ、って言われたんです」。宇野富士男から波多雪子、そして風見渚へと弁護の糸は流れるようにつながってゆく。ここまでの流れに著者のご都合主義は感じられない。
今となってはもはや、宇野富士夫と大久保清の事件を比べることに意味は薄れつつある。なぜなら、波多雪子の視点が中心となった本書は、大久保清をモデルとしただけの小説ではなくなってきているから。それでもあえて私は大久保清の事件をベースに本書を読んでみたいと思う。私は大久保清の弁護人に選任された方の名前を知らない。その方が弁護人としての本書の風見渚のように高邁な哲学を持っていたのかも知らない。もし、大久保清に波多雪子や風見渚のような精神的な支柱があれば、さぞ心強かっただろうと思う。
波多雪子から宇野富士男にあてた手紙には、風見渚に弁護を頼んだことと、「人間は自分のことを人に語らせてはいけません。それは、第一自分に対して失礼です。」というくだりがある。大久保清は「訣別の章 死刑囚・大久保清獄中手記」と題された手記を発表している。大久保清はそういう形で世間に対して自分を語ろうとした。この書を発行したのはアナーキストの肩書を持つ大島英三郎氏となっている。大島氏がどういう経歴の方かは知らないが、波多雪子が宇野富士男と書簡を交わしたように、大久保清も大島英三郎氏と書簡を交わしたのだろう。本書では以降、宇野富士男の心のうちが書簡の形で表現される。
宇野富士男が、現場検証で連れていかれた海を見て、感慨にふけるシーンがある。少し長いが引用してみる。
「富士男は静かに海の香りを鼻の穴に通した。そして眼をつぶった。その頬は微笑していた。その瞬間、彼は自分がどこに、どんな人生を背負って生きているかを忘れることができた。富士男は自分が小さな気泡になって海へ溶け込む実感を味わった。それは自分が無限に小さくなり、何者かに抱かれる感覚であった。小さくなると、自分の中に内包されていた悪も小さくなるのか。そうは行かない、と人々は言うであろう。しかし偉大になることに血道を上げる奴もいるとすれば、自分が小さくなることに安らぎを見出す人間もいる。それは、常に大きなものになろうと背伸びし、大きなものがいいものだと信じ、大きなものにしか存在の価値はないと思い込んできた常識に対する不遜な反抗の開館であった。」
「富士男は一瞬海に向かって頭を垂れた。富士男は海を見ることはこれが最後だろう、と予感した。だから富士男は海に訣別の挨拶を送り、もう一度しみじみとその無垢な喜びの色を見つめたのだった。」
このシーンは、多分、大久保清が生前出版した「訣別の章 死刑囚・大久保清獄中手記」を意識しているのだろう。私はその手記は読んだことがない。だが、この手記には詩も載っており、その中で大久保清はこのようなことを書いている。
「父母よ!私の骨と灰は
あなたがたにお願いしました
その梓川の清き流れに
私の全部を託して、長い旅に出ます
そして何日かかるかわからねど
きっとナホトカの港までゆくでしょう」
私はここにきて、著者が本書の舞台を三浦半島にした理由をおぼろげながら理解した。天上の青はアサガオの花弁の青。そして湘南の海の青、空の青。そして、自らの罪を清める清浄さの象徴としての青。罪は川となって流れ、海へと至る。そこに人の貴賤はない。人の裁きではなく、自然の、神の摂理によって罪は海へと流れゆく。その海の色はどこまでも青い。
富士男への書簡で、波多雪子はクリスチャンとしてキリスト教の話題を持ち出しては、富士男の心を少しでも改悛に導こうとする。だが、富士男は神だけは受け入れられないと拒絶する。波多雪子はそんな富士男のかたくなさに、少しも逆らわず、諭すように言葉をつむいでゆく。もともと自然の摂理に従い、自分に大いなる意志や役割を求めない姿勢で生きている波多雪子。人間の社会では全ては法廷という人による裁きの場で決着がつけられる。だが、波多雪子にとってはそうではない。キリスト教の教えでは、道徳については「裁くなかれ」と神がおっしゃったので人が人を裁くべきではないという。
そんな富士男に極刑の判決が下る。それにたいし、富士男は短く、
「たった一言、答えを聞かせてほしい。
愛していてくれるなら、控訴はしない」
と。
波多雪子はそれに対し、
「同じ時に生まれ合わせて、偶然あなたを知り、私はあなたの存在を悲しみつつ、深く愛しました。
この一言を書くのに、この二日を、苦しみ抜きました」
と返す。
波多雪子はこの一言が宇野富士男の刑を確定させ、死に追いやったと深く思い悩む。富士男は欲望の赴くままに残虐に人を殺したが、自分もまた、同じ殺人の罪を犯したのではないか、と。
しかし、著者はそれとは逆のことを言いたかったのではないか。愛するという言葉は、富士男に控訴という自我を捨てさせた。富士男はとうとう改悛の情を示さなかったかもしれないが、彼は法廷で自らの自白をひるがえさず罪を認めた。それは罪を自覚したからの態度ではなかったか。そして、波多雪子からの愛しました、との言葉を受けて控訴せず罪に服した。これは一つの罪を悔いた態度とみてよいのではないか。著者は暗にこう問うているのではないか。波多雪子の愛は、ついに一人の殺人犯に自らの犯した罪を心の底から自覚させたと。
大久保清がここまでの境地に至ったのか、それは知らない。だが宇野富士夫は、波多雪子によって一つの境地に至ったのだと思う。シリアルキラーだったかもしれないが、一人の罪人として死ぬことができたに違いない。
‘2016/08/17-2016/08/19