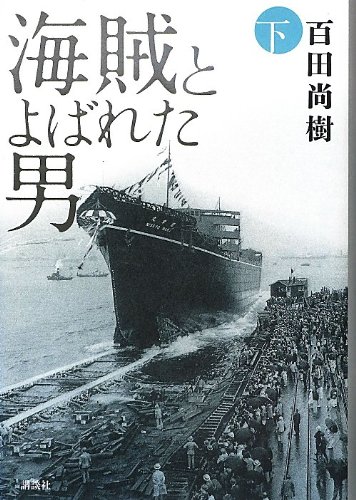

下巻では、苦難の数々を乗り切った國岡商店の飛躍の様が描かれる。大体、こういった伝記ものが面白いのは創業、成長時につきものの苦難であり、功成り名遂げた後は、起伏に欠けることが多く、自然と著者の筆も駆け足になってしまうものだ。上巻では敗戦によって一気に海外資産を失ったピンチがあった。そのピンチを國岡商店はラジオ修理の仕事を請け負ったり、海軍が遺した石油廃油をタンクの底から浚って燃料確保したりと、懸命に働いて社員の首を切ることなく乗り切った。
果たして、安定期に入り苦難の時期を過ぎた國岡商店の姿は読むに値するのだろうか。そんな心配は本書に限っては無用。面白いのだ、これが。
なぜ面白いかというと、本書では日章丸事件が取り上げられているからだ。國岡商店、つまり出光興産が世界を驚かせた事件。それが日章丸事件。むしろ、この事件こそが、著者に本書を書かせた理由ではないかと思う。 日本の一企業が石油メジャーに堂々とけんかを売り、英海軍も手玉にとって、イランから石油を持ち帰ったのだから。
日章丸事件を一文で書くとすればこうなる。日本から派遣された一隻のタンカーがイランから買い取った石油を日本に持ち帰った。それだけなのだ。だが、その背景には複雑な背景がある。まず、産油国でありながら石油利権を英国に牛耳られていたイラン国民の思いを忘れるわけにはいかない。長年の鬱屈が石油国有化法案の可決と石油の国有化宣言へとつながった。宣言を実行に移し、国内の全油田をイラン国営にした。それはイランにとってはよいが、英国石油メジャーにとっては死活問題となることは必然だ。石油メジャーの背後には、第二次大戦後、国力衰退の著しい英国の意向が働いていることはもちろん。イランの石油国有化は英国が世界中に石油不買の圧力を掛ける事態に発展した。 つまり、國岡商店が喧嘩を売ったのは、世界でも指折りの資源強国、そして海軍国家の英国なのだ。
本書ではそのあたりの背景やイランとの交渉の様子、その他、準備の進捗が細かく描かれる。いよいよの出航では、船を見送る國岡鐵三の姿が描き出される。日章丸に自社と日本のこれからを託す鐵三は、日章丸に何かあった場合、会社だけでなく自分の人生も終わることを覚悟している。まさに命を懸けたイラン派遣だったわけだ。そんな鐵三が日章丸を託したのは新田船長。海の男の気概を持つ新田船長が、海洋国家日本の誇りを掲げ、冷静かつ大胆な操艦でイランまで行き、石油を積んで帰ってくる。その姿は、8年前の敗戦の悔しさの一部を晴らすに足りる。かつて石油が足りず戦争に惨敗した日本が、英国を相手に石油で煮え湯を飲ませるのだから。しかも今回はイランを救う大義名分もある。日本は戦争に負けたが、経済で世界の強国に上りつめていく。その象徴的な事件こそが、日章丸事件ではないだろうか。
残念なことに、日章丸事件から数年後、モサデク政権は米英の倒閣工作によって瓦解し、イランの石油を國岡商店が独占輸入することはできなくなった。でも、それによって國岡商店は敗戦以来の危機を脱する。日章丸事件以降の國岡商店の社史は、さまざまなできごとで彩られていく。そこには栄光と困難、成功と挫折があった。自社で製油所を構えることは國岡商店の悲願だったが、10カ月という短期で製油所を竣工させたこと。製油所の沖合にシーバースを建設したこと。第二、第三の日章丸を建造したこと。宗像海運の船舶事故で犠牲者が出たこと。石油の価格統制に反対し、石油連盟を脱退したこと。「五十年は長い時間であるが、私自身は自分の五十年を一言で言いあらわせる。すなわち、誘惑に迷わず、妥協を排し、人間尊重の信念を貫きとおした五十年であった。と」(291ページ)。これの言葉は創業五十年の式典における店主の言葉だ。
店主としても経営者としても、見事な生涯だったと思う。私にはおよびもつかない境地だ。だが、やはり家庭面では完全とは行かなかった。とくに、先妻ユキとの間に子供ができず、ユキから離縁を申し出る形で離縁する部分は、複雑な気分にさせられる。また、本書には家庭のぬくもりを思わせる描写も少ない。國岡鐵三や、モデルとなった出光佐三の家庭のことは分からない。だが、長男を立派な後継者としたことは、家族に対しても、きちんと目を配っていたことの表れなのだろう。
ただ、それを置いても、本書には女性の登場する余地が極めて少ない。本書には男女差別を思わせる表現はないし、ユキが鐵三と別れる場面でも双方の視点を尊重した書きかたになっている。だが、女性が登場することが少ないのも確かだ。ユキ以外に登場する女性は、右翼に絡まれた受付嬢ぐらいではないか。しかも鐵三が右翼を 気迫で 追っ払うエピソードの登場人物として。ただ、本書に女性が出てこないのも、本書の性格や時代背景からすると仕方ないと思える。
女性があまり登場しないとはいえ、本書からは人間を尊重する精神が感じられる。それは國岡鐵三、いや、出光佐三の信念ともいえる。一代の英傑でありながら、彼の人間を尊重する精神は気高い。その高みは20代の私には理想に映ったし、40台となった今でも目標であり続けている。
ただ、佐三の掲げた理想も、佐三亡き後、薄らいでいるような気がしてならない。佐三の最晩年に起きた廃油海上投棄や、公害対応の不備などがそうだ。本書に登場しないそれらの事件は、佐三が作り上げた企業があまりに大きくなりすぎ、制御しきれなくなったためだろう。しかも今、佐三が一生の間戦い続けた外資の手が出光興産に伸びている。最近話題となった昭和シェル石油との合併問題は、佐三の理念が浸食されかけていることの象徴ともいえる。出光一族が合併に反対しているというが、本書を読めばそのことに賛同したくなる。
日本が世界に誇る企業の一社として、これからも出光興産には理想の火を消さずに守り続けて欲しいと思う。海賊と呼ばれたのも、既定概念を打ち破った義賊としての意味が込められていたはずだから。
‘2016/10/09-2016/10/09








