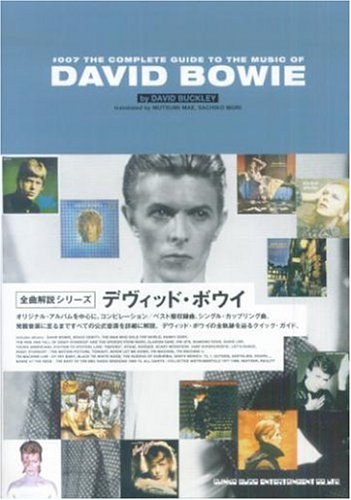
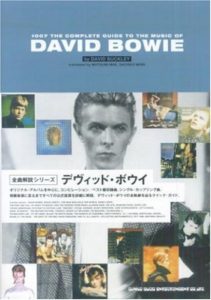
最寄り駅の図書館で、デヴィッド・ボウイの愛読書百冊という特集コーナーが設けられていた。それを見て、そういえばデヴィッド・ボウイがなくなって二年になる、と気づいた。彼が亡くなった際にはこのようなブログをアップした。
彼がこの世を去って二年になるが、まだ世の中に影響力を与え続けているのだからすごい。図書館で特集コーナーに出会ったことで、私も心を新たにデヴィッド・ボウイを聞き直してみようと思った。せっかくGoogle Musicに加入しているのだから全てのアルバムを聴いてみようと。こう決めてから二週間、私は仕事とデヴィッド・ボウイ漬けの日々を送った。
この期間は、ちょうど仕事が立て込んでいて朝までの作業が続いた。それもあって、全てのアルバムを二回以上は聞く時間があった。気になる曲が流れる度、本書の解説をチラチラ見つつ、デヴィッド・ボウイの世界に耽溺した。私が本書をきちんと読み直したのは仕事漬けの日々が終わり、本が読める時間がようやく取れるようになってからだ。本書は読み通す前に内容を何度もつまみ読みした。それは、私の読書スタイルにとっては珍しい。
本書が取り上げているのは、1969年のデビュー・アルバム『David Bowie』から2003年の『REALITY』までのアルバムだ。アルバム単位での解説と、曲ごとの解説の二段で構成されている。その中にはデヴィッド・ボウイがバンド形態を模索したプロジェクト”TIN MACHINE” で発表した二枚のアルバムも含まれている。
著者はミュージシャンの伝記作家として活動されている方のようだ。エルトン・ジョンやREM、デヴィッド・ボウイ、クラフトワークなどを取り上げた伝記の著者としてもクレジットされている。デヴィッド・ボウイについての伝記を書くくらいだから、アーチストとして尊敬も愛着も持っているはず。ところが本書は単なるデヴィッド・ボウイを礼賛するだけの本ではない。それどころか、デヴィッド・ボウイに革新さと創造性が失われた時期の作品は舌鋒鋭くけなしている。
本作で徹底的にやっつけられているのは、『TONIGHT』『NEVER LET ME DOWN』『TIN MACHINE』『TIN MACHINE Ⅱ』の四作だ。それらはどれもが80年代中期から90年代はじめの作品だ。1983年の『Let’s Dance』の世界的なヒットは、デヴィッド・ボウイから革新性や冒険心が喪わせた。それが著者には許せないらしい。上に挙げた作品に対し、著者は容赦なく責め立てる。唯一、”TIN MACHINE”でバンド形式をとったことは商業主義からボウイが抜け出すために必要な過程だったとの評価は与えている。とはいえ、アルバムへの評価や各曲の評価は総じて失望に満ちている。無残なものだ。
たとえば『TIN MACHINE Ⅱ』に収められた8曲目「STATESIDE」。この曲の解説を以下に引用するが、その辛辣さはもう笑うほかない。
この老いぼれブルース・ナンバーは、今までのボウイのレコーディング・キャリアの中で、どん底と言えるだろう。ハント・セールズがリード・ヴォーカルを担当して、”I’m going Stateside with my convictions(信念を持ってステイトサイドへ行くのさ)”と大声で叫び、ボウイがさらに説得力の無い皮肉を入れたコーラスで事態を収拾しようとするが、全部裏目に出ている。最も憂慮すべき点は、アメリカ的本物主義へのこの愚かしい敬意の曲が、ボウイがこれまで支持してきたものが全てまやかしであると証明してしまった、ということである。恐ろしい。
私のCDコレクションにも、Google Play Musicにも『Tin Machine Ⅱ』が収められておらず、私はこの「STATESIDE」を聞いたことがない。ここまで書かれるとかえって聴きたくなるほどだ。
また、本書は先に書いた通り、2003年に発表された『REALITY』までが対象だ。十年ぶりに復活作として発表された『THE NEXT DAY』と、デヴィッド・ボウイの死の2日前に発売された『BLACK STAR』は含まれていない。著書の評価をぜひ知りたいと思い、著者のページを調べたが、手がかりはなかった。その二作は著者も納得し、おそらく絶賛した出来栄えだったと思う。それほどまでに素晴らしい作品だった。
私のデヴィッド・ボウイに対する評価は先に挙げたブログにも書いた通りだ。その上で今回あらためて全ての曲を何度か聴きこんでみたが、その作品の深さには驚きが蘇る。メジャーなカルトヒーロー。相反するその二つの言葉こそ、デヴィッド・ボウイを表すキーワードとして後世に残っていくに違いない。音楽市場を取り巻く環境がこれだけ変わった今、彼のように難解さと革新性を保ちながら、著者のような評論家だけでなく一般の聴衆にアピールできるアーチストはこれから現れるのだろうか。私には確信が持てない。
本稿を機会に、私が聞きまくったデヴィッド・ボウイの曲。ここで彼の全キャリアで私がベストと思う曲を20曲挙げてみた。メジャーな曲もあれば、マイナーな曲もある。
Space Oddity
Changes
Five Years
Starman
Ziggy Stardust
Suffragette City
Aladdin Sane
Rebel Rebel
Speed Of Life
Sound And Vision
A New Career In A New Town
The Secret Life Of Arabia
Move On
Look Back In Anger
China Girl
Let’s Dance
Little Wonder
Dead Man Walking
A Small Plot of Land
Black Star
20曲を選ぶのって結構難しい。「Modern Love」も「”Heroes”」も「Ashes To Ashes」も「Diamond Dogs」も「If You Can See Me」も「Golden Years」も20曲からは外さざるを得ない。それぐらい、いい曲が多い。
これに比べるとアルバムを五作を選ぶほうがよほど楽だ。私が五枚選ぶとすれば『Earthling』『Black Star』『The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars』『Low』『Heroes』かな。
多分、著者が20曲と5枚を選んだとすれば、私のそれとは大幅に変わるはずだ。本書の評価を読んでいると、何となく著者の好みがわかる気がする。著者が推す曲はシングル曲やメジャーな曲ではない。例えば「Station To Station」や「Sweet Thing」への賛辞は溢れんばかりだ。
やはり、著者が最後の二枚のアルバムに対してどういう評価を下したのか知りたい。そして、デヴィッド・ボウイという巨大な才能が、どういう本を読んできたのかも。
図書館にあった愛読書の百冊は、私も読破したいと思う。百冊のリストはこちらのページで紹介されている。この中で私が読んだことがあるのはたったの10冊だけだ。読書人として無力を感じる。まだ道は長い。
‘2018/01/22-2018/01/27



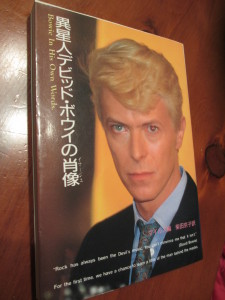 以来、洋楽にはまった私は、80年代、70年代、60年代と色んな音楽にどっぷり浸かった高校時代を送ります。その中でデヴィッド・ボウイが輝いていたことも知りました。80年代の「Let’s Dance」や「China Girl」だけでなく、70年代のベルリン三部作「Low」「”Heroes”」「Lodger」も恰好よく、グラムロックのアイコンであった頃や「Space Oddity」や「・・・Ziggy Stardust and ・・・」ももちろん。凄いと思いました。高校生が背伸びして大人の世界を覗き見るには、あまりにも眩しい存在でした。ここにアップした本はその頃に買いました。初版1986年だから古本屋で買ったのかな?
以来、洋楽にはまった私は、80年代、70年代、60年代と色んな音楽にどっぷり浸かった高校時代を送ります。その中でデヴィッド・ボウイが輝いていたことも知りました。80年代の「Let’s Dance」や「China Girl」だけでなく、70年代のベルリン三部作「Low」「”Heroes”」「Lodger」も恰好よく、グラムロックのアイコンであった頃や「Space Oddity」や「・・・Ziggy Stardust and ・・・」ももちろん。凄いと思いました。高校生が背伸びして大人の世界を覗き見るには、あまりにも眩しい存在でした。ここにアップした本はその頃に買いました。初版1986年だから古本屋で買ったのかな?