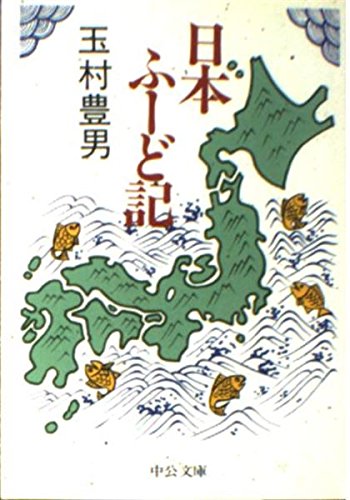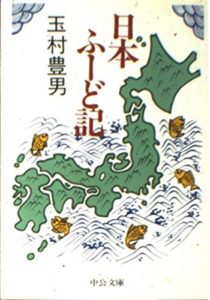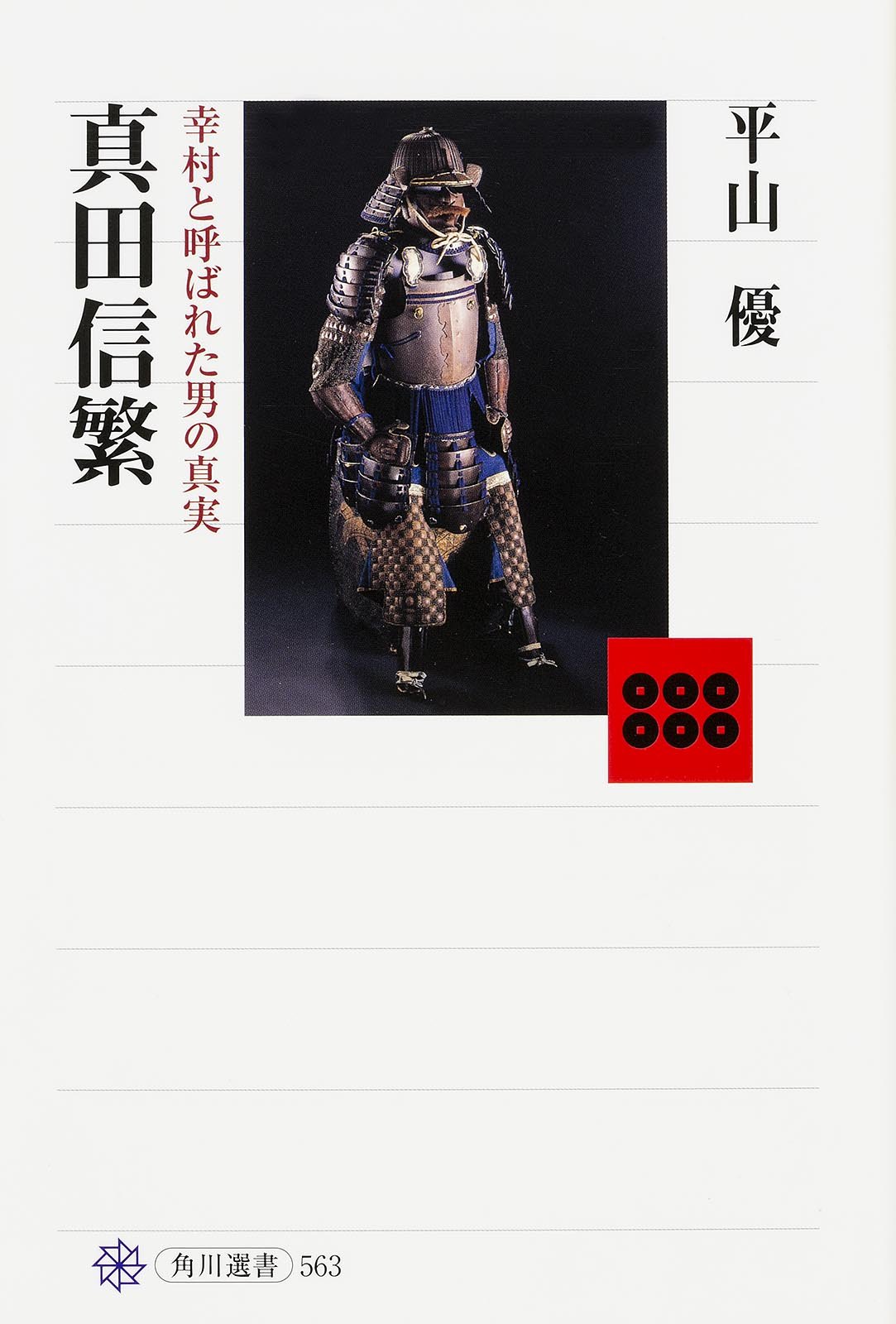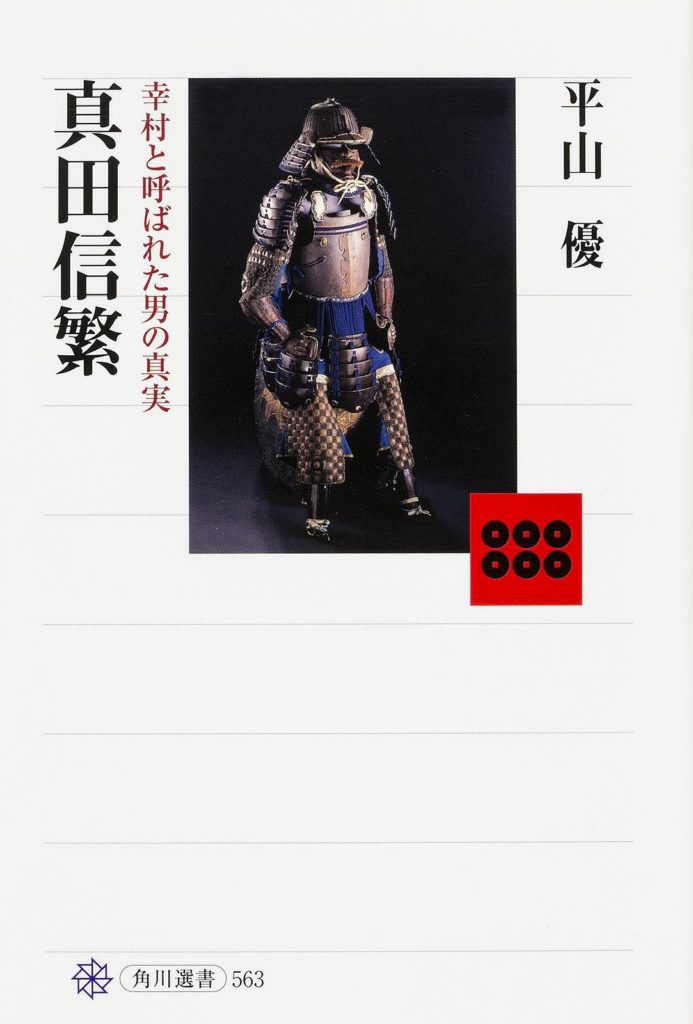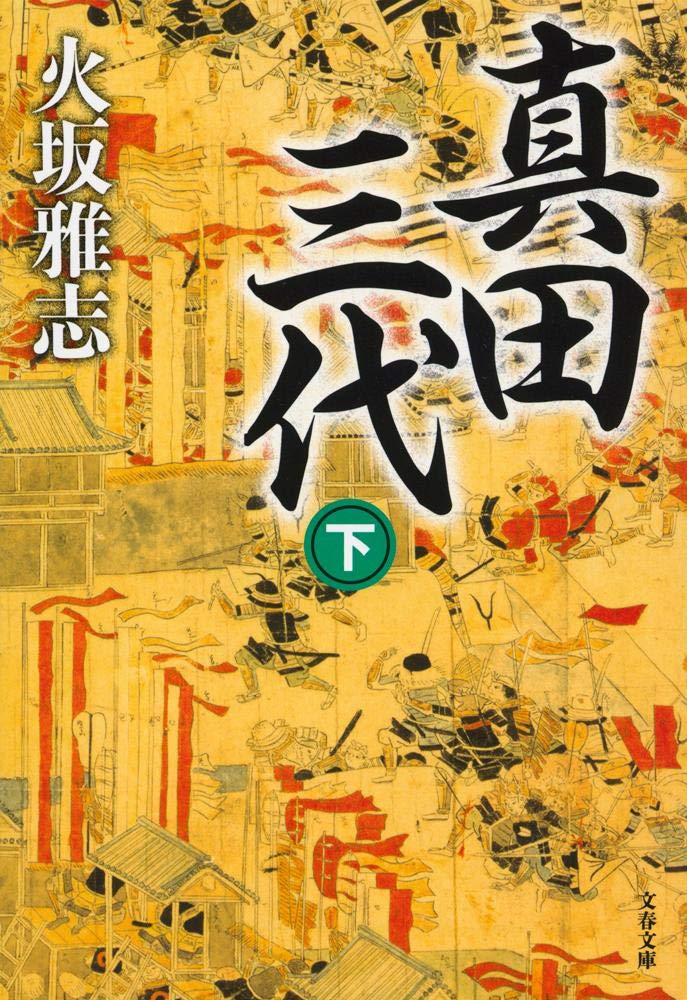
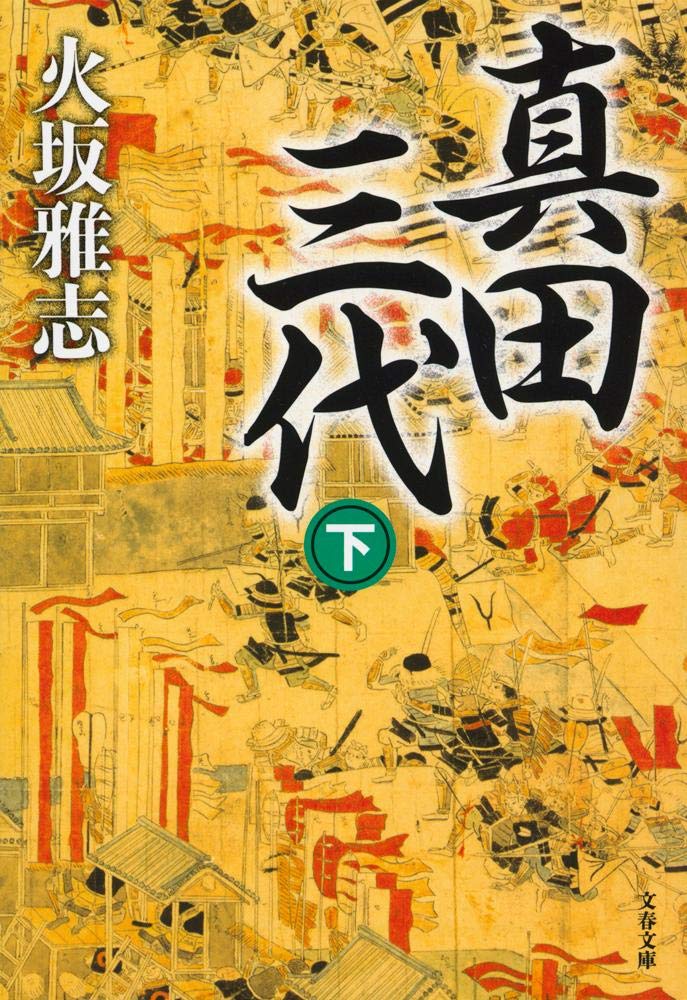
下巻では第一次上田合戦から始まる。
上田の城下町の全てを戦場と化し、徳川軍を誘い込んで一網打尽にする。それが昌幸の立てた戦略だ。
それには領民の協力が欠かせない。なぜ領民が表裏比興の者と呼ばれた昌幸の命に諾々と従ったのか。
「昌幸にはひとつの信条があった。
「戦いにおいては詐略を用い、非情の決断もする。だが、おのが領民と交わした約束は、信義をもってこれを守り、情けをかけて味方につけねばならぬ」」(86-87ページ)
周到に準備しておいた昌幸の策が功を奏し、徳川軍を撃退した真田軍。諸国の武将に真田家の武名がとどろく。
だが、昌幸の智謀がすごみを増す一方で、次男の幸村には父とは違う人格が生まれ始めていた。それは義の道。
幸村は、人質として過ごす上杉家の家風である義の心に感化される。
軍神と称えられた先代の不識庵謙信はすでに世にない。だが、主の景勝とその股肱の臣である直江兼続が差配する上杉家は、先代の義に篤い気風を受け継いでいた。
そこで幸村は策に走る父への疑問を抱く。生き残ることを優先すべきなのか、はたまた義を貫くべきか。
「おのれの利を追うことのみに汲々とするのではなく、さらに大局に立ち、おおやけのため、民のため、弱き者のために行動するのが、
「わしの考える義だ」
と、兼続は言った。」(128ページ)
これは私も常々感じている。利を追ってゆくだけでよいのなら、どれだけ楽か。金を稼ぐ苦労はあっても、それだけにまい進すればよいのだから。
従業員の人件費を削り、精一杯働かせる。顧客には高めの金額を提示し、その差額を利潤として懐に貯めこむ。
それができない私だから、飛躍も出来ないでいる。自分に恥じないような経営をしようと思うと、従業員を使い捨てにするマネはできない。見合った金額を支払い、顧客には高い金額を提示できない。これだと飛躍ができない。
私の根本の経営能力に問題があることもそうだが、こうした理念は卓越した努力と才能を伸ばした結果が伴わなければ倒れてしまう。悩んだことも数知れずだ。
ビジネスマンの愛読書は歴史小説だという俗説がある。歴史小説から教訓を読み取り、それをビジネスに生かそうとする人が多いからだろう。
それが本当かどうかはわからない。だが、私にとっては歴史を取り扱った小説から得られる教訓は多い。
本書を読んでいると、未熟な自分の目指すべき道の遠さとやるべきことの多さにめまいがする。
義を貫きたい幸村の志。それに頓着せず、昌幸は上杉家に人質としている幸村に信幸を接触させる。そして信幸を通し、上杉家を出て豊臣家への人質として大坂へ赴くように命ずる。
義のなんたるかを教えてくれた人物を不本意ながら裏切る羽目に陥った幸村の苦悩。
昌幸の視点には、天下の趨勢が豊臣に傾いていることが見えたのだろう。幸村を豊臣家の人質として送り込むこともまた、真田家を生き延びさせるための一手だった。昌幸の読みは当たり、秀吉は着々と天下を統一していく。
その過程に真田の名胡桃城をめぐる攻防があったことは言うまでもない。
ところが豊太閤の天下も秀吉の死によって瓦解を始める。それから関ヶ原の戦いに至るまで、石田三成と徳川家康、さらには上杉や諸武将の思惑が入り乱れる。
真田の場合、兄信幸が徳川四天王の本田忠勝の娘小松姫を娶っていた。幸村は石田三成についた大谷吉継を義父としている。
二人の境遇が真田家を大きく二つに割った犬伏の別れの伏線となる。
「澄んだ秋の夜空に、星が散っている。そのなかで、ひときわあざやかに輝く六つの星のつらなりがあった。
真田家の六連銭の旗の由来ともなった、
━━すばる
である。
「わしは若いころより、つねに心に誓ってきた。あのすばるのごとく、あまたの星のなかでも群れのなかに埋没せぬ、凛然たる光を放つ存在でありたいとな」
星を見つめながら昌幸は言った。
「徳川内府につけば、わしは有象無象の星の群れのひとつに過ぎなくなる。だが、男としてこの世に生を受けた以上、一度は天上のすばるを目指さねばならぬ。いまこそがその時だ」」(344-345ページ)
まさに私もこの志を持って独立した。しびれる場面である。
昌幸は長男の信幸とたもとを分かち、上田城の戦いでは策略を駆使して徳川秀忠の軍を足止めさせる。その結果、関ヶ原の本戦で秀忠軍は遅参した。
だが、西軍は関ヶ原の本戦で敗れた。局所の戦いでは勝ちをおさめたが、昌幸と幸村の二人は高野山へ流罪の身となった。
以来十数年。昌幸はついに九度山で想いを遺しながら亡くなった。そして、徳川家康は、天下取りの最後の仕上げにとりかかる。残すのは豊臣家の滅亡。
豊臣方も対抗するため、大坂に浪人を集める。幸村も大坂からの誘いを受け、最後の死に花を咲かせるために九度山から脱出する。
「「人の世は、思うようにならぬことのほうが多い。まして、わが真田家は周囲を大勢力に囲まれ、つねにその狭間で翻弄されてきた。だが、宿命を嘆き、呪っているだけでは、何も生まれませぬ。苦しい状況のなかから、泥水を嘗めてでもあらんかぎりの知恵を使い、一筋の道を切り拓いてゆく。それがしのなかにも、そうやって生きてきた祖父幸隆や父昌幸と同じ血が流れているのでござろう」」(465-466ページ)
ここからはまさに幸村の一世一代の花道だ。戦国時代、いや、日本史上でも稀に見る華々しい死にざま。真田日本一の兵と徳川方から称賛された戦い。
「叔父上は、数ある信濃の小土豪のなかから、真田家がここまで生き残ってこれたのはなにゆえと思われます。それは、知恵を働かせて巧みに立ちまわったからだけではない。小なりとはいえ、独立した一族の誇りを失わず、ときに身の丈よりはるかに大きな敵にも、背筋を伸ばして堂々と渡り合う気概を持つ。それでこそ、わが一族は、亡き太閤殿下、大御所にも一目置かれる存在になったのではございますまいか」
「目先の餌に釣られ、世の理不尽にものを言う気概を捨て去っては、一族を興した祖父様や、表裏比興と言われながらも、おのが筋をつらぬいた父上に申しわけが立ちませぬ」(497-498ページ)
幸隆から昌幸、そして幸村と、戦国の過酷な現実を生き抜き、しかも自らを貫き通した。さらには、大名家の家名まで後世に伝えることに成功した。
男としてこれ以上の事があろうか。
真田家の三代の生きざまを読んでいると、何やら胸の内にたぎるものが湧いてくる。私もちょうど幸村が討死した年齢に差し掛かった。
あとどれぐらいの花が咲かせられるだろうか。
本書はビジネスマンに限らず、まだまだ枯れるにははやい中年に読んでほしい。
2020/10/2-2020/10/2