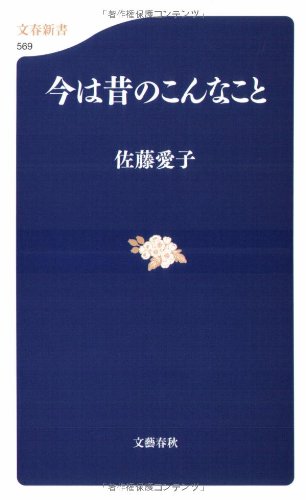女性が生きていくには、美しく健やかな生き方だけでは足りない。したたかで醜くなくては。
男性からは書きにくい、女性の生の実情。著者は汚れた部分も含め、生きていくために必要なあらゆるきれいごとを排した負の側面を女性ならではの視点から描く。
藤子は育児放棄寸前まで親から見捨てられ、学校ではありとあらゆるいじめを受けていた。それは裸にされて性器をいじられると言う、もはやいじめのレベルを超えたいじめ。
本書の前半部分を読み通すのは、相当の覚悟が必要だ。この救いのない藤子への扱いがいつまで続くのか。読者は小説が早く明るい方向へ切り替わってほしいとすら思うはずだ。
藤子の受難は、両親と妹が殺されたことによって次の段階へと進む。孤独の身になった藤子を救ってくれたのは伯母。伯母のもとで暮らすことになった藤子は引っ越し・転校する。そして同情という得難い武器を得る。同情によっていじめられる必要がなくなった藤子は、新たな学校で立場を得ることに成功する。そこでは打算だけを頼りにクラス内で地位を得ようとする藤子の姿が描かれる。その立ち回り方は醜く、人気者も裏に回れば汚れている。
女の子がクラスでうまく立ち回るには、清く正しくではやっていけない残酷な現実。著者はそれらも含めて冷酷に描いていく。
学校を卒業し、仕事や友人、恋人にも恵まれる藤子。ところが、恋人と友人との間で三角関係の複雑さに襲われ、ついには殺人に手を染める。どこまでも運命は藤子を更生から遠ざける。凄惨な死体処理を恋人と二人で行う中、恋人は藤子を恐れ、藤子に秘密を掴まれたとおびえるあまり、まともな社会生活を送る気力を奪われる。さらに恋人の親は資産家ではなく、元資産家でしかなかった事実。
単なるヒモに成り下がる恋人との殺伐とした毎日。
この時点で藤子の人生には選択肢がなくなってしまう。この結末を藤子のせいにするのか、それとも環境のせいにするのか。
決して自分の母のようにならないと誓っていたはずなのに、事態はどんどんと藤子の意に反する方向へと進んでいってしまう。
そんな藤子の姿は、生命保険の外交員スカウトも引き寄せる。新たなる仕事への勧誘。ところが羽振りの良さそうなスカウトも、裏側では悲惨な日々を過ごしている。子育てどころか、ネグレクト。藤子が幼い頃に受けたような悲惨な境遇をしなければならない虚栄に満ちた日々。
恋人との間に生まれた美波を異臭がするまで押し入れに閉じ込め、行き着く先は謎の失踪。
ここまで徹底的な転落劇を描いておいて、著者は藤子に何も救いを与えない。それどころか読者も闇に引き摺り込もうとしているのではないか。
読者はこの希望が見えない小説から何を汲み取ろう。何を教訓としよう。
刹那のお金を得るためなら、いとも簡単に目の前の人物を殺す。目の前の理不尽な現実を凌ごうとする藤子の生き方はすでに修羅。夜の蝶になってもそれは変わらない。すぐに化けの皮が剥がれ、それを糊塗するために次の犯罪に手を染める。
終わりのない地獄の日々は、ある日終わりを告げる。
続いて登場するのは、藤子の娘とされる著者。そもそもこの本は藤子を描く目的で描かれていた。
そこから後は、興を削いでしまうので書かないが、本書にはある仕掛けが施されている。この救いのない小説を、その仕掛けを味わうために読むということもありかもしれない。
小説とはあらゆる現実を切り取る営みだと考えれば、救いがない物語の中にも真実はあると見るべきだろう。
例えば本書の藤子の姿を見て、自分より下がいると安堵する読者もいるだろう。藤子の境遇に比べれば、自分の人生などまだマシと前向きになれる人もいるはずだ。または、自らの人生のこれからに起こりうる苦難や障害を本書から読み取り、避けてゆくために本書を役に立てると言う人もいるはず。
読みあたりが良く、感動できることだけが小説ではない。余韻は強烈に悪いけれども、印象に残るのならまたそれも小説。
著者の作品は他には読んだことはないが、大体似たような作風だと言う。また読んでみようと思うのかどうか、今の時点で私にはわからない。
だが、この救いようのない時代を生きる者の1人として、こうした人生を送っていたかもしれない可能性。こうした人生もまたありうるのだと思える想像力。それは本書のような小説を読まない限り決して触れることのない領域だろう。
それはまた、今の社会制度の歪みでもあり、教育制度の欠陥かもしれない。もちろん、資本主義そのものが人類にとって害悪なのかもしれない。人の心の度し難い弱さや醜さを見てとることも簡単だ。
事実からは事実に即した答えしか出てこない。フィクションは著者の想像力に委ねられるため、逆に事実に束縛されず、読者が自在に教訓を受け取ることができる。
雑誌や新聞のルポルタージュからは読み取れない人生の大いなる可能性。それこそが小説というメディアの秘める可能性だと思う。
‘2020/03/06-2020/03/08