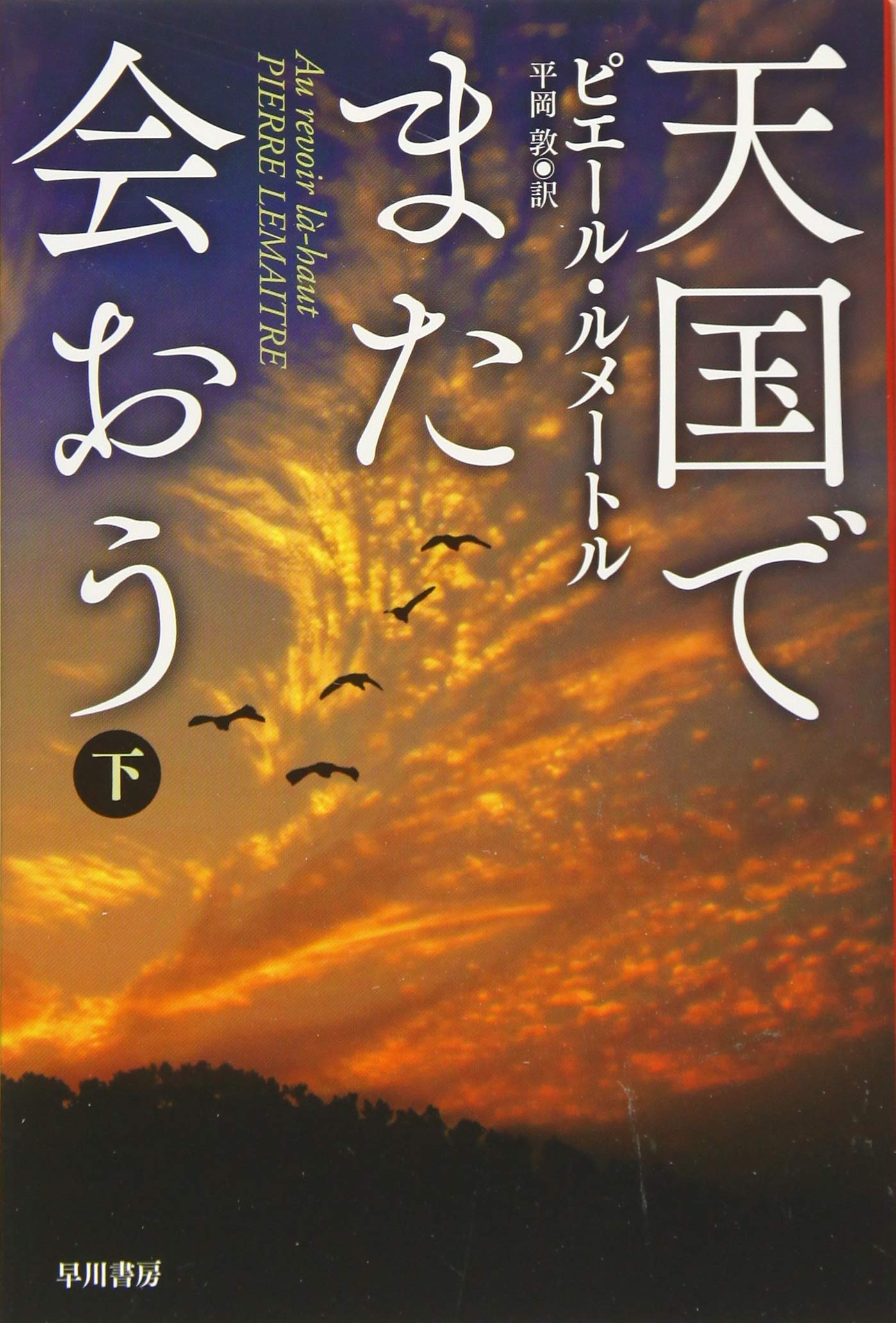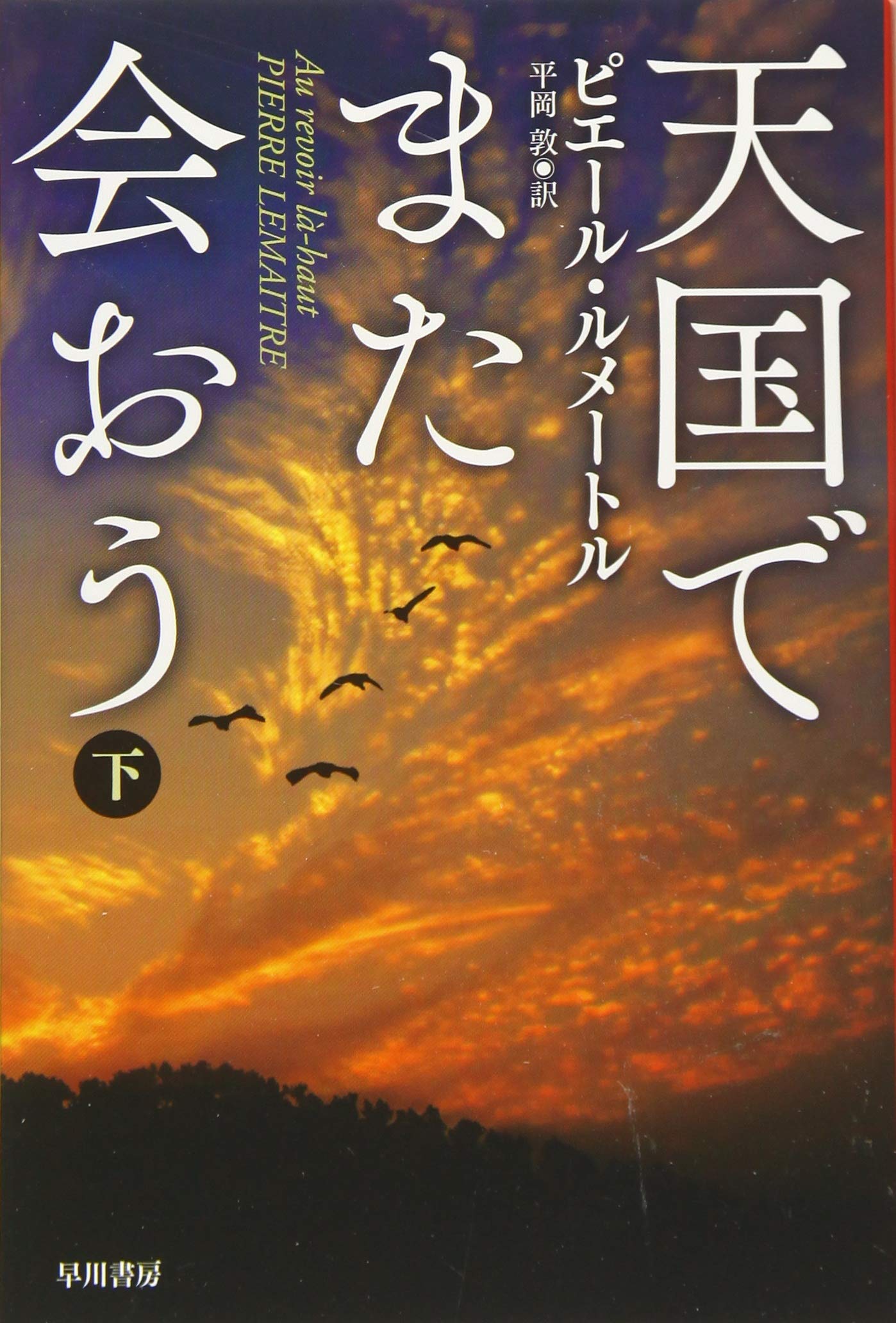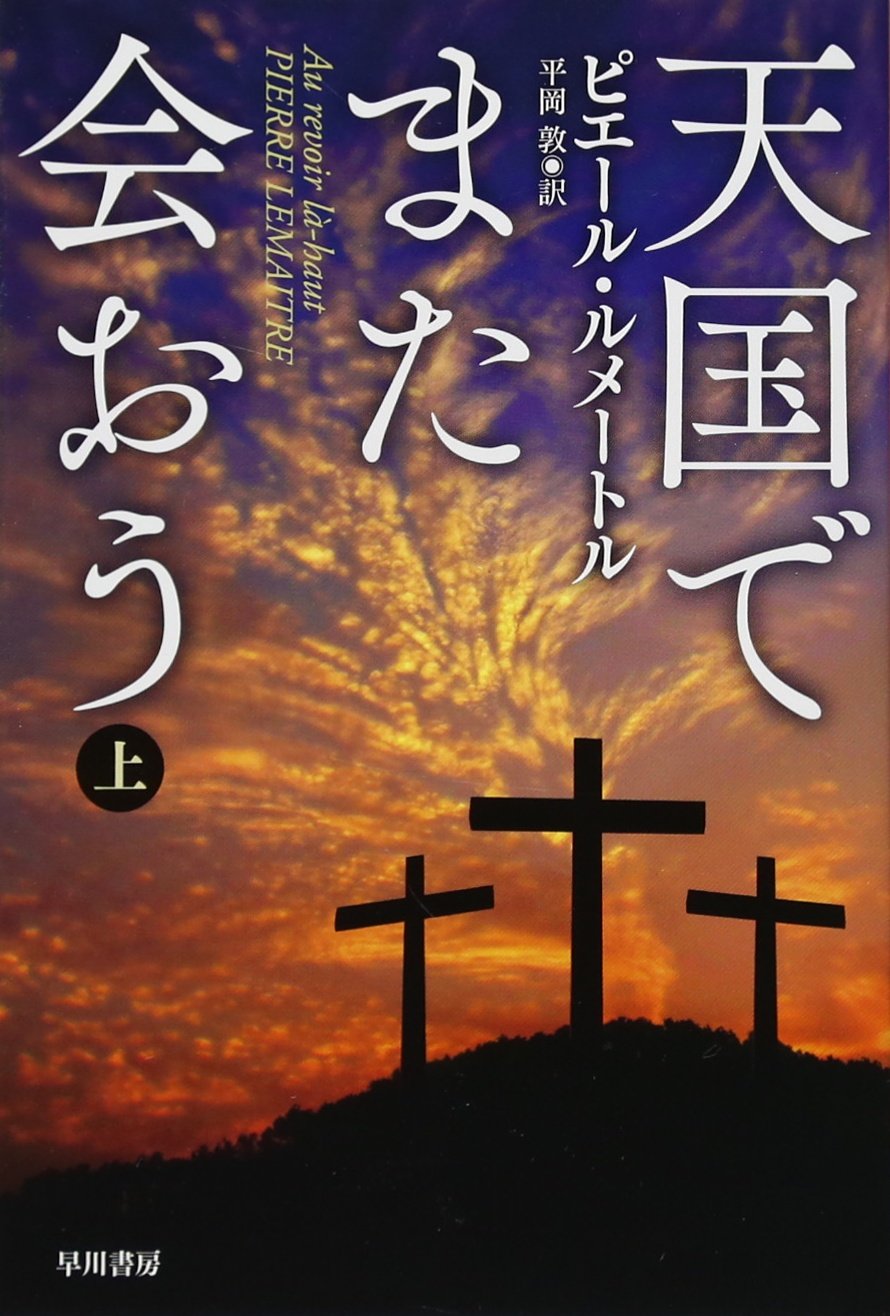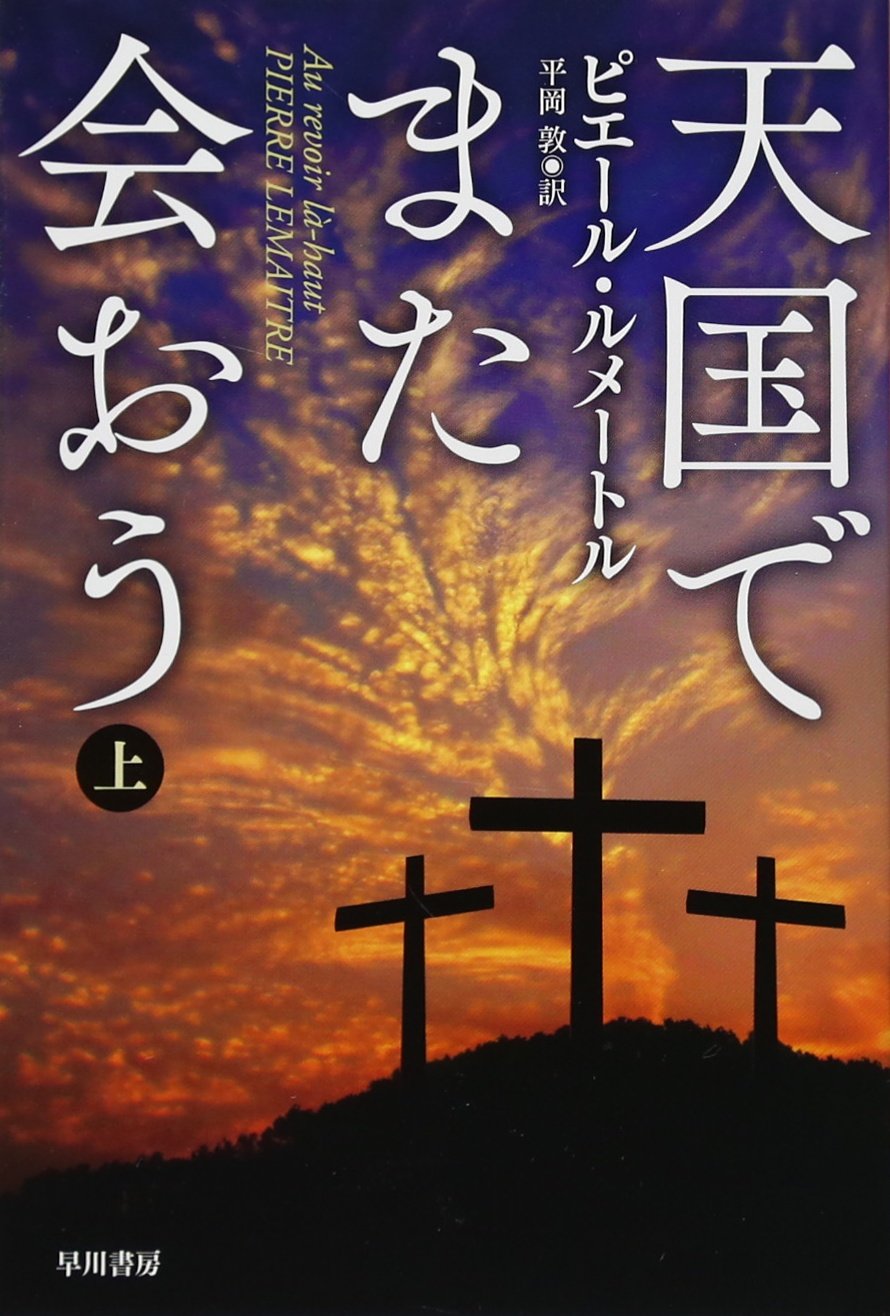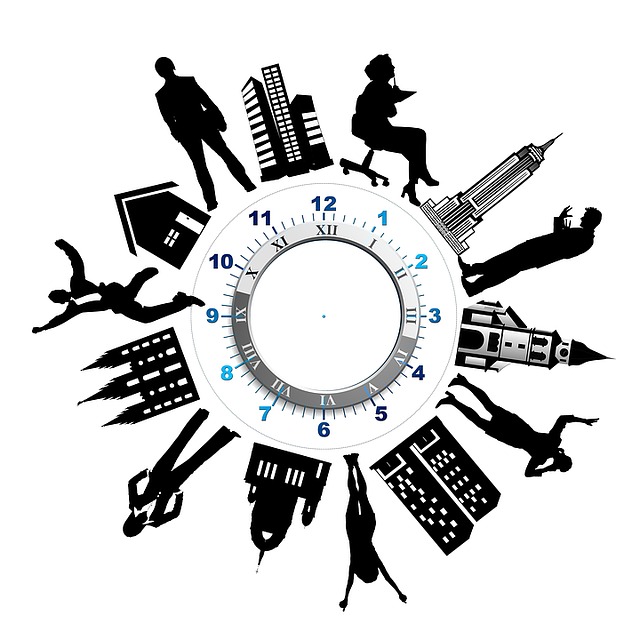3月2日に「こどもの居場所大会 in 東京」に参加しました。
開催された場所は日本橋にあるサイボウズ本社の27階です。
私にとっては行き慣れた場所で開催されたこのイベントですが、今回は実際に参加するのが大変でした。
その理由は、当日の朝に富士吉田にいたためです。
前日まで二泊三日のやまなしワーケーションに参加していました。皆さんと別れた後、私だけ富士吉田に向かい「よっちゃばれっ kintone 無尽 Vol.3」に参加し、西裏で二軒を皆さんと楽しんだ翌朝、私は東京に向かいました。
寝坊せずに、富士吉田駅から列車に乗り込めましたが、「かいじ」の車内では眠りこけていました。
開会は10時でしたが、ぎりぎり間に合いました。
私をお招きくださったサイボウズの中村龍太さんとお会いし、三日分の荷物が詰まったトランクをHOUSTON部屋に置かせてもらいました。

今回は私にとって新鮮な集まりでした。
こどもの居場所大会。つまり、主役は子供です。私にとってこどもの居場所と聞いて真っ先に思い出すのは学童保育です。
娘たちは合わせて6年間通っていましたし、私も役員を務めました。妻は保護者会長も務めていました。
しかし、学童保育以外の子供の居場所については、私はあまり理解していませんでした。
そもそも、わが国の教育制度について、私はとおり一般の知識しか持っていません。
私は西宮市立の幼稚園、小中学校、兵庫県立の高校、そして私立大学を経て今に至ります。その間、学童には行きませんでしたし、塾も少し通った程度です。
順当な学校生活を送ってきた反動からか、社会人になってからは常に道を外れっぱなしです。今も相変わらず既定の道から外れた人生を歩んでいます。
では、学生時代は学校生活に順応できていたかというと、結構危なっかしかったと思います。不登校にこそなりませんでしたが、中一の頃は休みがちでしたし、いじめられた経験もあります。
私の学生時代に、このような選択肢を提供してくれる人がいたら。そして、学校以外の選択肢があれば、私もそちらに頼っていたことでしょう。
今回はそうした居場所を運営している団体の方が多数集まり、運営事例について貴重なお話を伺うことができました。
どうしても授業の仕組みに馴染めない人。勉強についていけてない人。友達同士での人間関係がうまく構築できなかった人。そしてそもそも肉体的・精神的に障害を抱えていらっしゃる方。
現代は多様性を重視する時代です。
そうした一般的な教育制度に馴染めない方に対し、社会も選択肢を与えるべきだと思います。
また、画一的な教育が効果を発揮した高度経済成長期は遠くなり、今のわが国にあった多様性が教育にも求められているはずです。
私の祖父は教育学の研究者です。戦後すぐの明石附小プランという教育プランの策定運動の中心人物でした。
祖父が研究者として脂がのり切っている時期であれば、今の多様化の動きにもきっと関心を持ってくれたのではないかと思います。
今回参加されている方々は、教育の多様化を実践し、日々の運営を通して社会に貢献してらっしゃる方でしょう。
ただ、多くの団体が登壇していたため、私は全てにコメントができません。
ですが、いくつか触れさせてもらいます。
「シン・スクール」さんのゲーム・AI・IoTを使う先進的な取り組みには感銘を受けました。
また、「みんなのプロジェクト学校」の参加者たちによる自主的なイベント開催は居場所作りの神髄をみました。
「フリースクール 滝野川高等学院」さんの取り組みの広がりは、学校制度の枠の窮屈さをかえって意識させました。
さらに「なにかし堂」さんの医療をからめての街の居場所作りの取り組みは、参考にしたいと思わせてくれました。
最後に「れもんハウス」さんのカリキュラムとは縁の遠い自由な運営も居場所作りの可能性を見せてくれました。

それらの皆さんの話の後、サイボウズさんの中村さんから理事を務める「一般社団法人 ぴおねろの森」についての説明がありました。
ソーシャルデザインラボとしてのビジョンである「多様な価値観の人が安心して暮らしている社会づくり」の紹介の後は、私もスライドに登場し、紹介いただきました。
それを受け、私も来場の皆さんの前で立ち上がって挨拶しました。

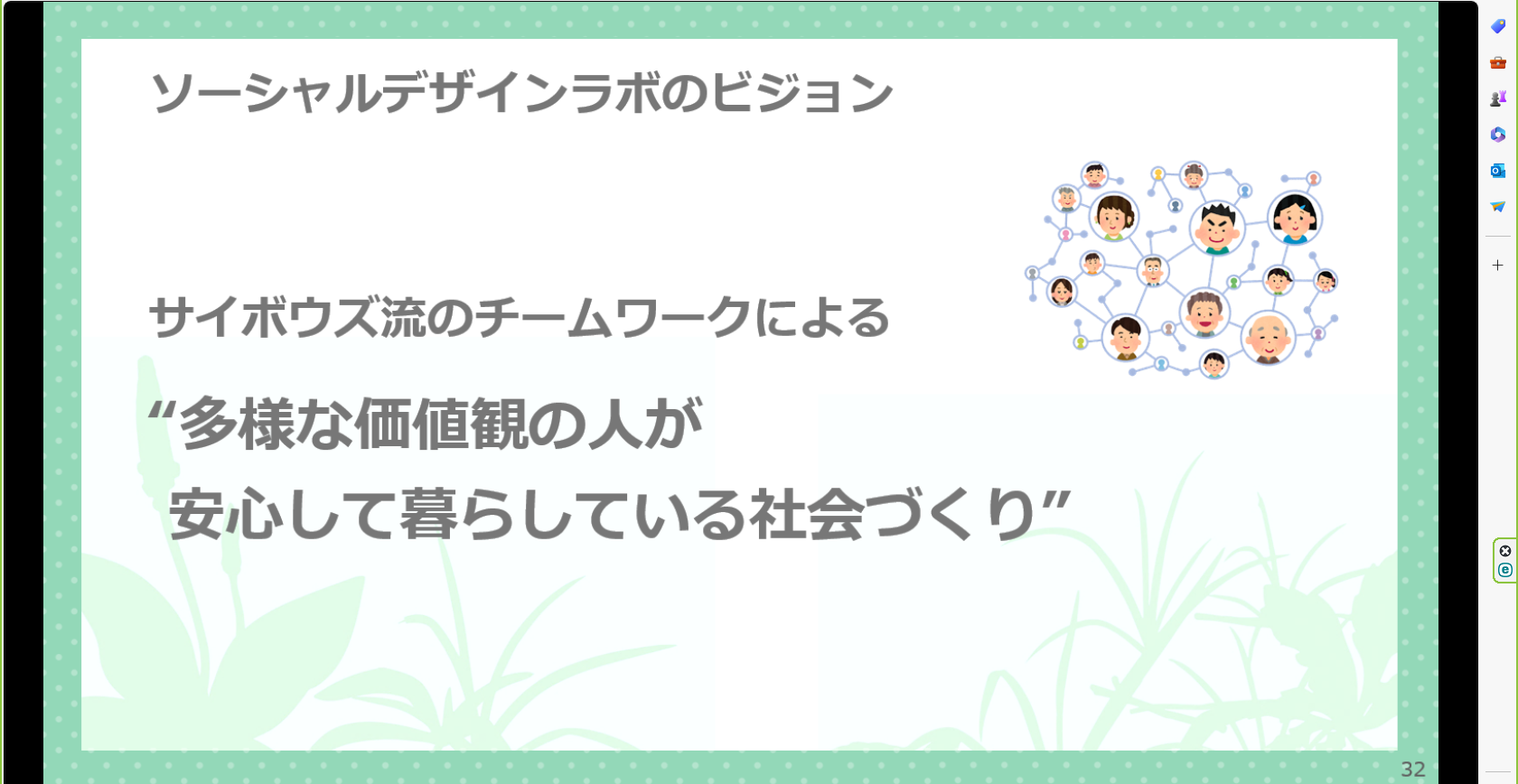
私も「多様な価値観の人が安心して暮らしている社会づくり」というビジョンには強く賛同します。
昔から同調圧力に苦手意識があり、他人と同じ行動を取ることに抵抗を感じていました。
そもそも、私がサイボウズのkintoneを推し始めたのは、この価値観に強く共鳴したからです。
技術者として可能性を感じ、自分が食べていけるという成算があったことも確かです。しかし、それだけでは10年近くもエバンジェリストを続けることはできません。
私も誰もが自分の好きなように生きられる社会を目指したいと思い、それに向けてできることをしたいと思います。
最近は案件を多数いただいており、経営者としてもやることが多すぎて初心を忘れかけていました。
今回の「こどもの居場所大会 in 東京」や中村さんのスライドはその気持ちを思い出させてくれました。
さて、昼食を食べに行った後、再開したセッションのいくつかを聞きそびれました。
聞けたセッションの中では、渋谷区議会議員の神薗まちこさんのお話は、非常に興味深かったです。
渋谷区の学校教育に関する取り組みについては、以前から断片的に耳にしていました。
その取り組みを先頭に立って進められている神薗区議の取り組みは興味深いものでした。
教育ICTは私にとってもスキルが活かせるよい場になりそうです。
また、その後の発達障害・特別支援教育の研究をされている加藤浩平氏の話もとても興味深いものでした。
この分野については全く知識がなかったのですが、コミュニケーションが苦手な子供もTRPGという媒体であれば場に入っていけるということも知らなかったです。知らないことを知り、自分がアップデートされた気分です。
終わった後も、私に話しかけに来てくださる方やご相談に来てくださる方など。
そういえば偶然にも弊社のサテライトオフィスのすぐ近くでも今度フリースクールが開校されるらしく、そういったご縁もつながりました。

弊社が皆さんをどのように支援できるか。
それらを開発するとご予算的にも難しくなるはず。となると初歩をお教えし、伴走しながらやるしかないはずなのです。
私個人として、そして弊社として、これから居場所作りをされている皆さんにどのように価値を提供していけるか考えています。
弊社としても、そのための仕組みを構築する必要があります。
今回の「こどもの居場所大会 in 東京」はそのよいきっかけになりそうです。
皆様、ありがとうございました。