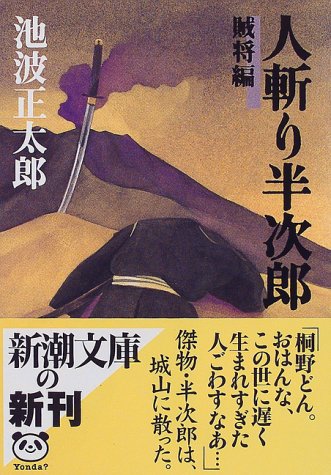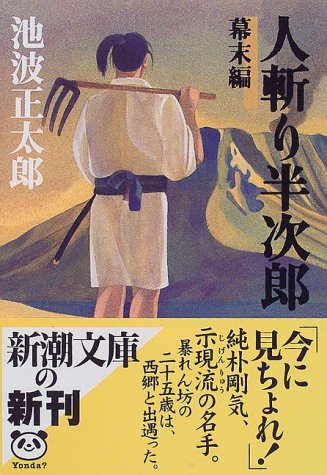本稿を書いている時点で、安倍首相の首相在職期間は戦後第4位になるそうだ。長期政権に向けて視界も良好、といったところだろう。
安倍内閣の政策を一つ一つあげつらえばきりがない。だが、よくもわるくも自民党の伝統路線を堅実に歩んでいることは評価できるのではないか。私が本稿を書き始めたとき、安倍首相はトランプ米国大統領との首脳会談に臨んでいる。トランプショックに巻き込まれるのか、それとも新たな日米関係が構築できるのか。安倍首相はトランプ米国大統領ともリーダーシップの上では相性がいいのではないか、ともいわれている。ここで盤石の信頼体制が築けたら、安倍内閣の体制もさらに強固なものとなるに違いない。対米従順といわれようが、ポチと言われようが、日米関係が日本の外交戦略上無視できないことはもちろんだ。
そして安倍首相は長期政権が確立できる見通しがついた時点で祖父以来の懸案に取り掛かることだろう。その懸案こそ、憲法改正。
安倍首相の祖父、岸信介元首相の悲願でもあった憲法改正。それは、安保改正法案の議決と引き換えに岸内閣が総辞職したあと、60年近くも実現する見通しすら立っていない。岸氏は首相を辞任した後も後継者たちに憲法改正を託し続けていたという。そして、それがなかなか実現しない事に苛立っていたという。
岸氏を描いた本書には、幼い頃の安倍首相が登場する。安保デモ隊の群れは岸首相宅の周辺にも押し寄せた。そんな周囲の騒ぎをよそに、岸首相は悠然と孫たちを呼び寄せ、のんきに遊んでいたという。幼い安倍首相がデモ隊に向けて水鉄砲を発射していた微笑ましいエピソードも本書には登場する。おそらく安倍首相は、祖父から憲法改正の悲願を繰り返し刷り込まれて成長したことだろう。安倍首相に与えた祖父岸氏の影響とはかなり大きかったと思われる。
私が本書を手に取った理由。それは安倍内閣の政策の源流が岸信介元首相に発することを確かめるためだ。そして本書を読んで、その目的は達せられたと思う。今の安倍政治を読み解く上で、岸氏の生涯を振り返ることは意味がある。
自民政治の後継者とみられる安倍首相だが、出身派閥は清和会だ。清和会といえば岸氏の流れを汲む派閥だ。一方で安倍首相にとって大叔父であり、岸氏の実弟にあたるのが佐藤栄作元首相だ。佐藤栄作氏といえば、吉田学校に学んだ吉田茂直系の後継者として知られている。岸氏は反吉田色の強い政治家として知られている。兄弟でも政治的な立場に違いがある。そして、安倍政治とは大叔父の佐藤栄作元首相よりも、岸氏の流れをくんでいる。ということは、吉田池田佐藤路線が戦後の日本の本流と仮に見なせば、安倍政治とは、自民政治の本流ではないということになる。
では、岸氏とはどのような人物だろうか。岸氏を一言で表す言葉として著者が選んだのは「絢爛たる悪運」。「絢爛」とは氏の栄達に満ちた一生を表し、「悪運」とは氏の波乱の生涯を表しているのだろうか。
波乱の生涯とは言っても、岸氏の生まれは恵まれていた方だ。岸氏が生まれた佐藤家が、長州藩でも名家にあたる家だからだ。岸氏の曾祖父にあたる佐藤信寛は、吉田松陰に兵法を伝授した人物として、長州藩に重きをなした人物。明治初期には島根県令を勤めたとも伝わっている。つまり、岸氏は長州閥として恵まれた一族に産まれたのだ。岸氏が産まれた時も明治の世を謳歌していたことだろう。
ところが岸氏の場合、父が養子だったことで波乱の人生に投げ入れられる。父の実家、岸家に婿養子で出されるのだ。以来、岸氏は、佐藤家と岸家の双方に気を遣って生きることになる。それは岸氏に硬軟取り混ぜた処世の術を身につけさせる。結果として岸氏は逆境に遭っても身を処すためのスキルを身につけた。
東大から商工省へ。ここで頭角を現した岸氏は革新官僚として統制経済を推進する。統制経済は、軍にとっては都合の良い政策である。その推進者として軍に目を掛けられた岸氏は、満州国の経済責任者として関東軍から招聘される。そして、商工省を辞めて満洲国へ。さらには東条内閣の閣僚に抜擢され、開戦の詔書に署名する。この辺りの経歴は、「絢爛たる」といってよい。
ところが戦局の悪化は、岸氏の主管である戦時生産に悪影響を及ぼす。生産が戦局の悪化で計画通りに進まなくなり、東条首相との関係が悪化する。その結果、岸氏は一転、東条内閣の総辞職に一役かうことになるのだ。岸氏は敗戦後に極東軍事裁判、いわゆる東京裁判でA級戦犯として訴追される。だが、東条首相と対立したことや、開戦二カ月前の戦争指導者会議に出ていなかったこともあり、無罪となる。この辺りが「悪運」と言われるゆえんだろう。
著者はここで悪運にまつわるエピソードとして、岸氏が巣鴨プリズンから無罪で出てくることや将来は総理となる託宣を告げにやって来た占い師のエピソードも挟む。
公職追放が解除されてからの岸氏は、政界復帰に向け準備を進める。その結果が、石橋内閣の副総理格である外相で入閣する。ところが石橋首相が病気で退陣を余儀なくされるのだ。そこで首相代理に昇格したのが副総理格だった岸氏。そのまま次期総理として二期に渡って組閣することになる。この辺りの岸氏の経歴こそが、昭和の妖怪と揶揄されたゆえんだろう。並みいるライバルは次々に病で舞台を去り、労せずして首相の椅子を手に入れるあたりが。
岸内閣の業績は、実は安保以外にもいろいろとある。だが、首相を退陣した後の岸氏にとって思い出されるのは、安保改定の攻防とデモ隊に囲まれる日々だった。樺美智子さんの死亡とアイゼンハワー米大頭領訪日断念といった一連の流れは特に印象深い出来事だったようだ。審議時間切れで安保が自動的に決議されるのを待つ間、首相官邸で過ごす岸氏の元を訪れていたのは実弟の佐藤栄作氏。ここで岸氏の口をついたのは幕末の長州で奇兵隊を立ち上げた高杉晋作の一句。「情けあるなら今宵来い、明日の朝なら誰も来る」
対米戦争を始めた内閣の閣僚であった岸氏は、アメリカに対しては複雑な思いを持っていたことだろう。安保改定を単なる対米追随から推進したのではないはずだ。戦後の日本が置かれた状況や国際関係の行く末も秤にかけた上で、最善手として安保改定を選んだはず。
最近、この年のノーベル平和賞候補として現職の岸首相が推薦され、候補に挙がっていたことを知った。もし受賞していたら実弟佐藤栄作元首相の受賞以上に物議を醸した事だろう。資料によれば、ノーベル平和賞に推薦したのはアメリカの上院議員だったとか。おそらくは推薦事由とは戦後国際政治を冷静に見極め、安保改定を推進したとかそんな事だろう。東條開戦内閣の閣僚でありながら、米国と手を握った現実感覚が推薦理由だったのかもしれない。こういった得体の知れない処世の鮮やかさも、悪運の強さとして、昭和の妖怪と言われた理由だと思う。
自民党金権政治のハシリ、対米追随のハシリ、と岸氏を誹謗するのはそれほど難しくない。それよりも難しいのは岸氏の構想に乗った憲法改正の実現だ。国際政治の変化に対応し、対米追随路線を進めたとはいえ、岸氏は憲法改正を悲願としていた。吉田元首相や岸氏は、GHQの権力の強さを肌で知っている。だからこそ、戦後の出発にあたっては、GHQから押し付けられた憲法を飲むしかないとの現実認識をもっていた。だが、それはあくまでも一時の方便に過ぎない。日本人が主体となって制定した自主憲法を望む思いは強いはず。一方、憲法が思いの外長期にわたって有効であり続けたことは、日本人は制定当初の憲法がいびつな手続きであったことを忘れ、慣れてしまった。その結果、改憲の機運も依然として弱い。
だが、当時は弱体だった中国が強大になっている今、果たして今の憲法が有事に対応できるのか。そう問われれば言葉につまるほかない。
祖父が果たせなかった改憲を孫の安倍首相は実現できるのか。トランプ大統領との首脳会談では、尖閣諸島は安保条約の適用範囲であるとの言質をトランプ大統領から得た。これによって安保の威光がいまもまだ失われていないことが明らかとなった。そして、米国の庇護が期待できれば、改憲の必要は少し弱まる。だが、それでもなお国防を自国でやるか他国に委ねるか、という問題は解決されていない。岸首相の時代から何も変わっていないのだ。
岸氏の生涯は、実は妖怪どころか、超現実主義の原則に沿っていた。現実主義とは、これからの日本を舵取りする上で欠かせない視点だと思う。その意味でも、岸氏の衣鉢を継ぐ安倍首相のこれからに注目したいと思う。
‘2017/02/06-2017/02/07