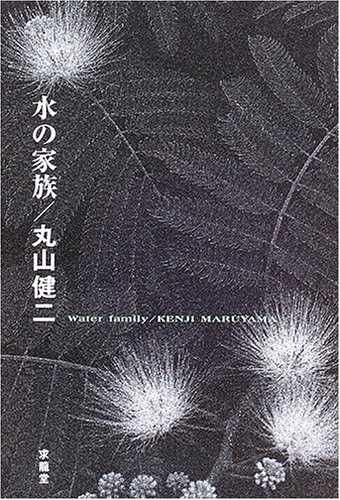
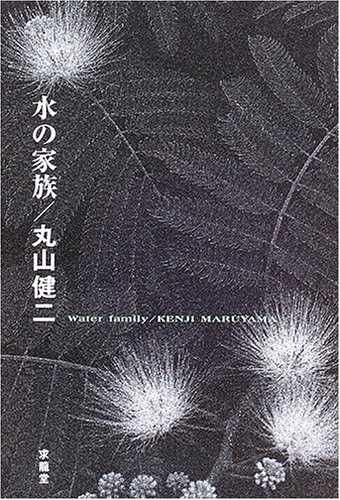
著者の作品は一時期よく読んでいた。孤高ともいうべき、極端にせりふの少ない作風。生きるとは孤独を身にまとうことを実践するように、群れることを極端に遠ざける姿勢。著者の作品は私の生き方にも少なからず影響を与えていると思う。
本書は再生復活版として著者があらためて手を入れて出版した作品だそうだ。再生復活版が原書からどのぐらい変わったのか。原書を読んでいない私には、それはわからない。多分、本質的には変わっていないはずだと思う。
セリフを極端に控え、言葉によるコミュニケーションを抑えめにする作風。そのため、著者の語りには一つの傾向がある。それは人でないモノを語り手とすることだ。私が著者を読むきっかけとなった『千日の瑠璃』は、その手法を極端に推し進めている。千日を一日ごとに違う章で書き連ねた 『千日の瑠璃』 は、意表をつく語り手からの独特の視点が印象的だった。なにせ毎回語り手が違うのだから。ある日は犬だったり、別の日は空だったり。『千日の瑠璃』で確立した手法は、源流をたどると一つは本書に行き着くはずだ。なぜなら本書の語り手は死者だから。
本書はタイトル通り、ある家族が描かれる。 草葉町というどこにでもありそうな町。そんな町に住むありふれた家族が本書の主人公だ。草葉町の近くには忘れじ川が流れ、天の灘に注ぐ。餓鬼岳が屹立して、麓に広大な草原を抱える。語り手には八重子という妹がいる。離れの仏間で寝たきりの母がいる。天の灘に毎日繰り出しては海の幸を持ち帰る父がいる。一人餓鬼岳の麓で馬たちと暮らす祖父がいる。夜ごと密漁に精を出すはみ出し者の弟がいる。実直に金融機関に勤める兄と、いささか嫁の立場になじめないように見える兄嫁がいる。そして語り手は生を持て余した死者だ。誰にも知られぬまま餓死しし、あばら屋で死骸と化している。
著者は神の視点を持つ語り手を求めるため、四兄弟の二番目である語り手に死んでもらう。そして死者の立場から語り手へと仕立てる。魂だけの存在であるため動くのは自在だ。 水に交じってどこにでも行き、さえぎる物のない視点で本書を語る。自由な境遇ゆえ、家族の営みや、家族を取り巻く土地の出来事をつぶさに見聞きする。この魂は死してなお自我を持っている。自分が死ぬに至るまでの挫折と蹉跌の日々を反芻して後悔する自我を。
語り手が生家から逐電するに至った理由。それは妹八重子との許されざる関係だ。兄妹の間の超えてはならない一線。それを目撃した母は仏間にこもり切りになってしまう。よりによって知恵遅れの妹に手を出してしまった罪の意識に苛まれた語り手は、良心の呵責に耐え切れず、生家と草葉町を離れて都会の騒がしさに身を投じる。都会のドライで非情な日々は語り手を消耗させ、ほうほうの体で草葉町へと舞い戻らせる。そして、どの面下げて実家に顔を出せようか、というなんの根拠もない面目にこだわる。そんな語り手は、竹林に荒れるがままに忘れ去られていたあばら家に住まううち、ついに餓死する。
著者はそんな語り手を突き放す。突き放しながらも語り手である彼の独白はさえぎらない。さえぎらないので、語り手がぼとぼとと漏らす愚痴とも後悔ともつかない語りを文章として採録する。そこには後ろ向きの気持ちしかない。一方、中途半端な自分の一生を償うかのような前向きな精神も語り手は発揮する。かつての自分を償うかのように、語り手は八重子の生き方に暖かい目を注ぐ。語り手ではないどこかの誰かと子を作った八重子は、子の世話を餓鬼岳の麓に住まう祖父とともに行う。山に住まう祖父は、たくさんの馬と八重子と孫とともに住む。そこにはただ自由がある。世間の干渉も、見えや体裁もない自由が。そんな彼らの日々を語り手は逐一語ることはない。なぜなら語り手は水を伝ってしか動けないからだ。
語り手が常に干渉し、観察できる水の家族たちは水に囚われている。父は日々海に出て作業をする。その一本筋の通った生き方は語り手にはまぶしく映る。何物にも妨げられないだけの堂々とした構えで漁にいそしむ父は、一家の中の重鎮にふさわしい。だが、寡黙すぎるゆえに家の問題に干渉しない。そしてひたすら日々の糧を持ち帰る営みに淫している。そして弟。密漁に情熱を傾ける弟も水に囚われた日々を送っている。地元の金融機関に勤める兄は傍目には堅実な日々を送っているようにみえる。だが、兄嫁の奔放さが兄の日々を脅かす。ある日兄嫁の奔放な行いに衝撃を受けた兄は雨の降りしきる中を泥酔する。兄もまた、水に屈するのだ。いうまでもなく、水とは本書において人間のしがらみの象徴だ。
水の家族の男性陣は水に囚われるが、それに反して水の家族の女性陣は水に囚われない。奔放な兄嫁は水そのものであるかのように、貞操すらも水のように扱い自在に生きる。母は家族の問題に背を向け、自らをよどんだ水として家に渦巻く。水に同化するのだ。妹の八重子もみずみずしい生の喜びを享受し、水の流れのように闊達と生き抜く。
そしてもっとも水に対して動じない者は祖父だ。馬を養いながら、手作りの凧を飛ばして日々を生きる祖父は、もはや何物にも影響を受けない。まさに水の柔軟さと剛直さを備えている。祖父がもっともその真価を発揮するのは大風のシーンだ。凧は竜と化して祖父を空へと運び去ろうとする。それに必死に抗い手なずけようとする祖父。雨風と祖父の戦いは祖父が勝利を収め、龍となった凧は糸が切ればらばらになる。水を制御した祖父が、一家の礎であることを表す場面だ。
それが合図となり、密漁がばれそうになり水の中であわや死にかけた弟は、かろうじて生還し真っ当な生活へのきっかけをつかむ。仏間にこもる母は表にでて漁から帰ってきた父と久しぶりに言葉を交わす。水のように奔放な妻に絶望した兄は、何事もなかったかのように妻を許し、元の暮らしへと収まる。八重子とその子は相も変わらず生を謳歌しする。そして、もっとも水に囚われ続けてきた語り手は、ついに死を脱し、時空を超えた境地へと昇ってゆく。
水に囚われながら、水を逆に生かしてきた人間の営み。それを一家族の在り方をとおして描いた本作は、まさに丸山節ともいうべき魅力に満ちた一編だ。
‘2017/05/25-2017/05/31



