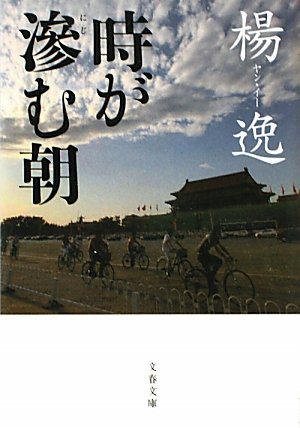
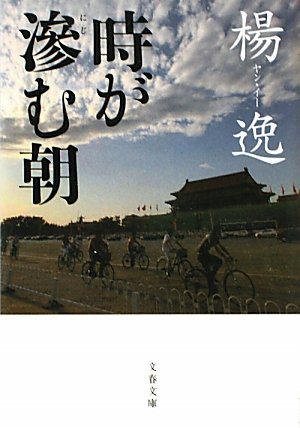
日本語を母語としない著者が芥川賞を受賞するのは初めてのことらしい。そのためか、本書には「ん?」と感じる表現が散見される。そうした表現は日本語の文章ではあまり見られない。それは中国で生まれ育った著者が、生まれながらにして日本語を使いこなしていないからだろう。でも、それもまた著者の文体だ。そう思えば気にならないし、むしろ独特の色合い、個性だと思えばよい。
それよりも本書で浮いているのは馬先輩が挟む英語だ。著者は馬先輩の凡人ぶりを際立たせるために、このような英語表言を挟み込んだのだろうか。明らかに本書の中では浮いてしまっている。
そうした点を除けば、本書はとても読みやすい。特に、私のような第二次ベビーブーム世代には、尾崎豊の登場だけで共感できると思う。
本書は、理想に燃えた若者が成長し、世間の流れに飲み込まれて行く様子が描かれる。舞台は中国。本書でいう燃える理想とは、中国の民主化だ。理想に燃えた青年たちが、親となって生活に追われ、本書の主人公のように中国を出て、異国で過ごす日々で、世間の中に紛れてゆく姿。そうした姿を著者は同じ時代を生きた人として見つめ、小説に著した。
一方でわが国だ。すでに時代や世代の精神なる言葉は聞かれなくなって久しい。私たちの世代に戦争はすでに遠い。学生運動すら、生まれる前後には下火になっていた。つまり、理想として掲げる対象がなかった。そんな中で青年の前半生を送ったのが私たちだ。
例えば私が第二次ベビーブーム世代を代表する何かを書こうとしたとする。ところが見事なまでに空っぽだ。無理もない。オイルショックがあったとはいえ、日本の経済成長はすでに十分な繁栄を私たちに与えてくれた。泡が弾けるまで好景気を満喫する日々。電化製品が色と音を弾けさせる街中。ゲームはよりどりみどり。いくつもあるテレビチャンネルが、好きなだけただで番組を見せてくれる。食い物や飲み物にも事欠かない。そんな日々のどこに若者が不満を抱えるというのか。せいぜい、オウム真理教で心の充足をうたう組織のおぞましさや、阪神・淡路大震災で世界の不安定さにおののくぐらいが関の山だろう。
ところが著者の世代には、書かねばならないテーマ(国の民主化)と事件(天安門事件)があった。それはある意味ではうらやましい。
少なくとも文学の材料として、日本の若者には共通の理想は掲げにくい。ところが、隣の中国には描くべき現実、掲げるべき理想が山のようにあった。共産党の一党独裁、地方の貧しさ、文化大革命の余韻。キリがない。そんな若者たちが民主化を求める声は、天安門事件において頂点にに達した。
私は当時、高校生になったばかり。どういうきっかけかは忘れたが、天安門事件に強烈な興味を持った。日々の新聞で天安門事件に関する記事を全て切りぬき、スクラップブックに貼り付けた。多分、スクラップブックは今でも実家の部屋に置いてあるはず。私にとって、天安門事件こそが、リアルタイムで最初に興味を持った国際的な事件だった。毎日飛び込んでくる衝撃のニュースに興奮し、新聞を隅から隅まで読み込む。リアルタイムで日々のニュースを熟読したのは、天安門事件が最初で最後だろう。だからこそ、本書で描かれた天安門事件は、私にとって共感の対象となった。
本書でもう一つ、第二次ベビーブーム世代にとって心惹かれる要素がある。それは尾崎豊だ。代表曲「I Love You」が本書ではキーとなる。テレサ・テンの歌声に陶酔し、成長した主人公だが、本書の後半では尾崎豊の「I Love You」に心を鷲掴みにされる。
中国の若者が掲げた理想への思いが、尾崎豊を通して日本で暮らす若者に届く。それは日本からの視点では生まれにくい発想だ。著者ならでは、といえよう。だが、著者が本書で描いたことによって、あらためて尾崎豊の存在とはなんだったのか、という疑問に考えが及ぶ。そこで思うのが、尾崎豊こそは、上にも書いた世代の精神を歌い上げた人ではなかっただろうか。衣食住が満たされ、あり余るモノに囲まれた日本の若者は何に理想を求めたか。それは管理からの脱出だ。退屈な授業と受験勉強。やっとの事でそれを突破したら、待っているのは定年まで続く組織での日々。しかももれなく通勤ラッシュがついてくる。尾崎豊は高度成長期の日本の若者ならではの現実のつまらなさと目指すべき理想を歌に乗せ、カリスマとなった。
主人公とその親友は本書の中で二狼とあだ名をつけられる。つまりオオカミだ。本書にはオオカミと豚の比喩も現れる。豚にはなるな、オオカミであれ、と。そのフレーズは明らかに尾崎豊の『Bow!』からの引用だろう。私が好きな尾崎豊の曲の一つだ。その曲の中で尾崎豊はこう叫んでいる。
鉄を喰え 飢えた狼よ
死んでもブタには 喰いつくな
私は二十三才のある日、一日中、尾崎豊の「シェリー」を聴いて過ごしたことがある。青年が襲われる理想と現実のギャップに、心の底から悩みながら。その時にも、その後にも尾崎豊の詩には何度も奮い立たされてきた。上に引用した「Bow!」もその一つ。どう生きたいのか、どう生きねばならないのか。中年になった今でもその理想は忘れられない。
本書に登場する尾崎豊の歌詞は「I Love You」だけだ。でも、オオカミと豚のくだりは、私にとっては完全に「Bow!」を連想させる。だからこそ私は本書は本書に共感が持てた。そして、中国の若者が理想を求めた気持ちもわずかながらでも理解できる。天安門事件の当時、私はまだ真面目に授業を受けていた。そして尾崎豊にはそれほど惹かれていなかった。だが、天安門事件に特に興味を惹かれた私には、理想を求める気持ちが少しずつ芽吹きはじめたのだろう。後年、私を助けてくれることになる尾崎豊の掲げた理想。そして中国の若者が抱く理想。それらが本書において時代の精神として結晶し、尾崎豊の歌として提示されている。その結晶の成長は、私自身の精神の成長にリンクしている。だからこそ、三十年近くたった今でも、本書に共感できるのだと思う。当時を思い返しながら。
もちろん、理想とは実現できないからこそ理想だ。本書の登場人物たちもそのことを理解しつつ年を重ねる。主人公は、自分を慕ってくれていた中国残留孤児で日本に戻った女性と結婚する。そして日本で苦労しながらパソコンを覚え、生活の糧を得る。二狼と称されたもう片方は、中国に残ってデザイン会社を立ち上げる。彼も理想や革命を語るよりも、いまや経営のためにはカワイイデザインを手がけることも辞さない。二人の師はフランスに亡命し、理想をともに掲げていた同志もアメリカやフランスに亡命し、それぞれが生きてゆくための糧を稼ぐことに必死だ。私もそう。ようやく40歳を過ぎて独立は果たしたものの、営んでいることは資本主義の一つの歯車に過ぎない。
理想と現実のギャップに苦しんだ今だからこそ言えるが、数年前に若者が立ち上げたSEALDsも、たしかに主張の空虚さはあったにせよ、世の中を変えたいとの熱意は理解できる。むしろ、若者とは理想を求めて当然の存在なのだ。そして現実の手ごわさに悩み、挫折する。だが、現実の高い壁に跳ね返されたのなら、より穏健な方法で少しずつ世の中を変えていけばよいだけのこと。いまの保守系の重鎮たちの昔を見てみるがいい。かつて左向きの主張にのめり込んでいた人間のどれだけ多いことか。
世の中の流れに乗るふりをして、心の中のオオカミを忘れなければいい。私はそうやって中年の今も人生に折り合いをつけている。本書の主人公たちもそう。国が異なろうとも、理想は持ち続ける。それが青年の美しさなのだから。
‘2018/09/17-2018/09/19


