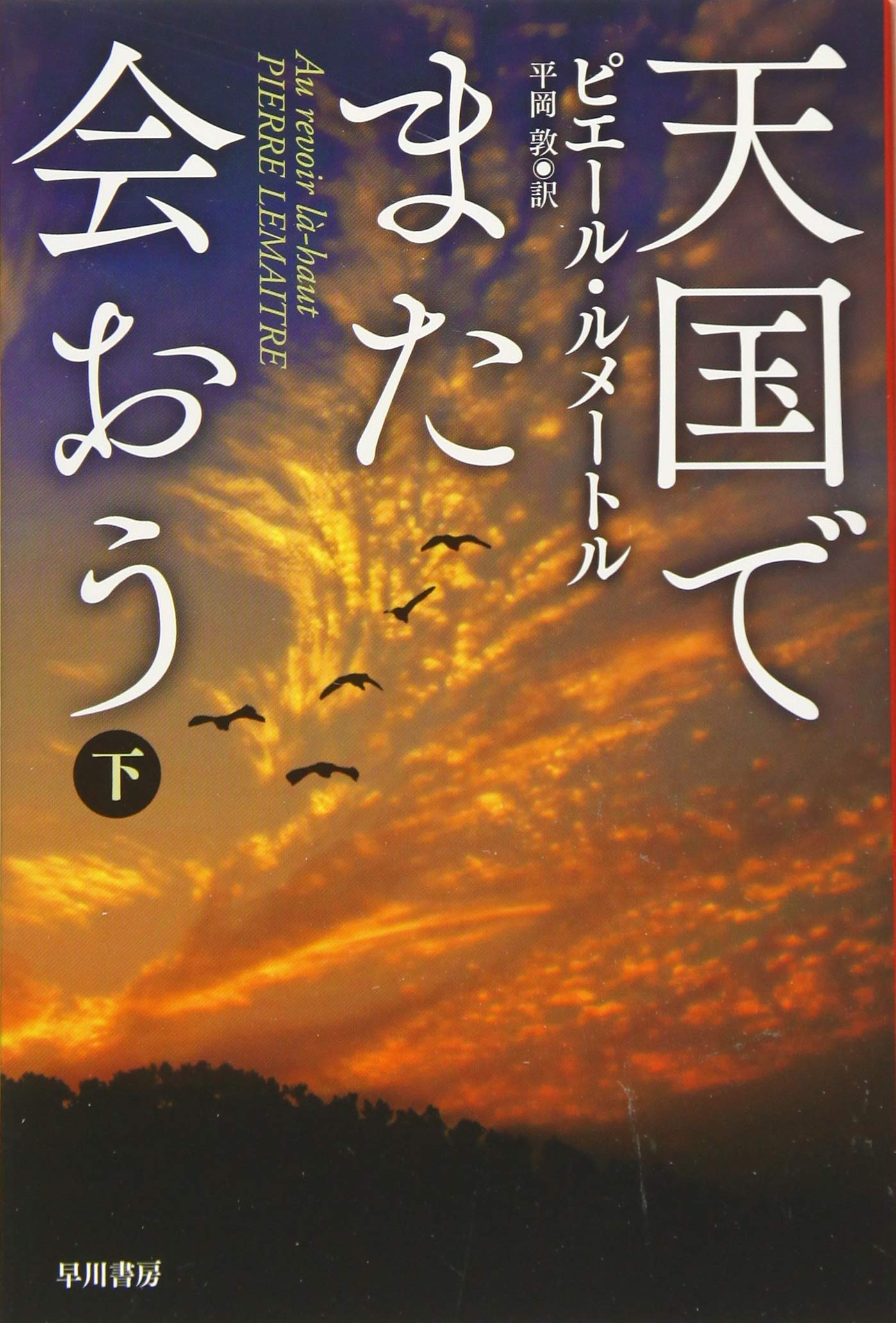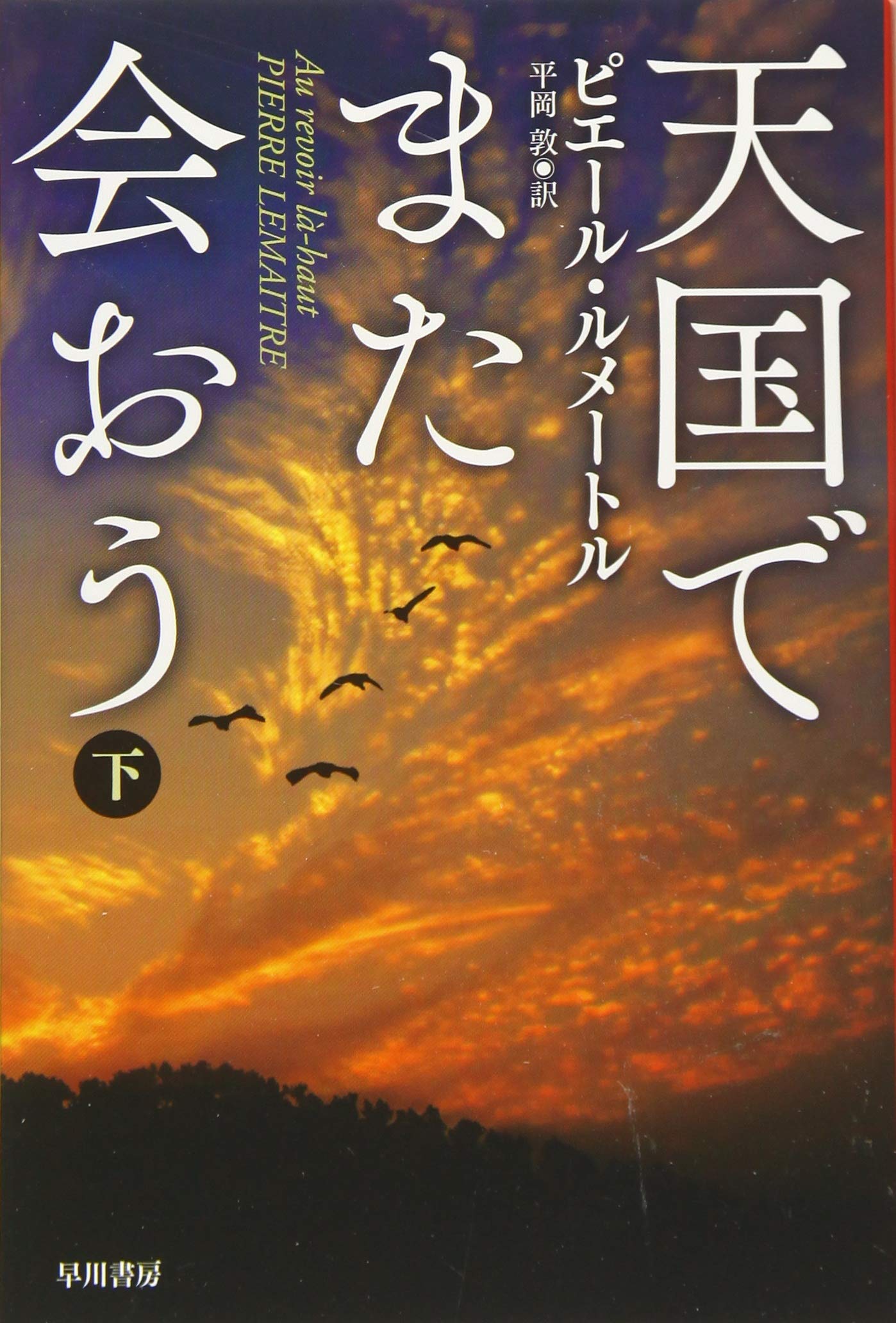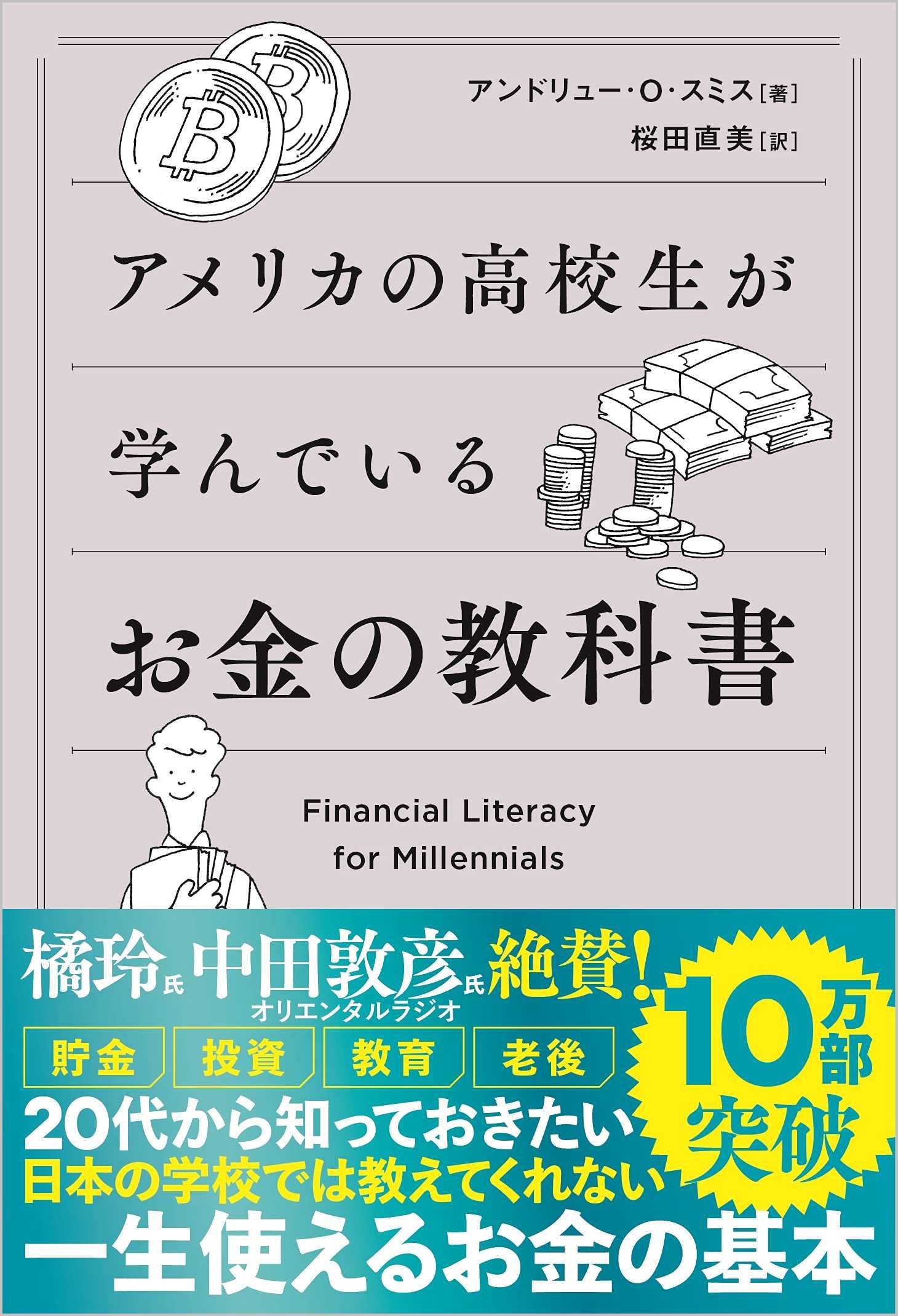

経済学の本をもう一度読み直さなければ、と集中的に読んだ何冊かの本。本書はそのうちの一冊だ。
新刊本でまとめて購入した。
前から書いている通り、私には経済的なセンスがあまりない。これは経営者としてかなりハンディキャップになっている。
私だけでなく妻も同じ。お金持ちになるチャンスは何度もあったが、そのために浪費に走ってしまった。だからこそ長年私も常駐作業から抜け出せなかった。その影響は今もなお尾を引いている。
私は若い考えのまま、お金に使われない人生を目指そうとした。金儲けに走ることを罪悪のようにも考えていた時期もある。
二十代前半は、金儲けに走ることを罪悪のように考えていた。
妻は妻で、生まれが裕福だった。そのために、浪費の癖が抜けるのに時間がかかった。
幸いなことに夫婦ともまとまったお金を稼ぐだけの能力があった。そのため、家計は破綻せずに済んだ。だが、実際に破綻しかけた危機を何度も経験した。
私たち夫婦のようなケースはあまりないだろう。だが、私たちに限らず、わが国の終身雇用を前提とした働き方は、お金について考える必要を人々に与えなかった。
一つの企業で新卒から定年まで勤めあげるキャリアの中で、組織が求める仕事をこなしていけばよかった。お金や老後のことも含めた金の知識は蓄える必要がなかった。それらは企業や国が年金や保険といった社会保障で用意していたからだ。
私もその社会の中で育ってきた。そのため、金についての教育は受けてこなかった。風潮の申し子だったといってもよい。
だが、私はそうした生き方から脱落し、自分なりの生き方を追求することにした。ところが、お金の知識もなしに独立したツケが回り、会社を立ち上げ法人化した後に苦労している。もっと早く本書のような知識に触れておけば。
世間はようやく終身雇用の限界を知り、それに紐付いた考えも少しずつ改まりつつある。
私も自分の経験を子どもやメンバーに教えてやらねばならない。また、そうした年齢に達している。
本書は、アメリカの高校生が学ぶお金についての本だ。
アメリカは今もまだ世界でトップクラスの裕福な国だ。経済観念も発達している。貧富の差が激しいとはいえ、トップクラスのビジネスマンともなると、わが国とは比べ物にならないほどの金を稼ぐことが可能だ。
それには、社会の仕組みを知り尽くすことだ。金が社会を巡り、人々の生活を成り立たせる。
人が日々の糧を得て、衣服に身を包み、家に住まう。結婚して子を育て、老後に安閑とした日々を送る。
そのために人類は貨幣を介して価値を交換させる体系を育ててきた。会社や税金を発明し、労働と経済を生活の豊かさに転換させる制度を育ててきた。
金の動きを理解すること。どのようなルートで金が流れるのか。どのような法則で流れの速度が変わり、どの部分に滞るのか。それを理解すれば、自らを金の動きの流れに沿って動かさせる。そして、自らの財布や口座に金を集めることができる。
その制度は人が作ったものだ。人智を超えた仕組みではない。根本の原理を理解することは難しい。だが、人間が作った仕組みの概要は理解できるはずだ。
本書で学べることとはそれだ。
第1章 お金の計画の基本
第2章 お金とキャリア設計の基本
第3章 就職、転職、起業の基本
第4章 貯金と銀行の基本
第5章 予算と支出の基本
第6章 信用と借金の基本
第7章 破産の基本
第8章 投資の基本
第9章 金融詐欺の基本
第10章 保険の基本
第11章 税金の基本
第12章 社会福祉の基本
第13章 法律と契約の基本
第14章 老後資産の基本
各章はラインマーカーで重要な点が強調されている。
それらを読み込んでいくだけでも理解できる。さらに、末尾には付録として絶対に覚えておきたいお金のヒントと、人生における三つのイベント(最初の仕事、大学生活、新社会人)にあたって把握すべきヒントが載っている。
それらを読むだけでも本書は読んだ甲斐がある。私も若い時期に本書を読んでおけばよかったと思う。
376-378ページに載っている「絶対に覚えておきたいお金のヒント10」だけは全文を載せておく。
絶対に覚えておきたいお金のヒント10
この本ではお金についていろいろなことを学んだが、いちばん大切なのは次の10項目だ。
1、シンプルに
お金の管理はシンプルがいちばんだ。複雑にすると管理するのが面倒になり、自分でも理解できなくなってしまう。
2、質素に暮らす
お金は無限にあるわけではなく、そして将来何が起こるかは誰にもわからない。つねに倹約を心がけていれば、いざというときもあわてることはない。
3、借金をしない
個人にとっても家計にとっても、代表的なお金の問題は借金だ。借金は大きな心の負担になり、人生が破壊されてしまうこともある。ときには借金で助かることもあるが、必要最小限に抑えること。
4、ひたすら貯金
いくら稼いでいるかに関係なく、稼いだ額よりも少なく使うのが鉄則だ。早いうちから貯金を始めれば、後になって複利効果の恩恵を存分に受けることができる。
5、うまい話は疑う
儲け話を持ちかけられたけれど、中身がよく理解できない場合は、その場で断って絶対にふり返らない。うまい話には必ず裏がある。
6、投資の多様化
多様な資産に分散投資をしていれば、何かで損失が出ても他のもので埋め合わせができる。これがローリスクで確実なリターンが期待できる投資法だ。
7、すべてのものには税金がかかる
お金が入ってくるときも税金がかかり、お金を使うときも税金がかかる。商売や投資の儲けを計算するときは、税金を引いた額で考えること。
8、長期で考える
今の若い人たちは、おそらくかなり長生きすることになるだろう。人生100年時代に備え、長い目で見たお金の計画を立てなければならない。
9、自分を知る
お金との付き合い方には、個人の性格や生き方が表れる。将来の夢や、自分のリスク許容度を知り、それに合わせてお金の計画を立てよう。万人に適した方法は存在しない。
10、お金のことを真剣に考える
お金は大切だ。お金の基本をきちんと学び、大きなお金の決断をするときは入念に下調べをすること。お金に詳しい人から話を聞くことも役に立つ。
‘2020/05/01-2020/05/11