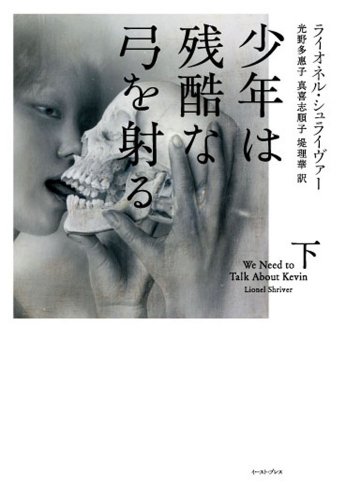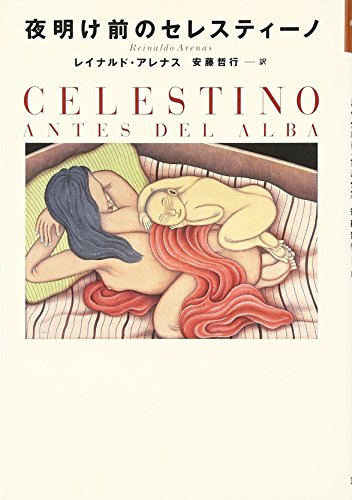
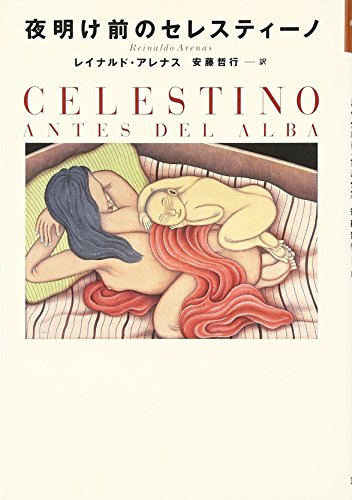
著者もまた、寺尾氏による『魔術的リアリズム』で取り上げられていた作家だ。私はこの本で著者を初めて知った。寺尾氏はいわゆるラテンアメリカにの文学に花開いた\”魔術的リアリズム\”の全盛期に優れた作品を発表した作家、アレホ・カルペンティエール、ガブリエラ・ガルシア=マルケス、ファン・ルルフォ、ホセ・ドノソについては筆をかなり費やしている。だが、それ以降の作家については総じて辛口の評価を与えている。ところが著者については逆に好意的な評価を与えている。私は『魔術的リアリズム』で著者に興味を持った。
著者は共産主義下のキューバで同性愛者として迫害されながら、その生き方を曲げなかった人物だ。アメリカに亡命し、その地でエイズに罹り、最後は自殺で人生に幕を下ろしたエピソードも壮絶で、著者を伝説の人物にしている。安穏とした暮らしができず、書いて自らを表現することだけが生きる支えとなっていた著者は、作家として生まれ表現するために生きた真の作家だと思う。
本書は著者のデビュー作だ。ところがデビュー作でありながら、本書から受ける印象は底の見えない痛々しさだ。本書の全体を覆う痛々しさは並みのレベルではない。初めから最後まであらゆる希望が塗りつぶされている。私はあまりの痛々しさにヤケドしそうになり、読み終えるまでにかなりの時間を掛けてしまった。
本書は奇抜な表現や記述が目立つ。とくに目立つのが反復記法とでも呼べば良いか、いささか過剰にも思える反復的な記述だ。これが随所に登場する。これらの表記からは、著者が抱えていた闇の深さが感じられる。それと、同時にこう言った冒険的な記述に踏み切った著者の若さと、これを残らず再録し、修正させなかった当時の編集者の勇断にも注目したい。私は本書ほど奇抜で無駄に続く反復表現を読んだことがない。
若く、そして無限に深い闇を抱えた主人公。著者の半身であるかのように、主人公は虐げられている。母に殺され、祖父に殺され、祖母に殺され。主人公は本書において数限りなく死ぬ。主人公だけではない。母も殺され、祖父も殺され、祖母も殺される。殺され続ける祖母からも祖父からも罵詈雑言を投げつけられ、母からも罵倒される主人公。全てにおいて人が人として認められず、何もかもが虚無に漂い、無に吸い込まれるような救いのない日常。
著者のような過酷な人生を送っていると、心は自らを守ろうと防御機構を発動させる。そのあり方は人によってさまざまな形をとる。著者のように自ら世界を創造し、それを文学の表現として昇華できる能力があればまだいい。それができない人は自らの心を分裂させてしまう。例えば統合失調症のように。本書でも著者の母は分裂した存在として描かれる。主人公から見た母は二人いる。優しい母と鬼のごとき母。それが同一人格か別人格なのかは文章からは判然としない。ただ、明らかに同一人物であることは確かだ。同一人物でありながら、主人公の目に映る母は対象がぶれている。分裂して統合に失敗した母として。ここにも著者が抱えていた深刻な状況の一端が垣間見える。
主人公から見えるぶれた母。ぶれているのは母だけではない。世界のあり方や常識さえもぶれているのが本書だ。捉えどころなく不確かな世界。そして不条理に虐待を受けることが当たり前の日々。その虐待すらあまりにも当たり前の出来事として描かれている。そして虐待でありながら、無残さと惨めさが一掃されている。もはや日常に欠かせないイベントであるかのように誰かが誰かを殺し、誰かが誰かに殺される。倒錯し、混迷する世界。
過剰な反復表現と合わせて本書に流れているのは本書の非現実性だ。\”魔術的リアリズム\”がいう魔術とは一線を画した世界観。それは全てが非現実。カートゥーンの世界と言ってもよいぐらいの。不死身の主人公。決して死なない登場人物たち。トムとジェリーにおける猫のトムのように、ぺちゃんこになってもガラスのように粉々になっても、腹に穴が開いても死なない登場人物たち。それは\”魔術的リアリズム\”の掲げる現実とはかけ離れている。だからといって本書は子供にも楽しめるスラップスティックでは断じてない。なぜなら本書の根底に流れているのは、世界から距離をおかなければならないほどの絶望だからだ。
むしろ、これほどまでに戯画化され、現実から遊離した世界であれば、なおさら著者にとってのリアルさが増すのではないだろうか。だからこそ、著者にとっては本書の背景となる非現実の世界は現実そのものとして書かれなければならなかったのだと思う。そう思わせてしまうほど本書に書かれた世界感は痛ましい。それが冒頭にも書いた痛々しさの理由でもある。だがその痛々しさはもはや神の域まで達しているように思える。徹底的に痛めつけられ、現実から身を守ろうとした著者は、神の域まで自らを高めることで、現実を戯画化することに成功したのだ。
あとは、著者が持って生まれた同性愛の性向にどう折り合いをつけるかだ。タイトルにもあるセレスティーノ。彼は当初、主人公にとって心を許す友人として登場する。だが、徐々にセレスティーノを見つめる主人公の視点に恋心や性欲が混じりだす。それは社会主義国にあって決して許されない性向だ。その性向が行き場を求めて、セレスティーノとして姿を現している。現実は無慈悲で不条理。その現実を乗り切るための愛や恋すら不自由でままならない。セレスティーノに向ける主人公の思慕は、決して実らない。そしてキューバにあっては決して実ってはならない。だから本書が進むにつれ、セレスティーノはどんどん存在感を希薄にしてゆく。殺し殺される登場人物たちに混じって、幽霊のように消えたり現れたりするセレスティーノ。そこに主人公の、そして著者の絶望を感じる。
繰り返すが、私は本書ほどに痛々しい小説に出会ったことがない。だからこそ本書は読むべきだし、読まれなければならないと感じる。
‘2017/08/18-2017/08/24