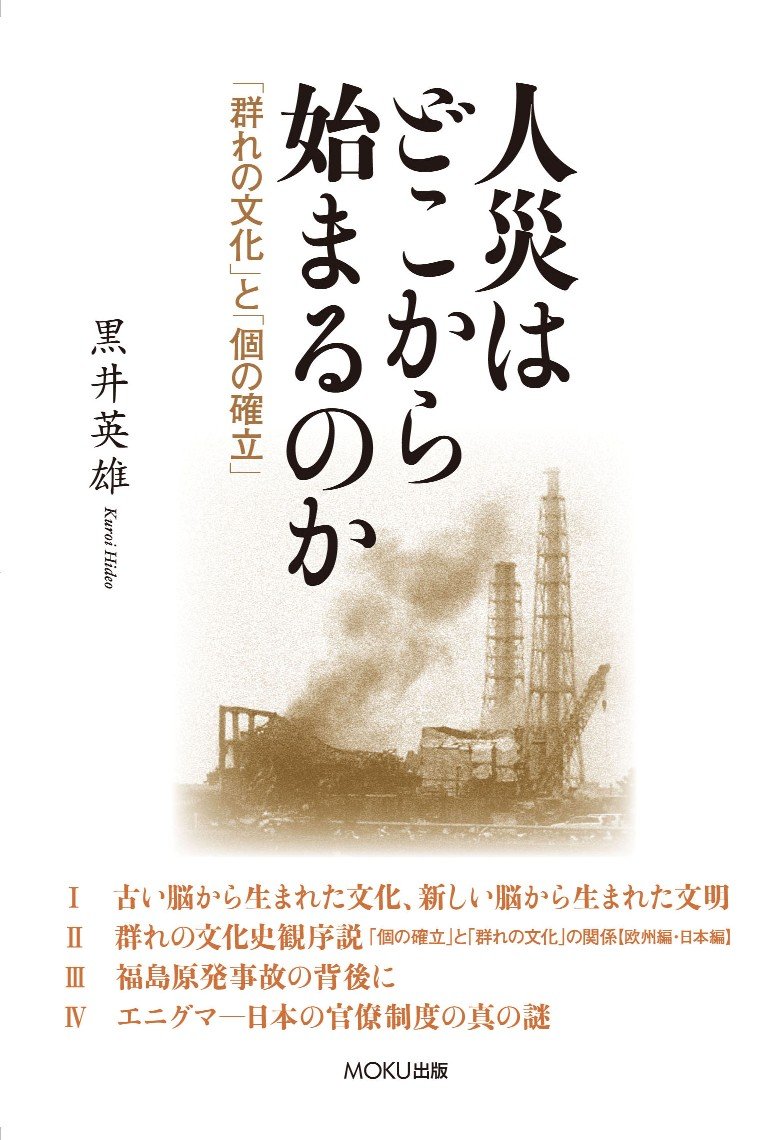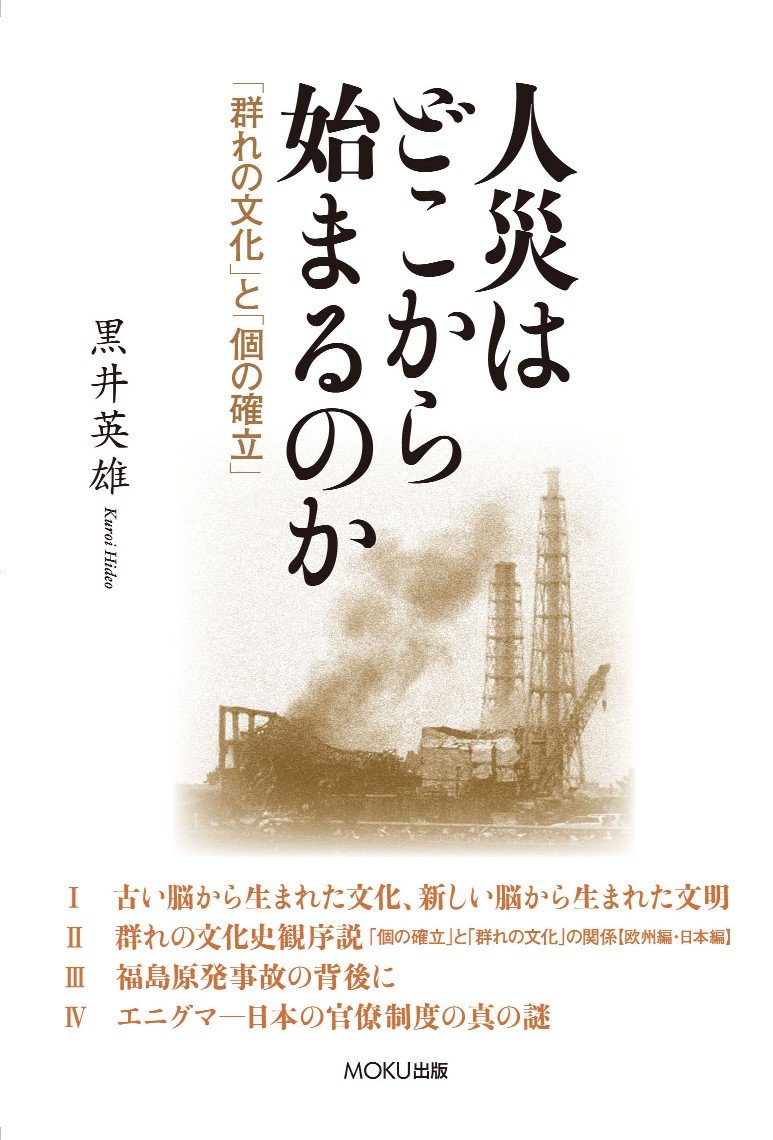「魔術的リアリズム」。当読読ブログでも何度かこの言葉を取り上げている。
「魔術的リアリズム」とは、ラテンアメリカの作家たちによって知られる文学潮流の一つである。現実をベースにした描写に超現実的なエピソードを織り込むことで物語に深みを持たせる。本書を読むまで私が「魔術的リアリズム」について理解していた定義はこんな感じだ。
それが独学の理解に過ぎないことは自分でも分かっていた。一度はこの言葉と正面から向かい合わねば。そう思っていたところに本書を見かけ、手に取った。
著者が「はじめに」で述べているとおり、「魔術的リアリズム」という語句の定義はしっかりと定められている訳ではない。そもそも読む人によって多様な受け取り方をされる事に文学の価値があるはず。とすれば、文学に何かを定義すること自体がナンセンスではないだろうか。
そんな事は著者にとっても先刻承知のはず。それを分かっていて敢えて「魔術的リアリズム」というものの本質を掴もうと切り込む。大学教授としてラテンアメリカ文学を教える著者にとって、避けては通れない課題。その成果が本書だ。
第一章 シュルレアリスムから魔術的リアリズムへ
とっかかりはシュルレアリズムだ。ダダイズムの系譜から連なるシュルレアリズム。意味をなさず繋がりのない言葉が続くあれだ。「魔術的リアリズム」の源にシュルレアリズムを置く著者の意図はすんなりと理解できる。源と書いたが、それはシュルレアリズムが「魔術的リアリズム」に先んじて現実からの開放を目指した事を指すのではない。実は「魔術的リアリズム」という単語が初めて世に出たのは、シュルレアリズムが最も華やかなりし時期。ドイツの美術評論家フランツ・ローが最初にこの言葉を使ったのが1925年。表現主義の絵画に対する批評の言葉として使われたという。シュルレアリズムを語る際はアンドレ・ブルトンの「シュルレアリズム宣言」は外せないが、出版されたのは1926年。つまり「魔術的リアリズム」の言葉はシュルレアリズムの聖典よりも早く世に出たことになる。そのため、一見すると「魔術的リアリズム」の源をシュルレアリズムに置くのは矛盾に思える。さらに著者によれば、フランツ・ローのいう「魔術的リアリズム」と本書で論じようとするラテンアメリカ諸作家による「魔術的リアリズム」に直接の関係はないそうだ。だが「魔術的リアリズム」の言葉がシュルレアリズムの潮流の中で生まれたことも確か。その系譜に沿うならば、シュルレアリズムが蒔いた芸術の新たなうねりは、確実にラテンアメリカ文学の将来に影響を及ぼすことになる。
そのうねりは、まずラテンアメリカからパリに遊学に来ていた三人の作家に影響を与えた。その三人とはグアテマラのミゲル・アンヘル・アストゥリアス、キューバのアレホ・カルペンティエール、ベネズエラのアルトゥーロ・ウスラル・ピエトリ。著者はこの三人の文学を比較し、その代表作とされる作品を分析する。この三人の代表作のうち、著者が最も高い評価を与えたのはアストゥリアスの「グアテマラ伝説集」。たしか岩波文庫にも収められていたはずだ。では残り二人についてはどうか。ところが著者の評価は冴えない。わたしはピエトリの名を本書で始めて知った。一方カルペンティエールは私の好きな作家の一人だ。さらに言えばここで著者が俎上に上げている「エクエ・ヤンバ・オウ」はかつて私も読んだ。確か関西大学出版部が出していたように思う。わたしの出身校ながら出版物を見かけた事が珍しかったので印象に残っている。だが肝心の内容については作者と同じくピン、と来なかった。著者も「エクエ・ヤンバ・オウ」をカルペンティエールの未熟な時期の作品と一蹴している。
こうなると著者が推す「グアテマラ伝説集」は是非とも読んでみなければなるまい。本書で知った「グアテマラ伝説集」の素晴らしさと先駆性は、わたしを新たな読書欲に駆り立てた。こうやってまだ見ぬ書を知る喜びといったら! 知ることはとても楽しい。学べる幸せは何事にも替え難い。
第二章 魔術的リアリズムの原型
第二章で著者は、ヨーロッパに芽生えた「魔術的リアリズム」がラテンアメリカで花開いたのがなぜか、という問いに答えを出す。それは「豊かな多様性に特徴づけられた統一体としてのラテンアメリカ、そのコスモポリタン性に求められるべき」(47P)であるという。
とはいえ、ラテンアメリカで「魔術的リアリズム」がすぐに花開いた訳ではない。そもそもシュルレアリズムからしてヨーロッパ本国では退潮に向かっていた。ファシズムの台頭とともに。ヨーロッパを引き揚げラテンアメリカに帰った三人の作家も、世界的な戦時色の中これといった作品を残せずにいた。第二次世界大戦とは世界中に戦争の惨禍をもたらしただけでなく、芸術的にも多大なダメージを与えたのだ。
しかし、大戦も終わり、発表の場が閉ざされていた作家たちは戦時中にため込んだ鬱屈を吐き出すように旺盛な創作に励み出す。その一人が第一章にも登場したカルペンティエールである。第二章で著者は主にカルペンティエール「この世の王国」を取り上げる。私もかつて読んだ際に強い印象を受けた。大戦中にカルペンティエールが訪れたハイチ。この地の豊かさに衝撃を受けたカルペンティエールは、重要な知見を手にする。それは「驚異の知覚は信奉を前提とする」事。この一文を著者は特筆する。これは「この世の王国」の序文に記されていたという。なお、だいぶ前に「この世の王国」読んだはずの私は当然のことながらこの一文を忘れていた。ここらへんが大学で文学を教える著者と素人の私の差なのだろう。
カルペンティエールはシュルレアリスムを「驚異的なものの存在を信じぬままに小手先だけで驚異を生み出そうとしていた」(54P)と批判する。その上で、「驚異の知覚と伝達には驚異自体を信じること、さらには基底となる世界観を共有することが不可欠だと論じている」(54P)と説く。カルペンティエールのこの見解は、批評家から批判されたらしい。それでもなお、著者が「この世の王国」をラテンアメリカ文学の重要なマイルストーンとしてあげたのは理由がある。それは著者によると、黒人の奴隷たちによって打ち立てられたハイチの王国を描写するにあたり、西洋人による西洋文化の視点からではなく黒人の奴隷からみた世界を描いているからだ。シュルレアリスムが所詮は西洋文化人の慰み物でしかなかったとすれば、第一章で触れた三人の作家が発表した作品も、西洋文化の視点から描かれたラテンアメリカに過ぎなかったという事だ。著者が指摘するのはこの点だ。「グアテマラ伝説集」の語りの主体は、マヤ・インディオだった。それは著者が「グアテマラ伝説集」を評価する理由の一つ。そして「この世の王国」もまたラテンアメリカからの語りで構成されている。「魔術的リアリズム」がラテンアメリカで発展するにはラテンアメリカ自身からの視点が欠かせない。その事は、著者にとって重要な点と位置付けられているようだ。その道標の一つとして「この世の王国」を外すわけにはいかなかったのだろう。
一方、返す刀で著者は「この世の王国」の限界も指摘している。限界とは、西洋的視点を交えずにラテンアメリカの物語を語ること。カルペンティエールは土着視点からの描写を目指しているが、作品の随所に西洋的比喩が出てくることだ。作中に西洋的比喩が現われる度、読者の知覚からはカルペンティエールの意図したラテンアメリカへの驚異が薄れてゆく。「驚異の知覚は信奉を前提とする」事を説いたはずのカルペンティエールが信奉を前提にできていない事実。ラテンアメリカの驚異を読者に披露する事を企図したはずのカルペンティエール自身が、驚異とは西洋から見た驚異に過ぎない根本の矛盾に気付かなかった時点で、その試みは頓挫するしかなかったのだ。著者の論理の進め方は実に鮮やかだ。
では、ラテンアメリカを語るには、土着の視点での語りを純粋に推し進めればよいのか。そうではないことを、著者はアストゥリアスの「とうもろこしの人間たち」を例に挙げて説く。アストゥリアスは第一章でカッコグアテマラ伝説集」の作者として登場した。「とうもろこしの人間たち」は、マヤ世界観へ極限まで寄り添った作品として描かれた。だがその結果、誰にも理解できない作品になってしまっているという。私はまだ読めていないが。つまりラテンアメリカの「魔術的リアリズム」も、西洋の教養人に読まれて初めて価値が見出される。土着民は小説などそもそも読まないのだから。でも土着民に寄り添いすぎると誰にも理解できなくなる。しかしながらラテンアメリカを西洋の視点から語ると破綻する。その地の文化に完全に密着した小説など、前提から無理だということ。それを悟ったカルペンティエールは「この世の王国」を最後に「魔術的リアリズム」から離れてしまう。
著者は袋小路に至ってしまった理由を、西洋とラテンアメリカを二極で捉えてしまったことに帰する。つまり西洋=先進、ラテンアメリカ=後進という二元化の考えだ。無意識のうちに西洋とラテンアメリカを単純に二分化してしまったことがカルペンティエールの失敗だと著者はいう。
第三章 魔術的リアリズムの隆盛
第三章では、二極化に替わる新たな軸を打ちだした作家の活躍が描かれる。彼らによって「魔術的リアリズム」はいよいよ世界的な隆盛を迎える。ここで紹介されるのは二極化の罠に落ち込まず、次なるレベルへと到達した作品だ。
第三章で取り上げられる作品は「転轍手」「ペドロ・パラモ」そして「百年の孤独」。まず著者は「転轍手」の分析において、前章までの諸作品に見られた西洋とラテンアメリカという対立軸が、正常と狂気という対立軸に置き換わったことを指摘する。つまりカルペンティエールをはじめとした旧来の作品がラテンアメリカを描こうとして失敗した原因が西洋とラテンアメリカの二極化にあったならば、これらの作品は正常から見た狂気を描く事で、ラテンアメリカ小説を対西洋という枠組みからは解き放ち、普遍的な文学として昇華させたのだ。
また「ペドロ・パラモ」では、小説の筋書きを推進する構造にも着目する。その構造とは円環構造にある。それは登場人物達のささやき。そのささやきがさらに次なる事態を引き起こし、作中の人物たちを廻り廻ることになる。著者は、円環構造の真の意義は作品の基調となる非日常的視点を内部に自己生産するところにある(92P)と喝破する。
「百年の孤独」では西洋とラテンアメリカに替わる新たな対立軸を作品内に打ちだすだけでなく、新たな構造も備えている。著者は「百年の孤独」をさらに精緻に分析し、その構造を明らかにする。「百年の孤独」は架空の街マコンドを舞台とした小説だ。多彩な登場人物。創始者、来訪者、町の後継者たちの言動が物語を動かしている。つまりは、語り手が単一ではないのだ。「百年の孤独」を一つの頂点として「魔術的リアリズム」は完成を見る。ではなぜ「百年の孤独」がここまで持てはやされたのだろうか。著者は超自然的出来事が「魔術的リアリズム」の要素の一つであることは承知の上で、ドイツの作家ギュンター・グラスの「ブリキの太鼓」と「百年の孤独」を対比する。「ブリキの太鼓」も超自然的な出来事が頻出する傑作だが、主人公が一人というところに物語展開の限界がある。ところが「百年の孤独」はマコンドに縁のある大勢の関係者が起こす、または関係者に起こる事象を描いている。そのため、多様な視点から魔術的リアリズムが描けるのだ。著者はそれこそが「百年の孤独」の価値である事を説く。そして、その語り手が物語の枠外にいるのではなく、縁ある者を含んだマコンドの世界、それ自体から発信されていることが重要だ強調する。
「百年の孤独」における語りの重要性については私も理解できる。その語りは奇想天外であるばかりか、現実のコロンビアともかけ離れていない。そこに単なるファンタジーではない「魔術的リアリズム」としての「百年の孤独」があると著者はいう。私が今までに読んだ小説のうち、再読したものはあまり多くないが、「百年の孤独」はその一冊だ。なので著者が言及することも理解できる。
本書で著者は、「魔術的リアリズム」の定義を何度か試みる。第三章の締めに置かれる以下の文もその一つだ。
フィクション化によって日常的現実世界を通常と異なる形で提示して「異化」し、同時に、現実世界に起こる、フィクションと見まがうばかりの異常な事件を「平板化」して受容可能にする、一見矛盾するように見える二つのプロセスを同時に達成した時点で、アストゥリアス、カルペンティエール、ルルフォと継承されてきた「魔術的リアリズム」は完成した。「魔術的」=「驚異的」であることと、「リアリズム」=「日常性」が見事に融合した結果こそ、『百年の孤独』にほかならないのだ。(117P)
第四章 魔術的リアリズムの新展開
1967年は、ラテンアメリカ文学にとって一つの頂点となった年だ。「百年の孤独」が世界的ベストセラーとなり、アストゥリアスがノーベル文学賞受賞がした年。第四章で著者は1967年を起点とした「魔術的リアリズム」をあらためて捉え直す。
本書はここまでラテンアメリカ文学の歩みを紹介して来た。だが、第三章までに登場する作家たちに、アルゼンチンのボルヘス、ビオイ・カサーレス、コルタサルといった名前が出て来ない。彼らもまたラテンアメリカ文学を語る上で欠かせない作家のはず。中でもコルタサルは私の認識では「魔術的リアリズム」に属する作家だ。だが著者はこれらの作家を「ラプラタ幻想文学」の範疇に括る。ラプラタとはアルゼンチンを流れるラプラタ川の事に違いない。「ラプラタ幻想文学」とは、アルゼンチンに縁のある作家たちをまとめるための言葉だと理解した。ではなぜ作者は彼らを「魔術的リアリズム」の本流に置かないのだろうか。著者によると「ラプラタ幻想文学」に連なる作家たちの作風は「魔術的リアリズム」とは一線を画するという。その根拠を著者は、現実世界との関わり方に置く。
フィクションの構築によって現実世界への新たな視点を求めた魔術的リアリズムの作家と違って、彼らはフィクションによって現実世界そのものの存在意義を消滅させようとしていた(133P)。
というのが著者が示す理由だ。つまり、語り手の立ち位置がフィクションの外側と内側どちらにあるかの違いと受け取れば良いだろうか。「魔術的リアリズム」の諸作品は、内側世界の共同体の住人として物語を語る。ちょうど「百年の孤独」のマコンドの住人のように。一方「ラプラタ幻想文学」の語り手は読者の側の現実世界から作品を語るといえばよいだろうか。私も好きな短編にコルタサルの「南部高速道路」がある。著者もこの一編を「魔術的リアリズム」に近いと評価する。それでもコルタサルは現実世界に軸足を置き、その視点から異常な世界を書いている。その点が著者の考える「魔術的リアリズム」とは少し違うという事だろうか。
第五章 闘う魔術的リアリズム
著者が「魔術的リアリズム」の正当な後継者として認めるのは「夜のみだらな鳥」だ。私も「夜のみだらな鳥」は読んだ。そしてとても衝撃を受けた。「夜のみだらな鳥」の異常な語り手の本質は、外部からの冷静な語りを一切受け付けないところにある。狂気の世界の内部からの語りにしか、「夜のみだらな鳥」の世界観は作りだせない。
著者は相当数のページを「夜のみだらな鳥」に割いている。「百年の孤独」と同等かそれ以上かもしれない。それだけ衝撃的であり、評論家にとっても挑み甲斐のある対象なのだろう。私自身、「夜のみだらな鳥」を紹介しろといわれても、上に挙げたような文しか書けない。しかし「夜のみだらな鳥」がラテンアメリカの文学において最高峰に位置する作品だということは分かる。私が読んだラテンアメリカの小説などほんの一部にしか過ぎないが、「夜のみだらな鳥」が醸し出す異様な世界観は、世界の文学史においても指折りのはずだと思う。
「夜のみだらな鳥」には多くのページを割いた著者だが、「魔術的リアリズム」を語るにはまだ足りないらしい。著者は、独裁者のモチーフもラテンアメリカ文学の特徴に挙げる。われわれ日本人はラテンアメリカを政治的な紛争が絶えない地域とイメージする。そして名だたる独裁者を輩出した地域としても。ラテンアメリカ文学には独裁者を扱った小説が多々ある。著者はラテンアメリカ文学の三大独裁者小説として「族長の秋」「至高の我」「方法再説」を挙げる。後者二冊は私はまだ読んでいない。が、この他にもバルガス・リョサによる「チーボの狂宴」も読んでおり、独裁者がラテンアメリカ文学に頻出するイメージである事は私にも納得できる。
本章で著者は、独裁者小説についても詳しく分析し、その定義を以下のように示す。
独裁者小説とは何かということにおいて、「魔術的リアリズム」の手法を使いながらも、独裁制を人間的現象として理解する意図が前面に打ち出されている。(177P)
独裁者小説がラテンアメリカ文学の潮流として興った理由を語る上でラテンアメリカ諸国を襲った軍事政権の登場は欠かせない。軍事政権が各国で政権を獲った事は、諸作家の執筆環境にも大きな影響を与えた。文学者は否応なしに政治に密着することになった。
「百年の孤独」の成功の影にはメキシコ政府による文学者を優遇する政策があった。そのことは、メキシコ文化センターという施設が果たした役割として第三章の冒頭で紹介されている。国によって成熟したラテンアメリカ文学は、国による縛りが強まると牙をむく。ラテンアメリカ文学の隆盛によって地位を高めた作家達の反抗は、これらの独裁者小説といって現れたのだろう。特にラテンアメリカの独裁国家といえばキューバは外せない。キューバの作家レイナルド・アレナスについての言及が本章には登場する。アレナスは、ホモセクシュアルとして迫害されたという。そんなアレナスが書く独裁者は、かなり異形だという。この事もラテンアメリカ文学と地域の繋がりを示す点として見逃せない。私はまだアレナスは未読なので、一度読んでみなければと思っている。
第六章 文学の商業化と魔術的リアリズムの大衆化
最終章で著者は「魔術的リアリズム」が商業ベースに乗ってしまった現状に切り込む。もちろん批判的な筆致で。そもそも著者が第二章で指摘したように「魔術的リアリズム」の諸作品は、一部の文学的素養のあるインテリにのみ読まれていた。こういった読者に熱狂的に支持されたが、同じ人々がブームの沈静化に一役買った点も見逃せない。そこで出版社は一般的な読者に対して「魔術的リアリズム」の手法を流用した作品を出版したのだろう。ここに登場する諸作家は私も何冊か読んでいる。その中でもイザベル・アジェンデの「精霊たちの家」は本章でも大きく取り上げられている。著者は「百年の孤独」と「精霊たちの家」を対比し、ラテンアメリカ文学ブーム後の作品の特徴を見極めようとする。著者が違いに挙げるのは、例えば「精霊たちの家」が運命に結実する物語であり、すでに完結してしまった世界であることや、勝ち組の価値観が全編に横溢したステレオタイプな語りの多いこと、である。
それら80年代以降に生まれた「魔術的リアリズム」作品には、一部読者にしか訴えない作品ではなく、コマーシャリズムに乗っていると著者はいう。そして、その事によって一般の読者を獲得した。著者はこれら作家の本質はエンターテインメント性にあり、そちらの土俵で評価されるべきという。
結びで著者は本書で示してきた概観を繰り返す。そして「非日常的視点を基盤に一つの共同体を作り上げ、そこから現実世界を新たな目で捉え直す」(220P)と「魔術的リアリズム」の定義を総括する。残念ながら、本書には他国への「魔術的リアリズム」の影響や、「魔術的リアリズム」の今後の進み方については触れた箇所はない。そこまで筆を進めるところまでは行かなかったようだ。
でも、本書によって今までのラテンアメリカ文学、中でも「魔術的リアリズム」の歩みや特徴が明らかにされた事には変わりがない。また、本書によって私が読んでいないラテンアメリカ文学をたくさん知った。そして「魔術的リアリズム」とは何ぞや、という私がそもそも本書を読むに至った動機も満たせた。本書で著者が語る分析や切り込み方はとても参考になった。よくよく考えてみると、当ブログを書き始めてから、文学論を読むのは初めてのような気がする。今まで文学論など学んだ事のない私。そんな私が全くの独学で書いてい当ブログだが、本書によって新たな視点を身につけられた事も大きい。
できれば本書は購入して座右の書にしたいぐらいだ。そして本書で紹介された諸作品は、既読のものも含めて再読したいと思う。
‘2016/06/04-2016/06/07