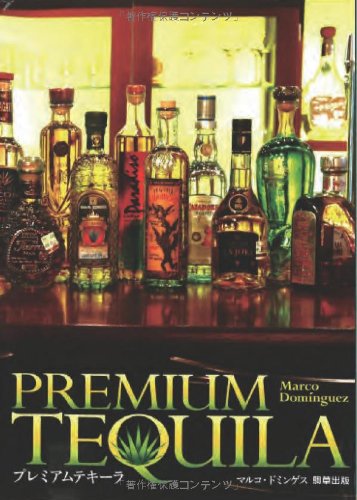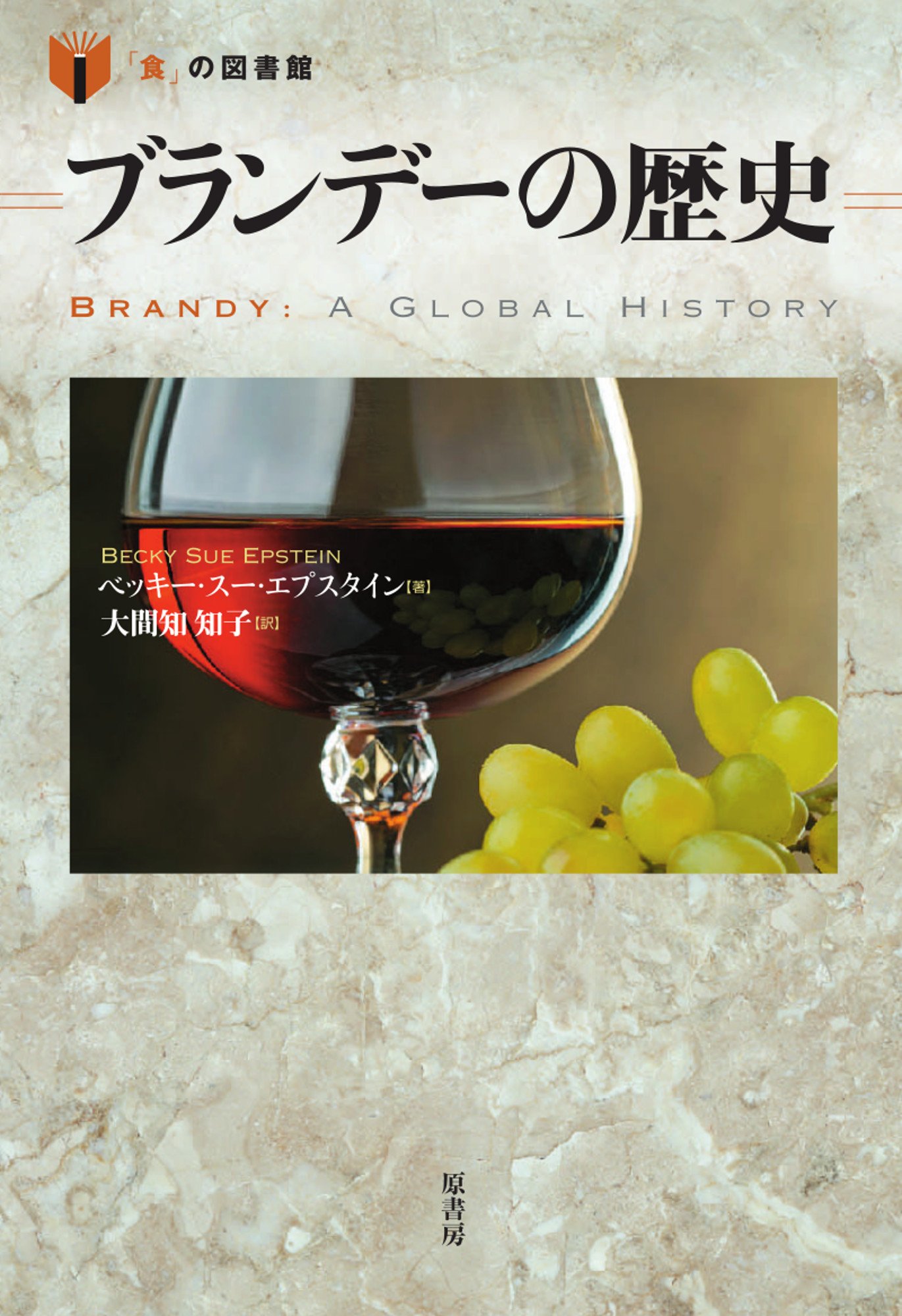
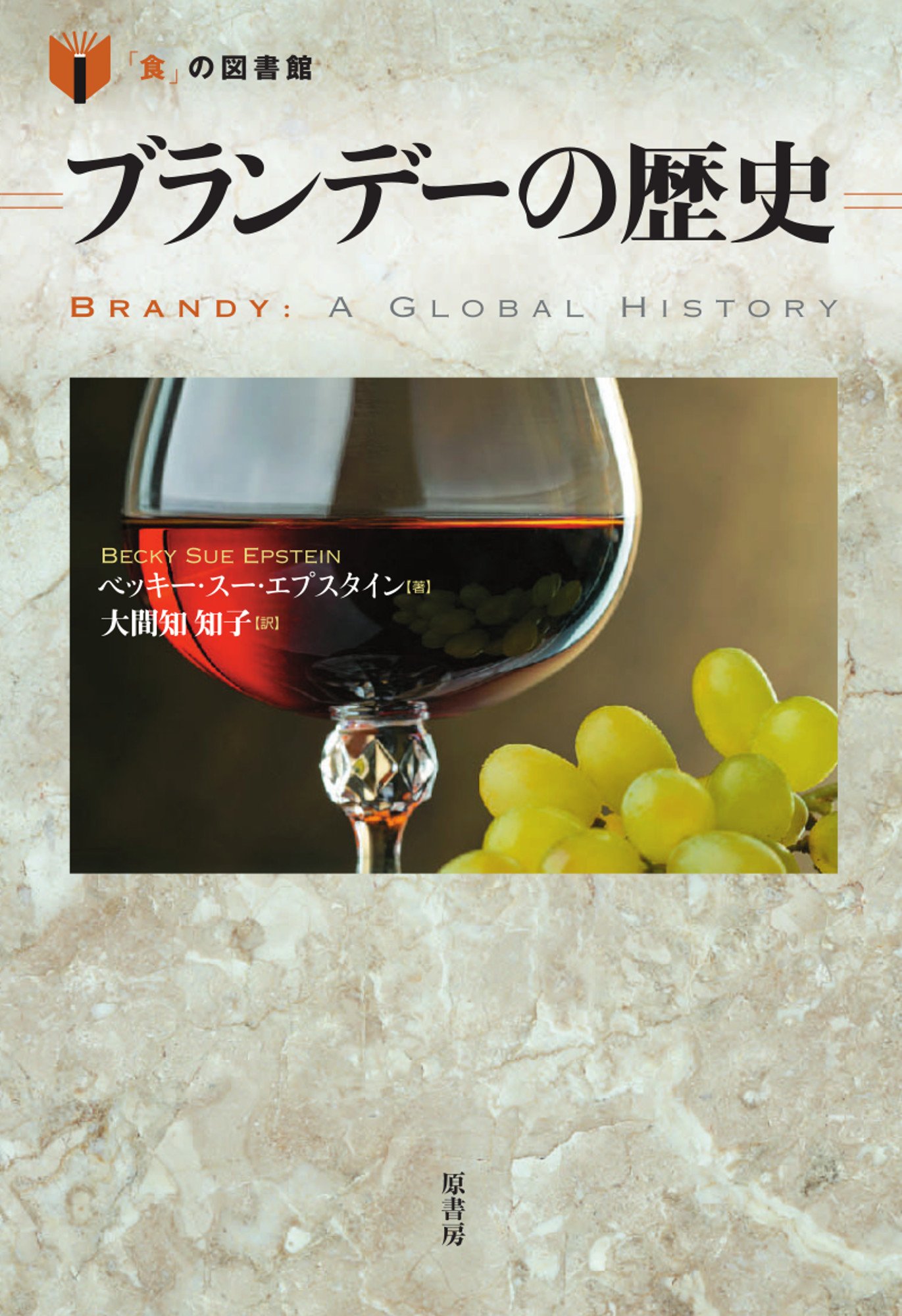
妻の祖父の残したブランデーがまだ何本も残っている。10本近くはあるだろうか。
最近の私は、それらを空けるためもあって、ナイトキャップとしてブランデーを飲むことが多い。一本が空けば次の一本と。なるべく安い方から。
こうやってブランデーを集中して飲んでみると、そのおいしさにあらためて気づかされる。おいしいものはおいしい。
まさに蒸留酒の一角を占めるにふさわしいのがブランデーだ。
同じ蒸留酒の中で、今人気を呼んでいるのはウイスキーやジンだ。
だが、ブランデーも酒の完成度においては他の蒸留酒に引けを取らないと思っている。
それなのに、ブランデーはバーでも店頭でもあまり陽の当たらない存在に甘んじているように思う。
それは、ブランデーが高いというイメージによるものだろう。
そのイメージがブランデーの普及を妨げていることは間違いない。
そもそも、ブランデーはなぜ高いのか。
ブランデーのによるものか。それなら、他の蒸留酒と比べてどうなのだろうか。原料はワインだけなのだろうか。ワインの世界でよく言う土壌や風土などによって風味や香りを変えるテロワールは、ブランデーにも当てはまるのだろうか。また、ブランデーの元となるワインに使用する酵母や醸造方法に通常のワインとの違いはあるのだろうか。蒸留に複雑なヴァリエーションはあるのだろうか。貯蔵のやり方に特色はあるのだろうか。
疑問が次から次へと湧いてくる。
そこで、一度ブランデーをきちんと勉強してみようと思い、本書を手に取った。
そうした疑問も含め、私はブランデーの知識を持ち合わせていない。そんな私にとって、本書はとても勉強になった。
そもそも、ブランデーの語源とは、焼いたワインを意味する言葉から来ている。
ブランデーの語源は、ウイスキーの歴史を学ぶと登場する。つまり、あらゆる蒸留酒の歴史は、ブランデーから始まっている可能性が濃い。
ブランデーには大きくわけて3つあるという。ワインから造るブランデー。ブドウではない他の果実から作られるもの(カルヴァドス、スリヴォヴィッツ、キルシュ)。ワインを造った時のブドウの搾りかすから造られるもの(グラッパ、マール)。
本書ではワインから造るものに限定している。
ブランデーの銘柄を表す言葉として、コニャック、アルマニャックの言葉はよく聞く。
では、その違いは一体どこにあるのだろうか。
まず、本書はコニャックから解説する。
当時のワインには保存技術に制約があり、ワインを蒸留して保存していたこと。
また、ボルドーやブルゴーニュといった銘醸地として知られる地で生産されるワインは、品質が良いためワインのままで売られていた。それに比べて、コニャック地方のワインは品質の面で劣っていたため、蒸留用に回されていたこと。
1651年の戦いの結果、ルイ14世から戦いの褒美としてワインや蒸留酒にかかる関税を免除された事。また、コニャック周辺の森に育つリムーザンオークが樽の材質として優れていたこと。
一方のアルマニャックは、コニャックよりも前からブランデーを作っていて、早くも1310年の文献に残されているという。
ところが、アルマニャック地方には運搬に適した河川が近くになく、運搬技術の面でコニャック地方におくれをとったこと。蒸留方法の違いとして、コニャックは二回蒸留だが、アルマニャックはアルマニャック式蒸留機による一回蒸留であることも特筆すべきだろう。
ブランデーの歴史を語る上で、19世紀末から20世紀初頭にかけてのフィロキセラによる害虫被害は外せない。フィロキセラによってフランス中のブドウがほぼ絶滅したという。
それによってブランデーの生産は止まり、他の蒸留酒にとっては飛躍のチャンスとなった。が、害虫はブランデーにとっては文字通り害でしかなかった。
だが、フランス以外のヨーロッパ諸国にはブランデー製造が根付いていた。
そのため、コニャックやアルマニャックの名は名乗れなくても、各地で品質の高いブランデーは作られ続けている。著者はその中でもスペインで作られているブランデー・デ・ヘレスに多くの紙数を費やしている。
また、ラテンアメリカのブランデーも見逃せない。本書を読んで一カ月後のある日、私は六本木の酒屋でペルーのピスコを購入した。ブランデーとは違う風味がとても美味しいかった。これもまた銘酒といえよう。
購入直後に五反田のフォルケさんの酒棚に寄付したけれど。
ブランデーはまた、オーストラリアや南アフリカでも生産されている。アメリカでも。
このように本書は世界のブランデー生産地を紹介してゆく。
ところが本書の記述にアジアは全くと言って良いほど登場しない。
そのかわり、本書では中国におけるアルマニャックの人気について紹介されている。日本ではスコッチ・ウイスキーがよく飲まれていることも。
本書は消費地としてのアジアについては触れているのだが、製造となるとさっぱりのようだ。
例えば山梨。ワインの国として有名である。だが、現地に訪れてもブランデーを見かけることはあまりない。酒瓶が並ぶ棚のわずかなスペースにブランデーやグラッパがおかれている程度だ。
日本で本格的なブランデーが作られないのは、ブランデーが飲まれていないだけのことだと思う。
私は本書を読み、日本でもブランデー製造や専門バーができることを願う。そのためにも私ができることは試してみたい。
本書はコニャックやアルマニャックが取り組む認証制度や、それを守り抜くためにどういう製造の品質の確保に努力するかについても触れている。
期待がもてるのは、ブランデーを使ったカクテルの流行や、最近のクラフトディスティラリーの隆盛だ。
周知の通り、アメリカではビールやバーボンなど、クラフトアルコールのブームが現在進行形で盛んな場所だ。
本書のそうした分析を読むにつけ、なぜ日本ではブランデー生産が盛んではないのだろう、という疑問はますます膨らむ。
今、日本のワインは世界でも評価を高めていると聞く。
であれば、ブランデーも今盛り上がりを見せている酒文化を盛り上げる一翼を担っても良いのではないだろうか。
大手酒メーカーも最近はジンやテキーラの販促を行っているようだ。なのにブランデーの販促はめったに見かけない。
私もブランデーのイベントがあれば顔を出すようにしたいと思う。そして勉強もしたいと思う。
まずはわが家で出番を待つブランデーたちに向き合いながら。
‘2019/9/7-2019/9/8