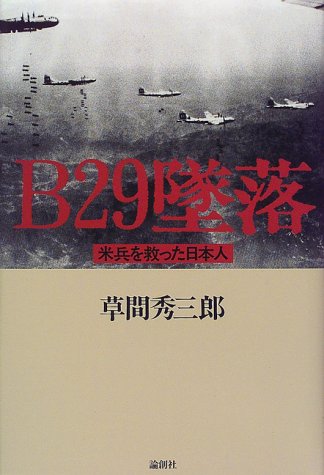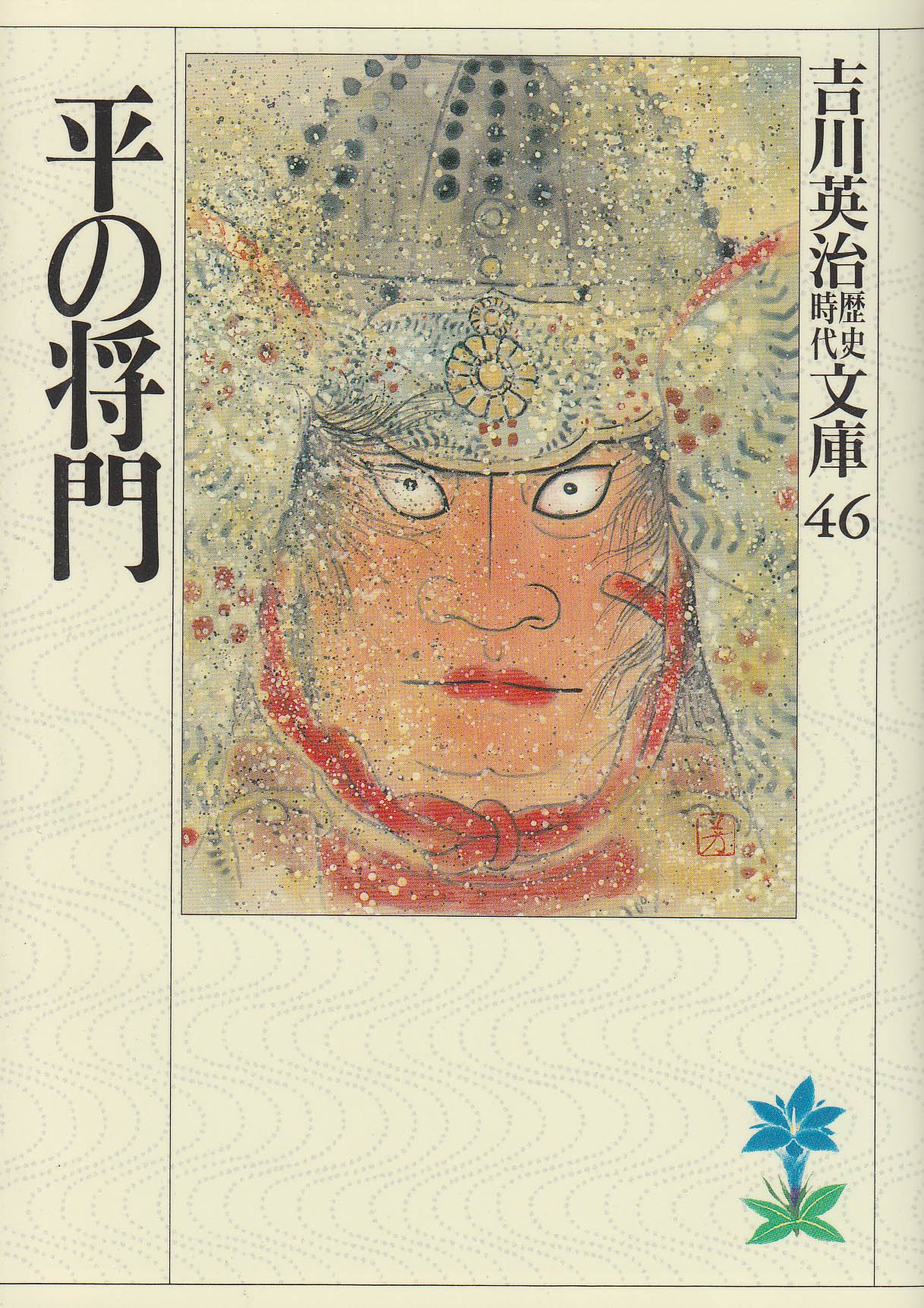

なぜ本書を読もうと思ったか。その答えは、単に時代小説が読みたくなったからにすぎない。
だが、私と平将門の間に何の縁もきっかけもなかった、といえばウソになる。平将門の首塚に数回訪れたことがあるからだ。
千代田区の丸の内にある首塚は有名だ。
乱に敗れ、京でさらされた将門の首が飛んで戻り、落ちたのがこの首塚の地、と伝えられている。
私は東京に住んで二十年になる。
そしてここ最近になって、ようやく都会や首都の東京ではなく、昔からの坂東に興味を抱くようになってきた。
実際、本書を読む少し前には鹿島神宮にも訪れ、坂東の広さや可能性を学んだばかり。
広い坂東において、千年も前の平将門の説が受け継がれている事実。それは、平将門という人物のカリスマ性を感じさせる。
それだけ当時の坂東(今の関東地方)の民衆に強い印象を与えていたのだろう。
それほどまでに都の人々を恐れさせ、坂東の人々に慕われた将門。果たして平将門とはどのような人物なのだろうか。
坂東の広大な地を一時とはいえ手中に収め、都を恐れさせた平将門。
この人物はどういう人物で、どういう生い立ちをへて青年になり、新王と名乗るまでになったのか。一度知ってみたいと思った。
もちろん本書が歴史小説であり、史実をそのまま反映していない事はよくわかっているつもり。
多分、著者による脚色もかなり含まれていることだろう。
だが、それでもいい。
著者が平安時代の坂東をどう解釈し、その時代の中で平将門をどう走らせたのか。そうした本書の全ては、著者による史実の解釈として楽したい。
まず、おじの平国香、平貞盛に東国の平氏の棟梁の座を良いように操られていた相馬小次郎の日々を描く。相馬小次郎とは平将門の幼名だ。
貞盛は将門を亡き者にしようと、豊田郡から横山まではるばる馬の種付けに遣わせる。
だが、豊田郡とは茨城県の下妻辺り。横山とは東京の八王子辺りだ。今の私たちの土地勘から考えると、茨城の真ん中から八王子までの距離を歩かされたわけだ。しかも当時、道が整備されているはずはない。
それを若干15歳ほどの元服したばかりの将門にやらせるあたり、かなりむちゃな話だ。ところが将門はそれをさも当たり前のことのように承り、出かけていく。それを実際にやり遂げようとした将門もすごい。
今の私たちにとってみると、相当の荒行にも思えるが、案外、見渡す限りが草原であり、道らしき道もないただの平野だと、当時の人々にとって距離感と言うものはないに等しいものだったのかもしれない。
著者はこのエピソードによって、現代の読者に距離感の違いを伝えようとしていると受け取った。
また、この当時の坂東の広さを考えてみるべきだ。
広さに加えて人口の少なさ。それはつまり、人に会う確率が少ないことを意味する。
広い坂東の大地で抗争をしたところで、お互いの勢力がどのように勢力を集め、どういう戦略で戦おうとしているのかすら分からない。
今より格段に情報の少ない時代であり、戦国の世のような状態ですらない。平将門の乱とは、実は素朴で小規模の抗争に過ぎなかったのではないか。
この時、東国の平将門にとって運命を握るべき人物がいた。藤原秀郷である。
この人物が、どの勢力につくかによって平将門の運命はがらりと変わる。
また、藤原秀郷が隠棲し、坂東の情勢を見定めていた地は、今で言う古河の辺りだ。
本書で描かれるのは、古河、筑西、府中、八王子。当時の海岸線が今よりもかなり北に寄っていたことも併せて考えると、こうした地名が登場するのにも納得がいく。人は少なく、争いも起きにくいが、それだけにかえって勢力が明確だったのだろう。
もう一つ、本書には将門が遠ざけられるように都に遣いにだされる下りがある。つまり、将門は都を知らない田舎者ではなかったのだ。これは私たちに新たな将門像を提示してくれる。
将門は都での日々で藤原純友と出会う。
後に二人は平安の世を大きく騒がせた藤原純友の乱と平将門の乱を起こした事で歴史に名を残す。
将門が藤原純友と京都で交わした約束。それは、時期を合わせて東西で同時に乱を起こし、朝廷を慌てさせるものだ。
将門が東国で乱を起こす際は、西国の藤原住友と連携する時期を合わせなければならない。
当時の連絡手段は早馬が使われる。だから、今の私たちの感覚ではとうてい想像できないほど、やりとりに時間が掛かっていた。今の情報社会に生きる私たちの感覚からは相当悠長に思えるほどの。
本書を読んでいて勉強になるのは、距離や時間の感覚の違いだ。
現代の私たちの感覚からは、大きくかけ離れている。それを踏まえなければならない。
それを無視したまま本書を読むと、本書で描かれる将門や住友の行動か意思決定の遅さにイライラする事だろう。
本書を読むには、そうした感覚の違いも味わいながら読むとよい。かつての関東平野は、もっと雄大で、もっとゆったりとし、もっとゆとりがあったのだ。
藤原純友とのタイミングは合わなかったとはいえ、一度は東国に覇を唱え、朝廷に対し新皇を名乗るまでに成長した将門。
果たして、平将門が敗れる事なく政権を維持できていたら、東国の歴史はどうなっただろうか。
都が東京に来るのタイミングはもっと早かったかもしれない。
ところが平将門が敗れた後、坂東の地に中央政府が根付くことは、鎌倉幕府を除けば徳川家康が都を構えるまで、800年ほど空白の期間がある。
なぜその間、何も起きなかったのだろうか。
それには、将門の乱が起きる前から頻発していた富士山の噴火や地震など、関東を舞台に起きた天変地異を考える必要がある。
そもそも平将門の乱であれほど将門が縦横無尽に動けたのは、それまでの天変地異で人口が激減していたからとは言えないだろうか。
そのことは、本書では触れていなかったにせよ、当時の平安朝が各地の天変地異に慌てふためいていたことを考えると、考慮すべき要因だと思う。
天変地異や疫病など、災いは全て怨霊のせいにされていた時期だったことも含め。
都の人には、平将門の乱も、坂東で続いた天変地異の最後の締めとして起こったととらえられていた節がある。
そう考えると平将門の首が関東に飛んで帰り、関東で祀られたことと、そしてその後、関東では天変地異の発生が止んだ事が、神田明神をはじめとした平将門の霊が関東の守護神として次第に祀られるようになった理由ではないだろうか。
そうした坂東の当時の地理に加え、天候や地政学を考えてみるとよい。
本書の背後には、そうした時代の流れや天災の不利にも負けず、精一杯駆け抜けようとした板東武士の心意気が見えないだろうか。
‘2018/10/25-2018/10/28