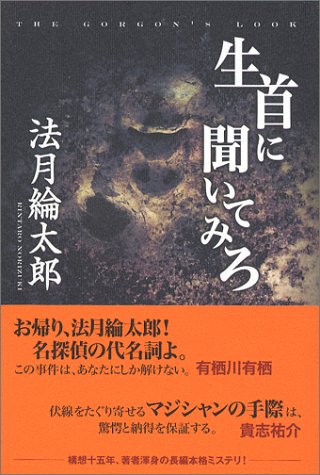
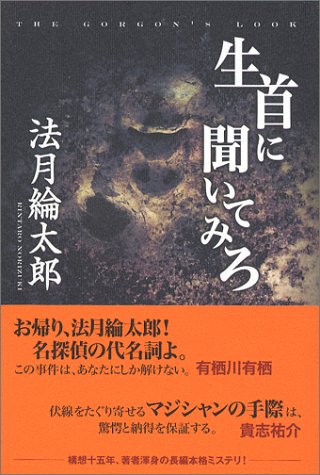
著者の推理小説にはゆとりがある。そのゆとりが何から来るかというと、著者の作風にあると思う。著者の作風から感じられるのは、どことなく浮世離れした古き良き時代の推理小説を思わせるおおらかさだ。たとえば著者の小説のほとんどに登場する探偵法月綸太郎。著者の名前と同じ探偵を登場させるあたり、エラリー・クイーンの影響が伺える。法月探偵の行う捜査は移動についても経由した場所が逐一書き込まれる。そこまで書き込みながら、警察による人海捜査の様子は大胆に省かれている。それ以外にも著者の作品からゆとりを感じる理由がある。それは、ペダンティックな題材の取り扱い方だ。ペダンティックとは、衒学の雰囲気、高踏なイメージなこと。要は浮き世離れしているのだ。
本書は彫像作家とその作品が重要なモチーフとなっている。その作家川島伊作の作風は、女人の肌に石膏を沁ませた布を貼りつけ型取りし、精巧な女人裸像を石膏で再現することにある。死期を間近にした川島が畢生の作品として実の娘江知佳をモデルに作りあげた彫像。その作品の存在は限られた関係者にしか知らされず、一般的には秘匿されている。それが川島の死後、何者かによって頭部だけ切り取られた状態で発見される。娘をモチーフにした作品であれば頭部を抜きに作ることはありえない。なぜならば顔の型をとり、精巧に容貌を再現することこそが川島の作品の真骨頂だからだ。なのになぜ頭部だけが持ち去られたのか。動機とその後の展開が読めぬまま物語は進む。
彫像が芸術であることは間違いない。前衛の、抽象にかたどられた作品でもない限り、素人にも理解できる余地はある。だが、逆を言えば、何事も解釈次第、ものは言いようの世界でもある。本作には川島の作品に心酔する美術評論家の宇佐見彰甚が登場する。彼が開陳する美学に満ちた解釈は、間違いなく本書に浮き世離れした視点を与えている。川島の作品は、生身に布を貼ってかたどる制作過程が欠かせない。そのため、目が開いたままの彫像はあり得ない。目を閉じた川島の彫像作品を意味論の視点から解説する宇佐見の解釈は、難解というよりもはやスノビズムに近いものがある。解釈をもてあそぶ、とでも言えば良いような。それがまた本書に一段と浮き世離れした風合いを与えている。
ただ、本書は衒学と韜晦だけの作品ではない。「このミステリかすごい」で一位に輝いたのはだてではないのだ。本書には高尚な描写が混じっているものの、その煙の巻き方は読者の読む気を失わせるほどではない。たしかに彫像の解釈を巡って高尚な議論が戦わされる。しかし、法月探偵が謎に迫りゆく過程は、細かく迂回しているかのように見せかけつつ、地に足がついたものだ。
探偵法月の捜査が端緒についてすぐ、川島の娘江知佳が行方不明になる。そして宇佐見が川島の回顧展の打ち合わせに名古屋の美術館に赴いたところ、そこに宇佐見宛に宅配便が届く。そこに収まっていたのは江知佳の生首。自体は急展開を迎える。いったい誰が何の目的で、と読者は引き込まれてゆくはずだ。
本書が私にとって印象深い理由がもう一つある。それは私にとってなじみの町田が舞台となっているからだ。例えば川島の葬儀は町田の小山にある葬祭場で営まれる。川島のアトリエは町田の高が坂にある。川島の内縁の妻が住むのは成瀬で、川島家のお手伝いの女性が住んでいるのは鶴川団地。さらに生首入りの宅配便が発送されたのは町田の金井にある宅配便の営業所で、私も何度か利用したヤマト運輸の営業所に違いない。
さらに川島の過去に迫ろうとする法月探偵は、府中の分倍河原を訪れる。ここで法月探偵の捜査は産婦人科医の施術にも踏み込む。読者は彫像の議論に加え、会陰切開などの産婦人科用語にも出くわすのだ。いったいどこまで迷ってゆくのか。本書は著者の魔術に完全に魅入られる。
そして、謎が明らかになった時、読者は悟る。彫像の解釈や産婦人科の施術など、本筋にとって余分な蘊蓄でしかなかったはずの描写が全て本書には欠かせないことを。それらが著者によって編みあげられた謎を構成する上で欠かせない要素であることを。ここまでゆとりをひけらかしておきながら、実はその中に本質を潜ませておく手腕。それこそが、本書の真骨頂なのだ。
‘2017/01/12-2017/01/15




