
We haven’t had that spirit here since 1969
一九六九年以来、その精神はここにはありません。
本書冒頭の扉にはイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」のあまりにも有名な一節が掲げられている。「ホテル・カリフォルニア」は、音楽ビジネスの退廃と閉塞を歌った曲として有名だ。この中にある1969年とはウッドストック・フェスティバルの開催された年。その年を最後に音楽からスピリットが失われてしまったと切ないメロディで歌われるこの曲は、ミュージシャン自身が歌うだけに説得力がある。酒のスピリットと音楽精神のスピリットを掛け、理想が失われつつある業界を憂う一節は、ロック史上に残る。私も何百回と聞いてきたが、これからも聞き続けることだろう。曲自体、イーグルスのメンバーや私がいなくなった後も残り続けるはずだ。
沖縄旅行から戻った私が続けて読んだ沖縄関係の本も本書で四冊目を重ねる。
本書は1969年を沖縄軍政の実質が終わった年としている。1969年1月にジョンソン大統領の後任となったニクソン大統領は、就任直後からベトナム戦争終結へと動き出したという。1969年に開かれた日米首脳会談でも沖縄返還は規定事項となった。沖縄の軍政の終わりが決まったのが1969年なのだ。沖縄返還は1972年だが、すでに沖縄の人々にとって軍政は終わっていた。そんな中、沖縄ではアメリカ軍政への不満が爆発するように1970年12月にコザ暴動がおこる。本書でもコザ暴動は物語の終わりを告げるエピソードとして登場する。
沖縄を囲む時代の空気と、基地の島の精神の変容。それを著者は冒頭に名曲の一節を掲げることでさりげなく問うている。
1945年の6月23日の沖縄戦の終結から、1972年5月15日に日本に復帰するまでの27年。本書が舞台とするのはその期間の沖縄だ。特に後半の数年は、ベトナム戦争が沖縄に暗い影を落としていた。沖縄返還をもって、日本は沖縄に復帰する。その復帰に尽力した功績で、佐藤栄作元首相はノーベル平和賞を受賞した。だが、その裏には沖縄がベトナム戦争の基地として活用された日々があったことは忘れてはならない。裏を返せば、沖縄返還はベトナム戦争が終結したからこそ実現したのかもしれない。ジョンソン大統領が米国の威信をかけてベトナム戦争の勝利へ突っ走る一方、戦場に赴く兵士には厭戦気分が広がっていた。そんな混乱した思惑がベトナムへの後方基地である沖縄に無縁だと考えるほうがおかしい。日本に返還される数年間、沖縄はかなり雑然としていたようだ。沖縄旅行の初日に訪れた平和祈念資料館には、アメリカの軍政下の日々が詳しく紹介されていた。実物大の街並みが再現され、私にも雑然とした街の雰囲気が感じられた。
本書はそのような背景のもとで展開される。沖縄には米軍基地がある。基地には軍人たちが大勢いて、それぞれの人生を生きている。軍人とはいえ、忠実な機械ではない。ましてやアメリカ本土ではフラワームーブメントが起こり、ヒッピー文化もますます華やかになっている。反戦運動も各地で盛り上がりをみせている。そんな世相の中、米軍基地に属する全ての軍人が職務に忠実と考える方が逆に不自然だ。
フリーダ=ジェインもその一人。有能な事務スタッフとして機密会議の資料や議事録を作っている彼女は、アメリカ人の血が半分入ったフィリピン出身。父の縁で軍に入ったが、彼女の母は自分を捨ててアメリカに帰った夫とアメリカを許せず、反アメリカの組織を束ねている。そして娘であるフリーダ=ジェインにも軍の秘密を漏らすよう、符丁だらけの手紙を送りつけてくる。
フリーダ=ジェーンは、b-52の機長であるパトリック・ビーハンに声を掛けられステディな関係になる。パトリックは機長であるが、ベトナムに爆弾を落とすことにストレスを感じている。毎回、出航の前夜には酒の力に頼っている人物だ。
嘉手苅朝栄は戦前、沖縄からサイパンへと移民した人物だ。サイパンは日米の間で凄惨な戦いの場となった。朝栄はサイパンが戦場になる前に沖縄に引き揚げてきたが、沖縄戦でも九死に一生を得るほどの状況に巻き込まれる。朝栄は戦後、小さな運送会社を経営していたが、結婚した妻が沖縄そばの店舗経営で軌道に乗る。そして朝栄は、事業のトラックが壊れたのを機に会社を畳み、無線の技術をを生かして電機修理のお店を営んでいる。
安南さんは朝栄とサイパンで旧知の人物。戦後は沖縄に腰を据えている。ベトナム出身だが、日本語は流ちょうで物腰も柔らかいため、沖縄に溶け込んでいる。祖国がアメリカに攻撃されている現状を見逃せず、ひそかにB-52の攻撃ルートをベトナムに伝える組織を作り上げた。
タカは朝栄の妻方の親族だ。彼は那覇でロックバンドを組んで活動していたが、地元のマフィアを諍いを起こし、基地でかくまってもらっている。
ここに挙げた主要人物は、沖縄とベトナム、サイパン、そしてフィリピン、アメリカにルーツを持つ。われわれ本土の人間が沖縄を語るとき、どうしても本土と沖縄の関係に目をやってしまう。せいぜい、沖縄と中国の関係を語るくらいだろう。しかし、当時の沖縄はさらに複雑な状況にあった。日本と沖縄と大陸の関係だけでは到底足りない。少なくとも本書に書かれるぐらいの関係は把握せねばならないはずだ。私にはそれが本書から得た気づきであり、とても新鮮に映った。ベトナム戦争が最も激烈な時期にアメリカの軍政の下に置かれ、かつ前線への基地だった沖縄では、本書に描かれるような複雑な思惑が外交の場と同じく繰り広げられていたのだろうから。
沖縄から見た世界とは果たしてどのようなものだったのか。本書の終わりの方で、タカがロックバンドとともに大阪万博の沖縄館に行くシーンがある。日本で開かれる万国博に沖縄館が置かれること自体の違和感。その事実は、沖縄が日本とは別の国であったことを示している。それは歴史的な事実でもある。今回の旅で訪れた平和祈念資料館の展示でも学んだ。27年間、沖縄は日本とは別の国だった。
ところが私が22年前と今回訪れた沖縄は間違いなく日本だった。多少の文化の違いはあるにせよ、パスポートが要らず、日本語を何の違和感なしに話せる島。沖縄県。私は沖縄をなんの疑いもなく日本と受け入れていた。ところが平和祈念資料館の展示と本書から学んだことは、沖縄が別の国だった事実だ。それも琉球王国の時代ではなく、私が生まれる前の年まで。だから本書のように、日本の影がうすい沖縄がとても新鮮に映る。
いまもなお、沖縄には米軍基地がかなりの面積を占めている。まだ、沖縄にとって戦後は続いている。そして沖縄の抱える矛盾が最も激しく姿を現していたのが、ベトナム戦争の後方基地であったこの時期だったと思う。
だからこそ本書には存在意義がある。安南さんとフリーダ=ジェーンの母がそれぞれ作った組織に存在意義があったように。フリーダ=ジェーンが次の攻撃地点など会議で得た情報を外に持ち出すリスク。フリーダ=ジェーンの家に庭師のバイトで来るタカがその情報を朝栄の店に運ぶリスク。朝栄が暗号化して店にある無線装置からベトナムに向けて発信するリスク。彼らがそれだけのリスクを引きうけたのには、沖縄が置かれた状況が矛盾に満ちていたからだろう。ベトナム戦争の大義について本書は触れない。だが、ベトナムの人々が枯葉剤やナパーム弾から逃げ惑う悲劇と、沖縄戦で人々が焼かれた悲劇は本書の中で密につながっている。あらゆる矛盾が混在した沖縄にあって、唯一矛盾しなかったことがベトナムと沖縄の戦場経験であるのは、とても皮肉なことだ。
タカは大学の反戦サークルにも関わりを持つ。反戦サークルは実際に軍からの脱走希望者を海外に逃す活動にも手を染めている。タカは、マーク・ロビンソンをスウェーデンに向けて脱走させ、さらに反戦への動きに巻き込まれてゆく。軍からの脱走希望者は、大義なき戦争の矛盾が戦争をなりわいとする軍人のアイデンティティに破綻として現れた証だ。パトリック・ビーハンもそう。ベトナムへの航行の前夜に酒に溺れ、インポテンツのためフリーダ=ジェーンとの愛の営みもままならない機長。彼も、その矛盾を全身で受け止め、苦しんでいた。
皆が感じる矛盾は、パリ協定の進展によって軽減される。つまりはベトナム戦争の終結に向けたアメリカの譲歩だ。アメリカの譲歩は、パトリック・ビーハンの負担も軽減する。それによってビーハンのインポテンツは治り、フリーダ=ジェーンとの愛情はより深まる。だが、矛盾が根本から解消されるためには残酷な結末が必要だ。著者はパトリック・ビーハンの操縦する機をエンジンの不調で墜落させ、結末をつける。
四人の機密漏えいは結局バレずに済んだ。脱走兵の支援工作も実行者が特定されることはなかった。もちろん、それらとビーハンの死にはなんの因果もない。だが、沖縄をめぐる幾重にも重なった矛盾を物語の中で大団円として解消させるため、著者はビーハンに死んでもらったのだと思う。直前にはフリーダ=ジェーンとビーハンをアブチラガマの戦争遺跡に連れ出し、沖縄戦の遺骨にも対面させる。
本書ではコザ騒動も描かれる。それはもちろん冒頭に書いた通り、アメリカ軍政下でたまった沖縄の人々の不満が爆発した結果だ。それと同じくコザ騒動にはアメリカの立場の弱まりと、ベトナム戦争の基地としての沖縄の意義低下、つまりは沖縄返還の前兆を感じた人々の前祝いの意味もあったのかもしれない。
だからこそ、コザ騒動やビーハンの死、アブチラガマなど重いテーマが続く後半の展開にも関わらず、本書にはすがすがしい読後感が感じられるのだと思う。
本書を読んだ時、私が訪れた沖縄は再び矛盾の噴出する地になろうとしている。私が今回訪れた際も、辺野古への反対行動への参集を呼びかける具体的な看板を見かけた。それらがどれほどのパワーを秘めているのか、誰にもわからない。特に本土の人間にとっては。その上、本稿をアップする前日に、現職の翁長沖縄県知事がなくなられた。基地に対して一貫して反対の立場をとってきた翁長氏の死が何をもたらすのか。本書の二冊前に読んだ佐藤優氏の結論も、外交官の立場でありながら沖縄に基地が集中することには反対で沖縄は日本にとどまっていたほうが得、とのことだった。
現状とこれからが不透明な今だからこそ、返還前の沖縄がどのようなことになっていたのか本書を読んで知ると良い。1969年以降にスピリッツがないと言ってられるのも今のうちだけかもしれないのだから。
‘2017/07/16-2017/07/17





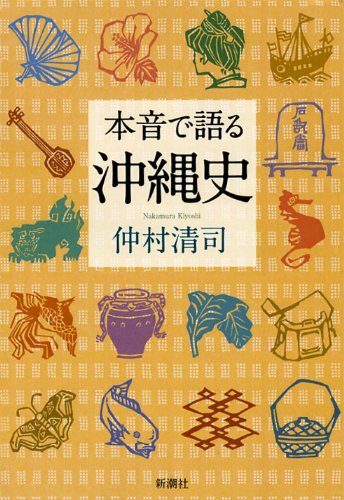



 これら基地周辺に住む人々にとっては、沖縄の人々の気持ちが少しは共感できるのではないでしょうか。沖縄の方々が蒙っている迷惑の実態を。私もつい先年まで町田市の中心部に住んでいました。町田市は、横田基地と厚木基地を結ぶ線上にあります。頻繁に北から南へと飛行機が通り過ぎ、そのたびに爆音が町田の繁華街を縦断します。その高度は機体番号が見えるのではないかというほど低く、特にNLP(夜間連続離発着訓練)の際は、夜中の25時過ぎでもお構いなしの轟音が響き、寝るどころの話ではありません。
これら基地周辺に住む人々にとっては、沖縄の人々の気持ちが少しは共感できるのではないでしょうか。沖縄の方々が蒙っている迷惑の実態を。私もつい先年まで町田市の中心部に住んでいました。町田市は、横田基地と厚木基地を結ぶ線上にあります。頻繁に北から南へと飛行機が通り過ぎ、そのたびに爆音が町田の繁華街を縦断します。その高度は機体番号が見えるのではないかというほど低く、特にNLP(夜間連続離発着訓練)の際は、夜中の25時過ぎでもお構いなしの轟音が響き、寝るどころの話ではありません。