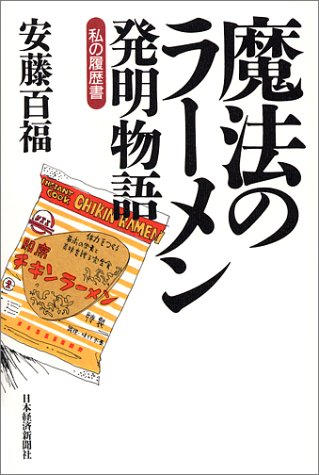
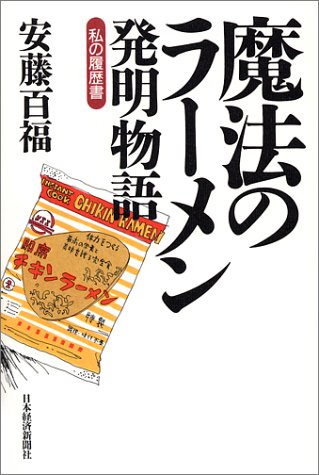
数年前、横浜にもカップヌードルミュージアムができた。私もそのニュースを聞いてから、家族を連れて何度も行こうと思っているが、いまだに伺えていない。
本書はチキンラーメンを発明し、世界に即席めんを広めた日清食品の創業者、安藤百福氏による自叙伝だ。
チキンラーメンから始まった即席めんのラインアップ。その豊かさは、コンビニエンスストアに行くたびに実感でき。
無数の商品が生み出されてきたし、いまも頻繁に棚の商品が入れ替わる。
おそらく、それらの商品の背景には開発者やマーケティング担当者、製造ラインの方々による努力が刻まれていることだろう。
だが、その裏側に、著者による幾たびも挫折を繰り返した人生があったことを、私はあまりよく知らずにいた。
本書は、日本経済新聞に連載された「私の履歴書」を基にしている。「私の履歴書」といえば功成り名遂げた方の自叙伝としてよく知られたコーナーだ。
本書の「はじめに」では、「私の履歴書」に連載を始めたいきさつが書かれている。
それによると戦後に輩出した著名な創業者のうち、残された大物の一人が著者だったらしい。
担当編集者からの依頼に対し、「特に人に向けて書くようなことはない」と著者が断っていたところ、逆に何か書くとまずい事でもあるのかと問われ、つい筆を取ったのが連載のきっかけだったようだ。
本書には著者の生い立ちから日清食品の躍進までの歴史が記されている。本書を読むと、著者の人生は挫折もあったが、ほとんどが努力と成長の連続だった事がわかる。
チキンラーメンの開発にあたって、著者が一年間自宅にこもりきっていた事はよく知られている。
その裏には、著者が頼まれて理事長に就任した信用組合が破綻し、ほとんどの家財を差し押さえられた実情があったらしい。実際、自宅のみしか残されなかったため、背水の陣を布いて即席めんの開発に当たったというのが真相のようだ。
私は本書を読むまで、その裏側に何か事情があったことなど考えたこともなかった。
差し押さえ。それが大きな挫折であることは確かだ。
だが、挫折する前の著者が信用組合の理事長の地位にまで登り詰めていたことを見逃してはならない。
著者には信用組合の理事長になるまでの人徳と実力があったことを示している。
戦前と戦中に著者は多様な事業に手を出し、それらをことごとくものにしてきたという。著者自身の努力とセンスの賜物だろう
そこを考えず、著者が一か八かを賭けて即席めんに手を出し、幸運にも一発当てたと早とちりすると、著者の生涯から得られる教訓を逃してしまう。
著者は台湾で生まれ、そこで繊維系の仕事に就き、商売を学んだようだ。そして、台北だけでは仕事の広がりに限界を感じ、異国である日本の大阪に出て仕事を起こした。台湾に生まれ、台湾の人でありながら、苦労と工夫を重ねて日本になじんだ事が著者の原点にあるようだ。
著者の人生を概観してみると、あらゆる事物への飽くことのない好奇心が成功に導いた事に気づく。
好奇心に加え、工夫に次ぐ工夫の連続。そこに妥協はない。
好奇心は発想の種を生む。
私は、周りにあるすべてに対する好奇心は、人生を成功させるために不可欠だと思っている。
もう一つ、著者の人生から感じ取れるのは、中年を迎えても人間には成功へのチャンスがあることだ。
そもそも著者が即席めんの発明に手を染めたのが、著者の人生でも後半生に入った後だ。47歳になって自宅で始めたチキンラーメンの開発の苦労は、本書に詳しく書かれている。
その姿はまさに単身の奮闘。この言葉に尽きる。
組織の力は確かに重要だ。だが、最初に努力し、火を起こすまでは一人の力でやるべき仕事なのかもしれない。
この事は、私にとってあらゆる意味で気づきになった。
むしろ、著者が最も言いたい事は、初めは組織だけに頼るなということかもしれない。
著者は、信用組合の理事長での経験を苦い思い出として回顧し、組織を運営のする事の難しさについて触れている。全くその通りだと思う。
一人の力で火を起こし、それを広げるにあたってようやく、組織の力が必要となる。
この事は社会人のほとんどには当てはまらない。だから、結果論だけを取り出せば、一山当てた著者だから説ける教訓だと片付けることもできるだろう。
だが、はじめは組織に頼るなとの教えは、今の新卒での採用が慣習となったわが国のあり方にも一石を投じるものだと思う。
また、カップライスの失敗についても著者は触れている。
開発に着手した当時、古米、古古米が倉庫に眠り、政府からも米の有効活用の要請があり、即席ライスを開発した。だが、見事に失敗したそうだ。
ところが、著者の遺志は没後に実現したことを今の私たちは知っている。そう、日清のカレー飯だ。見事に大ヒットし、今もまだよく見かける商品だ。
おそらくは泉下の著者も喜んでいるに違いない。
本書は、東食の倒産や阪神淡路大震災での社会貢献についてもページを割いている。
それによると、東食は倒産後、即座に日清との取引の再開にこぎ着け、その後の倒産からの復活につながったそうだ。
そうした社会貢献を成し遂げるまでになった日清食品の歴史は、著者が47歳からカップめんを開発して始まった事。
何人もの人生を凝縮したような著者の濃い人生が、まさに人生の後半から始まり、社会貢献にまでつながった事がすごい。
本稿をアップした私は先日、47歳になった。まさに著者がチキンラーメンを開発した年齢だ。
焦りはある。一方で諦めては負けだ、との思いもある。
ひょっとしたら、私自身、全く気づいていない何かをこれから成し遂げるかもしれない。
私自身、今の自分に安住しているつもりも、慢心しているつもりもない。だが、そうした罠はすぐそこに口を開けて待っているはず。間違ってもそうなってはならない。
その事を強く本書から感じた。
本書が面白いのは、私の履歴書の連載の後日談として「麺ロードを行く」と題し、著者が麺の故郷である中国の各地を訪れ、そこで麺を研究した成果を載せていることだ。
それもまた、日本経済新聞の連載だったらしい。
その中で紹介されている中国各地の麺の豊かなことと言ったら!
日本にもかなりの種類の麺が入ってきているが、まだまだ中国には及ばない。私たちの知らない麺の奥深い世界が広がっているようだ。
本書を読むと、そうした麺がもっと日本に入ってきてほしいと思う。
麺こそが、私たちの食生活を豊かにする。そのことに誰も異論はないだろう。
著者は長生きの秘訣を尋ねられたり、カップめんの容器に健康被害の風評が吹き荒れた際、97歳まで生きた自らの長寿を引き合いに出し、カップヌードルの健康性を吹聴していたとか。
私も最近、よく横浜に行く。
冒頭に書いたように、横浜にはカップヌードルミュージアムがある。
早くそこに行って、著者の実践の成果を見てみようと思う。
さらに、実家に帰ったときには、著者が住んでいた池田に建てられたカップヌードルミュージアムにも訪れたいと願っている。
その時、私は何を思うだろう。ひょっとしたら新たな道を見つけられるかもしれない。楽しみだ。
‘2019/4/26-2019/4/26


