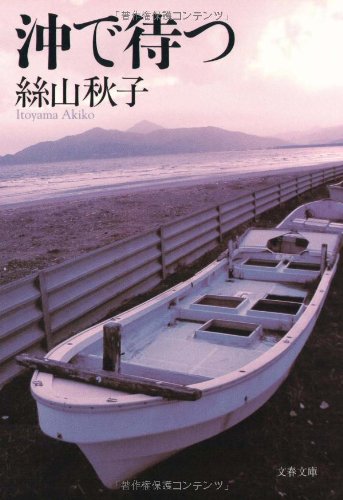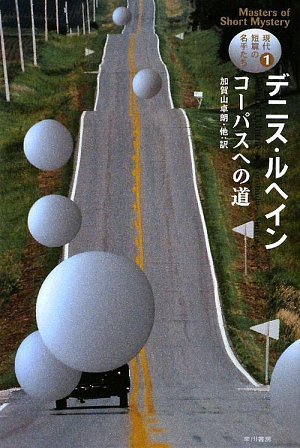老境に入った著者が過去の自分を思い返しつつ、そこから生まれた随想を文章にしたためる。
本書を一言で言い表すとこのようになる。
本書に収められた十の短編をレビューにまとめることは、正直言ってなかなか難解だ。
なぜなら、本編には、著者自身の人生を彩った出来事が登場し、著者の親族も登場し、そして著者が今までに発表した作品の登場人物が登場するからだ。
著者の代表作である『同時代ゲーム』はよく知られている。その世界観が著者が生まれ育った四国の山奥の村をモチーフとされていることも。
そうした作品に登場する人物は、著者の人生にも登場する人物でもある。そうした人物が本書にはあちこちで登場する。だから、著者の作品を読んでいないと読者には何のことか分からなくなってしまうのだ。
「火をめぐらす鳥」
この一編は、著者の生涯を持って生まれた息子との日々を描いている。
今や作曲家として著名な光氏と過ごした時間は、著者にどのような影響を与えたのか。
その一端が描かれる本編からは、光氏の存在が著者の作家活動に大きな影響を与えたことが見て取れる。
「「涙を流す人」の楡」
華やかな外交官との交流を語る内容が一転して、著者の育った四国の山奥の谷間の村の描写へと変わる。
その二者を繋ぐイメージがニレの木だ。楡を通して結びついた二つの世界。
その二つの世界の主人公である著者は時間によって隔てられている。
百戦錬磨の外交官との談論ができるようになった、と著者が感慨をもつ今。そして、四国の谷間の村の幼い頃の経験。
著者の育った谷間の村の狭いけれど豊かな世界が授けてくれたことは、著者の今と確かにつながっている。
その谷間の村の経験は、著者の作家活動にも大きな恵みをもたらしてくれた。そう著者は振り返る。
そしてそうした自分にさらなる成熟がもたらされたのも、外交官との交流があったからだと著者は述べる。
N大使の逝去に際して書かれたと思われる本編で、著者は今の自分の心で過去を再構成する。
それにしても著者の文章の読みにくさといったら!
「宇宙大の「雨の木」」
時間と空間をつらぬいて遍在する「不死の人」。
不死の人を小説に書きたいと願う著者が、文学の影響や好みを自由自在に語る。
三島由紀夫を批判し、フォークナーの作品世界を好む著者。
著者の探し求めるイメージの断片がさまざまに現れる。
“雨の木”は著者の作品でも登場する。
著者が想起する多様なシンボルが本編のように混交して現れることで、著者の小説の基本的なイメージが形をなしてゆく様子をうかがうことができる。
「夢の師匠」
谷間の村の「夢を読む人」と「夢を見る人」を見て育った著者の子供の頃の記憶。
彼らが戦争によって境遇を変えられてしまう様子は、著者に強い印象を刻む。
そのイメージを通し、続いての「治療塔」の構想へとまとまってゆくいきさつを記した一編だ。
平田篤胤全集の「仙童寅吉」の話と、ゲルショム・ショーレムの「ユダヤ神秘主義」に書かれた中世ヨーロッパの祈禱神秘主義をめぐる引用。
それらに刺激を受けたという著者がそれらを引用しつつ、SFへとイメージを広げてゆく。
「治療塔」
著者にとって珍しいと思われるSF作品。
筒井康隆氏と著者の交流は知られているが、本編は筒井氏の影響から生まれたのだろうか。
古い地球を見捨てる人類と、古い地球に留まり続ける人類。
新しい人類にならんとする人々は、治療塔で癒やされる。
著者にとって、人類や地球は理想の姿ではないだろう。ところが治療塔の概念は、人類が自ら根本的に成長を遂げることを諦めてしまっているかのようだ。
それは著者自身の諦めの表れなのだろうか。『治療塔』はまだ読んでいないので、機会があれば読んでみたいと思う。
「ベラックワの十年」
ダンテの「神曲」をモチーフにした著者の作品『懐かしい年への手紙』に登場させなかった道化者のべラックワ。
その姿を振り返りながら、自らの中の道化の部分や放埒さを思い起こそうとする一編だ。
本書の中では読みやすい部類に入る。
ノーベル賞を受賞し、難解と言われる作風のため、著者に近づきがたい印象を受けているのなら、本編で書かれた著者の姿から印象が変わるかもしれない。
「マルゴ公妃のかくしつきスカート」
性的に放縦だったとされるマルゴ公妃の生涯を振り返るテレビ番組をきっかけに、ある人物の放縦と性的な自由さを探ってゆく一編。
著者の思索の対象はマルゴ公妃だけではない。テレビ局のスタッフである篠君の言動も著者の興味を引く。その二人を通して、著者は人の自由さとは何かについて考えを深めてゆく。
著者にとって冒険とは文学的なそれに等しいと思う。だが、著者は自由で羽目を外した行いをする人物には見えない。きっと堅実だったと思う。動くよりも見る側の人。
その証拠に以下のような文章が登場する。
「事実、小説家は志賀、井伏といった例外的な「眼の人」をのぞいて、見る瞬間にではなく、文章を書き、書きなおしつつ、かつて見たものをなぞる過程でしだいに独特なものを作ってゆくのだ。」(202p)
「僕が本当に若かった頃」
著者が20歳の頃、家庭教師をしていた繁君。ひょんなことで繁君の消息がわかったことから、著者が当時のことを思い出し、つづってゆく一編。
まさに著者が若かった頃の話だ。
かつて著者の前から消息を絶った繁君に何が起こったのか。繁君はその理由を長文の手紙で知らせてくる。
本編に載っているその手紙は果たして著者の創作なのか。それとも繁くんの実際の手紙なのか。私にはわからない。
繁君の秘密が明かされてゆく様は本編は、ミステリーを読んでいる気分になる。
「茱萸の木の教え・序」
著者の故郷の四国から、孝子ことタカチャンの残した文書やその他の事績をまとめる段ボールが送られてきたことから始まる一編。
孝子とは、著者の従妹にあたる。起伏の多い人生を送った末、亡くなった。
著者の伯父がその一生をまとめたいと、作家である著者に託す意図で送ってきた資料の数々。
著者はタカチャンの思い出を振り返る。その中で著者は故郷で繁っていた茱萸の木に着目する。タカチャンの残した文の中でもいく度か取り上げられる茱萸の木。
伐採されてしまった茱萸の木に語りかけていたタカチャンの思いは何か。それを探りながら著者はタカチャンの一生をつづってゆく。
そうすることで著者なりに同時代を生きたタカチャンの鎮魂を果たそうとするかのように。
「著者から読者へ」
これは本書に収められた「僕が本当に若かった頃」を書いた著者から読者に向けての手紙の体裁をとっている。
著者にとっては「僕が本当に若かった頃」は、旅の疲れを癒やす作品でもあったようだ。
解説の井口時男氏の文章は、大江健三郎という巨大な作家の著作群の中で、本書が占める意味を克明に記している。
その中で本書のいくつかで登場した若い頃の著者=僕の出来事は、徹底的に言語化された「僕」というテキストになっていることが示される。つまり、本書は私小説ではないし、エッセイもどきの小説でもない。
本書は著者がその小説技法を存分に生かした巧妙な短編群なのだ。
‘2018/11/20-2018/11/28