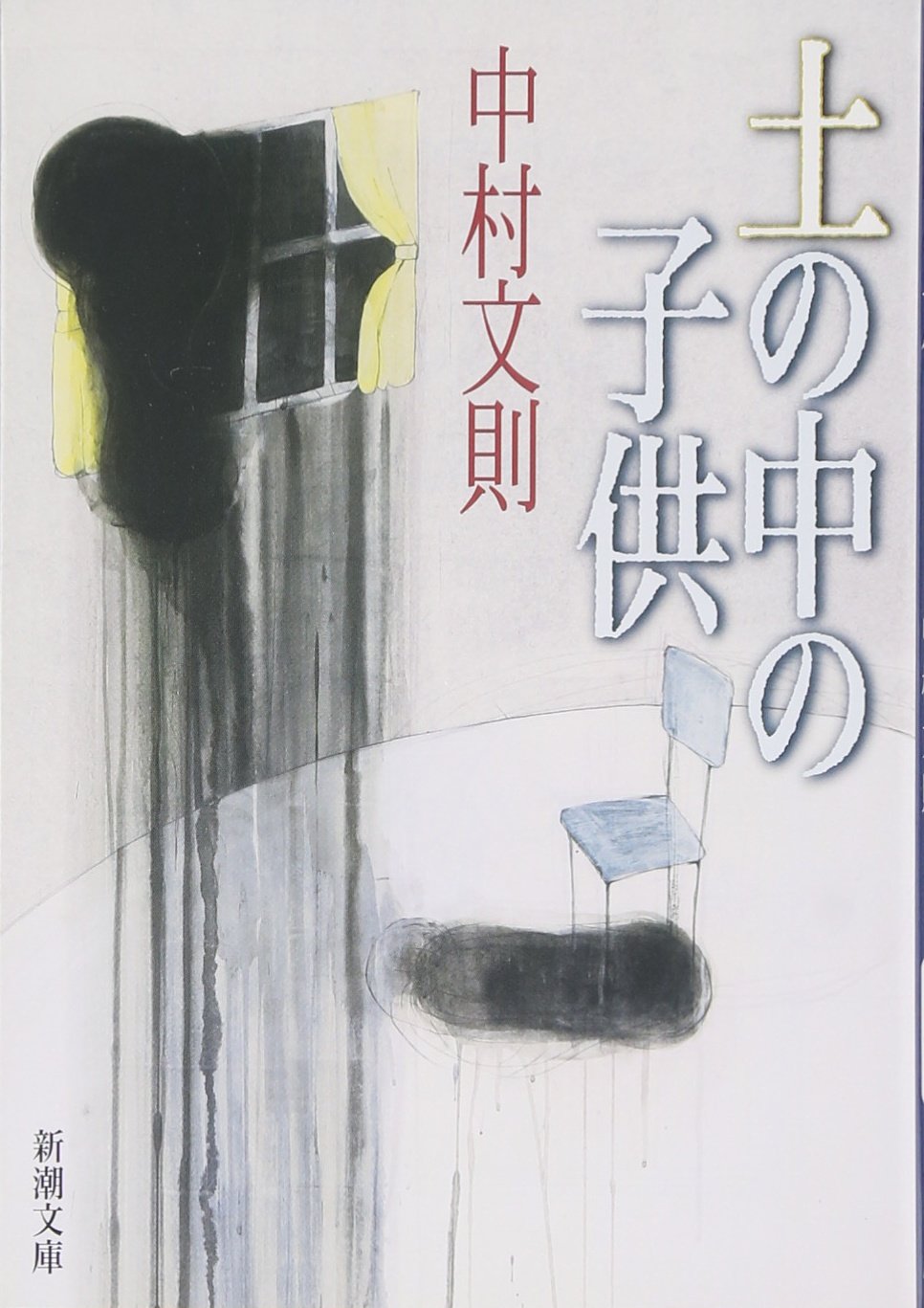
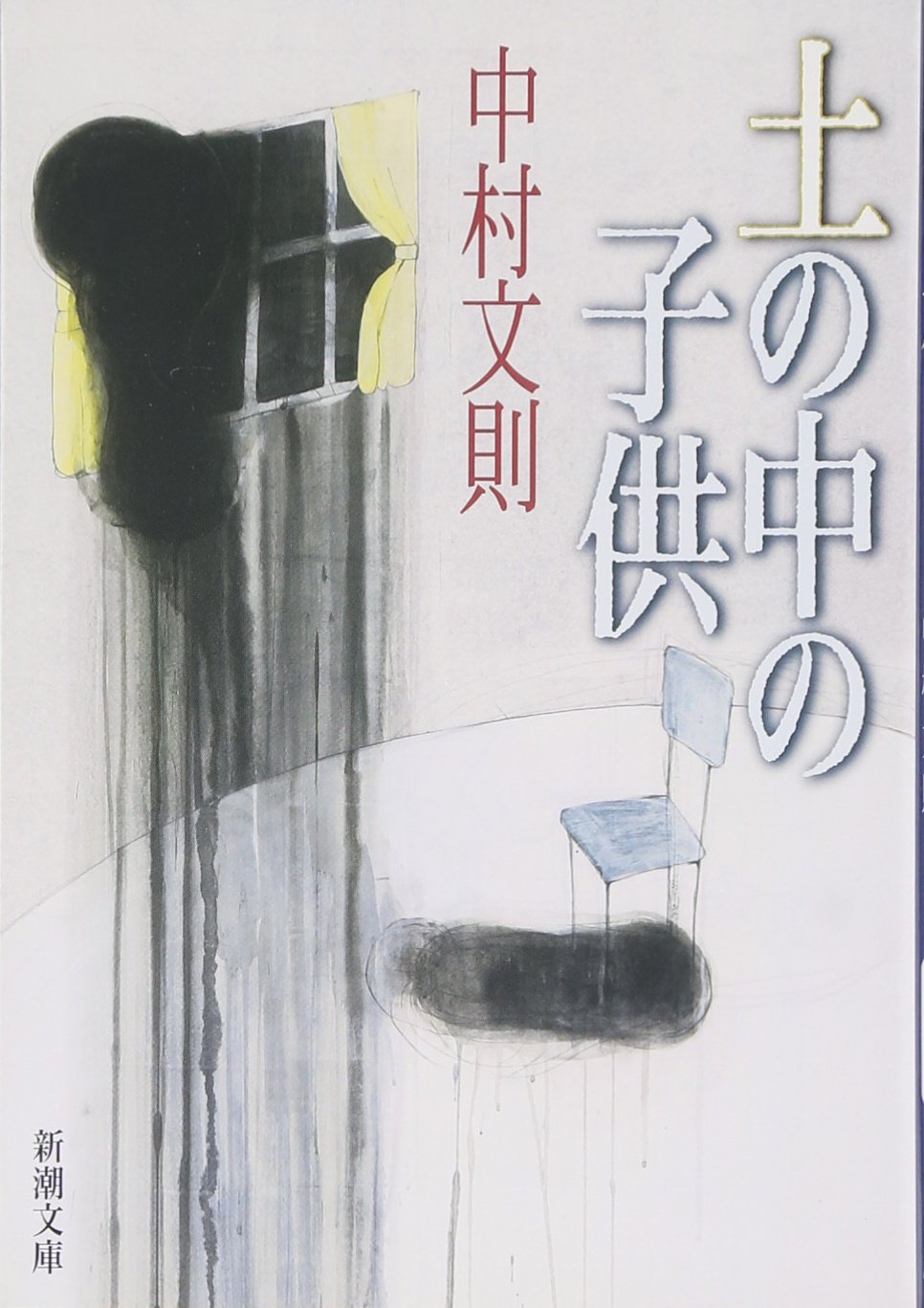
人はなにから生まれるのか。
もちろん、母の胎内からに決まっている。
だが、生まれる環境をえらぶことはどの子供にも出来ない。
それがどれほど過酷な環境であろうとも。
『土の中の子供』の主人公「私」は、凄絶な虐待を受けた幼少期を抱えながら、社会活動を営んでいる。
なんとなく知り合った白湯子との同棲を続け、不感症の白湯子とセックスし、人の温もりに触れる日々。白湯子もまた、幼い頃に受けた傷を抱え、人の世と闇に怯えている。
二人とも、誰かを傷つけて生きようとは思わず、真っ当に、ただ平穏に生きたいだけ。なのに、それすらも難しいのが世間だ。
タクシードライバーにはしがらみがなく、ある程度は自由だ。そのかわり、理不尽な乗客に襲われるリスクがある。
襲われる危険は、街中を歩くだけでも逃れられない。襲いかかるような連中は、闇を抱えるものを目ざとく見つけ、因縁をつけてくる。生きるとは、理不尽な暴力に満ちた試練だ。
人によっては、たわいなく生きられる日常。それが、ある人にとってはつらい試練の連続となる。
著者はそのような生の有り様を深く見つめて本書に著した。
何かの拍子に過去の体験がフラッシュバックし、パニックにに陥る私。生きることだけで、息をするだけでも平穏とはいかない毎日。
いきらず、気負わず、目立たず。生きるために仕事をする毎日。
本書の読後感が良いのは、虐待を受けた過去を持っている人間を一括りに扱わないところだ。心に傷を受けていても、その全てが救い難い人間ではない。
器用に世渡りも出来ないし、要領よく人と付き合うことも難しい。時折過去のつらい経験から来るパニックにも襲われる。
そんな境遇にありながら、「私」は自分に閉じこもったりせず、ことさら悲劇を嘆かない。
生まれた環境が恵まれていなくても、生きよう、前に進もうとする意思。それが暗くなりがちな本書のテーマの光だ。
そのテーマをしっかりと書いている事が、本書の余韻に清々しさを与えている。
「私」をありきたりな境遇に甘えた人物でなく、生きる意志を見せる人物として設定したこと。
それによって、本書を読んでいる間、澱んだ雰囲気にげんなりせずにすんだ。重いテーマでありながら、そのテーマに絡め取られず、しかも味わいながら軽やかな余韻を感じることができた。
なぜ「私」が悲劇に沈まずに済んだか。それは、「私」が施設で育てられた事も影響がある。
施設の運営者であるヤマネさんの人柄に救われ、社会のぬかるみで溺れずに済んだ「私」。
そこで施設を詳しく書かない事も本書の良さだ。
本書のテーマはあくまでも生きる意思なのだから。そこに施設の存在が大きかったとはいえ、施設を描くとテーマが社会に拡がり、薄まってしまう。
生きる意思は、対極にある体験を通す事で、よりくっきりと意識される。実の親に放置され、いくつもの里親のもとを転々とした経験。中には始終虐待を加えた親もいた。
その挙句、どこかの山中に生きたままで埋められる。
そんな「私」の体験が強烈な印象を与える。
施設に保護された当初は、呆然とし、現実を認識できずにいた「私」。
恐怖を催す対象でしかなかった現実と徐々に向き合おうとする「私」の回復。生まれてから十数年、現実を知らなかった「私」の発見。
「私」が救われたのはヤマネさんの力が大きい。「私」がヤマネさんにあらためたお礼を伝えるシーンは、素直な言葉がつづられ、読んでいて気持ちが良くなる。
言葉を費やし、人に対してお礼を伝える。それは、人が社会に交わるための第一歩だ。
世間には恐怖も待ち受けているが、コミュニケーションを図って自ら歩み寄る人に世間は開かれる。そこに人の生の可能性を感じさせるのが素晴らしい。
ヤマネさんの手引きで実の父に会える機会を得た「私」は、直前で父に背を向ける。「僕は、土の中から生まれたんですよ」と言い、今までは恐怖でしかなかった雑踏に向けて一歩を踏み出す。
生まれた環境は赤ん坊には一方的に与えられ、変えられない。だが、育ってからの環境を選び取れるのは自分。そんなメッセージを込めた見事な終わりだ。
本書にはもう一編、収められている。
『蜘蛛の声』
本編の主人公は徹頭徹尾、現実から逃避し続ける。
仕事から逃げ、暮らしから逃げ、日常から逃げる。
逃げた先は橋の下。
橋の下で暮らしながら、あらゆる苦しみから目を背ける。仕事も家も捨て、名前も捨てる。
ついには現実から逃げた主人公は、空想の世界に遊ぶ。
折しも、現実では通り魔が横行しており、警ら中の警察官に職務質問される主人公。
現実からは逃げきれるものではない。
いや、逃げることは、現実から目を覆うことではない。現実を自分の都合の良いイメージで塗り替えてしまえばよいのだ。主人公はそうやって生きる道を選ぶ。
その、どこまでも後ろ向きなテーマの追求は、表題作には見られないものだ。
蜘蛛の糸は、地獄からカンダタを救うために垂らされるが、本編で主人公に届く蜘蛛の声は、何も救いにはならない。
本編の読後感も救いにはならない。
だが、二編をあわせて比較すると、そこに一つのメッセージが読める。
‘2019/7/21-2019/7/21


