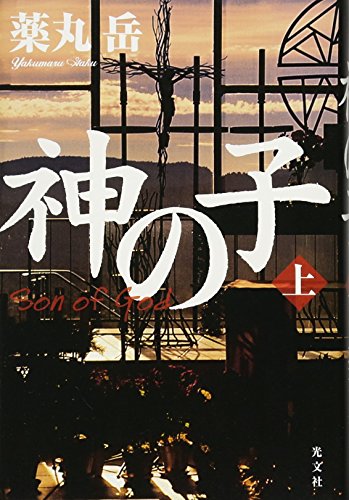地球温暖化は人類の経済活動による現象なのか。それとも太陽と地球の位置関係によって引き起こされるのか。人類が今の消費型の経済活動をやめなければならないのはいつか。それともすでに手遅れなのか。それとは逆に、いや、地球は温暖化などしていない。地球は寒冷化しつつあるのだと主張する向きもある。さらには海洋が大気中の二酸化炭素を吸収してくれるため温暖化することはないとの説も聞こえてくる。地球温暖化に関する全ての懸念は杞憂だという意見も。
地球に住むの全人類の中で、上に書いたような温暖化の問題に日々関心を持つ方はどれぐらいいるのだろう。
先進国民(私を含んだ)は、大小の差はあれ今の快適な暮らしに慣れている。衣食住はあり余るほど満ち、文化への好奇心や自己実現の機会に事欠かない現代。その特権を失いたくないと思っている方がほとんどだろう。既得権益を守ろうとする思いが先鋭化するあまり「地球温暖化は嘘っぱちだ」と口走る米国トランプ大統領のような方もいる。
それとは真逆の方向に奔走する人もいる。国全体が海中に沈む危機に瀕している南洋の島国キリバスの状況を悲観的に解釈し、今の世界の大都市の多くもキリバスと同じように海に沈むと煽る方々だ。
地球温暖化の懸念が真実であるならば、本来なら人類全体で共有すべき喫緊の課題であるはず。なのに、それがイデオロギーの対立にすり替わっている現状。その状況にいらだつ人は私以外にもいるはずだ。いい加減、何が正しいのかを知りたい。何が起こっているのか。または、何が起ころうとしているのか。私たちにはいつまで時間が残されているのか。文明に慣れた今の先進国の暮らしは未来の人類からは非難されるのか。それとも全ては杞憂なのか。それを知りたい。そう思って手に取ったのが本書だ。
本書の著者の筆頭に名の挙がるウォレス・S・ブロッカー教授は、1950年代から地球温暖化の問題を研究するこの分野の泰斗だ。世界で始めて地球温暖化が起きていることを公式に報告した人物でもある。教授は地球の地理と歴史を総じて視野に入れ、この問題に取り組んで来た方だ。つまり本書に書かれる内容は、根拠なき自説を無責任に振りかざすような内容ではないはず。そう信じて本書を読んだ。
本書の著者として挙がっているのは二名。教授とロバート・クンジグ氏だ。そして実際に本書を執筆したのはロバート氏の方だという。ロバート氏はサイエンスライターが本業であり、その職能をフルに生かしている。では教授は何をしているのか。おそらく、本書の監修のような立場だと思われる。本書には教授の生い立ちから研究に携わるまでの生涯、そして研究の内容と成果が書かれている。それらの記載が正しいか監修する立場で著者に名前を連ねているのだろう。
本書の序盤はロバート氏からみた教授の紹介にページが費やされている。温暖化の真実を本書からつかみ取ろうと意気込む読者は拍子抜けする。また、退屈さすら感じるかもしれない。だが、なぜ教授がこの道に入ったのかを知ることはとても大切だ。教授の生い立ちからうかがい知れること。それは、教授のバックグラウンドに宗教的、経済的な影響が少ないことだ。それはつまり、地球温暖化を指摘した教授の背景にはイデオロギーの色が薄いことを示唆している。あえて本書を教授の生い立ちから語るロバート氏の意図はそこにあるはずだ。
・教授の家族が敬虔なクリスチャンとなったこと。
・それに背を向けるようにブロッカー少年は科学への興味が勝り研究者の道を選んだこと。
・初期の研究テーマは炭素測定法による年代分析だったこと。
・この研究に踏み込んだのは偶然の出会いからだったこと。
炭素測定法の研究を通して世界各地に赴いた教授は、地球の気温の変化に着目する。それが地球が温暖化しているとの発見につながり、その事実を公表するに至る。本書は教授の研究が豊富に引用される。また、気候学者、考古気候学者など教授の研究に関する人々の研究成果やその人物像なども多彩に紹介される。
本書を読んで特に驚くこと。それは、過去の気温を類推するための手法がとても多岐にわたっていることだ。炭素測定だけではない。地層に含まれる花粉量。氷河が削り取った山肌の岩屑量。木の年輪の幅。もちろん、天文学の成果も忘れるわけにはいかない。地球が自転する軸のブレが周期的に変わること、太陽の周りを公転する軌道が歪んでいることや、太陽活動に周期があること。などなど。本書の中で言及され、積み上げられる研究成果は、本書だけでなく温暖化問題そのものへの信憑性を高める。
本書で紹介される研究成果から指摘できるのは、地球が一定の期間ごとに温暖化と寒冷化を繰り返して来た事実だ。長い周期、短い周期、中間の周期。そして、今の時期とは寒冷期と寒冷期の間なのだという。つまり、今の人類の発展とはたまたま地球が暖かいからだ、との結論が導き出される。
ならば、地球温暖化とは幻想に過ぎないのだろうか。人類の経済活動など地球にとっては取るに足りず、長期的に見ればその影響など微々たるもの。今の経済活動に一片たりとも非はない。既得権益に満ち足りていると、そういう結論に飛びつきがち。トランプ米大統領のように。
だが違う。
本書で紹介される科学者たちの研究は、そういう楽観的な早合点を一蹴する。観測結果から導き出される大気中の二酸化炭素の量は、天文単位の周期から予想される濃度を明らかに逸脱している。そしてその逸脱は産業革命以降に顕著なのだ。つまり、人類の経済活動が地球温暖化の主犯であることは動かしようもない明確な事実なのだ。
そして、海洋が二酸化炭素を吸収できる量を算出すると、あと数世紀分のゆとりがあるらしい。だが、その吸収速度は遅々としている。人類が排出する二酸化炭素を吸収するには到底追いつけないのだ。
学者たちが危惧するのは二酸化炭素の量そのものではない。むしろ気候のバランスが大幅かつ急激に崩れる可能性だ。そのバランスは二酸化炭素の割合によってかろうじて保たれている。過去の気候変動の痕跡を観察し、そこから推測できる結論とは、気候の変化が緩やかに起こったのではなく、地域によっては急激だったことだ。世界各地の神話に頻出する大洪水の伝説が示すように。例えばノアの箱舟が活躍した大洪水のような。
ある時点を境に南極の棚氷が一気に崩落する可能性。各所に残る氷河が一気に融解する可能性。そしてメキシコ湾流を起点として世界の海洋を長い期間かけて還流する大海流が突然ストップしてしまう可能性。世界の各地に残されている数々の証拠は、急激な気候変化が確実に起こっていたことを如実に示している。
今のままでは人類に残された時間はそう多くない。それが本書の結論だ。では、本書は単なる警世の書に過ぎないのだろうか。
いや、そうではない。
科学者たちは地球規模で発生しうるカタストロフィから救うため、さまざまなな可能性を研究している。本書に紹介されているのはそれらの研究の中でも温暖化抑止にとって有望と見られるアイデアだ。
アイデアのタネはシンプルなものだ。
「人間は自ら排泄したものを浄化するために下水システムを作り上げた。ならば排泄した二酸化炭素を浄化する仕組みがない現状こそがおかしい」
この原則は、私にとって目から鱗がはがれるようなインパクトをもたらした。私たちは排泄し垂れ流してきた二酸化炭素の処置についてあまりにも無関心だった。無味無臭で影も形もない二酸化炭素。それがために、何の良心の呵責を感じることなく放棄してきた。今、そのツケが人類を窮地に陥れようとしている。
教授の同僚ラックナー氏は、とあるプラスティックが二酸化炭素を有効に吸収することを発見した。あとはそれを炭酸ナトリウムで流して重曹に変化させ、そこからCO2を分離するだけだ。では、分離したCO2はどこに貯蔵するべきなのか。
一つは海洋だ。今も海洋は、 自然のプロセスの一環として二酸化炭素を吸収し続けている。このプロセスを人為的に行うのだ。深海に大量の液化二酸化炭素を注入し、海水と溶けあわせる。だが、この方法は既存の海洋生物への影響が未知数だ。
では、陸地に保存すればいいのか。CO2はカルシウムと結合して重炭酸カルシウムとなる。それはもはや固体。気体となって大気に拡散することはない。そしてカルシウムは玄武岩に豊富に含まれるという。ということは玄武岩の岩盤を深く掘り進め、地下にCO2を注入するとよいのではないか。その理論に沿って検証したところアイスランドが有力な貯蔵場所として上がっているそうだ。有効な温暖化対策としてプロジェクトは進んでいることが紹介されている。
他にも、成層圏に二酸化硫黄のガスを流すことで、太陽光線を反射して温暖化を回避する案も真面目に研究され議論されている。
このうちのどれが地球と人類と生物圏を救うことになるのか。おそらく温暖化の修復には数百年単位の時間がかかることだろう。その結末は誰にも分からない。だが、分かっているのは今、二酸化炭素の処分プロセスの対策をはじめないと、全ての人類の文明は無に帰してしまうということだ。営々と築き上げてきた建造物。世界中に張り巡らされたインターネット網。ビジネスのあらゆる成果。美しい景色。人類の文化のめざましい成果。それらがすべてうしなわれてゆく。
私たちは今、何のために生きているのだろう。家族を構え、子を育て、ビジネスに邁進する。それらの営為は、全て後世に自分の人生を伝えるためではないのか。少なくとも私にはそうだ。でなければこんなブログなど書かない。一方で刹那的にその場さえ楽しければそれでいいとの考えもあるだろう。だが、それすらもカタストロフィが起こったら叶わなくなる可能性が高いのだ。
私は情報業界の人間だ。つまり電気が断たれると飯が食えなくなる。そして、私は自然が好きだ。旅も好き。だが、旅先への移動は車や電車、飛行機だ。そのどれもが電気や燃料がないとただの重い代物。つまり私とは旅や自然が好きでありながら、電気や燃料を食い物にして自分の欲求を満たす矛盾した生き物なのだ。その矛盾を自覚していながら、即効性のある対策が打てないもどかしさに苦しんでいる。その矛盾はちまちまと電源のOn/Offを励行したからといって解消できる次元ではない。だから私はブログを書く。そして自然を紹介する。その行き着く先は、地球環境にビジネス上で貢献したいとの考えだ。
本書は、もっと世に知られるべきだ。そして、私たちは二酸化炭素の排出について意識を高めなければならない。もはや温暖化のあるなしなど議論している場合ではないのだ。本書は環境保護と経済優先の両イデオロギーの対立など眼中にないほど先を見ている。そして確固たる科学的確証のもと、データを提示し温暖化の現実を突きつける。そして突きつけるだけではなく、その解決策も提示しているのだ。
イデオロギーに毒された科学啓蒙書の類はたまに目にする。だが、本書はこれからの人類にとって真に有益な書物だと思う。少しでも多くの人の目に本書が触れることを願いたい。
‘2017/02/28-2017/03/03