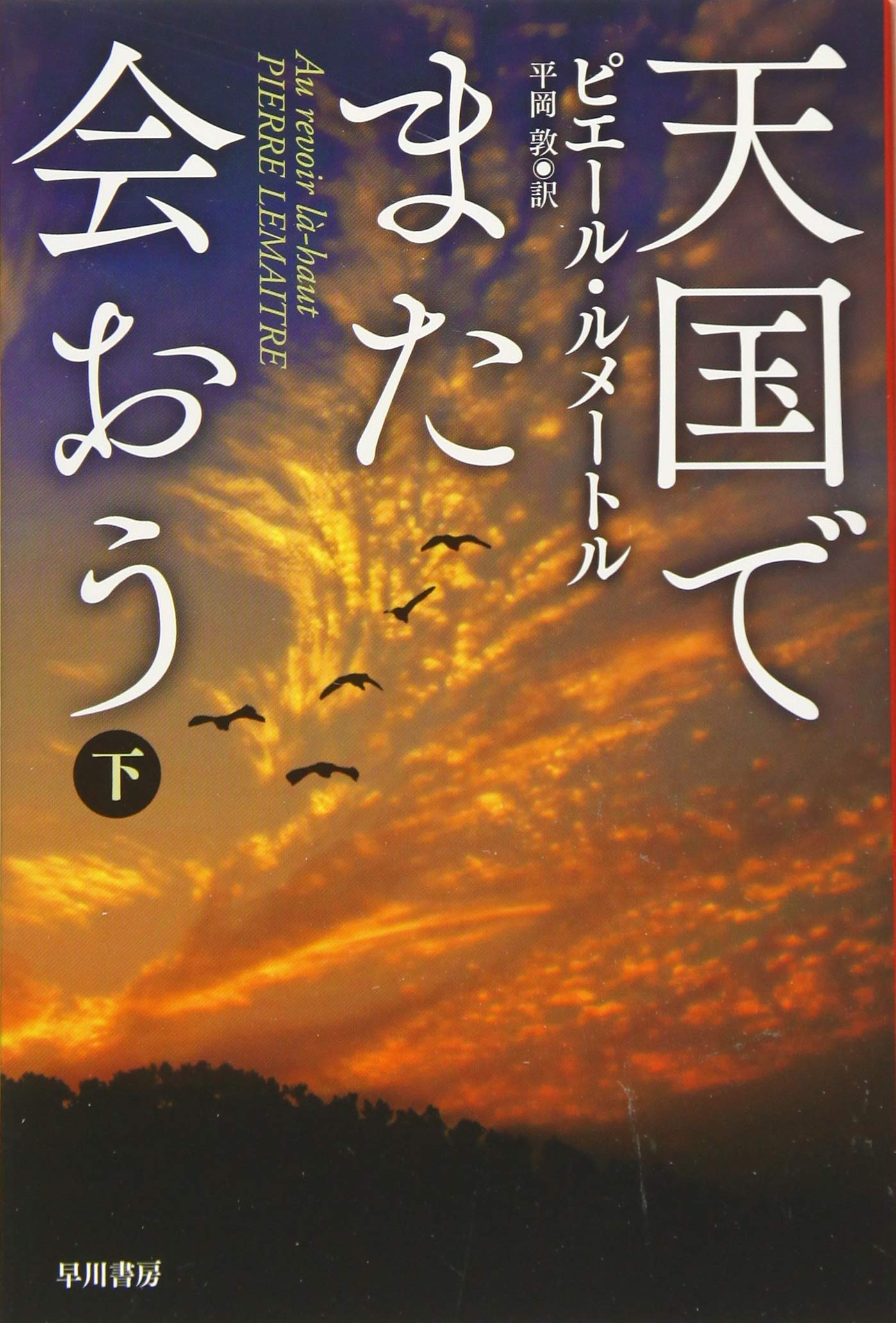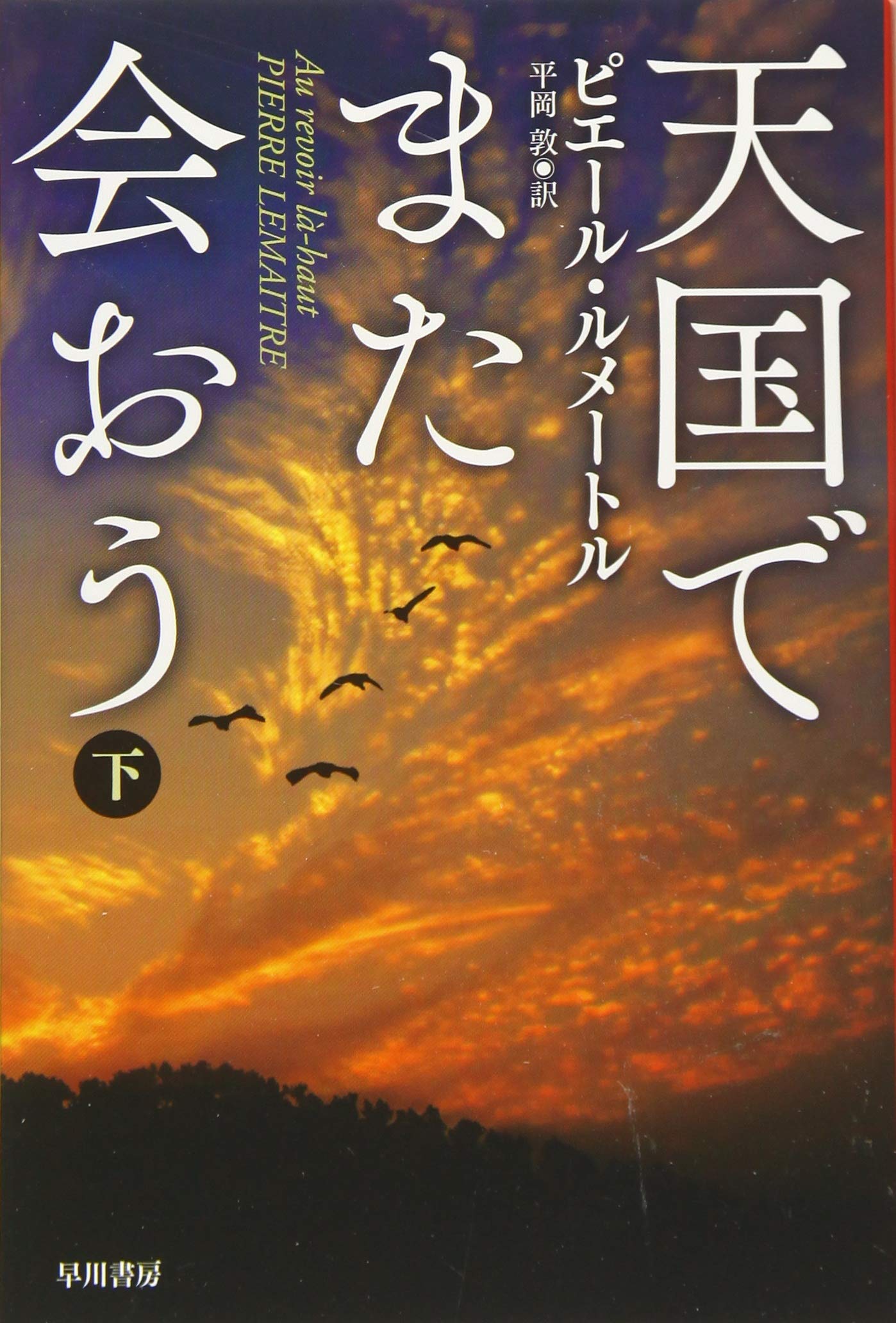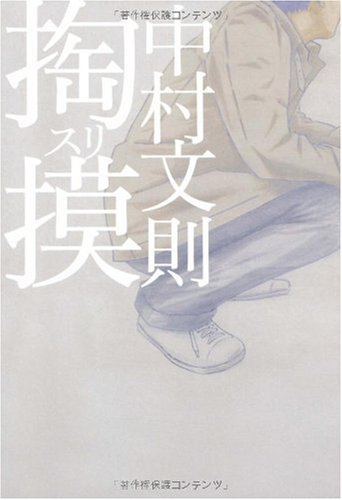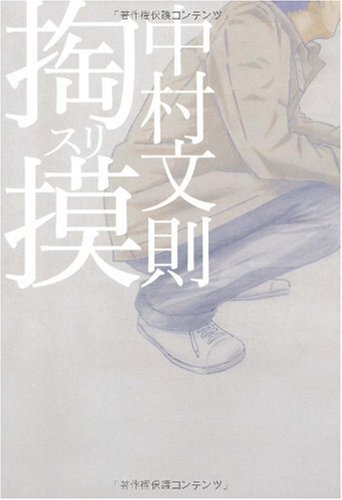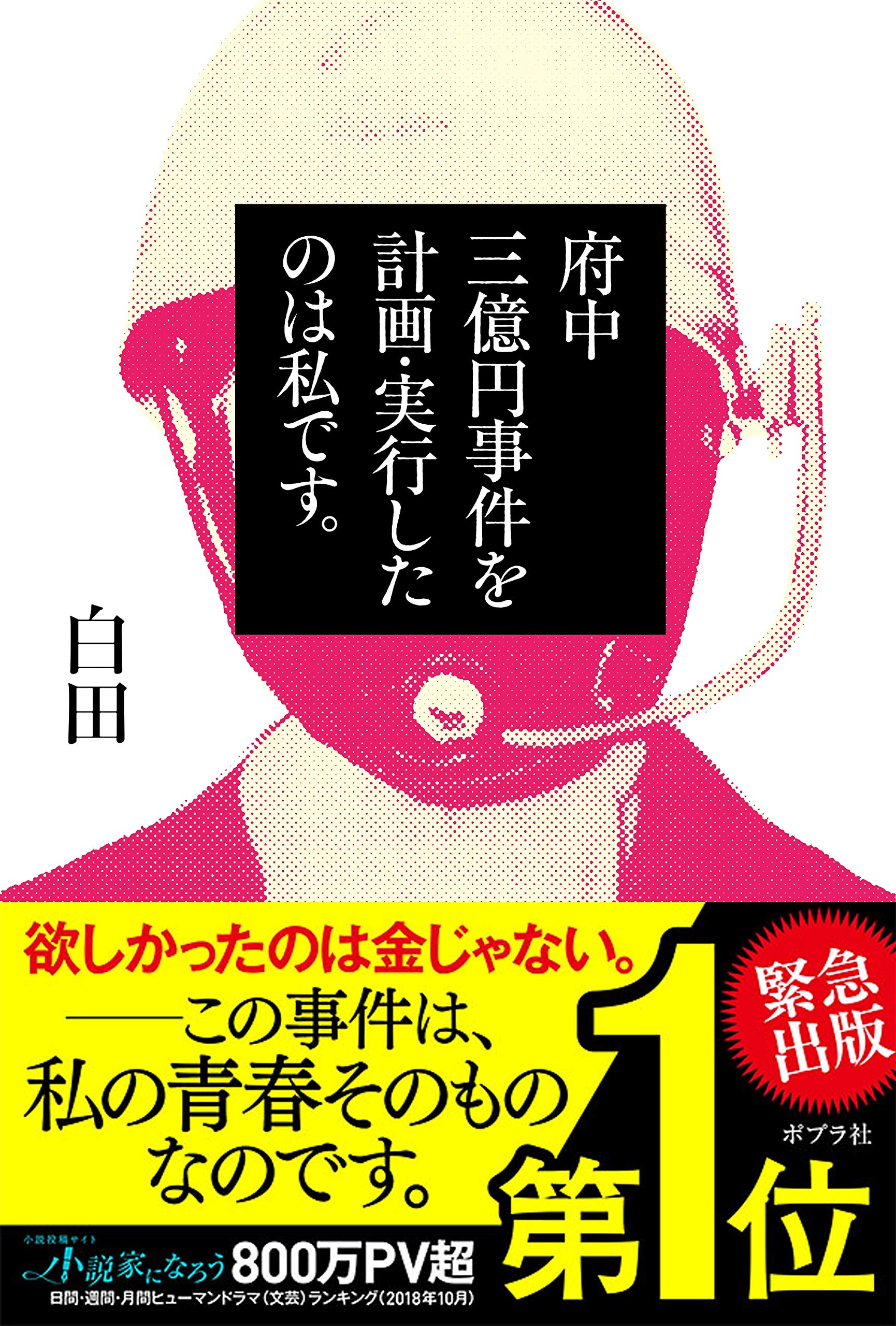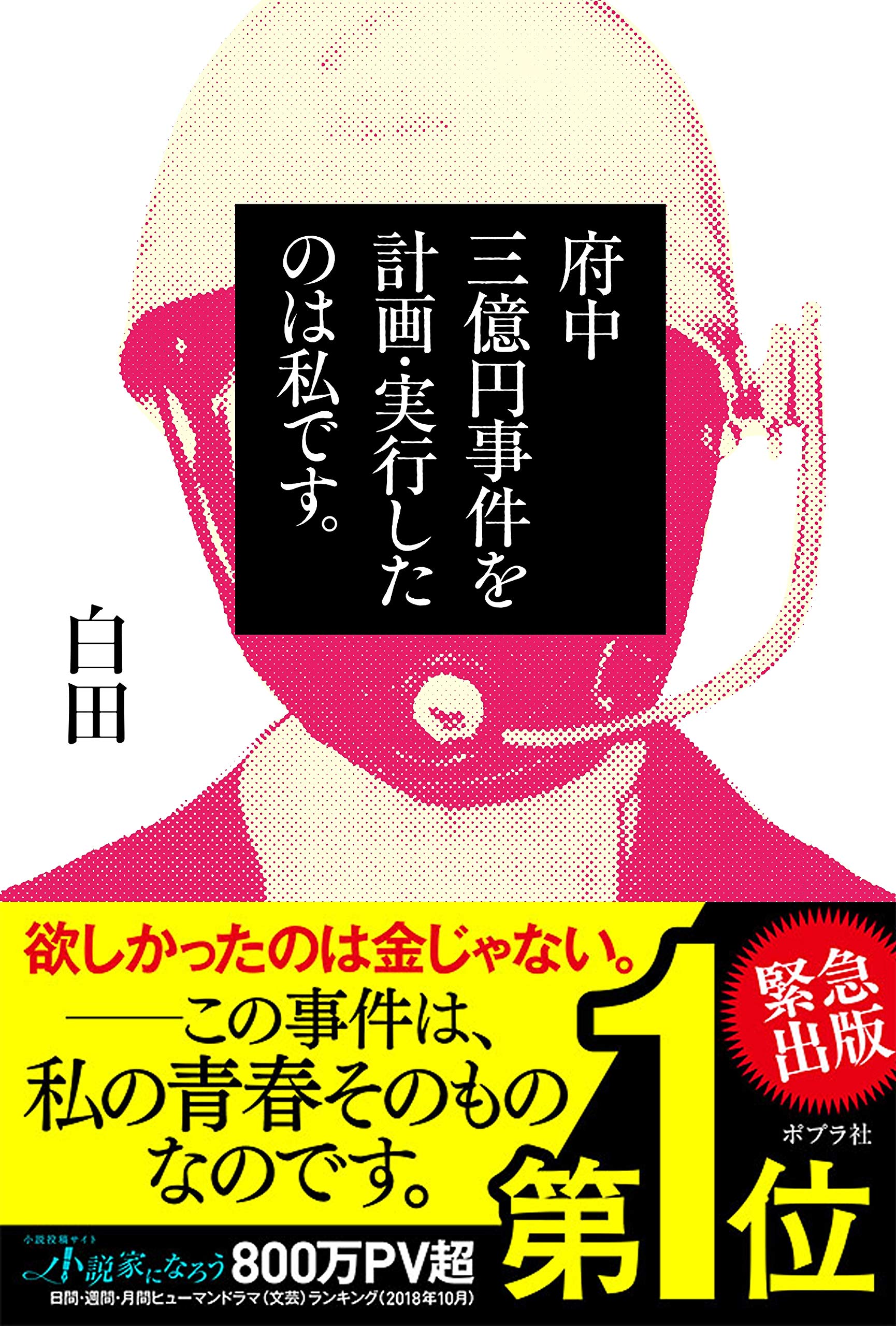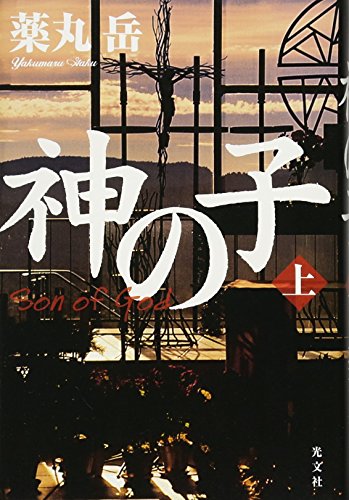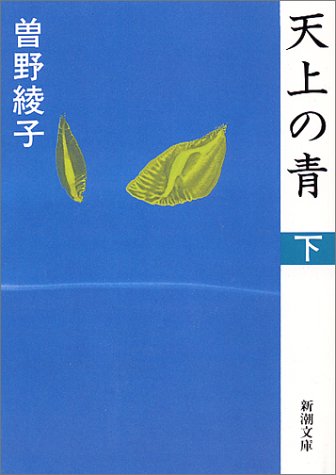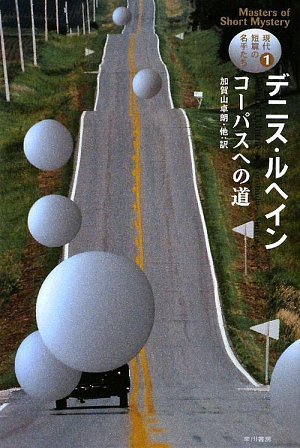本書はまた、奇抜な一冊だ。
私は今まで本書のような語り手に出会ったことがない。作家は数多く、今までに無数の小説が書かれてきたにもかかわらず、今までなどの小説も本書のような視点を持っていなかったのではないか。その事に思わず膝を打ちたくなった。
実に痛快だ。
本書の語り手は胎児。母の胎内にいる胎児が、意思と知能、そして該博な知識を操りながら、母の体内から聞こえる音やわずかな光をもとに、自らが生み出されようとしている世界に想いを馳せる。本書はそのような作品だ。
そんな「わたし」を守っている母、トゥルーディは、妊娠中でありながら深刻な問題を抱えている。夫であり「わたし」の種をまいてくれたジョンとは愛情も冷め、別居中だ。その代わり、母は夫の弟である粗野で教養のないクロードと付き合っている。
夜毎、性欲に任せて母の体内に侵入するクロード。その度に「わたし」はクロードの一物によって凌辱され、眠りを妨げられている。
そんな二人はあらぬ陰謀をたくらんでいる。それはジョンを亡き者にし、婚姻を解消すること。その狙いは兄の遺産を手中にすることにある。
だが、そんな二人の陰謀はジョンによって見抜かれる。ある日、家にやってきたジョンが同伴してきたのはエロディ。恋人なのか友人なのか、あいまいな関係の女性が現れたことにトゥルーディは逆上する。そして、衝動的にジョンを殺すことを決意する。
詩の出版社を経営し、自ら詩人としても活動しているジョン。詩人として二流に甘んじている上に、手の疥癬が悪化した事で自信を失っている。
「わたし」にとってはそのような頼りない父でも実の父だ。その父が殺されてしまう。そのような大ごとを知っているにもかかわらず、胎内にいる「わたし」には何の手も打てない。胎児という絶妙な語り手の立場こそが、本書のもっともユニークな点だ。
当然ながら、胎児が意思を持つことは普通、あり得ない。荒唐無稽な設定だと片付けることも可能だろう。
だが、本書の冒頭で曖昧に、そして巧みに「わたし」の意思の由来が語られている。
そもそも本書の内容にとって、そうした科学的な裏付けなど全く無意味である。
今までの小説は、あらゆるものを語り手としている。だから、胎児が語り手であっても全く問題ない。
むしろ、そうした語り手であるゆえの制約がこの小説を面白くしているのだから。
語り手の知能が冴えているにもかかわらず、大人の二人の愚かさが本書にユーモラスな味わいを加えている。
感情に揺さぶられ、いっときの欲情に身をまかせる。将来の展望など何も待たずに、彼らの世界は身の回りだけで閉じてしまっている。胎内で「わたし」がワインの銘柄や哲学の深遠な世界に思考を巡らせ、世界のあらゆる可能性に希望を見いだしているのに。二人の大人が狭い世界でジタバタしている愚かさ。
その対比が本書のユーモアを際立たせている。
胎児。これほどまでに、世界に希望を持った存在は稀有ではなかろうか。ましてや、「わたし」以外の胎児のほとんどは、丁重すぎる両親の保護を受け、壊れ物を扱うかのように大切に育てられているのだから。10カ月間。
ところが「わたし」の場合、夜ごとのクロードの侵入によってコツコツと子宮口を通じて頭を叩かれている。しかも、連夜の酒で酩酊する母の体の扇動や変化によって悪影響を受けつつある。そんな「わたし」でさえ、母を信頼し、ひと目会いたいと願い、世の中が良かれと希望を失わずにいる。
胎内で育まれた希望に比べ、現実の世の中のでたらめさと言ったら!
私たちのほとんどは、外の世界に出された後、世俗の垢にまみれ、世間の悪い風に染まっていく。
かつては胎内であれほど希望に満ちた誕生の瞬間を待っていたはずなのに。
その現実に、私たちは苦笑いを浮かべるしかない。
私も娘たちが生まれる前、胎内からのメッセージを受け取ったことがある。おなかを蹴る足の躍動として。
それは、胎内と外界をつなぐ希望のコミュニケーションであり、若い親だった私にとっては、不安と希望に満ちた誕生の兆しでしかなかった。
だが、よく考え直すと、実はあの足蹴には深い娘の意思がこもっていたのではなかったか。
そして、私たちは誕生だけでなく、その前の受胎や胎内で育まれる生命の奇跡に対し、世俗のイベントの一つとして冷淡に対応していないか。
いや、その当時は確かにその奇跡におののいていた。だが、娘が子を産める年まで育った今、その奇跡の本質を忘れてはいないか。
本書の卓抜な視点と語り手の意思からはそのような気づきが得られる。
本書のクライマックスでは誕生の瞬間が描かれる。不慣れな男女が処置を行う。
その生々しいシーンの描写は、かつて著者が得意としていた作風をほうふつとさせる。だが、グロテスクさが優っていた当時の作品に比べ、本書の誕生シーンには無限の優しさと、世界の美しさが感じられる。
トゥルーディとクロードのたくらみの行方はどうなっていくのか。壮大な喜劇と悲劇の要素を孕みながら、本書はクライマックスへと進む。
親子三人の運命にもかかわらず、「わたし」が初めて母の顔を見たシーンは、本書の肝である。世界は赤子にとってかくも美しく、そしてかくも残酷なものなのだ。
著者の作品はほぼ読んでいるし、本書を読む数カ月前にもTwitter上で著者のファンの方と交流したばかり。
本書のようなユニークで面白く、気づきにもなる作品を前にすると、これからの著者の作品も楽しみでならない。
本書はお薦めだ。
‘2020/07/03-2020/07/10