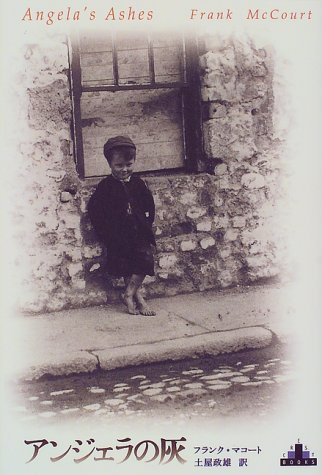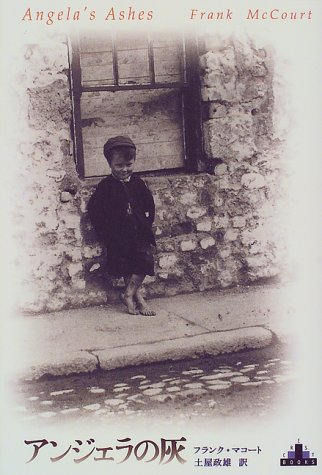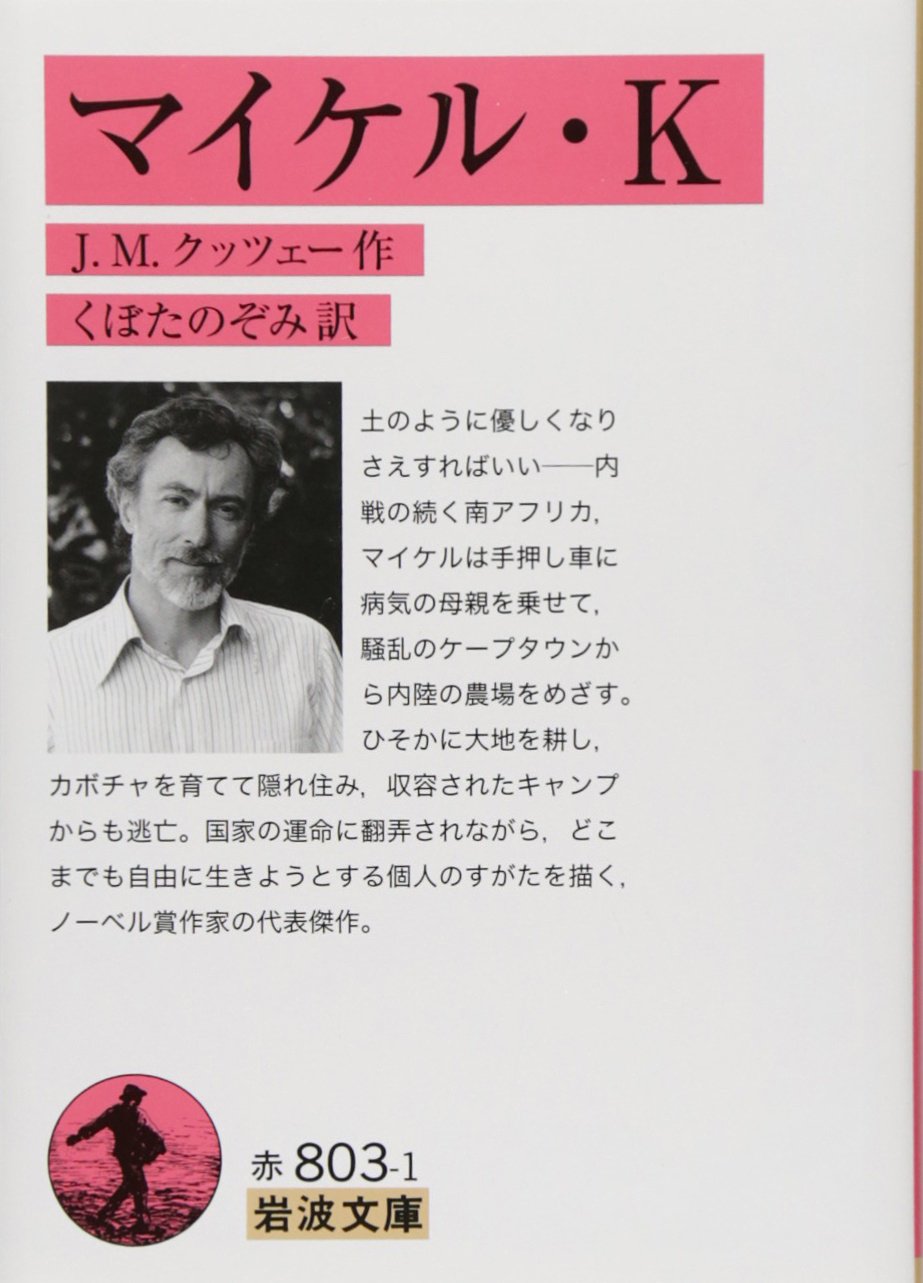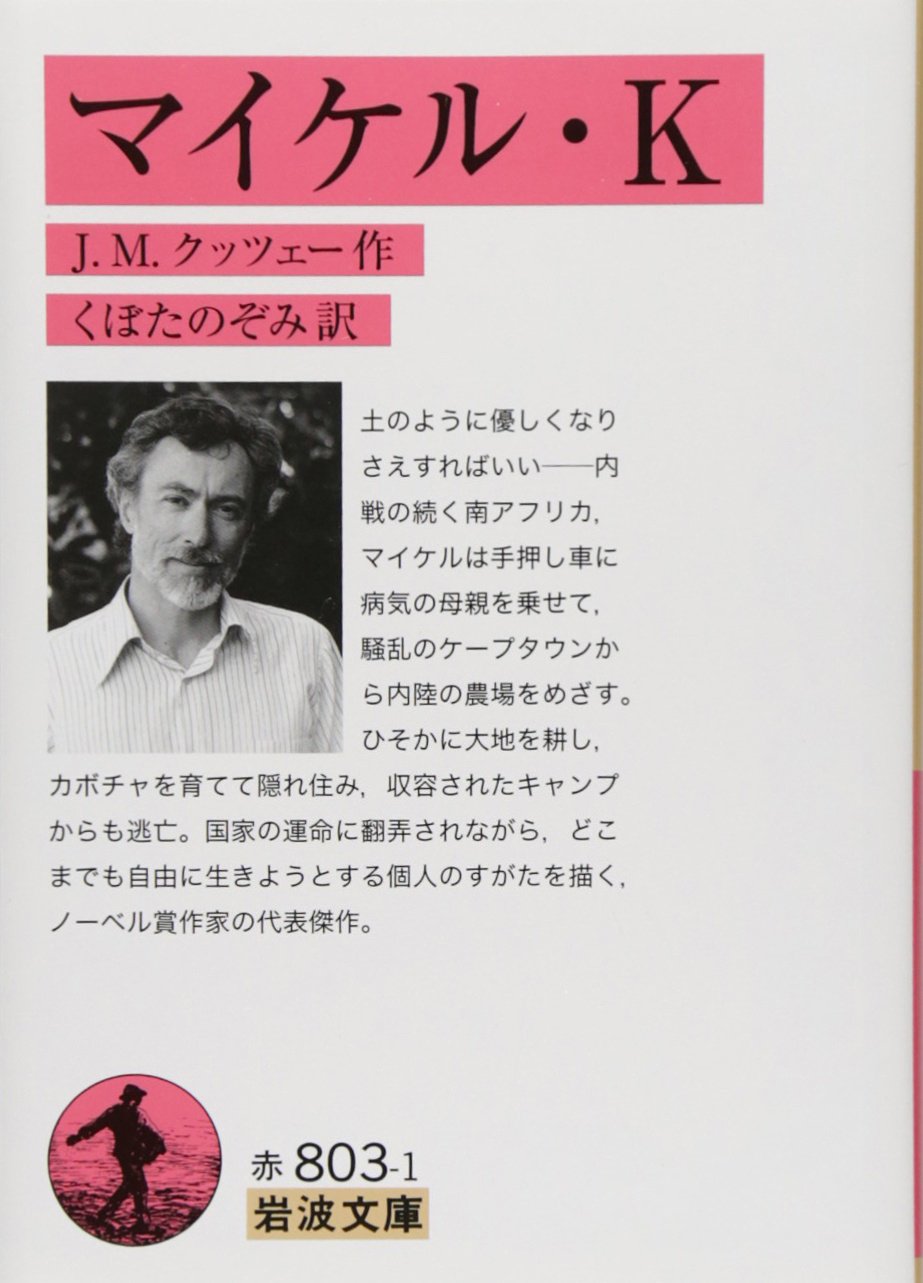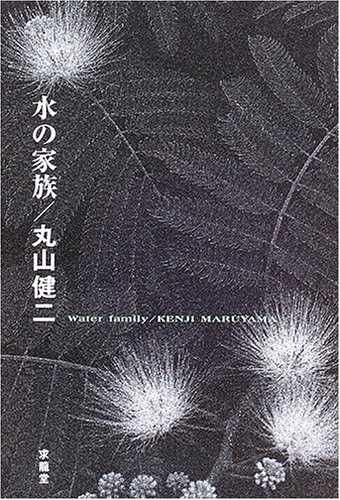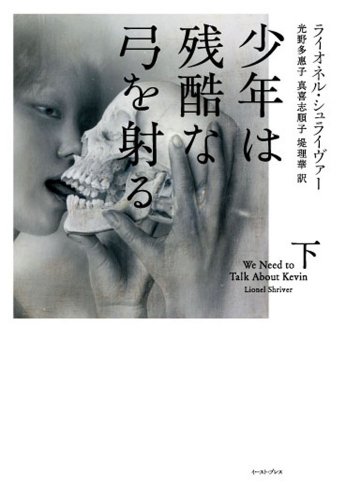実は本作の存在を知ったのは、劇場に入る数時間前のことだ。
それまで、本作を見に行く予定どころか、映画館に行くつもりすらなかった。
ぶっつけ本番で見た本作だが、とても面白かった。
それは、旅が好きで神社によく参拝する私の嗜好に合っていたからだと思う。
本作はロードムービーとしても楽しめる。
東京の日常を脱し、各地の神社を巡って出雲へと至る旅。それを思うだけでも気分は高揚する。さらに、神具の勾玉の力によって、普通の人間に比べて何十倍も早く動けるなんて羨ましすぎる。その設定だけで悶えてしまう。
コロナで移動が制限されている今、本作は私の心を旅へと、出雲へと駆り立ててくれた。
以下はネタバレが含まれています。
そもそもなぜ本作を見ようと思ったか。それは昨晩、私のTwitterに届いた画家さんについて詳しく知りたいというメンションに始まる。
そのメンションをきっかけに、私は25年前と2年前に訪れた出雲にまた行きたくなった。
メンションをくださった方は、私が25年前に日御碕灯台の前で出会った占いをする画家さんについて触れた2年前の出雲旅のブログを読まれたのだろう。ところが、私もその画家さんの詳細は詳しく知らない。
今回のメンションをきっかけに、まだお元気だというこの画家さんのことを知りたいと思った。
出雲にまた行きたい、と妻に言ったところ、妻も出雲に行きたい、と。その流れで、妻が興味を持っていた本作を見に行こうと決まった。
一緒に観に行った長女が、本作に出てくる某声優さんのファン(恵比寿様)だったことも本作の観劇を後押ししてくれた。
母を病でなくしてしまった主人公の葉山カンナ。幼い頃からカンナと一緒に走り、走ることの喜びを教えてくれた母の死を悲しむあまり、小学校で走る行事にも消極的でやる気が出ない。そればかりか、作り笑いでその場をやり過ごそうとする卑屈な女の子になってしまった。
一年が過ぎ、母が倒れたマラソン大会がやってきた。だが、カンナは走ることに真剣になれないまま、声をかけてくれた父のもとを走り去ってしまう。
たどり着いたのが家と学校の間にある牛島神社。ここで母の形見の勾玉を身に着けたところ、時間が止まる。さらに巨大な牛と人の言葉を操る白兎が目の前に現れる。
白兎のシロから聞いたのが、母弥生が韋駄天の末裔だったこと。
母が毎年十月に出雲大社で催される神在祭に、各地の馳走を運んでいたこと。
今年は今日の夜の7時から始まるため、それまでに各地を巡って馳走を集め、それを出雲に持っていかなければならないこと。間に合わない場合、来年度の神議りに差しさわりがあること。
縁結びの神である大国主命の力があれば、あの世にいる母と再び合わせてくれるかも!そう思ったカンナは勇躍して出雲へと走る。
だが、かつて韋駄天に敗れ、鬼になった一族の末裔である夜叉がカンナとシロから勾玉と馳走を奪う。かつて一族が被った恥辱をすすぎ、韋駄天の座に返り咲こうとする夜叉。
だが、やがて走ることに共通の喜びを感じているカンナと夜叉の間には絆が生まれ、夜叉も一緒に出雲まで同行する約束を交わす。
夜の7時までとはいえ、それは人間の尺度での時間。実際はその何十倍のスピードで動ける。各地の神社を巡り、その神社の祭神から賜った馳走を集めながら、出雲へと向かう。
その道のりがとても面白い。作中で確認しただけでも牛島神社から愛宕神社、さらに蛇窪神社が登場する。さらに鴻神社に移動する。そして神流川に向かう。
諏訪大社から奈良井宿、須賀神社から元伊勢神社、白兎神社、美保神社とたどっていく。
馳走を集めるにはこのルートが最短なのだろうけど、今までに聞いたことのないルートだ。
妻は本作に出てきた神社の多くを訪れたことがあるそうだ。だが、私は基点の牛島神社すら参拝したことがない。私が参拝したことがあるのは愛宕神社、諏訪大社、元伊勢神社、出雲大社くらい。
私にまだ参拝していない神社を教えてくれたのも本作の効能だ。神社の魅力とは、由緒書や境内の佇まいや本殿などの意匠だけでなく他にもあるはず。本作を見ていると神社についての知識をより深く知りたくなる。
本作の効能は他にもある。本作は子どもにも向けてメッセージを発している。それはあきらめない心だ。そして、自分の好きなことを信じる力。その気持ちを失わないことも本作のキーメッセージだ。
さらに、今の世の中は神社や神々のような人と人とを結びつける存在が忘れ去られようとしている。その結果、人の心から思いやりが失われ、イライラやと人をひがんだりねたんだりする感情が人の心を病ませている。本作にも黒く湧き上がる禍々しい気が描かれる。カンナの心やせわしない街の人々からも。
私も旅をして各地の神社を巡り、その清新で厳粛な境内から気を受け取りたい。ともすれば消耗する日常からわが身を守るためにも。
コロナで苦しんだからこそ、本作が伝えるメッセージは皆さんに届くはずだ。
それとともに、早くコロナが完全に収まり、人々が再び気を遣わずに旅ができる時代になることも願う。
なお、最後に少しだけ疑問が生じたことも書いておく。
それは、夜の7時までに出雲大社に馳走を届けなければならないのに、なぜ日の落ちた海岸でのんびり横になって休んでいるのだろう。そんなささいな疑問が頭から離れなかった。
もう一つ、これは制作の皆さんやスタッフの皆さんのせいではないはずだが、本作で描かれた大国主命から、なぜか某宗教法人の啓発アニメーションの世界を感じてしまった。見たこともないのに。なぜだろう。神谷明さんが話しているにもかかわらず。
それと、古代の出雲大社本殿って、神々が食事をする場所なんだろうか。これもふと疑問に思った。神議りならまだ分かるのだが。
でも、それも私の知識が不足しているだけかもしれない。まずは日本書記や古事記に触れ、知識を蓄えたいと思う。
‘2021/10/10 イオンシネマ多摩センター