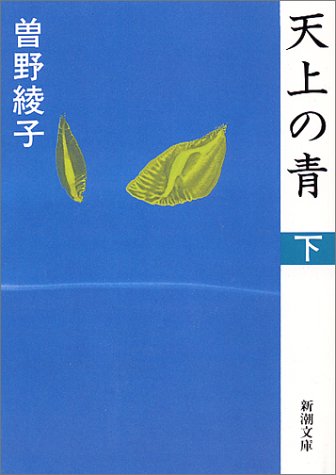二〇二〇年は東京オリンピックの年だ。だが、私はもともと東京オリンピックには反対だった。
日本でオリンピックが開かれるのはいい。だが、なんで東京やねん。一度やったからもうええやないか。また東京でやったら、ますます東京にあらゆるものが集中してまう。地方創生も何もあったもんやない。なんで大阪、名古屋、仙台、福岡、広島あたりに誘致せえへんねん。それが私の思いだ。今もその思いは変わらないし、間違っていないと思っている。
とはいえ、すでに誘致はなった。今さら私が吠え猛ったところで東京で二度目のオリンピックが開催される事実は覆らない。ならば成功を願うのみ。協力できればしたい。開催が衰退する日本が最後に見せた輝きではなく、世界における日本の地位を確たるものにした証であることを願っている。
そのためには前回、一九六四年の大会を振り返りたい。市川昆監督による記録映画もみるべきだが(私は抜粋でしか見ていない)、本書も参考になるはずだ。
本書の表紙に執筆者のリストが載っている。東京オリンピックが行われた当時の一流作家のほとんどが出ていると言って良い。当時の一流の作家による、さまざまな媒体に発表された随筆。本書に収められているのはそうした文章だ。当時発表された全てのオリンピックに関する文章が本書に網羅されているかどうかは知らない。だが、本書に登場する作家がそうそうたる顔ぶれであることは間違いない。
本書が面白いのは、イデオロギーの違いを超えて収録されていることだ。右や左といった区分けが雑なことを承知でいうと、本書において右寄りの思想を持つ作家として知られるのは、石原慎太郎氏と三島由紀夫氏と曾野綾子氏だ。左寄りだと大江健三郎氏と小田実氏が挙げられるだろう。それぞれが各自の考えを記していてとても興味深い。
本書は、大きく四つの章にわけられている。その四つとは「開会式」「競技」「閉会式」「随想」だ。それぞれの文章は書かれた時期によって章に振り分けられたのではなく、取り扱う内容によって編者が分類し、編んでいるようだ。
「開会式」の項に書かれた内容で目立つのは、日本がここまでの大会を開けるようになった事への賛嘆だ。執筆者の多くは戦争を戦地、または銃後で体験している。だから戦争の悲惨さや敗戦後の廃虚を肌で感じている。そうした方々は、再建された日本に世界の人々が集ってくれた事実を素直に喜び、感動を表している。
中でも印象に残ったのは杉本苑子氏の文章だ。東京オリンピックから遡ること二十一年前、開会式が催された同じ場所で学徒出陣壮行会が行われた。雨の中、戦地に送られる学徒が陸上競技場を更新する写真は私にも記憶がある。東條首相が訓示を述べる写真とともに。杉本氏はその現場の寒々とした記憶と、この度の晴れやかな開会式を比べている。そこには戦時とその後の復興を知る方の思いがあふれている。現代の私たちには学徒出陣壮行会など、教科書の中の一ページ。だが、当時を知る方にはまぎれもない体験の一コマなのだ。
他の方の文章でも開会式のプログラムが逐一紹介されている。事細かにそれぞれの国の行進の様子を報告してくれる方の多いこと。行進の態度から、お国柄を類推したいかのように。日本にこれだけの地域、民族、国の人々が集まることだけで感無量であり、世界の国に日本が晴れがましい姿を示すことへの素朴な感嘆なのだろう。戦争中は国際社会から村八分に近い扱いを受けていた。その時期の日本を知っていればいるほど、これほど大勢の人々が日本に集まる事だけで、日本が再び世界に受け入れられたと喜べる。それはすなわち、日本の復興の証でもあるのだから。そうした喜びは戦時中を知らない私にんも理解できる。
ただ、文学者のさがなのか、批評精神は忘れていない。例えば直前で大会への参加を拒否された北朝鮮とインドネシアへの同情。南北ベトナムの両チームが参加しない件。台湾が参加し、中華人民共和国が不参加なことなど。世界がまだ一つになりきれていない現状を憂う指摘が散見される。まさに時代を映していて興味深い。
ここで私が違和感を覚えたのは、先に左寄りだと指摘した大江健三郎氏と小田実氏の文章だ。小田氏の論調は、前日まで降っていた雨が開会式当日に晴れ渡った事について、複雑な思いを隠していない。それは、政治のイデオロギーを持ち出すことで、開会式当日の晴れ姿を打ち消そうとする思惑にも感じる。大江氏の文章にも歯にものが挟まったような印象を受けた。あと、開会式で一番最後に聖火を受け取り、聖火台へ向かう最終聖火ランナーの方は、昭和二十年の八月六日に産まれた方だった。そのことに象徴的な意味を感じ、文に著したのは数いる著者の中で大江氏のみであり、「ヒロシマ・ノート」を書いた大江氏がゆえの視点として貴重だったと思う。
開会式については総勢14名の作家の著した文が収められていた。この時点ですでに多種多様な視点と論点が混じっていて面白かった。
もう一つ、私が印象を受けたのは三島由紀夫氏の文章だ。引用してみる。
「ここには、日本の青春の簡素なさわやかさが結晶し、彼の肢体には、権力のほてい腹や、金権のはげ頭が、どんなに逆立ちしても及ばぬところの、みずみずしい若さによる日本支配の威が見られた。この数分間だけでも、全日本は青春によって代表されたのだった。そしてそれは数分間がいいところであり、三十分もつづけば、すでにその支配は汚れる。青春というのは、まったく瞬間のこういう無垢の勝利にかかっていることを、ギリシャ人は知っていたのである。」(32ページ)。
「そこは人間世界で一番高い場所で、ヒマラヤよりもっと高いのだ。」(32ページ)。
「彼が右手に聖火を高くかかげたとき、その白煙に巻かれた胸の日の丸は、おそらくだれの目にもしみたと思うが、こういう感情は誇張せずに、そのままそっとしておけばいいことだ。日の丸とその色と形が、なにかある特別な瞬間に、われわれの心になにかを呼びさましても、それについて叫びだしたり、演説したりする必要はなにもない。」(32-33ページ)。
続いては「競技」だ。東京オリンピックについて私たちの記憶に残されているのは、重量上げの三宅選手の勝利であり、アベベ選手の独走であり、円谷船主の健闘であり、東洋の魔女の活躍であり、柔道無差別級の敗北だ。もちろん、他にも競技はたくさん行われていた。本書にもボクシング、レスリング、陸上、水泳、体操が採り上げられている。
意外なことに、論調の多くは日本の健闘ではなく不振を指摘している。後世の私たちから見れば、東京オリンピックとは日本が大量のメダルを獲得した最初の大会として記憶に残っている。だが、当時の方々の目からみれば、自国開催なのに選手が負けることを歯がゆく思ったのではないか。特に、水泳と陸上の不振を嘆く声が目立った。それは、かつて両競技が日本のお家芸だったこととも無関係ではない。
そうした不振を嘆く論調が石原慎太郎氏の文から色濃く出ていたのが面白かった。
そして、ここでも三島由紀夫氏の文章がもっとも印象に残る。あの流麗な比喩と、修辞の限りを尽くした文体は本書の中でも一頭抜け出ている。本書を通した全体で、小説家の余技ではなく本気で書いていると思えたのは三島氏の文章のみだった。「競技」の章ではのべ四十一編が掲載されているのだが、そのうち九編が三島氏によるものだ。
やはり、競技こそが東京オリンピックの本分。そんな訳で「競技」の章には多くの作家が文章をしたためている。
続いての「閉会式」では、六編の文章が載っている。著者たちは総じて、東京オリンピックには成功や感動を素直に表明されていた。むしろ、オリンピックの外に漂っていた国際政治のきな臭い空気と、オリンピック精神の矛盾を指摘する方が多いように思えた。
興味深く読んだのは石原慎太郎氏の文だ。後の世の私たちは知っている。石原氏が後年、東京都知事になり、二度目の東京オリンピック招致に大きな役割を果たすことを。だが、ここではそんな思いはみじんも書かれていない。そのかわり、日本がもっと強くあらねばならないことを氏は訴えている。石原氏の脳裏にはこの時に受けた感動がずっと残り続けていたのだろう。だから二〇二〇年のオリンピック招致活動に乗り出した。もし石原氏が福岡県知事になっていたら福岡にオリンピックを持ってきてくれたのだろうか。これは興味深い。
続いては「随想」だ。この章ではオリンピック全体に対しての随想が三〇編収められている。
それぞれの論者がさまざまな視点からオリンピックに対する思いを吐露している。オリンピック一つに対しても多様な切り口で描けることに感心する。例えば曽野綾子氏は選手村の女子の宿舎に潜入し、ルポルタージュを書いている。とりたてて何かを訴える意図もなさそうなのんびりした論調。だが、各国から来た女性の選手たちの自由で溌溂とした様子が、まだ発展途上にあった我が国の女性解放を暗に訴えているように思えた。
また、ナショナリズムからの自由を訴えている文章も散見された。代表的なのは奥野健男氏の文章だ。引用してみる。
「だがオリンピックの開会式の入場行進が始まると、ぼくたちの心は素直に感動した。それは日本人だけ立派であれと言うのではなく、かつてない豊かさ、たのしさを持って、各民族よ立派であれという気持ちであった。インターナショナリズムの中で、ナショナリズムを公平に客観的に感じうる場所に、いつのまにか日本人は達していたらしい。それはゆえない民族的人種的劣等感からの、そして逆投影からの解放である。
ぼくはこれだけが敗戦そして戦後の体験を経て、日本民族が獲得し得た最大のチエではないかと思う。負けることに平気になった民族、自分の民族を世界の中で客観的にひとつの単位として見ることができるようになった民族は立派である。いつもなら大勢に異をたてるヘソ曲がりの文学者たちが、意外に素直に今度のオリンピックを肯定し、たたえているのも、そういう日本人に対する安心感からであろうか。」(262-263ページ)
この文章は本書の要約にもなりえると思う。
あと目についたのは、アマチュアリズムとオリンピックを絡めた考察だ。村松剛氏の文章が代表的だった。すでにこの時期からオリンピックに対してアマチュアリズムの危機が指摘されていたとは。当時はまだ商業主義との批判もなければ、プロの選手のオリンピック参加などの問題が起きていなかった時期だったように思うが、それは私の勉強が足りていないのだろう。不明を恥じたい。
また、日本の生活にオリンピックがもたらした影響を指摘する声も目立った。オリンピックの前に間に合わせるように首都高速や新幹線が開通したことはよく知られている。おそらくその過程では日に夜を継いでのモーレツな工事が行われたはずだ。そして国民の生活にも多大な影響があたえたことだろう。それゆえ、オリンピックに対する批判も多かった。そのことは本書の多くの文章から感じられた。中でも中野好夫氏は、オリンピック期間中、郊外に脱出する決断を下した。そして連日のオリンピックをテレビ観戦のみで済ませたという。それもまた、一つの考え方だし実践だろう。中野氏はスポーツそのものは称賛するが、その周囲にあるものが我慢できなかったのだとか。中野氏のように徹底した傍観の立場でオリンピックに携わった方がいた事実も、本書から学ぶことができる。オリンピックに対して疑問の声が上がっていたことも、オリンピックが成功裏に終わり、日本の誉めたたえられるべき歴史に加えられている今ではなかなかお目にかかれない意見だ。
私も二〇二〇年のオリンピック期間中は協力したいと書いたものの、中野氏のような衝動に駆られないとも限らない。
私が本章でもっとも印象に残ったのは石原慎太郎氏による文だ。石原氏の文は「随想」の章には三編が収められている。引用してみる。
「参加することに意味があるのは、開会式においてのみである。翌日から始まる勝負には勝たねばならぬ。償いを求めてではない。ただ敗れぬために勝たねばならぬ。
人生もまた同じではないか。われわれがこの世にある限り、われわれはすでに参加しているのだ。あとはただ、勝つこと。何の栄誉のためにではなく、おのれ自身を証し、とらえ直すためにわれわれは、それぞれの「個性的人生」という競技に努力し、ぜひとも勝たねばならぬのである。」10/25 読売新聞 ( 320-321ページ )
この文には感銘を受けた。オリンピックに限らず人生を生きる上で名言と言える。
二〇二〇年の東京オリンピックを迎えた私たちが本書を読み、じかに役立てられるかはわからない。だが、当時の日本の考えを知る上ではとても参考になると思う。また、当時の生活感覚を知る上では役に立たないが、日本人として過ごす心構えはえられると思う。それは私たちが二〇〇二年の日韓ワールドカップを経験したとき、世界中から観光客を迎えた時の感覚を思い出せばよい。本書に収められた文章を読んでいて、二〇〇二年当時の生活感覚を思い出した。当時はまだSNSも黎明期で、人々はあまりデータを公共の場にアップしていない。二〇〇二年の感覚を思い出すためには、こうした文書からそれぞれが体験を書いてみるのも一興だと思う。
それよりもむしろ、本書は日本人としての歴史観を養う上で第一級の資料ではないかと思う。二〇二〇年の大会では、一九六四年の時とは比べ物にならないほど大量の文章がネット上に発表されるはず。その時、どういう考察が発表されるのか。しかも素人の作家による文章が。それらを本書と比べ、六〇年近い時の変化が日本をどう変えたか眺めてみるのも面白いかもしれない。
‘2018/04/27-2018/04/29