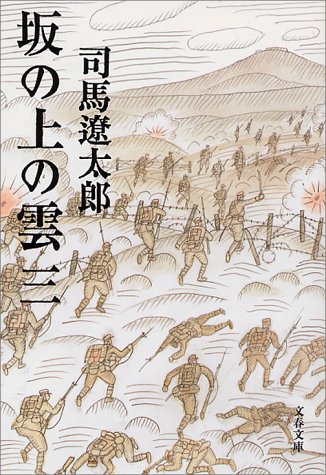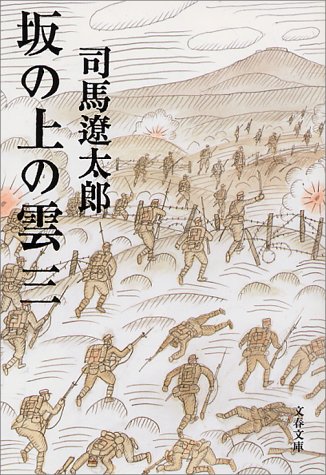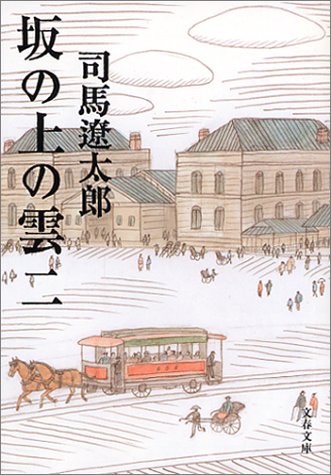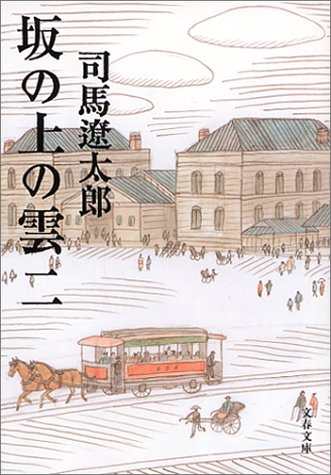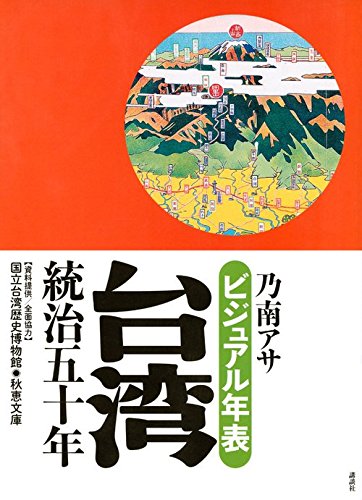
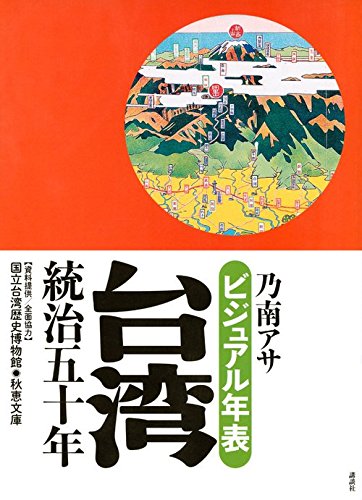
はじめ、著者の名前と台湾が全く結びつかなかった。
エンターテインメントの小説家として名高い著者が台湾にどのように関係するのか。
そのいきさつについては、あとがきで国立台湾歴史博物館前館長の呂理政氏が書いてくださっている。
それによると、2013年の夏に日本台湾文化経済交流機構が台湾を訪れたが、著者はその一員として来台したという。
著者はその縁で、もともと興味を持っていた台湾の歴史を描こうと思ったそうだ。
本書の前に読んだ「日本統治下の台湾」のレビューにも書いたが、私ははじめて台湾を訪れたとき、人々の温かさに感動した。そして、台湾と日本の関係について関心を持った。
著者もおそらく同じ感慨を抱いたに違いない。
はじめに、で著者はベリーの来航から90年間で、日本がくぐり抜けた歴史の浮き沈みの激しさを描く。
そして著者は、その時期の大部分は、日本が台湾を統治していた時期に重なっていることを指摘する。つまり、当時の台湾にはかつての日本が過ごした歴史が残っている可能性があるのだ。
本書はビジュアル年表と言うだけあって、豊富な図面とイラストが載っている。
それは、国立台湾歴史博物館と秋惠文庫の協力があったからだそうだ。
それに基づき、著者は台湾の統治の歴史を詳細に描く。歴代の台湾総督の事歴や、領有に当たっての苦労や、日本本土との関係など。
本書は、資料としても活用できるほど、その記述は深く詳しい。そして、その視点は中立である。
台湾にもくみしていないし、日本を正当化してもいない。
ただ、一つだけ言えるとすれば、日本は統治した以上は整備に配慮を払っていたことだ。
本書にも詳しく載っているが、図面による台湾の街の様子や地図の線路の進展などは、五十年の間に次々と変わっていった。それはつまり、日本の統治によりインフラが整備されていったことを表している。
特に有名なのは八田氏による烏山頭ダムの整備だ。そうした在野の人物たちによる苦労や努力は否定してはならないと思う。
歴代総督の統治の意識によっても善し悪しがあることは踏まえた上で。
特に児玉源太郎総督とその懐刀だった後藤新平のコンビは、一時期はフランスに売却しようかとすら言われていた台湾を飛躍的に発展させた。
日本による統治のすべてをくくって非難するより、その時期の国際情勢その他によって日本の統治の判断は行われるべきではないだろうか。
そうした統治の歴史は、本書の前に読んだ「日本統治下の台湾」にも描かれていた。が、本書の方が歴史としての記述も資料としての記述も多い。
私はまだ、三回の台湾訪問の中で台湾歴史博物館には訪れたことがない。初めての台湾旅行では故宮博物院を訪れたが、あくまでも中国四千年の歴史を陳列した場所だ。
台湾の歴史を語る上で、私の知識は貧弱で頼りないと自覚している。だから、本書の詳細な資料と記事はとても参考になった。
特に本書に詳しく描かれている当初は蛮族と呼ばれた高砂族の暮らしや、蛮行をなした歴史についてはほとんどを知らなかった。
高砂族を掃討する作戦については、本書に詳しく描かれている。それだけでなく、当時の劣悪な病が蔓延していた様子や、高砂族の人が亡くなった通夜会場の様子なども。本書は台湾の歴史だけではなく、先住民族である高砂族の文化にも詳しく触れていることも素晴らしい。
おそらく私が最初の台湾旅行で訪れた太魯閣も、かつては高砂族が盤踞し、旅行どころか命の危険すらあった地域だったはずだ。
そうした馴化しない高砂族の人々をどうやって鎮圧していったのかといういきさつ。さらには、男女の生活の様子や、差別に満ちた島をデモクラシーの進展がどう変えていったのか。
皇太子時代の昭和天皇の訪問が台湾をどう親日へと変えていったのか。本書の記述は台湾の歴史をかなりカバーしており、参考になる。
また、本書は日本の歴史の進展にも触れている。日本の歴史に起こった出来事が台湾にどのように影響を与えたのかについても、詳しく資料として記していることも本書の長所だ。
皇民化政策は、この時期の台湾を語るには欠かせない。どうやって高砂族をはじめとした台湾の人々に日本語を学ばせ、人々を親日にしていったのか。
八紘一宇を謳った割に、今でも一部の国からは当時のふるまいを非難される日本。
そんなわが国が、唯一成功したといえる植民地が台湾であることは、異論がないと思う。
だからこそ、本書に載っている歴史の数々の出来事は、これからの日本のアジアにおける地位を考える上でとても興味深い。それどころか、日本の来し方とこれからの国際社会でのふるまい方を考える上でも参考になる。
本書はまた、太平洋戦争で日本が敗れた後の台湾についても、少しだけだが触れている。
日本が台湾島から撤退するのと引き換えに国民党から派遣されてやってきた陳儀。台湾の行政担当である彼による拙劣かつ悪辣な統治が、当時の台湾人にどれほどのダメージを与えたのか。
そんな混乱の中、日本人が台湾での資産をあきらめ、無一文で日本に撤退していった様子など。
国民党がどのようにして台湾にやってきて、どのような悲惨な統治を行ったか。本書の国民党に対する記述は辛辣だ。そして、おそらくそれは事実なのだろう。
台北の中正紀念堂で礼賛されているような蒋介石の英雄譚とは逆に、当初の国民党による統治は相当お粗末な結果を生んだようだ。
だからこそ2.28事件が起き、40年あまり台湾で戒厳令が出され続けたのだろうから。
このたびの旅行で私は228歴史記念公園を訪れたが、それだけ、この事件が台湾に与えた傷が深かったことの証だったと感じた。
そして、国民党の統治の失敗があまりにも甚大だったからこそ、その前に台湾を統治した日本への評価を高めたのかもしれない。
本書がそのように政権与党である国民党の評価を冷静に行っていること。それは、すなわち台湾国立歴史博物館の展示にも国民党の影響があまり及んでいない証拠のような気がする。
本書を読み、台湾国立歴史博物館には一度行ってみたくなった。
この旅で、私は中正紀念堂の文物展示室の展示物である、蒋介石が根本博中将に送った花瓶の一対をこの目で見た。
根本博中将と言えば、共産軍に圧倒的に不利な台湾に密航してまで渡り、金門島の戦いを指揮して共産軍から守り抜いた人物である。
だが、中正紀念堂には根本博中将に関する記述はもちろんない。日本統治を正当化する展示ももちろんない。
そんな根本中将への公正な評価も、台湾国立歴史博物館では顕彰されているのかもしれない。
それどころか、日本による統治の良かった点も含め、公正に評価されているとありがたい。
そんな感想を本書から得た。
‘2019/7/24-2019/7/25