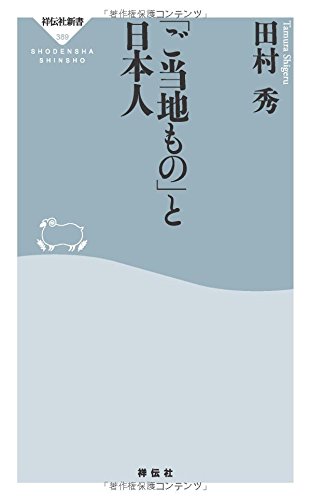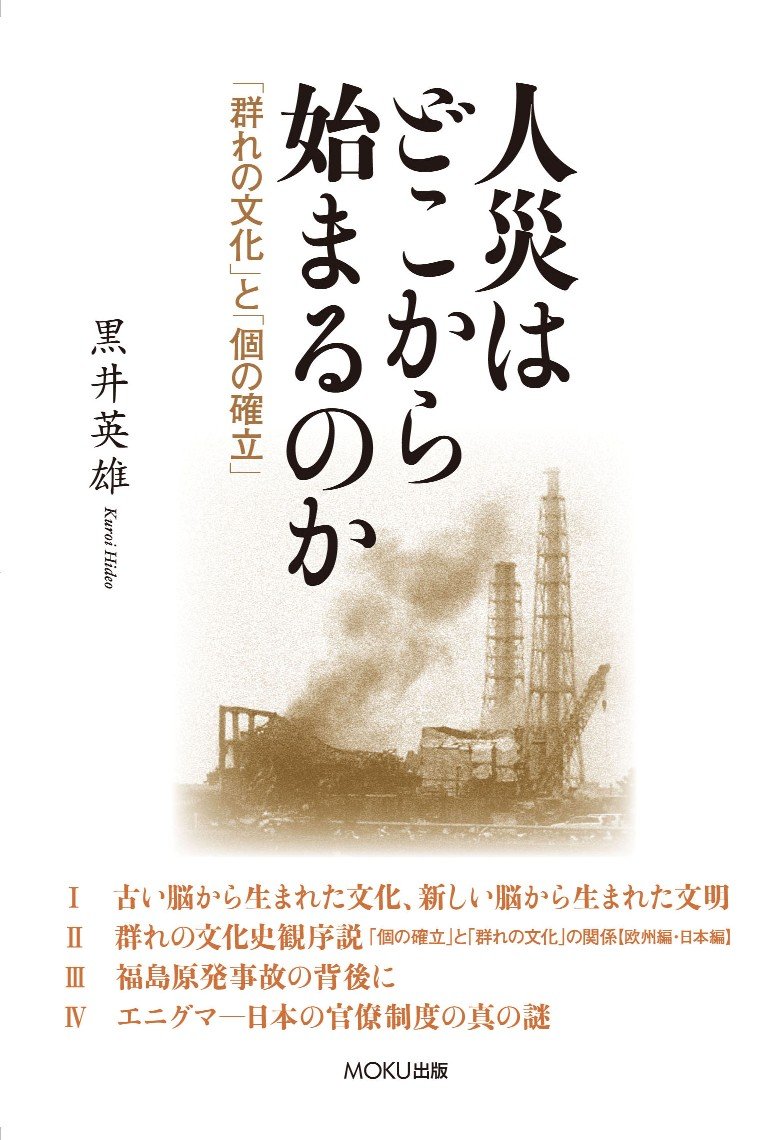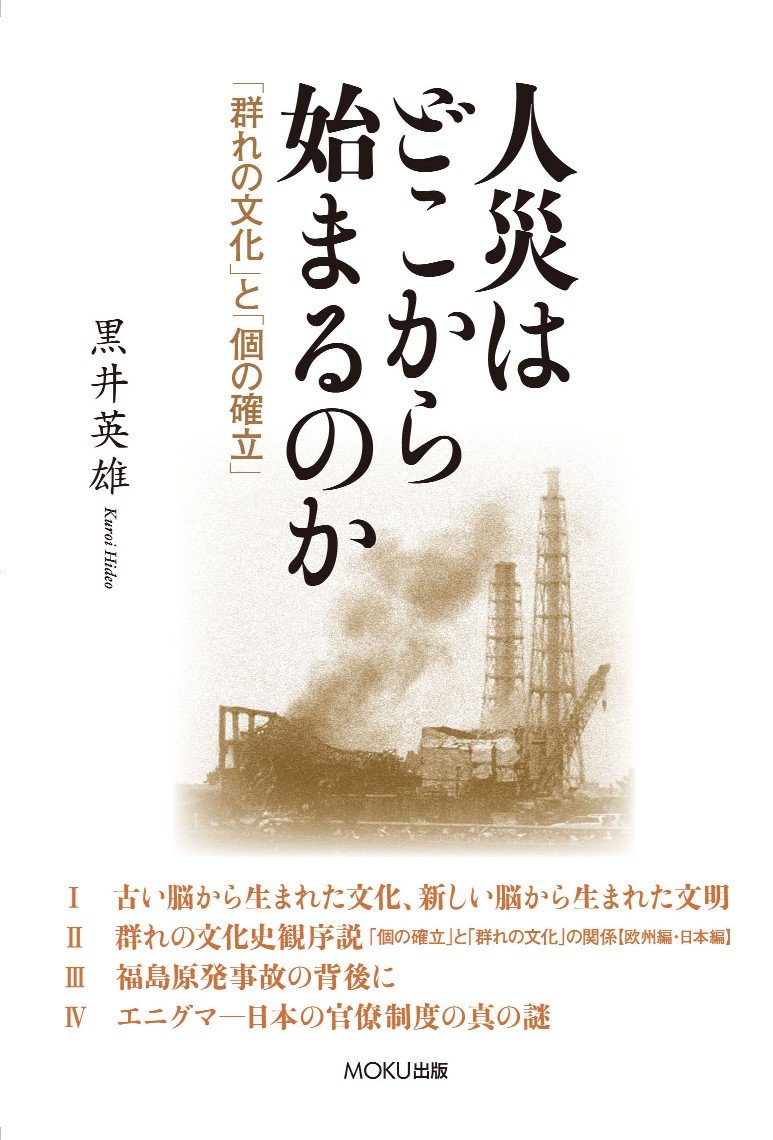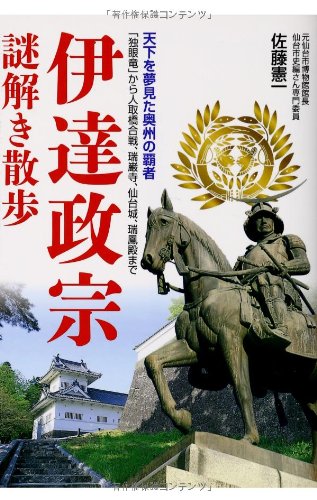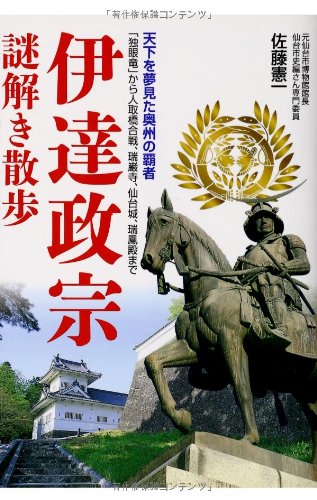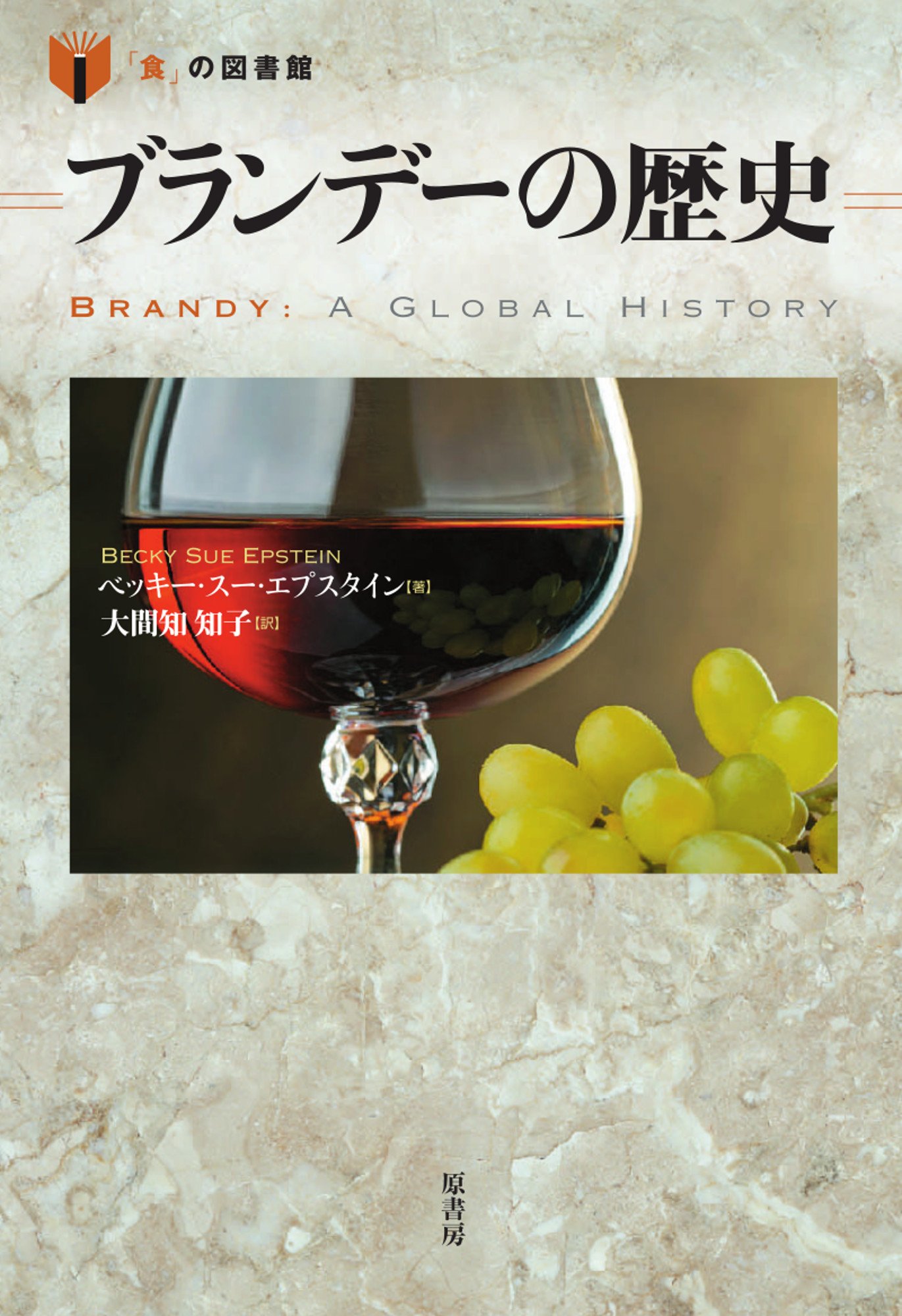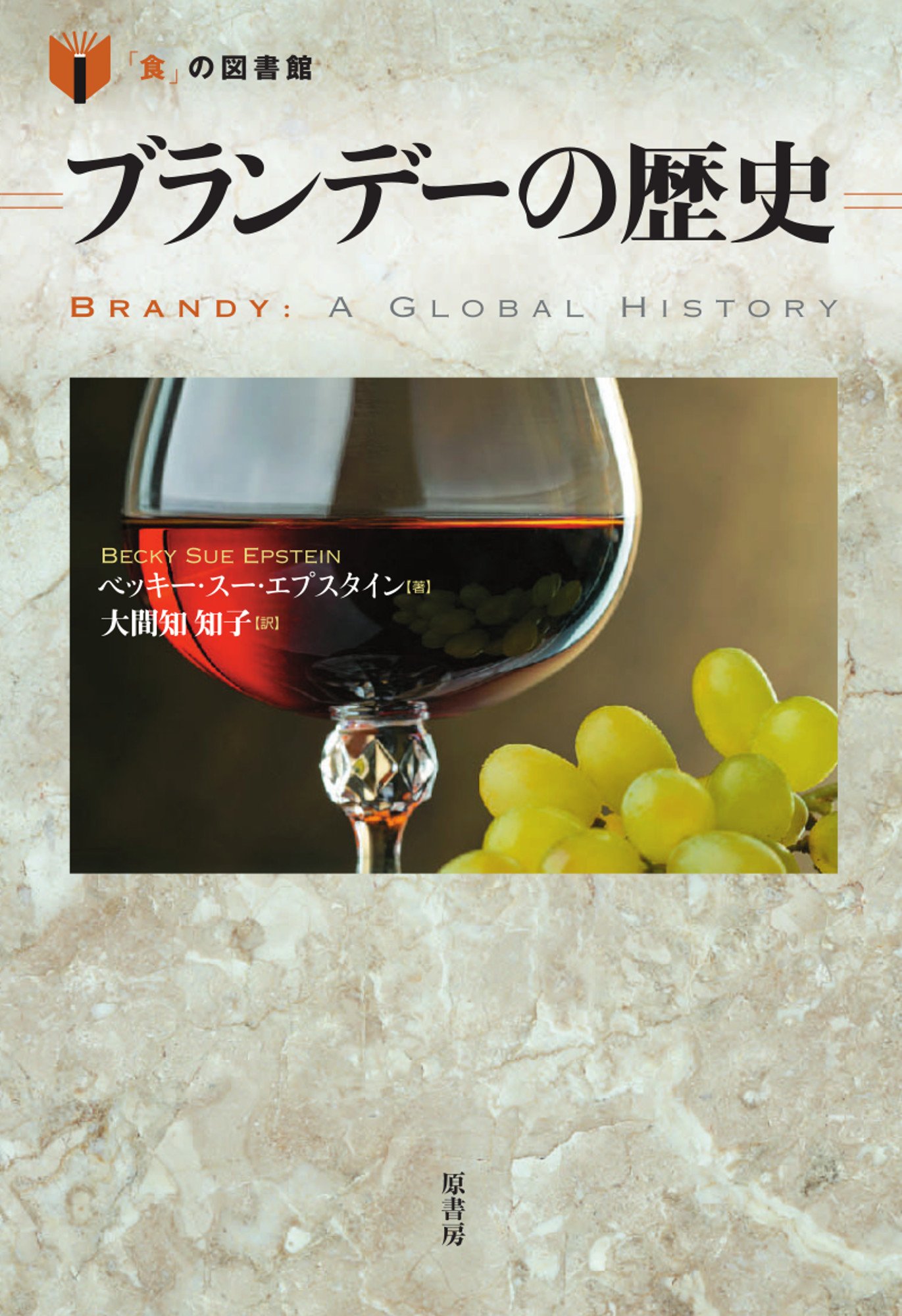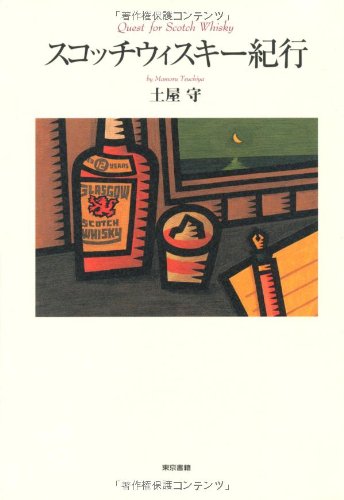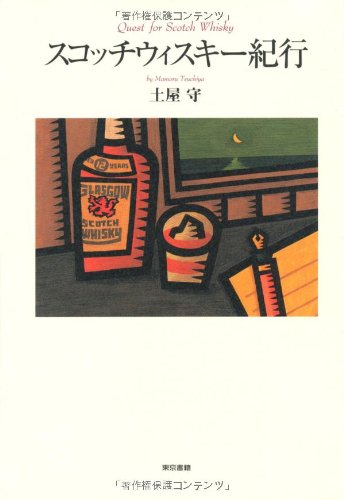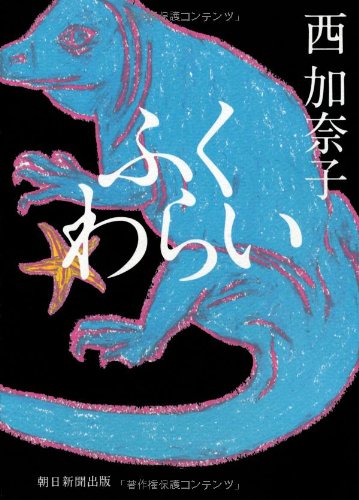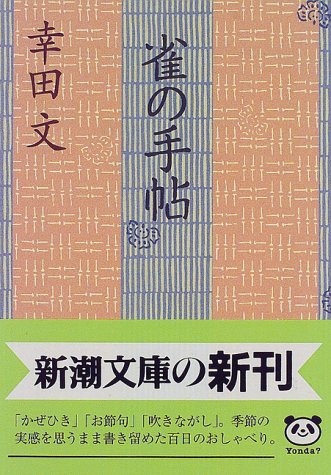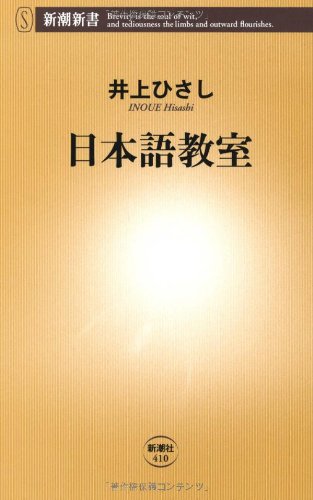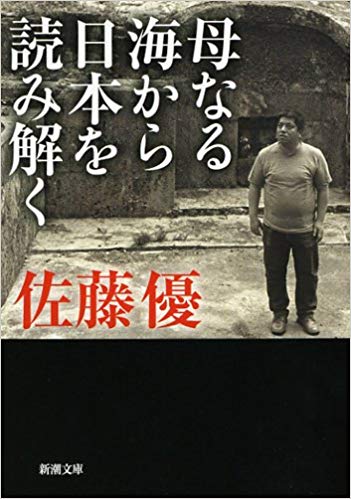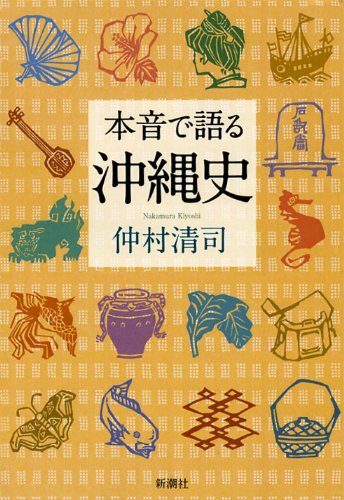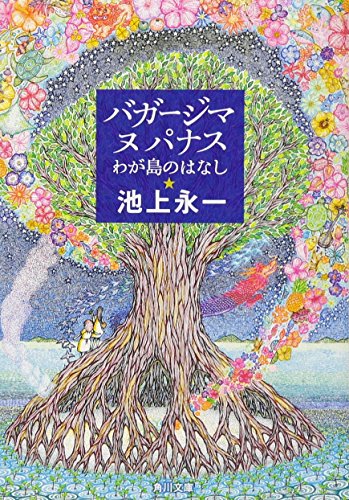本書は仲良くしている技術者にお薦めされて購入した。その技術者さんは仮想通貨(暗号通貨)の案件に携わっていて、技術者の観点から本書を推奨してくれたようだ。投資目的ではなく。
ブロックチェーン技術が失敗したこと。それは最初に投機の側面で脚光を浴びすぎたことだろう。ブロックチェーン技術は、データそれ自体に過去の取引の歴史と今の持ち主の情報を暗号化して格納したことが肝だ。さらに、取引の度にランダムに選ばれた周囲の複数のブロックチェーンアカウントが相互に認証するため、取引の承認が特定の個人や組織に依存しないことも画期的だ。それによって堅牢かつトレーサビリティなデータの流れを実現させたことが革命的だ。何が革命的か。それはこの考えを通貨に適用した時、今までの通貨の概念を変えることにある。
例えば私が近所の駄菓子屋で紙幣を出し、アメちゃんを買ったとする。私が支払った紙幣は駄菓子屋のおばちゃんの貯金箱にしまわれる。そのやりとりの記録は私とおばちゃんの記憶以外には残らない。取引の記録が紙幣に記されることもない。当たり前だ。取引の都度、紙幣に双方の情報を記していたら紙幣が真っ黒けになってしまう。そもそも、現金授受の都度、紙幣に取引の情報を書く暇などあるはずがない。仮に書いたとしても筆跡は乱雑になり、後で読み取るのに難儀することだろう。例え無理やり紙幣に履歴を書き込めたとしても、硬貨に書き込むのはさすがに無理だ。
だから今の貨幣をベースとした資本主義は、貨幣の持ち主を管理する考えを排除したまま発展してきた。最初から概念になかったと言い換えてもいい。そして、今までの取引の歴史では持ち主が都度管理されなくても特段の不自由はなかった。それゆえ、その貨幣が今までのどういう持ち主の元を転々としてきたかは誰にもわからず、金の出どころが追求できないことが暗黙の了解となっていた。
ところが、ブロックチェーン技術を使った暗号通貨の場合、持ち主の履歴が全て保存される。それでいて、データ改ざんができない。そんな仕組みになっているため、本体と履歴が確かなデータとして利用できるのだ。そのような仕様を持つブロックチェーン技術は、まさに通貨にふさわしい。
一方で上に書いた通り、ブロックチェーン技術は投機の対象になりやすい。なぜか。ブロック単位の核となるデータに取引ごとの情報を格納するデータをチェーンのように追加するのがブロックチェーン技術の肝。では、取引データが付与される前のまっさらのデータの所有権は、ブロック単位の核となるユニークなデータの組み合わせを最初に生成したものに与えられる。つまり、先行者利益が認められる仕組みなのだ。さらに、既存の貨幣との交換レートを設定したことにより、為替差益のような変動利益を許してしまった。
その堅さと手軽さが受け、幅広く使われるようになって来たブロックチェーン。だが、生成者に所有権が与えられる仕様は、先行者に富が集まる状況を作ってしまった。さらに変動するレートはブロックチェーンに投機の付け入る余地を与えてしまった。また、生成データは上限が決まっているだけで生成される通貨単位を制御する主体がない。各国政府の中央銀行に対応する統制者がいない中、便利さと先行者利益を求める人が押しかける様は、ブロックチェーン=仮想通貨=暗号通貨=投機のイメージを世間に広めた。そして、ブロックチェーン技術それ自体への疑いを世に与えてしまった。それはMt.Goxの破綻や、続出したビットコイン盗難など、ブロックチェーンのデータを管理する側のセキュリティの甘さが露呈したことにより、その風潮に拍車がかかった。私が先に失敗したと書いたのはそういうことだ。
だが、それを差し引いてもブロックチェーン技術には可能性があると思う。投機の暗黒面を排し、先行者利益の不公平さに目をつぶり、ブロックチェーン技術の本質を見据える。すると、そこに表れるのは新しい概念だ。データそれ自体が価値であり、履歴を兼ねるという。
ただし、本書が扱う主なテーマは暗号通貨ではない。むしろ暗号通貨の先だ。ブロックチェーン技術の特性であるデータと履歴の保持。そして相互認証による分散技術。その技術が活用できる可能性はなにも通貨だけにとどまらない。さまざまな取引データに活用できるのだ。私はむしろ、その可能性が知りたい。それは技術者にとって、既存のデータの管理手法を一変させるからだ。その可能性が知りたくて本書を読んだ。
果たしてブロックチェーン技術は、今後の技術者が身につけねばならない素養の一つなのか。それともアーリーアダプターになる必要はないのか。今のインターネットを支えるIPプロトコルのように、技術者が意識しなくてもよい技術になりうるのなら、ブロックチェーンを技術の側面から考えなくてもよいかもしれない。だが、ブロックチェーン技術はデータや端末のあり方を根本的に変える可能性もある。技術者としてはどちらに移ってもよいように概念だけでも押さえておきたい。
本書は分厚い。だが、ブロックチェーン技術の詳細には踏み込んでいない。社会にどうブロックチェーン技術が活用できるかについての考察。それが本書の主な内容だ。
だが、技術の紹介にそれほど紙数を割いていないにもかかわらず、本書のボリュームは厚い。これは何を意味するのか。私は、その理由をアナログな運用が依然としてビジネスの現場を支配しているためだと考えている。アナログな運用とは、パソコンがビジネスの現場を席巻する前の時代の運用を指す。信じられないことに、インターネットがこれほどまでに世界を狭くした今でも、旧態依然とした運用はビジネスの現場にはびこっている。技術の進展が世の中のアナログな運用を変えない原因の一つ。それは、インターネットの技術革新のスピードが、人間の運用整備の速度をはるかに上回ったためだと思う。運用や制度の整備が技術の速度に追いついていないのだ。また、技術の進展はいまだに人間の五感や指先の運動を置き換えるには至っていない。少なくとも人間の脳が認識する動きを瞬時に代替するまでには。
本書が推奨するブロックチェーン技術は、人間の感覚や手足を利用する技術ではない。それどころか、日常の物と同じ感覚で扱える。なぜならば、ブロックチェーン技術はデータで成り立っている。データである以上、記録できる磁気の容量だけ確保すればいい。簡単に扱えるのだ。そして、そこには人間の感覚に関係なくデータが追記されてゆく。取引の履歴も持ち主の情報も。例えば上に挙げた硬貨にブロックチェーン技術を組み込む。つまり授受の際に持ち主がIrDAやBluetoothなどの無線で記録する仕組みを使うのだ。そうすると記録は容易だ。
そうした技術革新が何をもたらすのか、既存のビジネスにどう影響を与えるのか。そこに本書はフォーカスする。同時に、発展したインターネットに何が欠けていたのか。本書は記す。
本書によると、インターネットに欠けていたのは「信頼」の考えだという。信頼がないため、個人のアイデンティティを託す基盤に成り得ていない。それが、これまでのインターネットだった。データを管理するのは企業や政府といった中央集権型の組織が担っていた。そこに統制や支配はあれど、双方向の信頼は醸成されない。ブロックチェーン技術は分散型の技術であり、任意の複数の端末が双方向でランダムに互いの取引トランザクションを承認しあう仕組みだ。だから特定の組織の意向に縛られもしないし、データを握られることもない。それでいて、データ自体には信頼性が担保されている。
分散型の技術であればデータを誰かに握られることなく、自分のデータとして扱える。それは政府を過去の遺物とする考えにもつながる。つまり、世の中の仕組みがガラッと切り替わる可能性を秘めているのだ。
その可能性は、個人と政府の関係を変えるだけにとどまらないはず。既存のビジネスの仕組みを変える可能性がある。まず金融だ。金融業界の仕組みは、紙幣や硬貨といった物理的な貨幣を前提として作り上げられている。それはATMやネットバンキングや電子送金が当たり前になった今も変わらない。そもそも、会計や簿記の考えが物理貨幣をベースに作られている以上、それをベースに発達した金融業界もその影響からは逃れられない。
企業もそう。財務や経理といった企業活動の根幹は物理貨幣をベースに構築されている。契約もそう。信頼のベースを署名や印鑑に置いている限り、データを基礎にしたブロックチェーンの考え方とは相いれない。契約の同一性、信頼性、改定履歴が完全に記録され、改ざんは不可能に。あらゆる経営コストは下がり、マネジメントすら不要となるだろう。人事データも給与支払いデータも全てはデータとして記録される。研修履歴や教育履歴も企業の境目を超えて保存され、活用される。それは雇用のあり方を根本的に変えるに違いない。そして、あらゆる企業活動の変革は、企業自身の境界すら曖昧にする。企業とは何かという概念すら初めから構築が求められる。本書はそのような時期が程なくやってくることを確信をもって予言する。
当然、今とは違う概念のビジネスモデルが世の中の大勢を占めることだろう。シェアリング・エコノミーがようやく世の中に広まりつつある今。だが、さらに多様な経済観念が世に広まっていくはずだ。インターネットは時間と空間の制約を取っ払った。だが、ブロックチェーンは契約にまつわる履歴の確認、人物の確認に費やす手間を取っ払う。
今やIoTは市民権を得た。本書ではBoT(Blockchain of Things)の概念を提示する。モノ自体に通信を持たせるのがIoT(Internet of Things)。その上に価値や履歴を内包する考えがBoTだ。それは暗号通貨にも通ずる考えだ。服や本や貴金属にデータを持たせても良い。本書では剰余電力や水道やガスといったインフラの基盤にまでBoTの可能性を説く。本書が提案する発想の広がりに限界はない。
そうなると、資本主義それ自体のあり方にも新たなパラダイムが投げかけられる。読者は驚いていてはならない。富の偏在や、不公平さといった資本主義の限界をブロックチェーン技術で突破する。その可能性すら絵空事ではなく思えてくる。かつて、共産主義は資本主義の限界を凌駕しようとした。そして壮大に失敗した。ところが資本主義に変わる新たな経済政策をブロックチェーンが実現するかもしれないのだ。
また、行政や司法、市民へのサービスなど行政が担う国の運営のあり方すらも、ブロックチェーン技術は一新する。非効率な事務は一掃され、公務員は激減してゆくはずだ。公務員が減れば税金も減らせる。市民は生活する上での雑事から逃れ、余暇に時間を費やせる。人類から労働は軽減され、可能性はさらに広がる。
そして余暇や文化のあり方もブロックチェーン技術は変えてゆくことだろう。その一つは本書が提案する音楽流通のあり方だ。もはや、既存の音楽ビジネスは旧弊になっている。レコードやCDなどのメディア流通が大きな割合を占めていた音楽業界は、今やデータによるダウンロードやストリーミングに取って代わられている。そこにレコード会社やCDショップ、著作権管理団体の付け入る隙はない。出版業界でも出版社や取次、書店が存続の危機を迎えていることは周知の通り。今やクリエイターと消費者は直結する時代なのだ。文化の創造者は権利で保護され、透明で公正なデータによって生活が保証される。その流れはブロックチェーンがさらに拍車をかけるはず。
続いて著者は、ブロックチェーン技術の短所も述べる。ブロックチェーンは必ずしも良いことずくめではない。まだまだ理想の未来の前途には、高い壁がふさいでいる。著者は10の課題を挙げ、詳細に論じている。
課題1、未成熟な技術
課題2、エネルギーの過剰な消費
課題3、政府による規制や妨害
課題4、既存の業界からの圧力
課題5、持続的なインセンティブの必要性
課題6、ブロックチェーンが人間の雇用を奪う
課題7、自由な分散型プロトコルをどう制御するか
課題8、自律エージェントが人類を征服する
課題9、監視社会の可能性
課題10、犯罪や反社会的行為への利用
ここで提示された懸念は全くその通り。これから技術者や識者、人類が解決して行かねばならない。そして、ここで挙げられた課題の多くはインターネットの黎明期にも挙がったものだ。今も人工知能をめぐる議論の中で提示されている。私は人工知能の脅威について恐れを抱いている。いくらブロックチェーンが人類の制度を劇的に変えようとも、それを運用する主体が人間から人工知能に成り代わられたら意味がない。
著者はそうならないために、適切なガバナンスの必要を訴える。ガバナンスを利かせる主体をある企業や政府や機関が担うのではなく、適切に分散された組織が連合で担うのがふさわしい、と著者は言う。ブロックチェーンが自由なプロトコルであり、可能性を秘めた技術であるといっても、無法状態に放置するのがふさわしいとは思わない。だが、その合意の形成にはかなりかかるはず。人類の英知が旧来のような組織でお茶を濁してしまうのか、それとも全く斬新で機能的な組織体を生み出せるのか。人類が地球の支配者でなくなっている未来もあり得るのだから。
いずれも私が生きている間に目にできるかどうかはわからない。だが、一つだけ言えるのは、ブロックチェーンも人工知能と同じく人類の叡智が生み出したことだ。その可能性にふたをしてはならない。もう、引き返すことはできないほど文明は進歩してしまったのだから。もう、今の現状に安穏としている場合ではない。うかうかしているといつの間にか経済のあり方は一新されていることもありうる。その時、旧い考えに凝り固まったまま、老残の身をさらすことだけは避けたい。そのためにもブロックチェーン技術を投機という括りで片付け、目をそらす愚に陥ってはならない。それだけは確かだと思う。
著者によるあとがきには、かなりの数の取材協力者のリスト、そして膨大な参考文献が並んでいる。WIRED日本版の若林編集長による自作自演の解説とあわせると、すでに世の趨勢はブロックチェーンを決して軽んじてはならない時点にあるがわかる。必読だ。
‘2018/03/09-2018/03/25