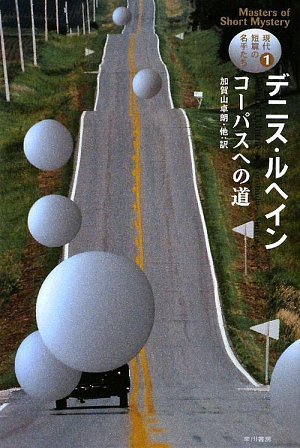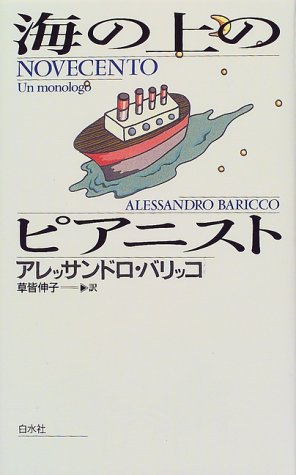
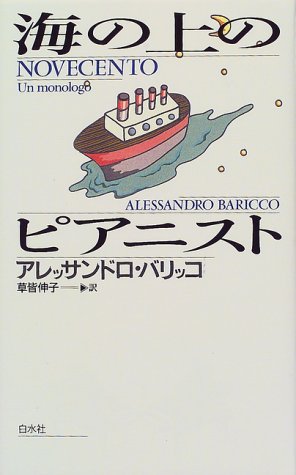
本作が映画化されているのは知っていた。だが、原作が戯曲だったとは本書を読むまで知らなかった。
妻が舞台で見て気に入ったらしく、私もそれに合わせて本書を読んだ。
なお、私は映画も舞台も本稿を書く時点でもまだ見たことがない。
本書はその戯曲である原作だ。
戯曲であるため、ト書きも含まれている。だが、全体的にはト書きが括弧でくくられ、せりふの部分が地の文となっている。そのため、読むには支障はないと思う。
むしろ、シナリオ全体の展開も含め、全般的にはとても読みやすい一冊だ。
また、せりふの多くの部分は劇を進めるせりふ回しも兼ねている。そのため、主人公であるピアニスト、ダニー・ブードマン・T・D・レモン・ノヴェチェント自身が語るせりふは少ない。
海の上で生まれ、生涯ついに陸地を踏まなかったというノヴェチェント。
私は本書を読むまで、ノヴェチェントとは現実にいた人物をモデルにしていたと思っていた。だが、解説によると著者の創造の産物らしい。
親も知らず、船の中で捨て子として育ったノヴェチェント。本名はなく、ノヴェチェントを育てた船乗りのダニー・ブードマンがその場で考え付いた名前という設定だ。
ダニー・ブードマンが船乗りである以上、毎日の暮らしは常に船の上。
船が陸についたとしても、親のダニーが陸に降りようとしないので、ノヴェチェントも陸にあがらない。
ダニーがなくなった後、ノヴェチェントは陸の孤児施設に送られようとする。
だが、ノヴェチェントは人の目を逃れることに成功する。そして、いつの間にか出港したヴァージニアン号に姿を現す。しかもいつの間に習ったのか、船のピアノを完璧に弾けるようになって。
そのピアノの技量たるや超絶。
なまじ型にはまった教育を受けずにいたものだから、当時の流行に乗った音楽の型にはまらないノヴェチェント。とっぴなアイデアが次から次へと音色となって流れ、それが伝説を呼ぶ。
アメリカで並ぶものはなしと自他ともに認めるジェリー・ロール・モートンが船に乗り込んできて、ピアノの競奏を挑まれる。だが、高度なジェリーの演奏に引けを取るどころか、まったく新しい音色で生み出したノヴェチェント。ジェリーに何も言わせず、船から去らせてしまう。
その様子はジャズの即興演奏をもっとすさまじくしたような感じだろうか。
本書では、数奇なノヴェチェントの人生と彼をめぐるあれこれの出来事が語られていく。
これは戯曲。だが、舞台にかけられれば、きらびやかな演奏と舞台上に設えられた船内のセットが観客を楽しませてくれることは間違いないだろう。
だが、本書が優れているのは、そうした部分ではない。それよりも、本書は人生の意味について考えさせてくれる。
世界の誰りも世界をめぐり、乗客を通して世界を知っているノヴェチェント。
なのに、世界を知るために船を降りようとしたその瞬間、怖気づいて船に戻ってしまう。
その一歩の距離よりも短い最後の一段の階段を乗り越える。それこそが、本書のキーとなるテーマだ。
船の上にいる限り、世界とは船と等しい。その中ではすべてを手中にできる。行くべきところも限られているため、すべてがみずからの意志でコントロールできる。
鍵盤に広がる八十八個のキー。その有限性に対して、弾く人、つまりノヴェチェントの想像力は無限だ。そこから生み出される音楽もまた無限に広がる。
だが、広大な陸にあがったとたん、それが通じなくなる。全能ではなくなり、すべては自分の選択に責任がのしかかる。行く手は無限で、会う人も無限。起こるはずの出来事も予期不能の起伏に満ちている。
普通の人にはたやすいことも、船の上しか知らないノヴェチェントにとっては恐るべきこと。
それは、人生とは本来、恐ろしいもの、という私たちへの教訓となる。
オオカミに育てられた少女の話や、親の愛情に見放されたまま育児を放棄された人が、その後の社会に溶け込むための苦難の大きさ。それを思い起こさせる。
生まれてすぐに親の手によって育まれ、育てられること。長じると学校や世間の中で生きることを強いられる。それは、窮屈だし苦しい。だが、徐々に人は世の中の広がりに慣れてゆく。
世の中にはさまざまな物事が起きていて、おおぜいのそれぞれの個性を備えた人々が生きている事実。
陸にあがることをあきらめたノヴェチェントは、ヴァージニアン号で生きることを選ぶ。
だが、ヴァージニアン号にもやがて廃船となる日がやってきた。待つのは爆破され沈められる運命。
そこでノヴェチェントは、船とともに人生を沈める決断をする。
伝説となるほどのピアノの技量を備えていても、人生を生きることはいかに難しいものか。その悲しい事実が余韻を残す。
船を沈める爆弾の上で、最後の時を待つノヴェチェントの姿。それは、私たちにも死の本質に迫る何かを教えてくれる。
本来、死とは誰にとっても等しくやってくるイベントであるはず。
生まれてから死ぬまでの経路は人によって無限に違う。だが、人は生まれることによって人生の幕があがり、死をもって人生の幕を下ろす。それは誰にも同じく訪れる。
子供のころは大切に育てられたとしても、大人になったら難しい世の中を渡る芸当を強いられる。
そして死の時期に前後はあるにせよ、誰もが人生を降りなければならない。
それまでにどれほどの金を貯めようと、どれほどの名声を浴びようと、それは変わらない。
船上の限られた世界で、誰よりも世界を知り、誰よりも世界を旅したノヴェチェント。船の上で彼なりの濃密な人生を過ごしたのだろう。
その感じ方は人によってそれぞれだ。誰にもそれは否定できない。
おそらく、舞台上で本作を見ると、より違う印象を受けるはずだ。
そのセットが豪華であればあるほど。その演奏に魅了されればされるほど。
華やかな舞台の世界が、一転して人生の深い意味を深く考えさせられる空間へと変わる。
それが舞台のよさだろう。
‘2019/12/16-2019/12/16