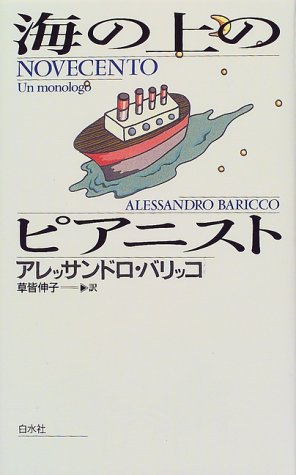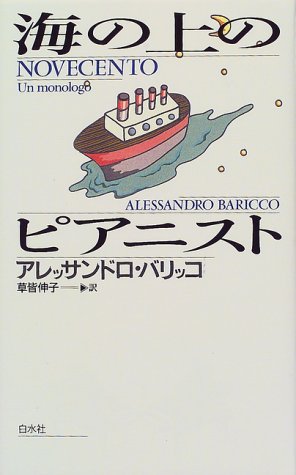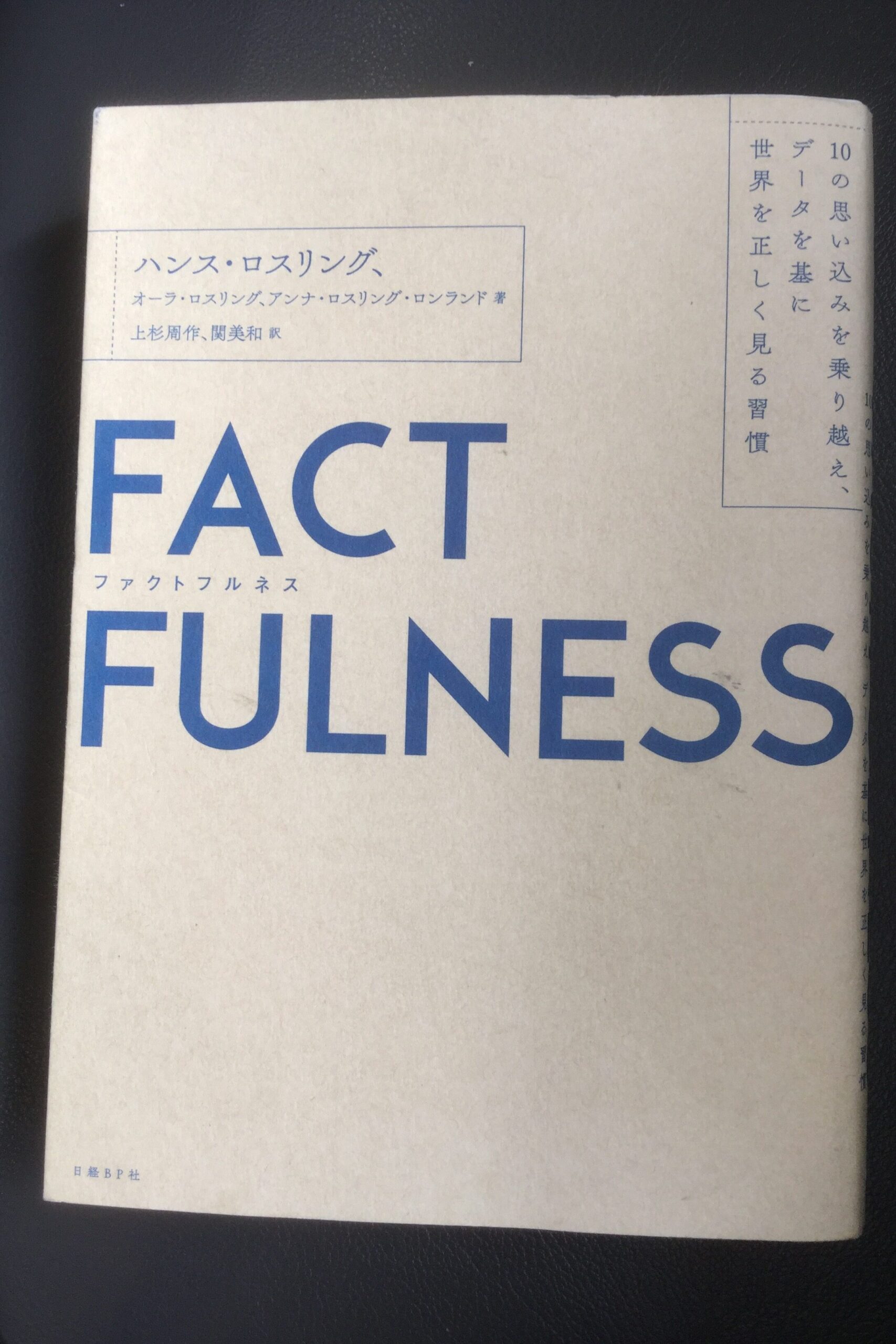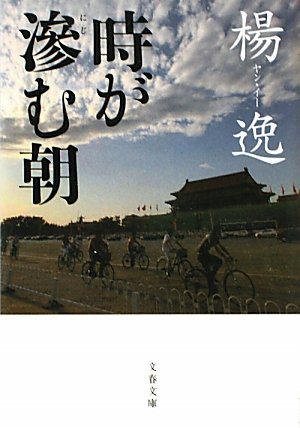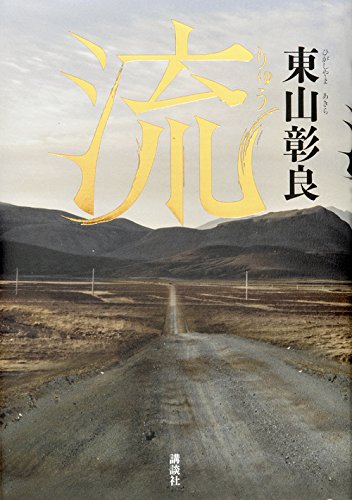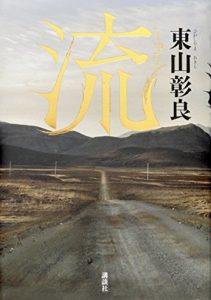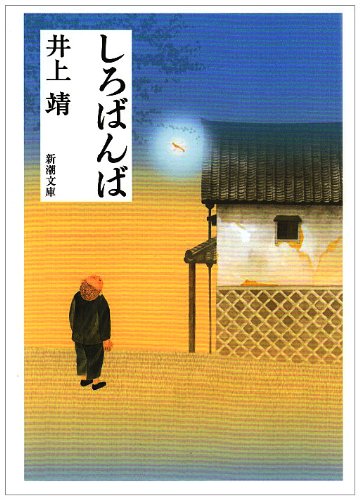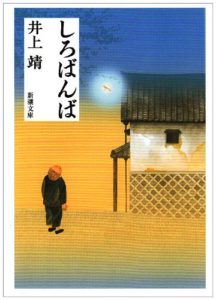あらためまして、合同会社アクアビットの長井です。
弊社の起業までの航海記を書いていきます。以下の文は2018/5/13にアップした当時の文章が喪われたので、一部を修正しています。
今回は新たな会社でシステムを独学で習得しまくる話です。この時の経験が私を起業に導いてくれました。
オフィス移転で恥をかく
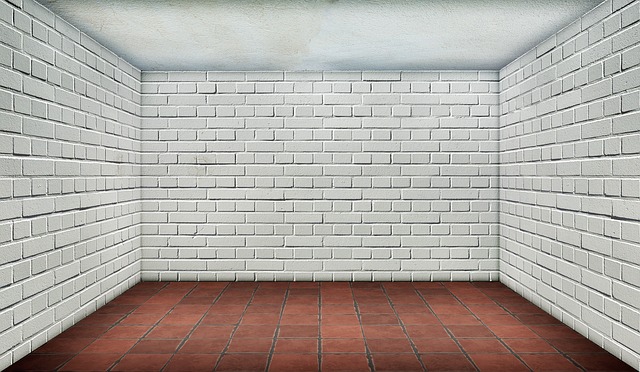
新しい会社の日々は、とても刺激的でした。
まず、私が入社してすぐに社屋の引っ越しがありました。新しい五階建てのビル。すべてが空っぽです。なにもありません。ネットワークどころか電源の場所も考慮されていません。全ては私に任されており、完全に白紙でした。そこでまずレイアウトを検討し、電源やネットワークの位置を設計しました。入社して早々、各部署の方と話を進めながら。
ファシリティ設計もネットワーク設計や電源設計も、当時の私にとって全てが初めての体験てした。やったことがなくてもやらねばなりません。やるのです。結果が良ければ全てがよし。ぶっつけ本番。あたって砕けろ。すると、なんとかなってしまうのではないか。
もちろん、何もなく終わるはずはありません。いくらVisioで図面を書いてみたところで、いざ本番となれば想定外の出来事が起こります。そもそも設計はあくまで机上の計画に過ぎません。物が実際に設置された時、計画とずれるのは当然のことなのです。そもそも私自身がオフィスのレイアウトやネットワーク設定など全くやったことがなく、計画はずさんだったはず。案の定、引っ越し当日は右往左往しました。
例えばモールです。モールってご存じですか?LANケーブルを保護し、しまい込むための塩ビ製の細長いカバーです。
モールは上と下に分離し、カチッとはめ込む構造になっています。ベロンと上下を分け、そこにLanケーブルをしまい込み、最後にパチリと上下をはめ込みます。ところが私はそんなこともすら知りません。
上下に閉じたままのモールのすき間に無理やりLanケーブルを押し込もうとしました。不可能を可能にする男、長井の面目躍如といいたいのですが、そもそも入るわけがありません。この時、来てもらっていた工事業者さんのあ然とした顔は今も思い出せます。
本連載の第十六回で、IMEを切り替える方法を知らなかった私が、半角カタカナでデータを打ち込み「ニイタカヤマノボレじゃないんだから!」と怒られた芦屋市役所でのエピソードは書きました。この時のモールの一件は、その時に負けず劣らず恥ずかしいエピソードです。土壇場で電源の場所が変更になり、それをお願いしたい時の電気業者さんが見せた絶望と諦めの顔も思い出せます。
自分に恥をかきまくって成長する

結局、私の二十代とはそういう恥ずかしい記憶の集まりです。でも今から思うと、恥をかいては捨ててきた積み重ねが私の成長につながっています。全ては血となり肉となりました。
もちろん、成長のやりかたは人によってそれぞれです。一つ一つの作業を丁寧にOJTで教わりながら恥をかかずに成長していく人もいるでしょう。ただし、それはあらかじめ決められたカリキュラムに沿っています。カリキュラムとは、習得の到達度を考慮して設計します。ということはカリキュラムに乗っかっているだけでは、成長の上限もあらかじめ決められています。
私の場合、乗っかっているカリキュラムからはみ出し、一人で突っ走ってばかりでした。そして失敗を繰り返していました。でも、それもよいのではないでしょうか。カリキュラムからはみ出た時、人は急激に成長できるような気がします。少なくとも、この頃の私はそうでした。
私の人生で何が誇れるかって、ほとんどの技術を独学で学び、恥をかきまくってきたことだと思っています。
私にとってこちらの会社で学んだ事はとても大きな財産となりました。情報技術のかなりを独学で習得しました。そして自分に対して恥をかき続けました。
私がかいた恥のほとんどは自分に対しての恥でした。というのも、この会社に私より情報技術スキルを持つ方はいなかったからです。つまり、自分自身がかいた恥は誰にも気づかれず、誰からも指摘されず、ほとんどが私の中で修正され、処理されていきました。その都度、自分の乏しい知識をなげきながら。
でも、そうやって自分の未熟さに毎日赤面しながら、私は会社の情報処理、ファシリティや機器管理やパソコン管理、ネットワーク管理の知識を着々と蓄えていきました。
自らが知らないことを学び、自分の無知に恥をかき続ける。今でもそうです。自分が知っていて安心できる知識の中でのみ仕事をすれば失敗はないでしょう。そのかわり成長は鈍いはずです。失敗の数もまた人生の妙味だと思います。
恥をかきすぎたら成長できた

入社した当初は、私を試そうと圧力をかける方がいました。が、徐々に難癖を付ける方は何も言わなくなりました。やがて私は自分の思うがままに環境を作れる立場になっていました。
もちろん職権の乱用はしません。自分の判断でこの機能が必要と判断し、稟議書を書き、上長に上げます。そのうちの九割方は決裁してもらえたように思います。会社には何社もシステムベンダーの方に来ていただきました。臆せずに自分で展示会にも出かけていき、知見を広げました。
時期は忘れてしまいましたが、自分でサーバーを構築したのもこの時期です。DELLのサーバーを購入してもらい、そこにRed Hat Linuxをインストールしました。さらに自分でSamba(オープンソースのファイルサーバー)を入れました。全ては白紙からの挑戦でした。
そのサーバーには後日、Apache(ウェブサーバー)やMySql(データベース)やPHP(プログラム言語)も自力でインストールしました。そうして自分なりの社内イントラネットを構築していきました。
私が入社した当初、その会社の販売管理はオービック社の商蔵奉行が担っていました。受発注や伝票発行の全てをそれでまかなっていました。そもそも私がこの会社に呼ばれたのも、システムのオペレーションミスによる誤請求があったためです。そこでFAXをOCR変換して取り込む仕組みも作りました。EDIも何パターンか導入しました。夜間バッチでデータを自動で取得し、受注データへ変換する仕組みも構築しました。
その過程で私は社内の受発注の仕組みから勉強し、システムが備えている販売管理に関する機能の理解も深めました。販売管理を行う際は、在庫管理も欠かせません。その二つは表裏一体です。この会社は自社の倉庫も持っていました。となると在庫管理から物流の知識に至るまでの知識も修めなければ。
それらの新たな知識の習得と並行して、社内の全パソコンは私が管理していました。入社までの半年、土曜日に訪問して全パソコンのメンテナンスを行っていたことは書きました。新社屋に移る際、ネットワークや電源の構成やレイアウトも把握しました。そうした日々の中、パソコンのメンテナンス・スキルも身に付き、ネットワーク構築やサーバー設計にも経験を重ねていきます。遅いノートパソコンのメモリ増設ぐらいなら行えるぐらいまでに。
この時期の私がどれだけ充実していたか。今の私からはまぶしく思えるほどです。好きなだけ学び、存分に成長していました。しかもそれが会社の効率の改善につながっていました。とてもやりがいに溢れた時期でした。そして幸せでした。
学べること。成長できること。その成長を自分で実感でき、さらに人に対して目に見える形で貢献できること。
少し前の私は、こうした一連の仕組みを全くしりませんでした。結婚した翌年あたりに友人たちが私の家に来て、自作パソコンを組み立ててくれたことがあります。この時に来てくれたのは、大学の政治学研究部の後輩とスカパー・カスタマーセンターのオペレーターさんと義弟でした。珍しい組み合わせ。そして皆が私より年下。
それなのに、私は彼らがやってくれている作業のほとんどが理解できませんでした。
そんな私が今や、新たな会社で情報統括を行う立場となりました。少し前まではニイタカヤマノボレと怒られていた私が。モールの構造を知らずに無理やり押し込もうとした私が。
これが人生の面白さだと思います。
ただし、私の人生には大きな試練がまだ続きます。
その試練とは家の処分。本連載の第三十七回、第三十八回、三十九回にも書いた家の処分です。
私が転職した大きな理由の一つは、そもそもこの家を処分するためでした。
次回は家の処分を二回にわたって書いてみます。ゆるく長くお願いします。